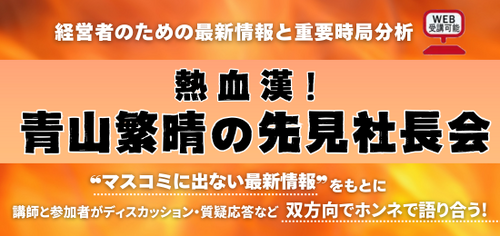政府による経済介入は終焉へ、人口減少下で企業・労働者・消費者が経験する「かつてない痛み」とは?
2025年1月7日(火)4時0分 JBpress
少子化による人手不足が深刻だ。その影響は、賃金の上昇や先端技術による省人化、女性・シニアの活用などに現れ、労働市場は著しく変化している。加えて日本は他の先進国に先駆け、これから本格的な人口減少時代を迎える。社会の前提が変容する中、日本経済の構造は今後どのように変化していくのか。本連載では『ほんとうの日本経済』(坂本貴志著/講談社現代新書)から、内容の一部を抜粋・再編集。現状を整理しつつ、日本経済の将来の姿とその論点を考察する。
第2回は、人手不足の常態化がもたらす日本の経済構造の転換と、それに付随する「ストレス」を明らかにする。
構造的な人手不足が、企業の変革と日本経済の高度化を要請する
ここまで解説してきたとおり、人口動態の変化は経済の需給環境を変化させる。そして、需給環境の変化は、企業や労働者、消費者の行動様式に変容を促す。
前節では人口減少局面において内生的に生じるであろう各経済主体の行動変化を記述してきた。そして、経済の環境変化に大きく関係している経済主体はもう一つ存在している。それは政府である。
これまでの人口調整局面において、政府は経済に対してさまざまな介入を行ってきた。近年の政府の経済政策の大きな方向性を振り返れば、その中心にあったのは、バブル崩壊以降に幾度となく繰り返されてきた政府による大規模な財政出動やアベノミクス以降の日本銀行による異次元金融緩和があげられる。
これまでの財政・金融政策の背景にあったのは、日本経済が慢性的なデフレーションに悩まされるなか、需要の喚起が必要であるとの共通認識であった。実際に、ここまでの各種データから見てきたとおり、人口調整局面において供給能力に比して需要が不足していたということは、確かに事実であったと考えることができる。
政府や中央銀行による積極的な経済への介入を肯定する立場の専門家には、拡張的な財政・金融政策によって需給環境を意図的にひっ迫させることでいわゆる高圧経済と呼ばれるような状況を作り出し、その圧力によって日本の経済成長を実現させようという考え方もあった。
そして、実際に近年の日本経済が直面している需給環境の大きな変化にこれまでの経済政策が貢献してきた部分もあったと考えることもできる。
しかし、それと同時にこれまで行われてきた日本銀行による大規模金融緩和は中央銀行のバランスシートを大きく膨張させ、政府による積極的な財政出動は政府債務を著しく拡大させるなど、過去に行われた政策は後世に多くの禍根を残した。足元でも日本円の急速な減価が進行するなど、過去の政策が引き起こしたさまざまな副作用を軽視することはできない。
これまでの人口調整局面に行われてきた政府や中央銀行による積極的な経済への介入にはどのような効果があったのだろうか。それは総じてポジティブな効果があったのかもしれないし、あるいはそうではなかったかもしれない。
この点、政府や中央銀行による積極的な経済への介入にどのような効果があったのかを検証することは重要である。これまでの人口調整局面において行われてきたこれらの政策の成否については、将来の然(しか)るべき時期にその審判は下されることになるだろう。
一方、過去に行われてきた政策に対する評価は別として、本書においてあくまで指摘しておきたいことは、このような経済の局面はもう既に終焉に向かいつつあるということである。
そして、さらに指摘しておきたいのは、これからの経済の需給環境を決定する主役は財政・金融政策ではなく、人口動態の変化に伴う構造的な人手不足に移りつつあるということなのである。
今後の日本経済においては、政府、中央銀行による積極的な介入なくしても、人口動態の変化に伴って自然と市場の需給はひっ迫した状態が常態化していくだろう。そうなれば、これからの日本の経済を占ううえで重要になるのは、経済全体の供給能力をいかにして高めていくかという、経済学が本来想定している問題に回帰していくことになる。
そして、これからの人手不足が常態化する局面においては、市場メカニズムが健全に発露するなかでそれが企業の変革を促す圧力となり、日本経済のさらなる高度化を促す原動力となるのである。
市場メカニズムが引き起こすストレスにどう向き合うか
今後、日本の人口が減少していくなか、世界経済における日本経済のプレゼンスが相対的に縮小していくことは避けられない。しかし、人口減少が経済全体の生産性の伸び悩みや人々の生活水準の低下につながるかまではわからない。
今後の展開として、若者人口の減少が社会全体のイノベーションの停滞につながる可能性もあれば、ここまで説明してきたように人手不足の圧力が日本経済の高度化を促すシナリオもありうる。
もっとも、今後、市場メカニズムが原動力となる形で日本の経済構造が転換していくことになったとしても、それは簡単な道のりではない。
賃金の上昇は企業に変革を迫る要因になるが、それと同時にこうしたストレスを乗り越えられない企業は、市場から容赦なく淘汰されていくことになるだろう。物価が上昇し、人手を介したサービスの提供が制約されていくなかで、消費者はこれまで享受してきた価格のつかない質の高いサービスを手放す必要に迫られる。
労働者はこれからの経済の局面で最も多くの利益を享受する主体になると考えられるが、デジタル技術がビジネスの現場に浸透していくなかで、新しいスキルの習得は労働者にとっても避けられない課題となる。これからの人口減少局面においては、企業や消費者などの経済主体はこれまでとは異なるストレスを経験するはずだ。
そう考えれば、これからの日本経済が経験する局面がバラ色の未来ではないことは明らかだ。今後、人手不足を解消するために市場メカニズムは経済全体の生産性を向上させるよう強力な圧力をかける。
そして、その過程においては、市場メカニズムがあらゆる経済主体に多大な努力を要請し、これらの経済主体はこれまでにない強い痛みを経験することになる。しかし、市場メカニズムが引き起こす痛みに向き合うことなしに、これからの日本経済の高度化が達成されることはない。
<連載ラインアップ>
■第1回 労働市場の需給逼迫による持続的な賃金上昇は、企業に何を強いるのか?
■第2回 政府による経済介入は終焉へ、人口減少下で企業・労働者・消費者が経験する「かつてない痛み」とは?(本稿)
■第3回 特定技能制度の拡充で外国人労働者は増大の一途…日本経済の今後を左右する労働市場の「最大の論点」とは?(1月16日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:坂本 貴志