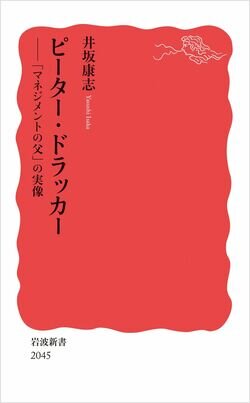過激化する資本主義の暴威に危機感 ドラッカーがポスト資本主義社会に不可欠と考えた組織とは?
2025年5月2日(金)4時0分 JBpress
「マネジメントの父」と呼ばれ、日本では1956年発行の『現代の経営』以来、数々のベストセラーを生んだピーター・ドラッカー。日本の産業界に多大な影響を与えたと言われる一方、その人物像が語られることは少ない。本稿では『ピーター・ドラッカー ——「マネジメントの父」の実像』(井坂康志著/岩波新書)から内容の一部を抜粋・再編集。没後20年となる現在も熱心な読者が絶えないドラッカーの人生と哲学、代表的な著書が生まれた背景を紹介する。
ドラッカーは強欲な資本主義をどう批判し、どのような資質を知識社会の担い手に求めたか。
資本主義に正統性はあるか
遡れば、1965年のW・ガザーティによる著作『若き経営エリートたち』に推薦の辞を寄せた際、「現代のアメリカの若手経営者は、仕事において有能な一方で、目的について思い煩うことがない」との危惧をドラッカーは表明している。彼らには仕事に対する自負もあり、ある種の熱意さえ感じさせるが、目的意識が欠如していた。
仕事にのめり込み、周囲の状況とは無関係にひたすらそれに打ち込むことになる。時流に乗り遅れないよう前のめりに働く中で、いつしか自分も社会も見失っていく。
『新しい現実』の序文に見えるのは、そうした危惧である。旧思想からは自由になったが、彼らは利益からは自由でない生活をしていた。利益をドグマ化して彼らは生きていた。これでは経済は心配なくとも、社会が心配だとドラッカーは語る。
利益追求にはある種の「業」がある。市場経済を彼は受け入れてはいるものの、それも他の経済、たとえば特権官僚が価格と供給量を決定する体制よりもいくらかましなだけに過ぎないと、ドラッカーは言っているのである。
後に『ワイアード』は「資本主義の教祖」とまで彼を呼んだが、その実、資本主義の批判者として、1986年、『パブリック・インテレスト』に「敵対的企業買収とその問題点」という論文を寄せ、過激化する資本主義の暴威を彼は論じている。
資本主義も、マルクス主義やナチスのイデオロギーには勝ったつもりでいても、利潤追求に一元化されてしまえば、新しいイデオロギーにからめとられることになる。敵対的買収は、とりわけその象徴ともいえる醜悪な現実だった。
「敵対的企業買収が資源の効率的配分につながるなどという議論は、とうてい正当化することができず、それはレイダー(乗っ取り屋)の私利私欲以外なんらの目的も持たない」。
当時アメリカの敵対的買収の件数は少なく見ても400〜500に及び、うち半数の事例では買収の標的となった企業は消滅している。買収された企業の経営が好転した例はほぼ見られなかったと彼は観察し、とりわけトップ経営陣の「ゴールデン・パラシュート」を批判した。
敵対的買収やレバレッジド・バイアウト(LBO)によって中堅クラス以下が職を失う一方、トップ経営陣のみが誰にも説明責任を負うことなく多額のボーナスを手にして悠々とどこかへ去っていく。現場で働く人々は彼らにとって自己利益を実現する手段に過ぎず、そのような経済活動で手にする自由は、人や社会の犠牲で成り立つ虚妄の自由にほかならない。
市場優位の中でビジネススクールも変質した。人文系の学部の存在意義を問われるようになった。MBAは学生獲得で熾烈な競争を行った。アメリカのMBA学費がきわめて高額なのはよく知られるが、1988年『ビジネスウィーク』は、巻頭に全米MBAランキングを掲載し、卒業生の獲得賃金やスカウト件数を指標に、誌面を構成した。
資本主義は、今のままでは人間社会全体をふたたび絶望に陥れる危険がある。それをよしとするのであれば、あえて声を大にして語る必要はない。しかし、多くの人々が目にしているのに、危機と問題に気づかないふりをしているのであれば、積極的に語らなければならない。脱出のための対抗哲学が必要である。さもなければ、きたるべき21世紀を浪費してしまうことになる。
『現代の経営』の結論では、そのことについて重要な主張を彼は行っている。
「最も重要な結論は、社会のリーダー的存在としてのマネジメントの社会的責任とは、公共の利益をもって企業の利益にするということである」。
公共の利益は、時々の責任ある決断によって実現するほかはない。その時彼の視界に入ったのが、NPOだった。かねてよりドラッカーは、社会にとってNPOは望ましいと見ていたが、この時点からは、望ましいものから、ポストモダンの社会に不可欠のものと認識するようになった。
前章で見たように、カリフォルニアに移住した彼は、地域社会、教会、学校、病院、図書館等に奉仕するリーダーの多くを学生として迎え入れ、時に相談相手にもなった。それはマネジメントとソーシャル・セクターとの間の架橋の試みにほかならなかった。
ポスト資本主義社会へ
世界史的事象の解釈には、かつての似た事象の体験が大きく影響してくる。80歳を迎えたドラッカーは、ヨーロッパ時代とも重なるような危機の認識を通して、原点回帰への志向を強めていった。最晩年、自分自身を「逆説家」であったと彼は述べているが、とりわけ90年代以後は、逆説としてしか説明できない領野へと自ら赴いていった。
『新しい現実』の4年後に刊行された『ポスト資本主義社会』(1993年)は、ブレンナー峠の先に広がる風景を克明に描いている。特に人間に直接関わるシステムへの言及、資本主義批判と表裏一体に論じられた教育批判がとりわけ印象的である。他の社会生態学的著作でも例外なく言及され、『ポスト資本主義社会』でも重視されているテーマが教育である。
知識社会の担い手となる資質を持つ人間像を、ドラッカーは次のように総括する。
「知識社会の中心は人である。知識は、通貨のような物的な存在ではない。知識は、本やデータバンクやソフトウェアの中にはない。そこにあるのは情報に過ぎない。知識は、人の中にある。人が教え学ぶものである。人が正しくあるいは間違って使うものである。それゆえ、知識社会への移行とは、人が中心的な存在になることにほかならない。したがって知識社会への移行は、知識社会の代表者たる教育ある人間に対し、新しい挑戦、新しい問題、さらにはかつてない新しい課題を提起する」
知識とは彼によれば、人間の中にあり、同時に社会との共生で成り立つものである。そのため、知識を社会との関係で成熟させていかなければならない。
1994年5月4日、ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大学院エドウィン・L・ゴッドキン講座に登壇し、「理論知のみでは競争力を維持できない」とドラッカーは語気を強めた。時はIT革命の前夜だった。
21世紀の課題として、知識労働者、テクノロジストの教育にドラッカーは目を向けている。テクノロジストとは、技巧とアートという2つの意味を併せ持つ、古代ギリシャ語でいう「テクネ」を用いる人々である。
学知のみでなく、「手のわざ」を通してものをつくる「制作の能力」を持つ人々である。ものをつくる仕事は、人間社会のどこにでもあり、誰にとっても他人事ではない。ふだんは見えにくく気づかれにくいが、社会のみならず、文明の存続にとってなくてはならない。
人間社会の現実には、合理では説明し尽くせない、勘所や要諦がいくつもある。あらかじめ合理的に提示できない暗黙知もある。『ハーバード・ビジネス・レヴュー』編集長T・ジョージ・ハリスによる1993年のインタヴューで、「人は自分の鉈(なた)を持ち、自力でよじ登っていかなければならない」と語っている。
知を現場の成果に転換するのは手の働きである。技能という「鉈」をテクノロジストは持っている。その例として、脳外科医、病院の検査技師、リハビリ訓練師、レントゲン技師、超音波映像技師、歯科医師、歯科関連技術師、自動車修理工等をドラッカーは挙げている。
近年は手を動かすことを嫌う風潮も蔓延している。テクノロジストは欠乏状態にあり、グローバル化と情報化が強まるほどにその傾向は強まっている。テクノロジスト養成には手間と時間がかかる。ドラッカーは日本に格別の期待をかけ、次のように述べている。
「日本の教育システムさえ、肉体労働のための人々と知識労働のための人々の2種類を生むにとどまっている。この知識の裏付けを持つテクノロジストの教育のための専門大学が設立されるのは2001年のことである」
専門大学とは、2001年開学のものつくり大学である。命名者は哲学者の梅原猛(たけし)、英文名Institute of Technologists を与えたのがドラッカーだった。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
筆者:井坂 康志