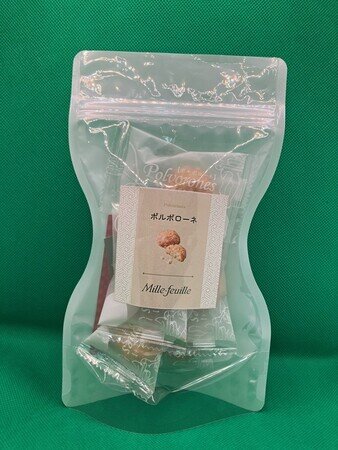「ガラガラ」は初日だけ? ついに始まった「中央線グリーン車」の車内の様子を調査&リポート
2025年3月21日(金)21時45分 All About
JR中央線快速および青梅線で3月15日からグリーン車サービスが始まった。2024年10月からの半年近いお試し期間とはどこが違うのか、車内の様子はどう変わったのか? 乗車リポートをお届けする。
東京駅から中央線快速グリーン車に乗車
3月15日、中央線快速&青梅線でグリーン車サービスが始まった。開始初日は土曜日。天気がよくなかったせいもあり、グリーン車はどの列車もガラガラだったとSNSなどで報じられていた。もともと首都圏各線のグリーン車サービスは土休日の利用状況は低調で、それゆえ以前は格安のホリデー料金が設定されていたほどだ。最近は物価高もあってか、グリーン料金が見直され、101km以上の乗車料金が新たに設定されるなど値上げされている。そんな中のサービス開始である。
開始後の実態を取材するため、平日の初日に当たる3月17日(月曜)のお昼前に中央線の始発駅である東京駅に赴いた。
中央線の快速電車は本数が多く、ひっきりなしに発着している。朝のラッシュアワーは過ぎているが、電車のドアが開くと、かなりの乗客が降り、足早に下りのエスカレータへと向かう。グリーン車からも数人が降りる。空いてはいるもののガラガラという状況ではなさそうだ。グリーン車のドア脇には係員がゴミ袋を持って待機、降車客に声を掛けながら空き缶などの回収をする。
係員は、降車客がいなくなったのを見計らって、ホームで列をなして待っている人々が中へ入るのを制しながら車内へ。見回りと簡単な清掃を行った後、ドア付近にあるボタンを押す。すると、座席が自動的に回転して、全部の座席が進行方向を向く。お試し期間中の座席は乗客それぞれが回転させる必要があったため、面倒がって反対向きに座る人もかなりいた。見た目にも落ち着かない車内だったが、整然とした車内は高級感が漂う。
係員がドア脇に立ち、ほかの係員と連絡を取った後、準備が整ったようで手招きで促されて車内へ。いつの間にか7〜8人が並んでいた。ホームでは新たに設置されたピカピカの専用券売機でグリーン券情報を手持ちのSuicaに記録している人の姿も見られた(紙のきっぷは発券されない)。
前に並んでいた人は1階に降りて行ったので、筆者が先頭になって2階へ。席はよりどりみどりだ。席を決めると、座る前にポケットからスマホを取り出し、グリーン券を購入済みのモバイルSuicaを天井にある「グリーン券情報読み取り部」にタッチする。ランプが赤から緑に代わったことを確認して着席。座席をリクライニングしてゆったりすると同時に電車は動き出した。すぐに車内放送が始まる。
中央特快大月駅行きの車内
乗ったのは中央特快の大月駅行きで、停車駅の案内、そして4号車と5号車はグリーン車で利用するにはグリーン券が必要であるとの放送。これは、もちろんお試し期間にはなかった案内だ。しばらくすると、アテンダントさんが見回りに来た。天井のランプが赤になっている人がいれば、グリーン券を持っているかどうか聞く。慌ててSuicaを取り出して読み取り部にタッチしてランプの色が緑に変わることもあるが、いまだお試し期間が続いていると思い込んでいる人もいる。アテンダントさんが、車内グリーン料金を払いますか? 普通車に移動しますか? と糺(ただ)す。有無を言わさず料金を請求しないところは優しい。見た限りでは、ほぼ全員が普通車に移動していた。
神田駅、御茶ノ水駅では乗り降りがなく、四ツ谷駅で1人、新宿駅では4人ほど乗車。大きなスーツケースを持った外国人カップルは、アテンダントさんにグリーン券の有無を聞かれると、普通車に移動していった。まだまだ不慣れな人が少なくないのでアテンダントさんも忙しそうだ。
車内ではドリンクやグッズなどを販売
中野駅を発車すると、アテンダントさんが車内販売にやってきた。ペットボトルや缶コーヒー、缶ビールなどをバスケットに入れている。2階建て車両は階段しかないので新幹線のようにワゴンは使えない。バスケットを持って歩くのは結構、重労働だ。中央線快速・青梅線グリーン車サービス開始記念グッズを売っていると聞いていたので、付箋とマスキングテープを購入。せいぜい2つで1000円程度かと思ったら合計で2000円とは高い。記念のボールペンは買うのを止めた。
特快なので中野駅の次は三鷹駅までノンストップ。この区間での乗車率が1番高かった。三鷹駅で初めて降りる人がいた。お試し期間中のような短距離乗車は皆無だ。もっとも、その人はSuicaを天井の読み取り部にタッチしていたから、各駅停車に乗り換えて武蔵小金井駅あたりまで行くようだ。同じ方向に向かう列車なら追加料金なしで乗り換え可能だ。くれぐれも降りる前にタッチするのをお忘れなく。
東京郊外から山梨県の山岳地帯へ
ホームが大混雑していた立川駅でも乗り降りがあり、電車は多摩川を渡って八王子方面へ。立川駅を出ると、日野駅、豊田駅、八王子駅と各駅に停車していく。高尾駅で「電車特定区間」(昔の国電区間)が終わり、列車区間へ。車窓には山々が迫る。トンネルが連続し、これまでの都市近郊区間とはがらりと異なり、旅気分に浸れる。ロングシートの普通車だったらこのあたりを走っていても日常の延長だが、クロスシートのグリーン車ならではの雰囲気だ。各駅に停車するものの駅間距離が長いので、通勤電車の各駅停車のようなイライラする気分にはならない。
ずっと座り続けるのもつらいので気分転換にトイレへ。洗面所もゴミ箱もお試し期間とは違ってフル稼働だ。そういえば、車内でWi-Fiも使えるのは有り難い。かなりの高度で桂川を豪快に渡ると、猿橋駅に停車。そして終点・大月駅に着く。
東京駅から1時間40分ほどのミニトリップは終わった。最後は2階席に5人ほどしか乗っていなかったので、大月駅も閑散としているかと思いきや、隣の普通車から大勢のインバウンド旅行客がスーツケースをころがしつつホームに降り立ち大混雑。ほぼ全員が富士急行線に乗り換えて富士山を見に行くようだ。改めて富士山が外国人に大人気なのを実感した。
Suicaグリーン料金およびおトクな乗車方法
ところでSuicaグリーン料金は、中央線の場合、東京駅から西八王子駅までが750円(50kmまで)、大月駅までは1000円(100kmまで)。紙のきっぷや車内でアテンダントさんから購入すると1010円(50kmまで)、1260円(100kmまで)となる。もちろん、乗車券は別途必要(東京駅〜大月駅=1520円)。私鉄の有料座席指定列車(京王ライナーなど)に比べると割高だし(京王ライナーは、新宿駅〜京王八王子駅=410円)、チケットレス(トク割)を使って特急「かいじ」に乗れば新宿から大月まで660円で乗れる。しかも、座席指定なので、全席自由席の普通列車グリーン車のような満席なら座れないという不安は皆無だ。もっとも、普通列車グリーン車はJRE POINTを貯めれば600ポイントで1乗車できる。あるいは、JRE BANKに預金していると、諸条件をクリアすれば、年間最大4枚まで普通列車グリーン券がプレゼントされる。各自の状況にあわせて賢く乗車して、時には混雑した満員電車を避けて優雅に過ごしてみたい。
この記事の筆者:野田隆
名古屋市生まれ。生家の近くを走っていた中央西線のSL「D51」を見て育ったことから、鉄道ファン歴が始まる。早稲田大学大学院修了後、高校で語学を教える傍ら、ヨーロッパの鉄道旅行を楽しみ、『ヨーロッパ鉄道と音楽の旅』(近代文芸社)を出版。その後、守備範囲を国内にも広げ、2010年3月で教員を退職。旅行作家として活躍中。近著に『シニア鉄道旅の魅力』『にっぽんの鉄道150年』(共に平凡社新書)がある。(文:野田 隆)