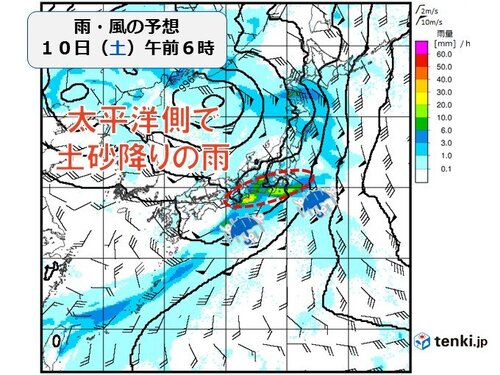「土砂・洪水氾濫」ハザードマップを全国整備へ…高リスク流域、数千か所の可能性
2025年5月20日(火)5時0分 読売新聞
昨年の能登半島豪雨では大量の土砂や泥水が流木と共に氾濫した(昨年9月22日、石川県輪島市町野町で)=武山克彦撮影
国土交通省は、土砂と泥水が一体となって氾濫する「土砂・洪水氾濫」に対応したハザードマップを全国で整備する方針を固めた。昨年の能登半島豪雨でも発生するなど、気候変動の影響で近年頻発化しており、発生リスクの高い流域は全国で数千に上る可能性がある。同省は今年度から特に危険な流域を優先し、自治体と連携してハザードマップの整備を進める。
土砂・洪水氾濫は、急激な大雨により上流域で斜面崩壊や土石流が発生し、大量の土砂が下流まで流されて
死者が16人に上った昨年9月の能登半島豪雨では、石川県輪島市などで土砂・洪水氾濫が発生。同1月の能登半島地震で崩れて斜面に残っていた土砂や木が雨で流され、下流の橋をせき止めるなどして土砂や泥水が氾濫。集落になだれ込み、人的被害も出た。
国交省によると、土砂・洪水氾濫は2000年代前半から増加傾向にある。気候変動による短時間の降水量の増加や森林の荒廃により、土石流や流木が発生しやすくなっているのが要因で、近年は18年の西日本豪雨や19年の台風19号などでも起きている。
国交省は22年、土砂・洪水氾濫のハード対策を進めるため、リスクが高い流域の抽出調査に着手。▽流域面積が3平方キロ以上▽発生が見込まれる土砂量10万立方メートル以上——と定義し、各都道府県に26年度までに抽出するよう求めている。
読売新聞が各都道府県に今年4月時点の抽出状況を取材した結果、11都府県(青森、宮城、秋田、東京、長野、愛知、奈良、大阪、和歌山、高知、熊本)で抽出が進み、計1092流域に上った。最多は長野県の290で、宮城県180、熊本県163、和歌山県150と続く。残りの道府県は調査前・中で、国交省は最終的に流域数は全国で数千に上るとみている。
国交省は、発生リスクが高まっている状況を受け、ハード対策に加えてハザードマップの整備も進めることにした。今年度中に自治体向けの手引の作成を始めるとともに、土砂や流木がたまりやすい形状の橋があるなど、特に危険性の高い50河川を優先し、土砂・洪水氾濫による想定浸水域のシミュレーションを35年までに行う。その結果を流域自治体が作成するハザードマップに反映させ、住民への啓発や避難対策に生かす。
被災自治体、ダムなどハード整備急ぐ
気象災害が激甚化する中、土砂と泥水が一体となって氾濫する「土砂・洪水氾濫」が各地で相次ぎ、甚大な被害をもたらしている。昨年9月に豪雨に見舞われた石川県輪島市町野町は、8か月近くたった今も被災の爪痕が深く残り、復旧の足かせとなっている。
「家財が全てだめになり、悪い夢だとしか思えなかった」。町野町寺地地区に暮らしていた
自宅は土砂の片付けが終わらず、公費解体の見通しは立っていない。「再び大雨に見舞われるかもしれない」との不安は拭えず、自宅を再建せずに市の災害公営住宅に入ることを検討しているという。
能登半島の被災地は、地震と豪雨で地盤が弱った状態が続く。国交省北陸地方整備局や県は、6月の出水期を前に、寺地川を含む3河川で仮設の砂防ダムや流木を止めるワイヤネットの整備を急いでいる。
各都道府県で発生リスクが高い流域の抽出が進む中、過去に被災した自治体などは対策に動き出している。
宮城県は昨年度、抽出された180流域のうち、過去に土砂崩れや土石流が発生した4流域を優先し、ダムの設置などを進める計画を策定した。2019年の台風19号では県内で土砂・洪水氾濫が発生し、道路などに土砂や流木がたまって救助活動も難航した。県防災砂防課の担当者は「過去に崩れたことのある箇所は再発しやすく、早急に対応したい」と話す。
砂防・地すべり技術センターの小山内信智・研究顧問は「土砂・洪水氾濫は土砂が何度も下流に押し寄せ、被害が大きくなる。ハード整備に加え、ハザードマップに基づき住民への周知や警戒・避難対策も進めていくべきだ」と指摘する。