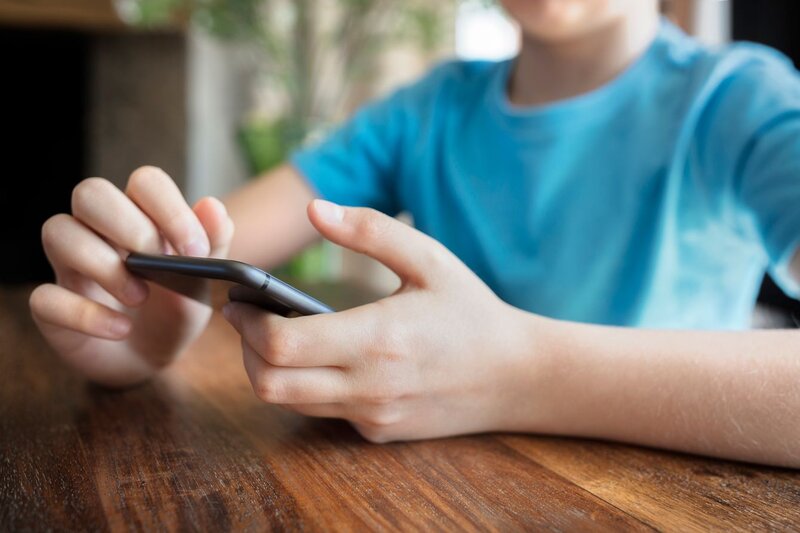スマホ依存の子どもに「いい加減にやめなさい!」は逆効果…正しいしつけができる親の声かけ
2025年3月8日(土)18時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/BrianAJackson
※本稿は、下村弥沙妃『3日で自発的に動く子になる!信頼声かけ』(Gakken)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/BrianAJackson
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/BrianAJackson
■ゲームやスマホを敵ではなく味方にする
ゲームやスマートフォン(以降、スマホと記す)の問題。近年の子育てお悩み件数のトップ3に入ります。
今やすっかり生活に密着し、持ち始める時期の平均年齢も年々低年齢化しているようです。
では、いつから持たせていいの? 一日何分までなら使わせていいの?
ゲームやスマホに関するお悩みは後を絶ちません。私たち親世代が、子どものころとは違う生活環境にどう対応したらいいか分からない、というのが本当のところでしょう。
ここでは、そんなゲームやスマホに関する子どもとの関わり方を考えていきます。
まず、ゲームやスマホに関しては、「賢く利用する道具」として捉えるようにしましょう。
「悪」と頭ごなしに決めつけて、遠ざけようとしていませんか? 確かに、使い過ぎると様々な悪影響を与える研究結果もありますので、子どもが自由に好きなだけ使うことは見過ごすことはできません。
でもこれは、ゲームやスマホに限ったことでしょうか? 例えば嗜好品や食事や趣味なども同じですが、何事も適度にバランスよく取り入れれば、体や心の健康に大いに役立ち、暮らしを豊かなものにしてくれます。ですから、快適な生活を彩る道具として扱うことが大切ですよね。
ゲームやスマホも同じです。生活を快適なものにする道具として扱い、さらには正しく使う「責任」を学んでいくものとして、子どもと根気よく関わっていきましょう。
■親が怒ると不信感や不満が増えるだけ
ケース1:長時間ゲームをする(スマホを使う)子どもへの声かけ
一旦、ゲームやスマホを手にすると、制限なく使い続ける子ども。夢中になって使っている様子を見ると、中毒になるのではないか。または、中毒に既になってしまっているのではないかと、心配になる親も多いのではないでしょうか? この心配こそ、ゲームやスマホを子どもから遠ざけようとする原因の一つでしょう。
×「いい加減にやめなさい!」
×「ゲームばかりしてないで勉強しなさい!」
使い続けてやめる気配がない様子を見ていると、こうも言いたくなりますよね。中には、何度言ってもやめないから、取り上げてしまうという方もいらっしゃるでしょう。
でもその前に、一旦冷静になってください。ゲームやスマホに夢中になっている時に、突然こんなふうに怒られたり取り上げられたりしたら、子どもはどんな反応をするでしょうか?
きっと、親への不信感や不満が募ってしまうと思いませんか? そうなってしまっては、良い親子関係を築くのは難しくなってしまい、この問題を効果的に解決することも困難になってしまいます。
写真=iStock.com/andreswd
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/andreswd
■自分をコントロールするきっかけにする
そこで、次のような声かけをしてみましょう。
○「どのくらいゲームをしたら(スマホを使ったら)満足できそう?」
これまでの親の対応や、学校での学びから(最近の学校では、教育がなされていることがほとんどです)、長時間ゲームやスマホを使うことが良くないということを、子どもは分かっています。
それでも長時間使い続けてしまうのは、自分をコントロールできない未熟さ故なのです。
だからこそ、ゲームやスマホを「自分をコントロールするトレーニングの道具」として利用していきましょう! その取り掛かりとして、この声かけはとても効果的です。
■罰を与える=子どもの自己肯定感を下げる
ケース2:約束の時間を過ぎてもゲーム(スマホ)をやめない子どもへの声かけ
ゲームやスマホを与える時に、使い過ぎを防ぐためにルールを決めているご家庭も多いのではないでしょうか。「平日は○時間まで」「宿題が終わったら○分まで」など、その内容はご家庭によって様々でしょう。
しかしルールを決めたにもかかわらず、約束の時間を守らない子ども。その様子を見ていると、親としてはガッカリするやら、怒りを覚えるやら……。対応に困ってしまいますよね。
むしろ、こんな時こそスマホやゲームを「社会性を身に付ける道具」として活用していきましょう!
×「約束を守れなかったから、今日から禁止ね」
約束を守れなかったのだから、当然のしつけとして、ゲームやスマホを取り上げるという方もいらっしゃるでしょう。
でもこの対応は、子どもに罰を与えることになります。これって、とても危険‼ なぜなら、この対応の奥に隠されているメッセージが、子どもの自己肯定感をひどく下げてしまう可能性があるからです。
■罰としつけの決定的な違いとは
そのメッセージとは、「あなたは罰を受けるに値する人間なのだ」という、人間としての価値を落としてしまう内容。あなたの気持ちの中に、しつけと罰が混同していませんか?
では、どう対応したらいいのでしょうか?
○「残念だけど、1週間ゲーム(スマホ)を預かるね。1週間経ったら、また正しく使えるか試してみようね」
この対応は、子どもからゲームやスマホを離すという点では同じですが、先の×の対応とは隠されているメッセージが全く違います。
そのメッセージとは、「今は正しく使えなかったけど、1週間後のあなたならきっと正しく使えるって信じているから」という、成長への期待を感じさせること。
さらに、「残念だけど」と付け加えることで、子どもに罰を与えることなく寄り添う姿勢を示しています。
これこそが、罰としつけの大きな違いなのです。
■子どもが高額課金をしてしまう理由
ケース3:課金したがる子どもへの声かけ
高いお金を払って手に入れたゲームやスマホに、更に課金だなんて……。私たち親が子どもだったころにはなかった、新しい文化(?)に戸惑い、一種の恐怖を覚える親もいらっしゃるのではないでしょうか。
課金をすることで怖いことが起きるのではないか。そもそも、その必要性が全く理解できない。そう思ってしまうことも多いでしょう。その気持ちから、頭ごなしに「ダメ!」と禁止してしまうのも分かります。
でも、頭ごなしに否定されたと子どもが感じてしまったら、正しいしつけにつなげることができないのは、よく考えれば気づくことでしょう。
×「課金はいけません」
こんな対応をされる方もいらっしゃることでしょう。
でも、子どもが課金をしたがるということは、そこに何かしらの価値を感じているという証拠。課金をする・しないの前に、その気持ちにまずは寄り添ってあげましょう。その上でこそ、効果的な話し合いが成立するのです。
写真=iStock.com/kwanchaichaiudom
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kwanchaichaiudom
■親子で本音を話し合ったうえでルールを決める
○「あなたにとっては価値のあるお金の使い方なの?」
この声かけは、子どもの気持ちに寄り添っています。きっと子どもは嬉しくなって、「うん、そうなんだ」と素直に答えることでしょう。
そう答えてきたら、むしろチャンス。「どんなところに価値を感じるの?」「課金することで、どんな良いことがあるの?」と、続けて質問してみましょう。
さて、子どもはなんて答えるでしょう? この会話こそが、親子の価値観を確認し合い、信頼関係の構築につながるのです。
この場合、親子で価値観が違っても良いのです。大切なのは、親子で本音を話し合えるという信頼関係を築くことなのですから。
その話し合いの結果、課金をするかしないか、どの程度課金をするかを決めていけば良いのです。
■「夜中までスマホ」を防ぐ声かけ
ケース4:ベッドにゲームやスマホを持ち込んで夜中まで使う子どもへの声かけ
ベッドにゲームやスマホを持ち込んでまで夢中になって、夜中まで使い続ける子ども。そんな姿を見ていると、直ちに「何とかしなくては」「厳しく注意しなくては」と、親としての責任感から厳しくしつけようとする方もいらっしゃることでしょう。
確かに、ベッドに持ち込んでまでダラダラと使い続けることは、健全とは言い難い状況です。だからこそ、子どもには効果的で正しいしつけが必要となります。
×「ベッドにゲーム(スマホ)を持ち込んではいけません」
当然、こんな声かけをする方も多いのではないでしょうか? それの何がいけないのか? と思われますよね。
実は子どもに限らず私たち人間は、内容にかかわらず否定されると、無意識に相手を「敵」とみなしてしまう本能に近い習性があります。内容にかかわらず、というところがポイントです。
下村弥沙妃『3日で自発的に動く子になる!信頼声かけ』(Gakken)
どんなに親が正しいことを言っても「敵」とみなされてしまえば当然、穏やかな話し合いや効果的なしつけはできませんよね。そこで、こんな声かけをしてみましょう。
○「家族みんなでゲーム(スマホ)の置き場所を決めて、使わない時はそこに置いておこうね」
これには、効果的なしつけにつながるポイントが二つあります。
一つは、子どもを否定していないので、敵とみなされることなく話し合いができること。もう一つは、子どもの正しい行動に対する信頼です。信頼された子どもは、当然それに応えようとします。まずはそんな信頼を伝えることから、正しいしつけはスタートするのです。
----------
下村 弥沙妃(しもむら・みさき)
小児科看護師、育児アドバイザー
1977年、三重県生まれ。看護学校卒業後、大学病院の小児科病棟へ就職。理想の育児を徹底的に学ぶべく数々の資格を取得し、2011年より自己肯定感を高める育児セミナー、カウンセリング、育児相談を開始。評判を呼び、ロコミだけで最長2年半待ちのセミナーとなる。2020年に長男がエレクトーンと両立しながら1年で灘中学に合格し、次男も難関校の滝中学に合格。現在までに、育児セミナー、個人セッションのほか、公立中学校PTA研修講師、公立小学校特別授業講師、児童発達支援事業所専属心理士など1万人以上の心身の健康をサポートしている。メディア出演も多数。株式会社マインドプラスアカデミーode代表取締役、一般社団法人保育福祉サポート協会統括主任、児童発達支援管理責任者(R4年基礎研修)、強度行動障害支援者、チャイルドマインダー、メンタルトレーナー、HSPカウンセラー、食育インストラクターほか。
----------
(小児科看護師、育児アドバイザー 下村 弥沙妃)