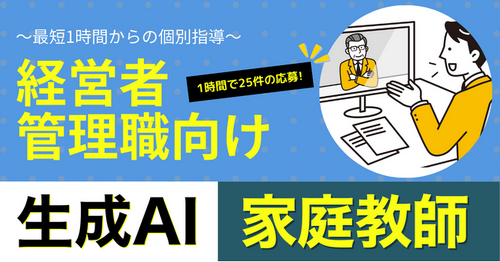体育会系熱血教師なみにタチが悪い…書類が作れない、授業が下手な"デキない50代教師"がウヨウヨいるワケ
2025年4月12日(土)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
※本稿は、静岡の元教師すぎやま『教師の本音 生徒には言えない先生の裏側』(SB新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/maroke
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
■学校をダメにする教師
教師を主人公にしたドラマは昔から人気があります。
そんな学園ドラマに出てくる主人公は、ほとんどがいわゆる『熱血教師』。生徒のためならわき目もふらずに突っ走り、ときには保身しか頭にないような校長やイヤミな教頭と衝突することも辞さないようなタイプ(教頭は学校で一番大変な仕事なのにドラマではだいたい悪役なので可哀想です(笑))。
そして、そういうドラマに憧れて教師になったという人も少なくないと思います。
実際の現場には今も、いわゆる『熱血教師』は一定数存在します。いつもクラスの中心にいて、体育祭の時には先頭に立ってクラスを盛り上げ、部活もバリバリやって、時には本気で生徒とぶつかり合っていくような。
しかし、私は正直、そういう熱血教師があまり好きではありません。同じように思っている先生は少なからずいると思います。
なぜなら、熱血教師が今の学校で求められている学びのあり方と、対極に位置する存在だからです。
今の学校での教育観では、主役はあくまで子どもたち。ところが熱血教師のドラマでは、主人公は先生です。子どもたちを導くヒーローとして描かれています。熱い想いで生徒を導く立派な先生と、愚かで、ときに道を踏み外してしまう生徒たち、という図式です。
昭和から平成の前半にかけては、たしかにそういう図式が明確にありました。
当時は今と違って、大人と子どもが得られる情報量には絶対的な格差があったからです。圧倒的知識量を持っている人生の先輩と、まだ何も知らない子どもたち。その頃にはそういう力関係が、たしかに存在していたと思います。
でも今の時代は、学びの主役は子どもです。
教師には教え込んだり、やらせたりするのではなく、生徒が主体的に学び、自ら問題を解決していけるように授業を設計し、伴走し、場をコーディネートするような役割を求められているのです。
ところが熱血教師はこの真逆。自分が先頭に立って生徒を引っ張り、生徒の意見よりも自分が言いたいことを言うタイプです。
■自分が主役になってしまう
熱血教師は、自分が主役です。目立ちたがり屋なので、集会や行事の時にはドンドン前に出て、冗談を言ったりして生徒のウケを狙います。
生徒は先生の熱気に当てられて、なんとなく学んだような気にさせられてしまうかもしれません。先生が自分たちのことを思ってくれていて、熱心にやってくれているように思うかもしれません。
熱血先生が一生面倒を見てくれるならそれでもいいかもしれません。でも生徒は3年後には巣立っていくのです。熱血先生という強烈なリーダーに寄りかかって育った生徒たちは、それから何を支えに生きていけばいいのでしょう?
私が見てきた中で尊敬できるなと思った先生は、そんな派手なパフォーマンスをしたり、下らないダジャレで生徒の人気を取ったりはしません。
丁寧に事前指導をし、大事な場面では、生徒が前面に出て、自分でできるように育てる。それを教室の後ろから微笑みながら見守っている。そういう先生こそ本物の教師だと思うのです。
■実はけっこういる「仕事ができない教師」
そして、熱血教師よりももっとタチが悪いのが『仕事ができない教師』です。
たとえば、Excelの使い方がわからない、書類の提出期限を守れないなど。それ以前に、書類をちゃんと作れず、適当な書類を作って出してくる人もいます。
教員は「授業案(指導案)」というのを書きます。企業での企画書と同じようなものです。
これは書式が特殊だったり、書き方が面倒だったりという問題もたしかにあります。それで、中には「授業案なんて必要ない」「そんなの書かなくても授業はできる」と言う人もいます。
いやそういう主張をする前に、書式というのはルールなのでちゃんと守るべきだし、それ以前に日本語も支離滅裂、内容もスッカスカな人も多いのです。こんなの民間では通用しませんよね。私は今、企業からSNSコンサルティングのご依頼をよくいただくのですが、もし「企画書なんて書けません」とか「アイデアは頭の中にあります」なんて言ったら、どこも取引してくれないでしょう。
私は20代の頃から『研修主任』という役に任命されることがたびたびありました。それで、全職員の授業案をチェックするのですが、もうビックリするような出来で出してくる人がいます。20代の私が50代の先生の授業案に赤ペンを入れて、真っ赤にして返すのです。
それも内容の問題というより、「目標が書いてありません」とか「整合性がとれていません」みたいな授業以前の問題ばかりなのです。
さらにそういう先生は「授業案なんて手間がかかるだけだから書く意味がない」と豪語するのですが、そういう割に授業がうまいわけでもないので困ります。
生徒との関係作りが下手な先生もたくさんいます。しょっちゅう生徒とトラブルになってしまうような先生です。中には、言ってはいけないようなことをすぐに言ってしまったり、突発的に叩いてしまうようなタイプもいます。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
■「ダメな先生」も現場に居続けてしまう
周囲の先生方は「またあの先生か……」と思いながら、なんとかフォローしようとするのですが、生徒からしたらそんなこと関係ありません。あっという間にすぐに授業崩壊してしまいます。
残念なことにそういう先生が、実はけっこういるのです。授業も下手、生徒との接し方も下手、担任も持たせられない、部活の顧問も任せられないという先生もいます。
民間企業だと、ちょっと考えにくい話かもしれません。場合によっては閑職に追いやられて給料を下げられたり、『追い出し部屋』みたいなところに追いやられたりして、ジワジワと退職に追い込んでいくような案件です。
でもダメな先生は、周りに配慮されながら現場に居続けます。
なぜかというと、まず教員は公務員なので、簡単にクビを切れないから。クビを切れないどころか、給料を下げて締め上げることもできないのです。むしろそれでも年と共に給料は上がり続けます。
辞めさせることができないので、現場としてはある意味それを『守る』ような状態にならざるを得ません。そういう先生をそのまま放置しておくと、授業が崩壊し、それがキッカケで学級が崩壊し、最終的には学校全体が荒れることになるから。
なるべくボロが出ないように、仕事を極力減らしたり、授業数を減らしたりして、その分は他の先生がカバーすることになります。
その結果、仕事ができる先生のところに仕事が集中し、がんばっている人が割を食うような形になってしまうのです。
特に、『仕事をしない教師』のシワ寄せが『できる若手』にいってしまうケースがよくあります。そのため、周囲から『できる若手』と思われているような、がんばっている先生から心を病んでいくのが実情です。
今も他の教員の倍ぐらいの事務を背負って毎日朝早くから夜遅くまで必死にがんばっている若い先生がたくさんいます。そういう先生が学校を回しているのです。
■バブル世代の教師問題
こういう話をすると「差別だ」「偏見だ」と言われることがあるので、とても言いにくいのですが、『仕事ができない教師』として、現場で特に問題視されがちな世代があります。それはいわゆる『新人類世代』『バブル世代』と呼ばれる世代(1955〜70年ごろの生まれ)の人たちです。
その世代の先生方は『でもしか先生』などと、現場でも陰で囁(ささや)かれていることもありました。「教師にでもなるか」「教師にしかなれない」人たちという意味。
最近は『ジェネレーションハラスメント』という言葉があり、世代を一括りにして批判すると怒られてしまうこともあるのですが、これは私が実際に現場で何度か耳にした話として聞いてください。
■働かない中高年教員を数少ない中堅教員が支える
1970年代後半〜80年代、日本はもっとも経済成長し、好景気に沸いた時代でした。
その時代、世の男性たちの間では「商社に勤めてバリバリ稼いだ男が勝ち組。公務員や教師になるような奴は負け組」というような風潮があったのです。
だからあの時代に教師になった人たちの中には、半ば仕方なく教師になった人たちも多い、という話は教師の間でもよく聞く話でした。
実際、当時の教員採用試験の倍率を見てみると、教員不足のここ数年と同じぐらいの水準と、低迷しています。
出典=文部科学省「令和6年度(令和5年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント」のデータを基にSBクリエイティブ株式会社が作成[静岡の元教師すぎやま『教師の本音 生徒には言えない先生の裏側』(SB新書)より]
私が現場で見てきた中でも、この世代は極端に志が低かったり、仕事ができなかったりする人が多かった印象を個人的には持っています。もちろん、ものすごく仕事ができる人もたくさんいましたし、尊敬できる優秀な先生もたくさんいましたが……。
しかも、とても厄介なのはこの世代の教員はとにかく多い!
文部科学省が発表している教員の年齢構成を見ると、明らかに世代による教員数に偏りがあることが如実にわかります。2013年(平成25年)時点で59歳(1954年生まれ)〜49歳(1964年生まれ)の人たちだけ突出しているのです。
逆にガクッと凹んでいるところが私の世代、いわゆるロスジェネ世代・就職氷河期世代です。ロスジェネというのはロストジェネレーションの略で、失われた世代という意味。就職難のせいでどこの職場でも少ない、今40代前後の世代のことをいいます。
そのせいで、「職場の半分は50代、30代は私1人」みたいな時もあったくらいです。
静岡の元教師すぎやま『教師の本音 生徒には言えない先生の裏側』(SB新書)より
このアンバランスさのせいで、働かない中高年教員を、数少ない中堅教員が支えるという歪みの原因になってしまっているわけです。
一方で今の若い先生たちは、逆に熱意のある人が多いように思います。
今、世間では教師という職業に対してネガティブなイメージが広まっていますよね。そんな中であえて教育の世界に入ってきたような人たちです。とんでもない情弱(情報弱者)か、逆にものすごく志の高い人か、どちらかなのでしょう(笑)。
実際、現場でも一生懸命働いてくれ、仕事の覚えもよく、生徒からも好かれる先生が多かったように感じています。
■“体育会文化”の悪影響
私が熱血教師と並んで、今の学校教育に悪影響を与えていると考えているのが『体育会系文化』です。
体育会系の先生の発言力が大きいというのは、どこの学校でも普通に見られます。
地域による違いはあるとは思いますが、たとえば野球部の先生の人事が優先的に決められる地域があります(明文化はされていませんが、地域の教員はみんな理解していることです)。
夏の高校野球に見られるように、野球は学校だけでなく地域を挙げて応援するようなスポーツです。もしも野球強豪校に野球ができる先生が赴任しなかったなんて事態になったら、地域の野球部OBみたいな人から教育委員会にものすごいクレームが入ります。
そのため、野球部がある学校には必ず野球ができる先生が配属されます。
逆に、学校に卓球ができる先生がいない、バスケ部があるけど顧問はバスケ経験者じゃない、ということはよくあるのですが、野球部ではそのようなことはほぼありません。
校長も、運動部の顧問で毎年成果を出して、中体連の支部長を経験して、たたき上げで校長になった、という人が少なくありません。そういう校長は体育会系の教師、部活をがんばっている教師が大好きです。
運動会や応援合戦、組体操も、体育会文化の最たるものです。整然と並んで入場行進する姿は、日本人からすると清々しいかもしれませんが、外国出身の生徒の中にはすごく嫌がる子もいます。「こんなのやるのは軍隊だけだ」と言うのです。
日本人は、小学生からの教育ですっかりこういうのに慣れてしまっていると思いますが、日本の学校は学校全体に、体育会系文化、軍隊的なノリがかなりあります。たしかに、外からは異様に見えるでしょう。
■飲み会の締めで校歌を歌う
私は学生時代、大の運動嫌いで、ゲイだからかもしれませんが、男臭く「オー!」みたいな声を出すのもどうしても苦手でした。だから、自分が子どもの頃から、そして、教員になってからも、ずっとこの体育会系文化には疑問を持っています。
そして、そのような体育会系のノリは、実は学校内に限りません。これはどうやら私が働いていた県限定らしいのですが、教員の飲み会の最後に『エール』をやるのです(笑)。
「フレー、フレー、○○中!」みたいなやつ。
静岡の元教師すぎやま『教師の本音 生徒には言えない先生の裏側』(SB新書)
若手教員が前に立って音頭をとってみんなで「フレーフレー」と言わされるのです。そして最後はみんなで肩を組んで校歌斉唱となります。
戦前のバンカラ大学生みたいなノリです。教員になったとき、「こんな世界なんだ……」と、衝撃を受けたのを覚えています。
私は、そのノリがもう本当にイヤで「もうやりたくない、やるんだったら飲み会は出ません」と言ったことがあるのですが、すると生徒指導主事の体育の先生と学年主任の先生に応接室に呼び出されて、2人がかりで説得をされたんです。「すぎやまさんがやってくれなかったら誰がやるの⁉」と。
いや、誰もやらなくて結構です。
----------
静岡の元教師すぎやま(しずおかのもときょうしすぎやま)
YouTuber、TikToker、LGBTQ、教育評論家
静岡県掛川市出身。10年以上中学校教諭として勤務したのちに、2018年に退職。現在は先生のホンネ、学校のウラ側を解説するインフルエンサーとして活動中。現在総フォロワー数70万人超。フォロワーの多くは中高生で、若者心理やSNS文化に詳しい教育者として、自己啓発、SNSなどのテーマで、執筆・講演を行っている。2021年には「ゲイ」であることをカミングアウト。LGBTQの啓発活動として、講演会や企業向け研修会なども行っている。2024年に不登校生徒向けのオンラインのフリースクール「新時代スクール」を創設。クラウドファンディングで応援を募り、支援総額780万円超を達成。著書に『教師の本音 生徒には言えない先生の裏側』。
----------
(YouTuber、TikToker、LGBTQ、教育評論家 静岡の元教師すぎやま)