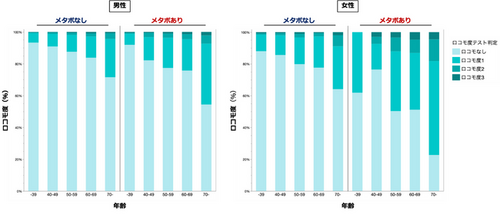【積水化学グループ】自然の知恵を技術に—コンクリーションが支える持続可能な社会「自然に学ぶものづくり研究助成プログラム」後編
2025年4月17日(木)10時0分 PR TIMES STORY

前編で紹介した「自然に学ぶものづくり研究助成プログラム」は、技術革新と社会実装を両立する意欲的な研究を支援してきた。自然界に存在する生物の構造や機能、プロセスを模倣し、技術や製品の開発に応用するアプローチ「バイオミミクリー」は、持続可能な技術開発の分野で注目されている。
しかし、積水化学の本プログラムは、単なる模倣にとどまらず、自然の仕組みを科学的に解明し、新たな材料や技術の創出につなげることを目指している。その中でも、名古屋大学・吉田英一教授が研究する「コンクリーション」は、持続可能な建築・インフラ分野に革新をもたらす可能性を秘めた技術の一つだ。
コンクリーションとは、自然が生み出す極めて硬い岩石構造のこと。数万年以上もの長い年月をかけて形成されると従来考えられてきたが、吉田教授はそのメカニズムを解明し、短期間での生成を可能にする技術を研究している。本プログラムを起点に始まったこの研究は、基礎科学の探究から産業への応用に踏み出しつつある。
吉田教授と、プログラムの運営を担う積水インテグレーテッドリサーチの中嶋節男、大石大祐が、コンクリーションの技術的意義と社会実装の可能性を語る。
自然のプロセスを応用し、長寿命の材料を探っていく

恐竜やアンモナイトの化石が並ぶ、名古屋大学博物館。地質学に関する標本も豊富で、岩石や鉱物の標本も数多い。その一角で、館長の吉田英一教授が球状の塊を手に取る。一見すると化石のようだが、吉田教授は「これがコンクリーションと呼ばれるものです」と説明する。
「コンクリーションは炭酸カルシウムが堆積し、岩のように硬く形成される構造体で、地層の中から見つかります。多くの場合、化石を包み込むように形成され、極めて硬く、長期間劣化しません。いわば、天然のコンクリートともいえるものなのです」
コンクリーションの内部には、カニなどの生物が原形をとどめたまま残っていることもある。これは、スカベンジャー(死骸を食べる生物)によって死後食べ尽くされる前に硬化したことを示唆するものだ。研究では、直径数センチのコンクリーションは数週間、数十センチで数カ月、メートルサイズでも数年で形成されることが判明している。吉田教授は、「このメカニズムを応用できれば、これまでにないシーリング材、建材の開発につながると考えました」と研究の原点を振り返る。

左)約1600万年前のイワガニのコンクリーション(ジョージア)
右)名古屋港の浚渫(しゅんせつ)工事で発見された約7000年前のカニコンクリーション群
研究の発端は、核燃料サイクル機構(現 原子力研究開発機構)で放射性廃棄物の地層処分を研究していた吉田教授のキャリアにある。吉田教授はチェルノブイリ事故をきっかけに、より安定した封じ込め技術の必要性を痛感したという。
「放射性廃棄物の地下隔離では長期的な安全性が求められます。同様に、気候変動問題に対応するための二酸化炭素の地下貯留(CCS)でも、何世代にもわたる封じ込めが不可欠です。しかし、現在のセメント系をはじめとする封止材では、それを保証するのは容易ではありません。そこで、自然界で長期間安定して存在するコンクリーションに着目し、シーリング材としての可能性を探り始めました」

名古屋大学 吉田英一教授(名古屋大学博物館 館長)
コンクリーションは風化に強いのが特徴だ。コンクリートは水と反応し、時間とともに劣化していく。「道路の側溝などを見てもわかるように、コンクリートは数十年でひび割れが生じることがあります。産業革命以降、コンクリートは広く使われていますが、数百年〜1000年以上の長期的な安定性が保証されているわけではありません」と吉田教授は指摘する。
名古屋大学の研究チームはコンクリーションの形成メカニズムを解明し、短期間で人工的に生成する技術の開発を進めてきた。これはコンクリート、セメントの代替となる高耐久な建材の創出につながる可能性を秘めるものだ。
今後の社会実装に向けた展望について、本プログラムの事務局を務め、吉田教授に伴走しながら積水化学との共創を支えてきた積水インテグレーテッドリサーチの中嶋節男はこう語る。
「自然界で長い時間をかけて培われた仕組みを、短期間で応用する技術に発展させることができれば、建築・インフラ分野にとどまらず、幅広い分野への展開が期待されます。自然の知恵を生かした材料開発が、持続可能な社会づくりに貢献する。その一歩を、この研究が切り拓こうとしているのです」

積水インテグレーテッドリサーチ 取締役 中嶋節男
自然が生んだ強靭な素材─コンクリーションの可能性を探る
コンクリーション技術は、長期的な封じ込め技術として期待されてきたものだ。当初は、放射性廃棄物の隔離や二酸化炭素の地下貯留といった用途での活用が検討されていた。しかし、それにとどまらず、耐久性や自己修復機能を生かし、インフラの維持管理や長寿命化、環境負荷低減といった領域へと応用の幅を広げている。こうした特性を生かすことで、建築・土木分野の課題解決に貢献できる可能性がある。
こうした特性を検証するため、地下350メートルのトンネルで実証実験が行われた。実験中、マグニチュード5.4をはじめとする11回もの直下型地震が発生し、実験中の地下岩盤を揺らした。地震によるコンクリーション化効果を確認できる千載一遇の機会だと言える。通常、地震による揺れによって岩盤中には新たな割れ目が生じ、シーリングが損なわれる。しかし、コンクリーションは地震後も再形成を続け、シーリング機能を維持することが確認された。
「地震などの外的要因によるダメージを受けた後でも、コンクリーションが自ら再形成し、シーリング機能を維持できることが、今回の実証実験で確認されました。これは、日本のような地震の頻発する地下岩盤でも長期的な封じ込めが可能であることを示す重要な成果です」と、吉田教授は手応えを語る。この成果は、英国の科学雑誌ネイチャーの電子版にも掲載された。
実用化に向け、研究チームは液体タイプとパウダータイプの2種類のコンクリーション化剤を開発。それぞれ異なる用途に適用できることが分かってきた。
「最初に開発したのは液体タイプです。積水化学のエポキシ樹脂をベースにコンクリーション化のプロセスを組み込み、接着剤としての機能に加え、自己強化の仕組みを持たせました」と吉田教授。さらに、パウダー化によりセメントと混ぜて使用できるようになり、コンクリートのひび割れ修復や、グラウト材の浸透性向上など、新たな応用が期待されている。

コンクリーション化剤
今後の展開として、オーダーメイドのコンクリーション化剤の開発も視野に入る。「液体・パウダーそれぞれの特性を生かし、用途ごとに最適な配合を選択できる仕組みを構築することで、より幅広い分野での活用が進むでしょう」と、吉田教授は期待を寄せる。
社会実装に向けた動きも加速している。吉田教授は研究会を立ち上げ、ゼネコンや国の研究機関、大学など30以上の機関と連携。国内外の企業からの打診も増え、技術の市場適応が進んでいる。
積水化学と進める産学連携の取り組みについて、中嶋と共に伴走してきた大石は「事業として取り組む段階に入ったと感じています」と手応えを語る。
「コンクリーションの研究は、最初の3年間は実験データを積み上げるフェーズでしたが、ここ2年で実証結果がそろい、社内でも正式な研究テーマとして動き始めています。基礎研究から社会実装へのフェーズに入っていることは、『自然に学ぶものづくり研究助成プログラム』としても、大きな意義があります」
吉田教授は、これまでに蓄積した技術知見を積水化学と共有し、業界全体での標準化と普及に向けて連携している。次章では、本プログラムの役割と今後の展望を見ていく。

積水インテグレーテッドリサーチ 係長 大石大祐
研究から社会実装へ。「自然に学ぶものづくり研究助成プログラム」が支える挑戦
本プログラムは、基礎研究と実用化の橋渡しとして機能し、企業とアカデミアの協働による革新的な技術開発を推進してきた。吉田教授は、このプログラムが研究の発展に果たした役割を振り返る。
「企業の技術支援や異分野との連携を通じて、単なる学術研究にとどまらず、社会実装へとつなげる道が開けました。研究者だけでは実現できない規模のプロジェクトが動き出し、今では国内外のインフラ維持・補修技術への応用が進められています」
コンクリーション技術の可能性は、さらに多様な分野へと広がりつつある。トンネルや橋梁(きょうりょう)の補修、気候変動対策としての炭素貯留、さらには文化財の修復など、長期的な安定性が求められる領域での導入が期待されている。これらの社会課題に応えるため、積水化学との連携を通じて、品質保証や施工方法の確立、規格化といった技術の実用化が進められている。
「研究支援を受けるだけでなく、実際に社会へと送り出す。このプログラムは、研究者にとっても貴重な経験となりました」と吉田教授は語る。積水インテグレーテッドリサーチの中嶋もまた、その意義を強調する。
「技術の可能性を広げ、それを産業や社会の変革へとつなげていく。これこそが、企業が研究を支援する真の価値です。コンクリーション技術は、その最前線のケーススタディといえるでしょう」

ニュージーランド南島 約5000万年前の地層から産出した球状コンクリーションと吉田教授
これからの社会において、持続可能な技術革新はますます重要になっていく。その鍵を握るのは、既存の枠組みを超えた発想と、研究から実用化までを見据えた一貫した開発の推進にある。本プログラムは、研究者たちの基礎研究を支えながら、未来志向の技術開発へとつなげてきた。
コンクリーション技術は、長い年月をかけて自然が生み出した知恵を生かし、持続可能な社会の実現へと貢献する。その挑戦の先にあるのは、「壊れない」技術ではなく、「修復しながら進化する」未来だ。研究者、企業、社会が一体となり、新たな技術を育み、実装することで、持続可能なイノベーションが現実のものとなる。
積水化学の「自然に学ぶものづくり研究助成プログラム」は、これからも新たな技術を育み、社会に実装することで、持続可能な未来の創造を加速させていく。

【関連リンク】
【SEKISUI|Connect with】
https://www.sekisui.co.jp/connect/
⼈々の暮らしの多様な分野で積⽔化学の製品・技術がどのように活かされているのか。
その開発にはどんな想いや物語があり、それは地球に暮らす⼈々や社会とどのようにつながっていくのか。
「SEKISUI|Connect with」は、積⽔化学とつながる未来創造メディアです。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ