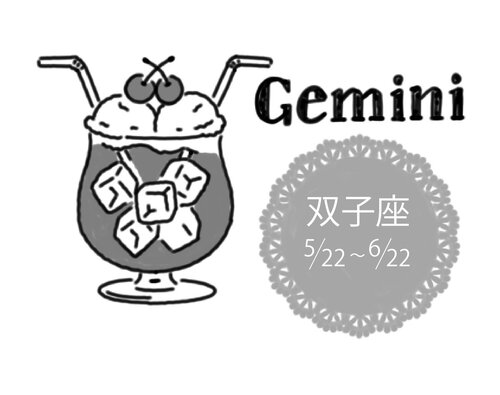「親ガチャの結果」は子供時代より40代に表れる…双子研究が明らかにした"年収と遺伝"の知られざる関係
2025年4月23日(水)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/TanyaJoy
※本稿は、冨島佑允『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』(アルク)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/TanyaJoy
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/TanyaJoy
■どこまでが遺伝で、どこまでが環境要因か
突然ですが、ここでちょっと自分の人生を振り返ってみてください。みなさんがこれまでに成し遂げてきたことのうち、何割くらいが生まれ持った能力によるもので、何割くらいが後天的な努力によるものだと思いますか?
当てずっぽうで構いませんので、比率を思い浮かべながら読み進めてみてください。今回は、遺伝と環境のどちらが人生にとって重要なのか、という話です。
人間の行動や特性のうち、どこまでが遺伝によるもので、どこまでが環境によるものであるかは、古くから議論されてきました。この問題は、「nature vs. nurture」というフレーズで広く知られています。nature(ネイチャー)とは、遺伝などによる生まれつきの特性であり、nurture(ニューチャー)は、親のしつけ、経験、勉強などの後天的な要素のことを指します。つまり、日本語でいえば「生まれか、育ちか」ということです。
「生まれか、育ちか」は、「遺伝か、環境か」と言い換えることができます。環境要因は、人が成長するなかで経験するすべてのことをいいます。これには、家庭環境、教育、社会的経験、文化、経済状況などが含まれます。
人間の人生においてnatureとnurtureのどちらの影響の方が大きいかという謎は、世界中の人々が興味を持つテーマです。ですから、それを調べるために、世界各地で「双子研究」がなされています。これはその名のとおり、双子を調べることで遺伝の影響を確かめる研究です。
■遺伝の影響は大きい
双子研究の歴史は意外に古く、19世紀にさかのぼります。世界で初めて双子研究を行ったのは、人類学者のフランシス・ゴルトンでした。ゴルトンは進化論で有名なチャールズ・ダーウィンの親戚にあたり、研究のきっかけもダーウィンが出版した『種の起源』に刺激を受けたことだとされています。
ちなみに、『種の起源』はダーウィンが進化論について記した本であり、今では歴史を変えた名著として知られています。先ほどの「nature vs. nurture」という言葉も、ゴルトンが生み出したものです。ゴルトンはまず、当時の有名人の血縁関係について調べることから研究をスタートしましたが、この方法で研究を深めるのには限界があると感じ、双子を使った研究に切り替えました。
ゴルトンの研究法は、多くの双子に質問表に答えてもらうというやり方でした。1875年、その結果を「双子の研究」(The history of twins)という論文にまとめて発表し、遺伝の影響は環境の影響よりも大きいと結論づけています。
ゴルトンが双子分析を行っていた時代、実は遺伝の法則はまだ知られていませんでした。遺伝の法則である「メンデルの法則」が世間に認知されたのは1900年のことであり(メンデルは1865年にこの法則を発表したが注目されず、1900年に別の学者に再発見され日(ひ)の目(め)を見た)、ゴルトンの「双子の研究」の論文より25年も後のことでした。
■一卵性双生児を研究すると遺伝の影響がわかる
現代では、遺伝のしくみは詳細に解明されていて、双子分析は創始者であるゴルトンの時代よりも洗練されたものになっています。
ここで重要になるのが、一卵性双生児の研究です。一卵性双生児とは、もともと1つだった受精卵が2つに分裂して生まれた双子のことで、このタイプの双子は100%同じ遺伝情報を持っています。これに対して、二卵性双生児は2つの受精卵が同時に成長して双子として生まれてきたものなので、普通の兄弟姉妹と同じく、遺伝的な類似性は50%になります。こうした背景から、双子研究は遺伝と環境の影響を分けて考えるのに非常に有効な方法となっています。
例えば、遺伝子が100%同じである一卵性の双子が異なる環境で育った場合、彼らが示す性格や健康、能力の違いを調査することで、「環境」がどれだけ人間の発達に影響を与えるかを明らかにできます。同時に、同じ環境で育った二卵性双子のデータを比較することで、「遺伝」がどれだけ強い影響を持つのかを示すことができます。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
双子研究を行う際の基本的な方法には、大規模な調査や詳細なケーススタディがあります。「大規模調査」では、多くの双子を対象に、性格や能力、健康状態などのデータを広範囲にわたって収集します。これにより、統計的な手法を用いて遺伝と環境の影響を分析することができます。
一方、「ケーススタディ」では、特定の双子のペアを詳しく調べることで、個々の事例から深い洞察を得ることを目指します。これには、詳細なインタビューや心理テスト、場合によっては医学的な検査を行うことも含まれます。
■「遺伝ガチャ」はあながち無視できない
この研究法によって、多くのおもしろい発見がなされています。例えば、慶応義塾大学名誉教授の安藤寿康先生が行った研究(図表1)を見てみましょう。これは個人のいろいろなステータスにおいて、遺伝と環境のいずれの影響が大きいかを分析した結果です。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
身長や体重、運動能力、数学や音楽の才能、文章力などについては、遺伝の影響が相当に大きい(8〜9割)ことが見て取れます。一方、外向性や同調性などの社会的な傾向の一部は環境の影響が優勢ですが、それでも4割近くは遺伝の影響を受けています。
みなさんは、「遺伝ガチャ」という言葉を聞いたことがありますか? 「ガチャ」とは、元はカプセル入り玩具の自動販売機である「ガチャガチャ」あるいは「ガチャポン」から来ているそうです。
ガチャガチャは、コインを入れてハンドルを回すと玩具入りカプセルが出てくるのですが、欲しいカプセルが出るかどうかは運次第なため、くじ引きに近いものです。これがオンラインゲームのくじ引きを表す「ガチャ」という言葉に転じ、さらにそれが転用されて、自力ではどうしようもない運任せの要素を「○○ガチャ」というようになったそうです。
そうした表現を借りて、遺伝による生まれつきの才能の違いは「遺伝ガチャ」といわれています。図表1の双子分析の結果を見ると、遺伝ガチャという概念も、あながち無視はできないですね。
■双子のIQは似通っている
次に、多くの人の関心をひき、盛んに研究されているテーマでもある「知能」を深掘りしてみましょう。図表2は、日本人の双子にIQテストを受けさせた結果を表にしたものです。横軸が双子の一方のIQ、縦軸がもう一方のIQを表しています。もし双子のIQが全く同じであれば、そのデータは45度線のライン(図表の太線)に乗るはずです。
図表を見てみると、データは概ね45度線のラインに沿ったように分布していることがわかります。これは多くの場合、双子のIQがかなり似通っていることを示しています。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
この図表への理解をさらに深めていきましょう。左上の数字は「相関」といって、比較している2つのデータが何割くらい連動しているかを表しています。一卵性双生児(遺伝子がまったく同じ)は相関が0.72とありますが、これは、IQテストの結果が7割も連動していることを意味しています。
日本に限らず、他の国で同様の調査を行っても双子のIQは非常に似通ったものになることが知られています。図表3はアメリカの研究ですが、同じような結果になっていることがわかります。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
■年齢が上がるにつれて、遺伝の影響は強まる
どうやら、知能については遺伝の影響がかなり大きそうです。さらに驚くべきことに、成長するにつれて遺伝の影響がむしろ強まるという研究もあります。直感的には、人間は年齢とともに経験を重ねていくので環境の効果が強まっていきそうな気がしますが、実際には逆なのです。
図表4はイギリスの学者による研究で、1万1000ペア(2万2000人)の双子に知能テストを受けてもらった結果を表しています。今まで紹介した研究と異なるのは、年齢ごとに区切って調べている点です。図表4では、幼少期(9歳時)、青年期(12歳時)、成人初期(17歳時)の成績を比較しています。このグラフを見ると、年齢が上がるにつれて遺伝の影響が右肩上がりに大きくなっているのがわかります。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
この結果は意外に思われるかもしれませんが、人間は経験を重ねることで、自分本来の遺伝的な素質を引き出せるようになっていくのだと考えられます。子ども時代は親や先生から言われた通りの勉強をしていたものが、だんだんと自分なりの興味や主体性で動くようになり、試行錯誤をしながら自分に合った学び方を身につけていきます。そうして、自分本来の姿になっていくのです。
■40代で最大になる
また、日本人男性の年収と遺伝の関係を調べた研究を紹介します。この研究結果を見ると、若い頃は環境の影響が支配的(遺伝は2割程度)である一方、年齢が上がるにつれて遺伝の影響が大きくなっていき、40代では遺伝の影響が6割近くに達します。
出典=『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』
この結果も、先ほどのIQと似たような説明ができます。働き始めの頃は、企業ごとの初任給の違いや、親のコネの有無などの環境によって年収が決まります。しかし、仕事を続けていくうちに昇格や昇給、転職などで差がついてきて、次第に自分本来の実力に見合った年収になっていくのだと考えられます。結果として、もっとも「脂がのっている」働き盛りの40代において、遺伝の影響が最大になるということです。
冨島佑允『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』(アルク)
このように、データを見ると遺伝の影響がかなり大きいことがわかりますが、努力がムダだとか、結局は才能には勝てないんだなどと落ち込む必要はありません。というのも、遺伝はその人が持つ潜在能力を表しているものだからです。つまり、年齢とともに遺伝の影響が大きくなるのは、経験を重ねることで実力を発揮する術を身につけていくからだと考えられるのです。
要するに人間は、最初は環境に翻弄されてしまうけれども、経験を重ねるうちに自分なりのやり方を身につけ、環境を克服して本来の実力を発揮できるようになっていくということです。人間は人生における挑戦と挫折から自分自身について学ぶことで、本来の自分に近づいていくのです。
----------
冨島 佑允(とみしま・ゆうすけ)
データサイエンティスト、多摩大学大学院客員教授
1982年福岡県生まれ。京都大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科修了(素粒子物理学専攻)。MBA in Finance(一橋大学大学院)、CFA協会認定証券アナリスト。大学院時代は欧州原子核研究機構(CERN)で研究員として世界最大の素粒子実験プロジェクトに参加。修了後はメガバンクでクオンツ(金融に関する数理分析の専門職)として各種デリバティブや日本国債・日本株の運用を担当、ニューヨークのヘッジファンドを経て、2016年より保険会社の運用部門に勤務。2023年より多摩大学大学院客員教授。
----------
(データサイエンティスト、多摩大学大学院客員教授 冨島 佑允)