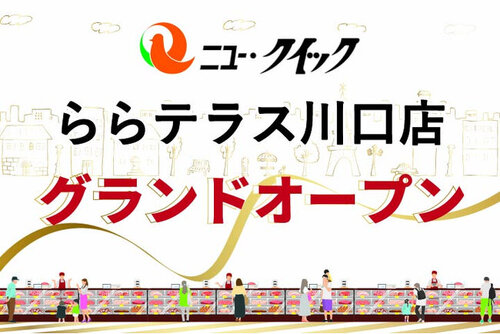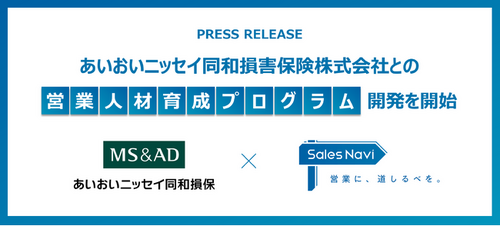だからキーエンスには「売れない営業マン」がいない…トップ営業が教える「成果を爆上げするための型」
2025年4月25日(金)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/metamorworks
※本稿は、田中大貴『売れる組織 売れる営業』(実業之日本社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/metamorworks
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/metamorworks
■営業職、医師、美容師…いずれも専門職なのにここまで違う
営業職は、誰にでもできる仕事と思っていないでしょうか。
それは誤解です。私は、営業職は専門職のひとつだと捉えています。にもかかわらず、営業職を独り立ちさせる教育環境はほとんど整っていません。そこに、営業パーソンの苦悩する原因があると思っています。
営業職と医師、美容師を比較してみましょう。
まずは医師です。大学医学部で6年間の教育を受け、卒業後に医師国家試験に合格すれば医師免許を取得することができます。
医師免許を取得してはじめて、研修医(旧初期研修医)として2年間、専攻医(旧後期研修医)として3年間の経験を積むことができます。いわゆるOJTのようなものです。
5年間の経験を積むと、専門医試験の受験資格を手にすることができます。その専門医試験に合格して、ようやく一人前とみなされます。
大学受験から始まる高難度の試験をクリアし、高度に整備された研修制度による学びを経て、人の命を扱う業務に従事することができます。
一方、美容師になるには厚生労働大臣、または都道府県知事の指定した美容学校で2年間の課程を修了(通信課程は3年間)する必要があります。修了すると、美容師国家試験の筆記試験、実技試験の受験資格が得られます。
筆記試験、実技試験ともに合格してはじめて、美容師免許を取得して美容師名簿に登録することができます。
多くの美容師はサロン勤務となりますが、すぐに顧客の髪の毛をカットできるわけではありません。先輩美容師からの指導のもと、アシスタントとしてトレーニングを積みます。
現場における試験をクリアしてはじめて、ようやく顧客の施術ができる。そのために日ごろから勉強と練習を重ね、合格してようやく独り立ちできます。
それに対して、営業職には医師や美容師のような資格や免許は必要ありません。必然的に、教育体制も整っていません。多くの営業パーソンは四年制大学を卒業後に就職し、その企業で営業職に就きます。
■半人前の段階で放り出され、試行錯誤の日々
ただ、4年間の大学生活で営業について学ぶ機会はほとんどありません。営業は良い意味でも悪い意味でも、学歴や年齢に関係なく、誰もが就ける職種なのです。
営業職に就いてからも、医師や美容師とは違います。ごく一般的なケースは、入社後に自社の扱う商品やサービスを勉強し、すぐに先輩の営業に同行しながらOJTで学びます。
しかし、どの先輩から指導を受けるかによって教えられる内容は異なります。しかも、十分な時間をかけてもらえることはなく、まだ半人前の段階で放り出されます。
「あとは経験。自分で感覚を掴んでください。頑張って!」
そう言われても、ひとりではほとんど何もできません。
「何が正しくて、何が間違っているのか」
「何をやるべきで、何をやるべきではないのか」
正解がわからないなか、自らの「感覚」を頼りに、OJTで見聞きしたことを見よう見まねで試行錯誤するしかありません。仕事をするなかで、営業のコツを掴んだ人は成果をあげることができますが、ほとんどの営業パーソンは思うような成果をあげられず悩んでしまいます。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
■型=教科書があれば営業の成果はもっとあがる
このような経過をたどる営業パーソンがきわめて多いと思います。これは企業の規模の大小を問わず、都市でも地方でも同じです。もちろん、高学歴の学生が入社する上場企業でも変わりません。では、なぜこうなってしまうのでしょうか。
繰り返しですが、営業に「教科書」と呼ばれるものがないからです。
医師や美容師には、国家試験というモノサシがあります。それに合格するための教科書が緻密に整備されています。合格しようとする人は、その教科書を必死に勉強します。
その結果、医師や美容師になるための基礎知識や最低限のスキルを獲得することができるのです。
一方、営業には国家試験も民間の資格試験もありません。ですから、それをクリアするための教科書もありません。だからこそ、的確な営業教育をすることが難しいのです。
そのため、営業パーソンには多くの疑問や課題が生じます。
●何が正解なのかわからない
●OJT以外の営業教育がないため、営業のやり方がわからない
●会社の研修を受けても、実践的な内容に欠けている
●先輩や上司によって指導力にバラつきがある
さらに、マネージャーの立場からも次のような課題が浮き彫りになります。
●何が正解なのかわからない
●経験や勘、思いつきに基づくため一貫した指導や教育ができない
●日常業務が忙しく、指導や教育に十分な時間をかけられない
●複数のメンバーに対して、同じような指導をすることが億劫になる
企業の視点から見ても、多くの課題が発生しています。
●適切な営業教育が何なのかわからない
●入社時の営業教育のカリキュラムがない
●営業として一人前になるまでのステップが明確になっていない
●営業教育をしているのに、営業パーソンが期待通りに育たない
これらの課題があるかどうか多くの企業に尋ねると、100%に近い企業が該当すると答えます。ほとんどの企業が、どのようにして営業の水準を高めるかについて悩んでいることが明らかになっています。
■ひとりあたりの生産性を上げることで売り上げの最大化を図る
営業パーソンとして同期入社したAさんとBさんがいたとしましょう。AさんとBさんはともに、四年制大学を卒業して入社しています。それぞれの大学のレベルもほとんど変わりません。営業としての能力はともに未知数です。
出典=『売れる組織 売れる営業』
図表1のように、AさんとBさんのスタート地点は同じです。ところが、2年目になるとAさんの成果がBさんを上回り、3年目になると挽回できない差まで開いてしまっています。
営業としての能力は変わらないはずなのに、コツを掴んだか、良い上司に巡り合ったかどうかで、このような現象が起こるのが営業現場の実情です。
売り上げの8割は2割の社員に依存するという「パレートの法則」があります。
10人の営業パーソンの組織とした場合、2人の売れる営業、6人の普通の営業、2人の売れない営業という分布になる傾向があります。
これは組織として営業の成果が分散化している状態であり、決して理想的な形ではありません。
この分散化を解消するために必要なのが、営業教育なのです。
出典=『売れる組織 売れる営業』
人数は同じでも、ひとりあたりの生産性を上げることで売り上げの最大化を図る必要があります。最終的には、売れる営業7、普通の営業2、売れない営業1の分布になるよう、標準化するイメージです。
標準化の源になるのが、営業の型です。教育を通じて営業の型を会得させ、営業パーソンによってバラつきが生じる成果を高位安定に導く必要があるのです。私がこの考えに至ったのは、新卒で入社したキーエンスでの経験があったからです。
■「売れない営業をつくらない」キーエンスの型
キーエンスでは、営業の型が1から10まで完璧にでき上がっていました。その型通りに営業すれば、一定以上の成果をあげることができます。
つまり、企業として「売れる営業をつくる」というスタンスではなく、むしろ「売れない営業をつくらない」というスタンスだったのです。
よく考えれば、企業として120点の「超売れる営業」を育成するのは大変な労力と費用がかかりますし、何より再現性にも乏しい。
しかし、80点の売れる営業であれば、超売れる営業よりも再現性高く育成することが可能です。80点の売れる営業が組織内に大量にいたほうが、組織としての生産性は間違いなく上がります。
もちろん、いわゆる金太郎飴を大量生産しようと言っているわけではありません。
言うまでもなく、営業パーソンにはそれぞれ個性や強みがあります。その個性や強みを発揮するためにも、ある一定水準の営業力が必要なのです。基本的な営業力もないのに、個性や強みを主張しても相手にされません。
■型がないから、それぞれの個性や強みを生かせない
その営業力を担保するのが、営業の型なのです。ところが、多くの企業には型がないため、メンバーの成長力に差が生まれています。一部の売れる営業の成果に依存し、どうにか帳尻を合わせていますが、それぞれの個性や強みを生かすことができません。
田中大貴『売れる組織 売れる営業』(実業之日本社)
その点、誰もが習得できる営業の型があると、メンバー個々の成長が実現でき、個性や強みを生かしてより魅力的で成果をあげられる営業パーソンに育て上げることができます。
私が新卒からおよそ2年半の時間を過ごしたキーエンス、その後舞台を移し約11年間を走り続けたプルデンシャル、営業力の高さに定評があるリクルートのような企業は、営業の土台となる型をしっかりとつくり込んでいます。
だからこそ、組織としてきわめて安定した成果をあげ続けられるのです。
私は、自らの営業経験からも、理論的な裏づけからも、営業の型づくりが絶対に必要だと考えています。
----------
田中 大貴(たなか・だいき)
Sales Navi 代表取締役
2008年同志社大学文学部を卒業後、キーエンスに入社。連続で目標を達成したのち、2010年にプルデンシャル生命保険にスカウトされ入社。以来11期連続社長杯入賞。2017年に、当時全国最年少でエグゼクティブ・ライフプランナー(部長)に就任。2017〜2021年度には、日本の生命保険募集人登録者、約120万人のなかで上位0.01%しかいないとされるMDRT TOT会員に認定される。順風満帆な営業人生を送る一方で、「道しるべがないがために営業に悩んでいる組織や人」の存在を知り、「営業の道しるべを創る」というビジョンを掲げて2021年にSales Naviを創業。事業を推進する傍ら、ひとりでも多くの営業パーソンが抱える課題や悩みを解決したいという想いから「営業の教科書」をつくることを決意し、『売れる組織 売れる営業』を執筆。
----------
(Sales Navi 代表取締役 田中 大貴)