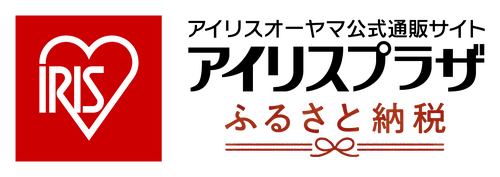アイリスオーヤマの“憲法第1条”「利益を出せる仕組みこそ重要」はなぜ生まれたか
2024年6月20日(木)4時0分 JBpress
バブル崩壊(1990年代初め)、リーマンショック(2008年)、コロナショック(2020年)など経済的な危機に見舞われるたびに大きく成長してきたアイリスオーヤマ。その秘訣について、同社の大山健太郎会長は「ピンチをチャンスに変える経営」ではなく、「ピンチが必ずチャンスになる経営」の結果と説く。同氏の著書『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』(日経BP)では、「経常利益の50%を毎年投資に回す」「新製品比率50%に設定」といった独自のKPIとともに、会社を変える「15の選択」を提示している。本連載では、同書の内容の一部を抜粋・再編集して紹介する。
第1回は、アイリスオーヤマの経営の原点を解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 アイリスオーヤマの“憲法第1条”「利益を出せる仕組みこそ重要」はなぜ生まれたか(本稿)
■第2回 業界の定説に反したアイリスオーヤマの「農作業用の半透明タンク」が大ヒットした理由とは
■第3回 「経常利益の50%を毎年投資に回す」アイリスオーヤマの深謀遠慮(7月3日公開)
■第4回 アイリスオーヤマの強さの源泉「プレゼン会議」はどのように行われているのか(7月10日公開)
■第5回 組織を腐らせる「ヌシ」を生まないために、アイリスオーヤマが構築した独自の仕組みとは(7月17日公開)
■第6回 ニューノーマル時代の勝ち残りに直結する、アイリスオーヤマの5つの企業理念とは(7月24日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
ビジネスチャンス優先の経営
アイリスの経営は、ビジネスチャンス優先です。いつ何どき、目の前にチャンスが出現してもすぐに対応できるように、常に準備をして待っています。そのために、自社の強みに特化する「選択と集中」戦略と、目先の効率は下がるかもしれないが、決して機会損失を起こさない「選択と分散」戦略の両方を追求してきました。
それぞれの戦略の違いについては後で詳しく述べますが、集中戦略は、目先の効率は高めますが、外部環境の変化には弱い。環境変化を自社の成長に取り込むためには、目先の効率をあえて下げ、資本を分散させる戦略も必要です。「稼働率7割」はその一つです。
ピーター・ドラッカー氏は、環境にただ対応するのではなく、環境を自ら変えることの重要性を指摘しています。私はそれを実践してきたつもりです。景気が悪くなったら経費削減に取り組み、影響を軽微に抑えるだけでは不十分なのです。
これまでのアイリスの歴史を振り返れば、およそ10年ごとに起きる環境変化のたびに大きく成長しています。具体的には1991年の土地バブル崩壊、1997年の金融危機、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、そして2020年のコロナショックです。そうしたピンチが来たときに慌てるのでもなく、嵐が過ぎ去るのをただ待つのでもなく、確実にチャンスに変えて、業績を伸ばしてきました。
もっとも、最初からそのような経営ができていたわけではありません。2020年でアイリスは創業して62年になりますが、最初の環境変化は1973年の第一次オイルショックでした。オイルショックのリバウンドで私は会社を潰しかけています。あんなにみじめで、悲しい経験は二度としたくないと思い、どんな環境でも利益の出せる仕組みを確立すると誓ったのです。
アイリスオーヤマの「経営の原点」は、1964年です。
会社の原点は、私の父が大山ブロー工業所を創業した1958年ですが、父は独立してからわずか5年で、がんに侵されていることが分かり、程なくして他界しました。8人きょうだいの長男だった私は大学進学を望んでいましたが、母と7人の弟妹を食べさせなくてはならない。1964年、19歳で社長を継ぎました。
工場はプラスチック製品の下請け加工で、孫請け以下の零細企業です。5人の従業員がいて、機械はどれも中古。当時の年商は500万円でした。ここが経営の出発点です。
ただし、経営の相談がしたくても、父はもうこの世にいません。もちろん、「こうしたほうがいいよ」とアドバイスをくれる上司もいない。誰にも頼れず、白紙状態で経営者人生を歩き始めました。なぜ、うまくいかないのだろう。どうすればうまくいくのか——。毎日が「なぜ」「どうすれば」の繰り返しでした。
あの頃の会社の強みは何だったのかというと、それは結局、自分の若さでした。
寝ずに働いても、大丈夫な体力がありましたから、昼は営業に出て、夕方から配達をこなし、従業員が帰った夜中に機械を動かす…。その合間に、従業員とご飯を食べながら、語り合う。こんな毎日を過ごしていました。
そして、来る注文は断らない。すべて「イエス」で対応していました。断らずに引き受けていると、「あそこに相談すれば何とかしてくれる」と信用力が得られます。難しい仕事をこなしていると、技術力が高まってきます。
「町工場のおやじで終わりたくない」「下請けではなく、自社ブランドを世に送り出したい」という思いが強くなってきました。そして21歳のときに作ったのが、養殖用のブイ(浮き球)。それまでのブイはガラス製が一般的でしたが、私はブロー成型の技術を生かしてプラスチック製のブイを開発しました。これが「軽くて、壊れにくい」と評判になります。当時はプラスチックの勃興期で、他の素材に代替することで市場が開けました。
オイルショックで倒産の危機
次に開発したのが、田植えで使う育苗箱です。1960年代半ばから普及し始めた田植え機に取り付ける、苗を育てる箱なのですが、こちらはもともと木製が主流でした。しかし、木製では寸法の誤差が生じやすく、耐久性が低いという問題がありました。それをプラスチック製に変えることで、ヒット商品となったのです。
やがて、水産業・農業のメインマーケットである東日本からの受注が増えると、需要に近いところで製品を供給する生産拠点が必要になってきました。そこで、物流網が発達し、降雪が少ない宮城の地を選び、1972年、仙台工場(現・大河原工場)を新設します。19歳で社長に就いたときに年間500万円だった売り上げは、宮城県に進出した27歳のときには7億6000万円にまで伸びていました。
その後の私の経営理論を決定づけるオイルショックが起きたのは、そんなときです。
1973年のオイルショック直後は石油製品の需要が高まり、モノを作ればどんどん売れるという状態でした。トイレットペーパー同様、市場はプラスチック製品の買い占めに動き、ブイや育苗箱を作る大山ブロー工業所も設備を増強して需要に応えていました。最新設備を入れた仙台工場では150人ほどの社員が働いていました。
しかし、混乱が収束すると、仮需要のリバウンドで1975年を境に需要は急減。壮絶な値崩れが始まったのです。大山ブロー工業所の売り上げはたった2年間で、14億円から7億円に半減。工場の稼働率が下がり、売価が原価を下回ります。
直前に仙台工場をつくって規模を拡大したことで、借り入れは膨らんでいた。大量生産で効率化を図ろうとしたことが仇となったわけです。どのメーカーも在庫が山積みになり、売れば売るだけ赤字になる事態に陥ってしまいました。大山ブロー工業所も、10年間で築き上げてきた会社の資産をたった2年で失うことになったのです。
東大阪の工場を閉める
もはや、2つの工場を抱える体力はありません。設備が新しく、規模も大きく、そしてメインマーケットに近い仙台工場を残し、父から継いだ東大阪の工場を閉める。これ以外に選択肢はありませんでした。
大阪から仙台への異動を承諾してくれた社員は4人。大阪で働いていた残り46人、そして仙台にいた社員150人の約半数に、辞めてもらうことになったのです。自社ブランド製品のブイ、育苗箱もヒットさせた。青年経営者の端くれのつもりでしたが、私のマネジメントのどこかに欠陥があったのです。
特定の製品でヒットを飛ばしても安泰ではない。わずか1、2年で会社は簡単に駄目になる。オイルショックのような環境変化が数年後に再度起きたら、もう会社は持ちません。競合他社に追随されて価格競争になれば、やはり利益率は大きく落ちるかもしれない。どんな時代環境においても利益を出せる経営とは、どのようなものか。二度とリストラをしないという強い思いを胸に、私は会社を抜本的につくり直すことにしたのです。
このときに誓った「いかなる時代環境においても利益の出せる仕組みを確立する」という言葉を、1991年に、大山ブロー工業所からアイリスオーヤマに社名変更したときに制定した企業理念の第1条に掲げることになります。
これは、いわばアイリスにおける“憲法第1条”です。企業理念というと、多くの会社では「顧客第一」や「社会貢献」の文言が最初に来るのではないでしょうか。利益を出すためには顧客や社会に貢献しなければならず、それらを後回しにするつもりはありません。ただ、二度とリストラをしないよう、利益を出し続けることが私の中で絶対条件でした。
仕組みという言葉にこだわったのは、個々の製品は重要ではないことをオイルショックで学んだからです。ヒット商品に頼っていると、製品開発力が弱まり、時代の変化に適応できなくなるというリスクも生じます。それを防ぐのが、仕組みです。
<連載ラインアップ>
■第1回 アイリスオーヤマの“憲法第1条”「利益を出せる仕組みこそ重要」はなぜ生まれたか(本稿)
■第2回 業界の定説に反したアイリスオーヤマの「農作業用の半透明タンク」が大ヒットした理由とは
■第3回 「経常利益の50%を毎年投資に回す」アイリスオーヤマの深謀遠慮(7月3日公開)
■第4回 アイリスオーヤマの強さの源泉「プレゼン会議」はどのように行われているのか(7月10日公開)
■第5回 組織を腐らせる「ヌシ」を生まないために、アイリスオーヤマが構築した独自の仕組みとは(7月17日公開)
■第6回 ニューノーマル時代の勝ち残りに直結する、アイリスオーヤマの5つの企業理念とは(7月24日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:大山 健太郎