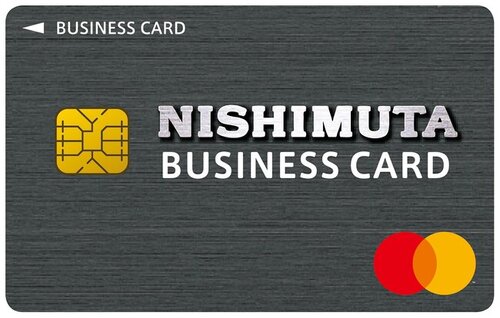サラリーマンより節税できる!個人事業主の税金面でのメリットとは?
2025年1月31日(金)7時0分 マイナビニュース
個人事業主はいろいろな節税ができると聞いたことがある方も多いでしょう。実際に、個人事業主には会社員にはない税金面での優遇が複数あります。この記事では個人事業主の税金のメリットを解説します。
個人事業主が節税できる方法は主に「経費」と「控除」
個人事業主が節税できる方法として、経費と控除の2つがあります。経費に関しては、仕事に関係する支出を経費として計上し、利益を減らすことで所得税や住民税の軽減が可能です。
控除は、所得から差し引くことで課税対象となる所得額を減らせる制度のことです。会社員で「配偶者控除」や「扶養控除」などを利用したことのある方も多いと思いますが、それ以外にも個人事業主の方が利用できる控除があります。
個人事業主が活用できる制度を、経費編と控除編にわけて見ていきましょう。
【経費編】個人事業主が活用したい節税方法
個人事業主が経費にできる支出はさまざまあり、事業によって異なります。今回は自宅で仕事をする場合で使う事の多い経費を解説します。
○パソコンやスマホなど仕事で使う機器の購入費
仕事用にパソコンやスマホ・タブレットなどを購入した時、購入費を経費として処理できます。購入金額が10万円未満の場合、消耗品費として計上可能です。
10万円以上の場合は、原則として備品として資産に計上し、減価償却をする必要があります。ただし、一定の条件を満たす中小企業などは「少額減価償却資産の特例」が適用され、30万円未満の資産を一括で損金として算入可能です。
○家賃や光熱費
自宅の家賃や電気代のうち、仕事で利用した分を経費として計上できます。仕事の分を算出するのに「家事按分」という方法を利用します。
1つの例として時間で按分する方法があり、たとえば24時間のうち6時間を仕事で使うなら、1/4である25%を経費として計上可能です。
○通信費
パソコンのインターネット代や携帯電話料金も、仕事で使う分は経費にできます。パソコンで使用するクラウド型のセキュリティソフトや会計ソフトなどの料金も通信費として処理可能です。
インストール型のソフトの場合は「消耗品費」で処理をします。
○中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
取引先の事業者が倒産した場合に備える共済制度で、毎月一定の額を掛金として納付します。掛金は事業の必要経費として計上可能です。
また無担保・無保証で、掛金の最大10倍までの貸付を受けられるのもメリットです。
【控除編】個人事業主が活用したい節税方法
経費の次に、控除の制度を解説します。
○青色申告特別控除
個人事業主として活動するなら、ぜひ利用したい控除制度の1つがこちら。確定申告で青色申告をすることで、最大65万円の控除が適用され、その分税金が安くなります。
青色申告をするには、複式簿記で記帳し、貸借対照表や損益計算書なども提出する必要があります。会計ソフトなどで書類作成をサポートしてもらえますので活用しましょう。
○小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の経営者が事業を辞めたときに、生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備しておく共済制度です。毎月一定の掛金を納付し、掛金は全額所得控除の適用を受けられます。
小規模企業共済で納めた掛金の額に応じて、低利子での貸付を受けることも可能です。
○iDeCo
iDeCoは私的年金制度で、毎月掛金を拠出して投資信託などで運用します。掛金が全額所得控除になり、利益が非課税となり、資金を引き出す際には退職所得控除などを受けられる点がメリットです。
個人事業主は厚生年金がなく国民年金のみのため、将来の年金受給額が低くなる可能性が高いです。節税しながら資産形成ができるiDeCoは、老後に備える有力な方法の1つとなります。
安藤真一郎 あんどうしんいちろう マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。 この著者の記事一覧はこちら