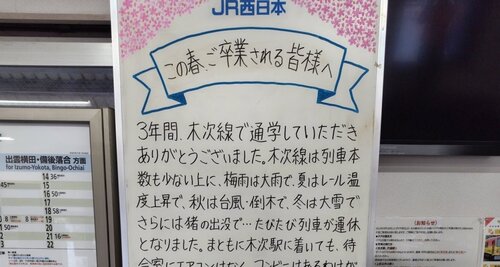降りしきる雨、2本のレールが延びるトンネルの向こうに…消えてまだ10年も経っていない廃線「西武安比奈線」跡で待っていた“行く末”
2025年3月31日(月)7時0分 文春オンライン
〈 開業は関東大震災の2年後…消えた“帝都復興の輸送路”「西武安比奈線」跡には何がある? 〉から続く
関東大震災の2年後に開業した「西武安比奈線」は、入間川の河川敷まで延びていた砂利輸送路線。帝都復興の輸送路として活躍したこの路線が正式に廃線になったのは2017年のことである。
まだ町の中に“ほぼそのまま”の形で残っているという廃線跡を訪ねることになった著者。降りしきる雨の中、関係者の案内のもと安比奈線への分岐地点だった西武新宿線「南大塚」から廃線跡に歩を進めていった——。

足元に気をつけながら進んでいく。何やらレールが見えてきた
足元に注意しながら進んでゆくと、脇に和菓子屋さんが店を構える入間川街道との交差地点。入間川街道は、いわば現在の国道16号の前身といっていい。
1960年代に整備された国道16号の上にはレールは埋め込まれていなかったが、入間川街道にはいまもレールが残る。ここもまた、きっと昔は踏切だったに違いない。
草地になっている廃線跡の空き地には、いまもレールが残っている。列車が走らなくなってから60年以上経つから、残っているレールも60年以上も前のものなのだろう。
ただ、交差する道路上では列車が走る幅のままなのに対し、草地の上のレールは2本が仲良くくっついて並んでいた。離れていたのをわざわざ移動させたのだという。草刈りなどの管理をしやすくするためだろうか。
などと思いながら草地を進んでゆくと、ぷつりと周囲の住宅地が途切れる場所に出た。周囲の風景もそれまでとはちょっと変わって、田畑が目立つ開けた地。
新河岸川などの小河川が流れていて、廃線跡は小さな橋梁や築堤でその中を一直線に進んでゆく。橋梁が残っているところは安全かどうかがわからないということで遠回り。
ごく一部だけ、田畑の中の廃線跡に沿うような道路もあって、その道路から廃線を跨ぐ板が渡されていた。
廃線跡の向こう側に暮らす民家の人が設けたのだろうか。いわば勝手踏切のようなものだが、少なくともいまでは列車が来ることは絶対にないのだから、足元不如意を除けば安全性に懸念はない。
見えてきた森を抜けて廃線跡をたどっていく
そして、その先の廃線跡の行き着く先に見えてくるのは、森である。いよいよ入間川河川敷近しといったところだろうか。この小さな森の中では2本のレールは昔のレール幅そのままに置かれていて、その上を覆うように緑の木々が生い茂る。
決して列車の走ることのないレールが2本まっすぐと延び、緑のトンネルの向こうに明かりが見える。雨降りであっても、いや雨降りだからこそ、なかなか実に幻想的な廃線跡の風景だ。
列車が行き交っていた時代には、もちろんこれほどに木々がレールの真上まで茂っていたということではなかろうと思う。廃線跡だからこその景色といっていい。そして同時に現役時代がどんな様子だったのか、思いを馳せるのもまた、悪くない時間である。
そんな小さな森の中を抜けると、レールごと埋められたと思しき道路を越えて、またも森の中へと廃線跡は入ってゆく。
その先にはどうやらもう進むことはできないらしい。それまでとはまったく違い、かなり厳重なフェンスと共に入念な立ち入り禁止の文字が掲げられていた。
見ると、そこにはいかにも古そうな橋梁の跡。万にひとつ、誰かがそこに入り込んで橋が落ちてしまったら、ということなのだろう。
そして、この古びた橋の先はもう入間川の河川敷だ。八瀬大橋という入間川を渡る橋に通じる道を歩いてゆくと、その真下を潜るように廃線跡が続いているのが見える。ただ、道路が完全に廃線跡を埋めてしまっていて、さらに周囲も河川敷の木々の中へと消えている。
廃線跡が消えた先を眺めれば、「安全第一」と壁面に掲げられた工場のようなものが見える。この場所では現在も砂利の採取が行われているという。きっと安比奈線もこの工場のあたりまで続いていたのだろう。
現役時代、このあたりに広がっていた光景は…
現役時代、貨物専用の終着駅の名は安比奈駅といった。関東大震災後、つまり大正時代の終わり頃から営業を開始して砂利を運んだ西武安比奈線。
最初は非電化の路線で、おそらく蒸気機関車が活躍していたのだろう。が、終戦からそれほど経っていない1949年には電化路線になっている。戦後復興に伴い砂利需要が急増し、輸送力を強化したに違いない。
その当時、いまや木々の生い茂るばかりの河川敷には安比奈線の安比奈駅とそこから河原まで続くトロッコの線路が広がっていたという。
川底から採掘した砂利はトロッコに積んで運ばれて、件の工場あたりで選別をしてから列車に載せ替え、安比奈線を走って南大塚駅へ。そして西武新宿線に乗り入れて都心方面、または本川越方面へと運ばれていたのだ。
ちなみに、入間川河原のトロッコ線や安比奈駅構内での貨車入替には陸軍の鉄道連隊の貨車や機関車が使われていた。どうして西武鉄道が鉄道連隊の車両を手に入れることができたのかはよくわからない。
きっとあれこれ手を回して、使いやすそうなお古の車両を確保したのだろう。関東大震災後や終戦後は、とにかく砂利の需要が高まっていた時代であった。
正式な廃止からは10年も経っていない「安比奈線」の“この先”
しかし、首都圏に近い川の砂利を採掘して運んで都市建設、という時代はいつまでも続かない。野放図に川を浚渫して砂利をさらってばかりいては水害の原因にもなりかねない。
そういうわけで、少しずつ砂利の採取量が制限されるようになり、1964年には入間川の砂利採取は原則禁止されてしまった。そうなれば、安比奈線の役割も終わりである。
ほぼ同時期に多摩川や相模川でも砂利採取が禁じられているが、そちらの砂利鉄道はそのまま通勤通学路線として残る。
ただ、まだまだ周囲の都市化も進んでいなかった安比奈線にあっては、そういうニーズもなかったのだろう。結局、運転を“休止”したまま歳月が流れることになる。
その後、安比奈駅付近に車両基地を建設する計画があったり、はたまた旅客線として復活させて沿線の宅地開発を進める計画があったりはしたようだ。
いずれも実現しないまま、2017年に正式に廃止になった。廃線後は、いったいどうなるのか。それはまだよくわからない(というか決まっていないのだろう)。もしかすると、遊歩道のようになるのかもしれない。そうなれば、緑のトンネルはなかなかの見どころになりそうだ。
ともあれ、いまから100年前に営業を開始し、関東大震災と戦後の復興に陰ながら力を尽くした砂利鉄道・西武安比奈線。もしかしたら、ぼくらの町のどこかにも、安比奈線が運んだ砂利が使われている……かもしれない。大都会・東京の礎を築いた、廃線跡なのである。
写真=鼠入昌史
〈 新宿、池袋を出発し…実はかなりレアな存在“東京発の観光列車”には何がある? 〉へ続く
(鼠入 昌史)