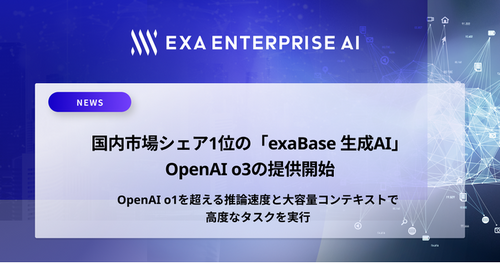【水野誠一 連載】竹中直純(下)動くプログラムがあれば走らせてみればいいじゃないかという概念を人間の頭脳に近い生成AI言われているものに対して適用していいのか
2025年4月24日(木)7時0分 ソトコト
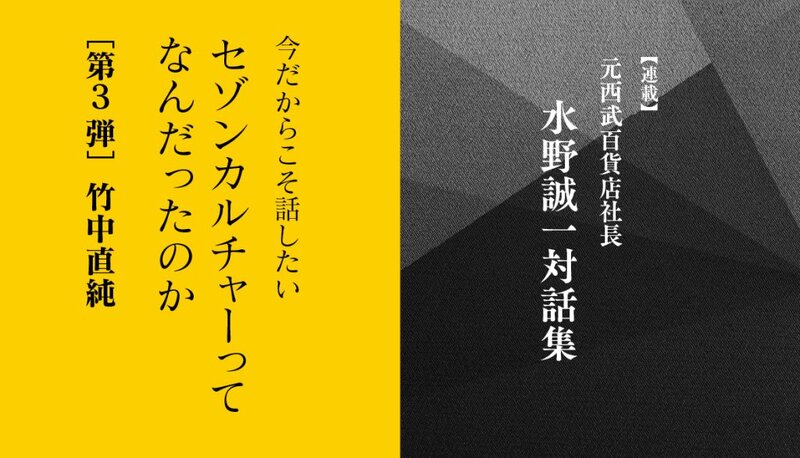
西武百貨店の社長から米国のIT企業の顧問へ。水野誠一の世代を超えた交流から、今回は実業家でプログラマーの竹中直純がゲストとして招かれた。
「ニコニコ動画」で仮想と現実をつなぐ一つのきっかけをつくった彼は、今、人間の動きをどう捉えているか。また生成AIの時代に投げかける提言とは。

「ニコニコ動画」でインターネットとリアルワールドをつなぐ
水野 未来検索ブラジルの後、ブラジル社は何をやったんですか。
竹中 Groongaという検索エンジンがひと通り出来上がって落ち着いた後にどうなったか。
有象無象の情報空間の中で、人が正しい情報に到達するには検索はまず必要でした。そこから先ですね。
普段の生活では、インターネットで何かが全て起こるわけではなくて、リアルワールドで何かが起こって、それがインターネットに載ることが多いですよね。その構造は変わらないじゃないですか。それで、ブラジル社は次に何に着手したかというとインターネットとリアルワールドをつなぐことを考え始めました。結果としてコメントがバーって流れるので有名な「ニコニコ動画」を作りました。
水野 仮想と現実をつなぐということですね。
竹中 そうですね。
ドワンゴ社をはじめとする協力社の方々と一緒に、定期的に20人ぐらいで集まって、お弁当を2つ食べるくらいの長時間、ああでもないこうでもないって話してるうちに、出てきたのが「ニコニコ動画」だったんです。
手軽に動画を上げることの有効性はYouTubeがその時点で数年間、世界で実証していた。そのような動画の中には面白くないものも多い。しかし、それに皆からのコメントがつくことで、内容が面白くなくても面白くなる。これは大発見だったんですね。
動画を見てコメントをつけ、それが動画に被さって表示されることが、当時は新しかった。そしてそれが昔からあるスポーツ観戦やお祭りの楽しさ、つまり共時性を動画鑑賞に持ち込めていると感じたんです。
ところがやはり動画ごとに人気が出たり、出なかったりしますよね。そうすると、タレント化が起こるんですよ。
水野 ずば抜けて人気のある人が必ず現れるんですね。
竹中 はい。そのタレントに収益を与えることで、よりその面白いものを継続してもらおうという動きが出てきます。ユーチューバー未達の時代に果敢にその方法を模索したのがドワンゴでした。そのタレントを基本的にはプラットフォームでコントロールしようとしたんです。
水野 その後、カドカワとひっついたでしょう。
竹中 はい。ドワンゴ単体でもそれ以前から、コンテンツカンパニーでもあったので、アニメのように制作委員会方式で内容のクオリティコントロールを含めてタレントをプロデュースして出していくというやり方をしたんです。
例えばクリエイター奨励基金をつくったり、コンテストみたいなことをして、その成果に応じてお金を渡します、というようなことを試しながら最適な方法を探していたんですよ。
水野 時間がかかりそうで、現代的ではないですね。
竹中 そこへやってきたのがYouTubeです。
彼らは単純に言えば、メイン収益である検索広告売上金の一部を、そのクリエイターたちに全部分けますということをやった。そうすると、そのクリエイターに配る金額として、桁が1個上の額を配れたんですよ。「好きなことで生きていく」というコピーで、渋谷駅にヒカキンの大広告が現れた頃ですね。
水野 大事にしようとしたんだろうけど、ドワンゴはやり方が古すぎたね。
竹中 クリエイターを大事にする、守るというのは川上さんのポリシーでもあったんですよ。
コンテンツをプロバイダーが制限するかどうかは、政治や憲法も絡むような難しい判断です。いろんな発言が出てくる中にコンテンツ保護主義はひとつの考え方として当然出てきます。カドカワは今でも保護主義だと思いますが合理主義でもあります。もっと過激な保護主義の出版社もありますけどね。
水野 ブラジル社はどう関わっていたんですか。
竹中 ニコニコ動画がコンテンツ奨励をフルコントロールでやっている。YouTubeは対照的に単純にView数勝負で分配している。どっちが勝つかわからない。
だから両方とひっつきました。タレントはどちらでも動画をあげられますからね。その後、結果的にビジネスとしてうまくいったのは、YouTube方式だと世の中的には思われていますよね。しかしプラットフォームは息の長いビジネスです。まだ何があるかわかりません。
プラットフォームとは関係なく重要なのはクリエイターなので、マネジメントも行っています。所属してもらうことで企画を共に考えたり、企業としてのメリットを提供したり。例えば彼らは若く社会経験に乏しくて税務なんて知らないことも多いので「税金を納めるにはこうするんだよ」と教えたりなんてこともあります。
仮想空間と現実が行き来するなかで失われたのはパブリックの概念
水野 仮想世界から生まれたクリエイターをリアルの世界へとつないでいるんですね。
竹中 はい。最近やってるのは、クリエイターと共に1〜2万人のリアルイベントを企画しています。実際に会場に足を運んで周りを見ると観客の方は感激して涙を流して感動していたりします。
僕たちが会場を抑えて、セキュリティ周りもきちんとやって、企画を立てたり、ステージ上の段取りなど全部やって、みんなにお弁当買って、みたいなことをやって、収益を責任もって預かって配分するといった業務をやっています。
結局アナログなんすよね。インターネットからリアルワールドへ来ると。昭和のアイドルのコンサートと光景的には同じです。
水野 仮想空間の1対1から始まって、誰でもスターになれるっていう要素は大事ですよね。この間起こった殺人は怖かったけれど、あれは特殊な事例。びびっちゃダメだね。
竹中 SNS以前は、自分や自媒体を通すことで、良い物事を視聴者に紹介したいという動機がタレントや編集者の中にあったんです。だから半ばパブリックな存在として自分自身は器だという気持ちがどこかにあった。でも、今は”自分”で止まるんです。
「私を見てください」なんですね。
百貨店もそういう意味でパブリックなものだった。西武の目利きが揃えた洋服や調度品、食料品を皆さんに紹介して、手数料は取るけれど、ここに来れば良いものが揃ってますよという構造。でも今はインターネットでものを買うにしても客側が能動的に探す方が多い。
水野 パブリック意識が弱くなってしまった。
竹中 情報との向き合い方が1対1なんですよね。そしてタレント側がその1になると起こる弊害として、発信に整合性を取らなくてよくなる。つまり、1対1だと嘘がつけてしまう。
水野 嘘じゃなくて本当のことが言えるということもあるでしょ。
竹中 はい。それはメリットの方です。本当のことも言い放題。でもデメリットとしては嘘もつき放題になるんですよね。
水野 何を信じるかでリアルでの格差が激しくなりますな。
竹中 誰を選ぶかがとても重要になるんですよね。
AIを倫理的に議論する場の必要性
水野 AIがリアルな生活に入ってくることへの倫理的な議論というのも、日本ではあまりなされていない気がしますね。
竹中 OpenAI社で、サム・アルトマンが辞めてまた戻ってきた騒動がありましたよね。
社内の倫理委員会から嫌われたので「辞めるわ」と言って実際辞めたら時価総額がドーンと下がって「やっぱり戻ってきてください」と言わせて。アルトマンの作戦勝ちで、もう彼には逆らえない、という雰囲気を作ったように思います。
そのアルトマンがやろうとしてるのは「OpenAI社の商業化とオープン化の両立」。だから倫理問題やロボット三原則の再評価などの話が出てきている。腕のついたAI付きの機械が人を殺すかもしれないから、防がなければならない。でも商業優先が根源にはあるように思います。
今問題なのは、例えば薬ならば、治験や臨床試験を経て厚生労働省が認可するという仕組みが出来上がっていますよね。つまり倫理、人命優先の仕組みが社会的に受け入れられている。
ところがAIの世界は、少なくともOpenAI社はアルトマンの一件でガラッと変わってしまったんですよ。つまり、やってみてダメならやめればいい、やり直せばいいという、ラフコンセンサス方式になっちゃった。そもそもソフトウェア開発者の間には元々そういう方針「荒い合意とワーキングコード(Rough Consensus and Running Code)」といって、とにかく動くプログラムがあればそれを信じるというIETFのモットーがあり尊重されています。OpenAI社はアルトマンが戻ったあと、そっちに引き戻された感じがあります。
しかしそのモットーが人間の頭脳に近い動作をするような、生成AIと言われているものに対して適用していいのか、通用するのかということを、今、僕ら人間は問われているんです。けれども、日本ではその手の文化的な議論、倫理的な議論はほとんど行われていません。
水野 日本のデジタル庁はやっているのかな。竹中さんはデジタル庁をどう評価してきたのか、それは今日聴きたかったことの一つなんです。
竹中 デジタル庁は、局所最適化的にはうまくいってると思いますよ。
だから、デジタル庁のウェブページを見れば現在、シンプルで質の良いウェブ技術の集大成みたいなつくりになってます。
無駄がなくて、欲しい情報になるべく早くたどり着けるっていう意味では、とても出来の良いものです。他の省庁と比べても、一般的な企業のウェブページと比べても、すごくよくできてる。
でも、それでいいかどうかで言えば、全然良くなくて。
水野 センスの欠如?そこが問題ですねえ。
竹中 日本の官公庁は本来の意味ではまだデジタル化できてないです。というか、デジタルの本質をわかっていないと思います。
ちょっと話は逸れますが、デジタル情報の解像度を上げていくと細かく細かく、きめが細かくなって、アナログに近づいていくんですよ。
水野 うん、そうですね。写真にしても、デジタル写真が最近になってようやくアナログ写真の滑らかさに近づいてきて、画質にうるさいプロが、仕事に使うようになった。
竹中 僕らを構成する原子だって物理学の最先端の量子重力理論では、波だと言われています。物質波みたいなものが、もう間違いないものだと思われて研究されてるんですよ。すみません、わかりにくいことを言ってますけど。
空間の最小解像度はどこなのかは、まだわかってないんです。
今はプランク長(1.616229×10⁻³⁵メートル)っていう定数があって、ものすごく小さい数なんですけど、世界がコンピューターディスプレイみたいにピクセルのような格子でできているとすればそれより細かい空間が存在できるのか、意味があるのかということについて、今のところ全くわからないのです。つまりこの事実は我々の世界は本質的にものすごく細かいデジタルで表すことができるのではないかということを示しています。
でも、僕たちはこの世界をアナログだと認識していますよね。結局アナログとデジタルを区別することなんてできないんですよ。そのような認識を国家や行政が持てば、DXというお題目がそれほど重要じゃないことはわかると思います。
水野 でも明らかに、音楽がデジタル化した初期、実に味気のない聴こえ方になってしまったじゃないですか。何となく気づきましたよ…音楽というのは、音から音への変化の間に、わずかな?無音に近いリエゾンが発生したりするじゃないですか、これが微妙にブツギレに聞こえるような気がしたり…
いずれにしてもこれからは、デジタルなものをいかにアナログに近づけるかということが「技術進歩の先」に求められるんではないかということですね。坂本龍一さんもそんなことを考えていたんじゃないかな。
竹中 音楽のデジタル化は実質CDから始まりました。CDの規格では1秒を44,100に区切ってその瞬間瞬間の音の強さを65,536段階にして記録しています。しかし人間の聴覚は個人差はありますが、それよりも高感度なのです。アナログに近づくという意味では、ひとつはハイレゾという、より高解像度(1秒を96,000に区切って音の強さを1677万段階にするような)で記録するという方法がある一方で、アナログレコードへの回帰が起こっています。最新の統計では音楽パッケージの市場で最も伸びたのがアナログレコード市場だったという面白い結果も出ています。
僕は坂本さんのプライベートスタジオで、人間の聴覚について話したことがあるんですが、48,000Hz/24bit「1秒を48,000に区切り音の強さを1677万段階」で聴覚的には充分で、もっと重要なのは録音環境とマスタリングだねぇと言ってました。が、その後何年かして同じスタジオで小さな鐘やクリスタルのボールを鳴らしたりして「こういう音がそれだけでもう音楽なんだよね」と言っていたのがとても印象深く記憶に残っています。
今のAIは論理の帰着ができない人のためのツール

水野 竹中さんが、以前、何かのインタビューで、AIが現れることによって、自らの中に文化的な蓄積のある人とそうではない人の格差が広がるということを言ってましたね。
竹中 誤解を恐れず言うなら、今のAIはある意味”バカ”のためのツールです。
AIは論理的演算能力と三段(以上の)論法で結論をどこかに着地させるようにできています。論理の帰着がバカでもできるというツールなんです。
でも世の中の8割の人が、AIなしでまともにそれができない。その人たちのために論理破綻を起こさず、辻褄の合った答えを出すツールだと見做せるんです。
でも、同じことが自分の頭で簡単にできる2割の人には、今は不要なツールです。
だけど、AIのすごさをわかって本当に使いこなせるのは、その2割で、現在実用にできる部分をうまく使ったり、公開されているモデルを改造していたりします。実用の例としては音声をテキストに変換したり、僕の場合はWebデザインに使うスタイル言語が多過ぎてとても覚えてられないのでその部分だけ書かせたりしてます。
残念ながら日本のメディアはその8割の人たちに対して、あなたの写真がジブリ風になります、とか、AIで仕事が無くなる業種とかいう煽りばかり繰り返していますね。
それは単なる副作用であって、レイ・カーツワイルのいう”シンギュラリティ”はそういう意味ではないんです。人間の活動の質が変わって、人間以外の知性(つまりAI)を認め、何語でしゃべっても意思疎通ができる社会になる。
水野 その多言語同時通訳は実現が目前まで来ていますね。僕が付き合っている中国の会社もかなり高度なイヤホン型・通訳機をつくっています。
竹中 いろいろできてますよね。来年ぐらいかな、Appleが同時通訳機能をAirPodsにつけるっていう噂も出ていて、で、それを試験的に試したっていう人もいますね。
言語がバラバラになったきっかけの事件として、旧約聖書に書かれている「バベルの塔」の話(旧約聖書 創世記 11章)が出てきますよね。
人間の堕落と塔を作って神に近づくという侮辱的行為を神様が許さず、バラバラにした言語の再統合が起こるということですよね。無理やりテクノロジーの力で引き上げる。
言語の上位には文化もあります。それが混ざる。どうなるのか。今後5年間ぐらいで、我々はどうそれをどう捉えるか。これはけっこう大変なことで、結論はわかりませんが、少なくともそこまで生きていたいなと思います。
水野 なんか人間がますます学んだり考えたりしなくなるのかな。
竹中 8割の人はそうなりますね。びっくりするぐらい差がつくと思います。
水野 それは今ある経済格差や偏差値のような数字の問題ではなくて、人間としての本質的な格差になっていきそうな気がしますね。我々が無関心ではなく、しっかりと考えていかないとダメな時代になりますね。
だから、今こそ絶えず問題を提起するセゾン文化の役割があったはずなんですけどね。
構成:森綾 http://moriaya.jp/