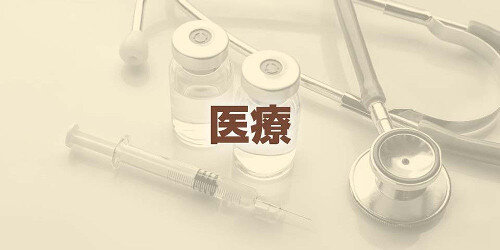iPS医療 日本発の研究ようやく結実へ
2025年4月23日(水)5時0分 読売新聞
これまで治療法がなかった病気を、iPS細胞(人工多能性幹細胞)などを使って治す再生医療が実用化に大きく近づいた。治療法を早期に確立し、患者に届けてもらいたい。
京都大学病院は、人のiPS細胞から作った神経細胞をパーキンソン病の患者7人の脳に移植したところ、症状の改善がみられたとする治験結果を発表した。画期的な成果である。
パーキンソン病は、運動の調整に関わる脳内物質ドーパミンが減ることで、手足が震えたり動作が遅くなったりする難病だ。国内患者は29万人とされる。ドーパミンの量を増やす薬で症状を抑えられるが、根本的な治療法はない。
今回の治験では、効果が表れて介助が不要になった人もいるが、実用化には更に多くの患者を対象に効果を確認する必要がある。
だが、錠剤などを大量生産できる旧来の医薬品と異なり、細胞などを使った高度な医薬品は、開発や品質管理が格段に難しく、大規模な治験も容易ではない。
このため、今回の細胞医薬品の製造販売を行う製薬企業は、再生医療に適用される「条件・期限付き承認(早期承認)」制度を活用することで、多くのデータの収集を目指すという。
この制度は、すべての治験を終えてから承認・販売する通常の手続きとは異なり、小規模な治験後にまず「仮免許」に当たる早期承認を取得し、治療効果を示すデータを集めて本承認を目指す。
医療分野の技術革新を促し、新薬を患者に早く届ける有用な制度と言える。だが、今回の治験とは別に早期承認が適用された5製品では、2製品は効果を証明できずに申請が撤回され、残る3製品も本承認には至っていない。
今回の製品についても、安全性や効果を十分に検証することが欠かせないが、実用化の道が開かれたことへの期待は大きい。
iPS細胞は山中伸弥・京大教授が開発し、2012年にノーベル賞を受賞した。政府はiPS研究に資金を重点投入し支援してきた。十数年来の研究がようやく実を結びつつあるのではないか。
最近は、パーキンソン病のほか、脊髄損傷や糖尿病の治療にiPS細胞を使う研究も進展している。例えば大阪大学発の新興企業は、心臓病の患者に移植するため、iPS細胞から作った心筋細胞シートの製造販売承認を申請した。
産学の連携を強化し、長く待ち望まれてきた日本発のiPS医療の実現を目指してほしい。