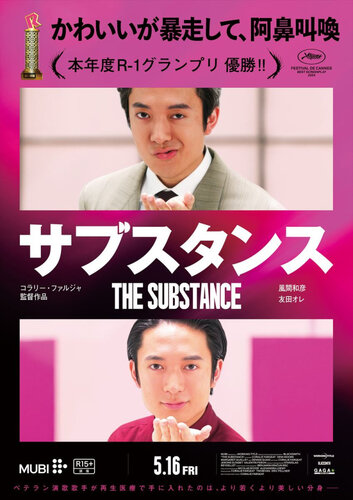アカデミー賞受賞なるか…伊藤詩織氏の映画「Black Box Diaries」協力者を無断でさらす隠し録画・録音の是非
2025年2月28日(金)18時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/smolaw11
写真=iStock.com/smolaw11
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/smolaw11
■3月3日の米アカデミー賞授賞式で受賞の快挙なるか?
性被害を実名で訴え、日本の「#MeToo(ミートゥー)」運動のきっかけを作ったジャーナリストの伊藤詩織氏が監督したドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』(ブラック・ボックス・ダイアリーズ)がもめている。アメリカのアカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞に日本人の作品として初めてノミネートされるなど、海外で高い評価を受けているが、3日3日(アメリカ時間で2日)のアカデミー賞授賞式を前に、いまだに国内で上映のめどがたっていない。
その背景に、かつて伊藤氏の裁判を支えていた元代理人弁護士たちが「許諾のない映像や音声を使っている」と批判していることがある。彼らは日本外国特派員協会で2月20日会見を開き、「伊藤氏は国内でこうした許諾問題が持ち上がっていることを、海外で説明していない」とも指摘した。
伊藤氏は同日会見を開く予定だったが、体調不良のため中止を決定。一方で、未許諾の映像や音声が含まれていたことを謝罪し、国内用と海外用に修正版を作ったという声明を出した。ただ、会見時に記者陣に公開する予定だった、これらの修正版を公にすることは見送られた。
『Black Box Diaries』は、伊藤氏が元TBS記者の山口敬之氏から性加害を受けたと訴え、刑事裁判では不起訴になったが、民事裁判で勝訴するまでの軌跡を追っている。伊藤氏自身の身辺で起きた出来事を記録する形で撮られており、セルフドキュメンタリーというジャンルに入る。なぜこの映画に、伊藤氏の味方だった弁護士たちがこれほど強く反発しているのだろうか。おそらくこの映画が、ドキュメンタリー映画としてもジャーナリスト活動としても、かなり異質のものであることが関係している。
■隠し撮りや隠し録音が多いことをどう判断するか
『Black Box Diaries』の特徴としてまず挙げられるのは、隠し撮りや隠し録音を多く利用していることだ。伊藤氏自身、「隠せる所ならどこにでも隠して、小さな録音機を身につけていた」と映画の中で語っている。
隠し撮りや隠し録音、つまり許諾のない撮影や録音は、他のドキュメンタリー映画でもないわけではない。社会悪の追及を狙う直撃取材型のアクション・ドキュメンタリーではたびたび見かけるものだ。代表的な監督としてマイケル・ムーアはよく知られているし、日本にも原一男がいる。ホロコーストの証言を集めた『ショア』で、クロード・ランズマンは顔を出さないという約束を破って、元ナチスの男性の映像を使っている。こうした作品は論争を生んできたが、同時に賞賛も浴びてきた。
■無断で映されたのは加害者側でなく、伊藤氏の協力者や支援者
だから一般的には首を傾げるような手法を使っていても、優れた作品と見なされてきたドキュメンタリー映画は多い。しかし『Black Box Diaries』が独特なのは、無断撮影や無断録音の対象が前述の作品に見られるような加害者側や権力側ではなく、伊藤氏の協力者や支援者側だったことだ。
例えばその中には、タクシー運転手、ドアマン、刑事、メディアで働く女性が集まった会合の参加者、そして代理人弁護士の一人だった西廣陽子氏の映像や音声が含まれる。タクシー運転手は伊藤氏と山口氏をホテルまで乗せた時のこと、ドアマンはホテルの入り口でそのタクシーを迎えた時のこと、そして西廣氏はドアマンの証言を裁判でどう扱うかについて、それぞれ伊藤氏に話すところなどが使われている。彼らは伊藤氏に敵対しておらず、協力関係にある。
写真提供=© Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ
映画賞「BAFTA Film Awards in London」に参加した伊藤詩織氏、イギリス、2025年2月26日 - 写真提供=© Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ
■元弁護士は「自分が伊藤さんの意向を拒否したように描かれた」
中でもドアマンは「会社から言われても証言しようと思うし、自分の名前を出してもいい」とまで話している。ただ、この会話自体が録音されていること、自分の言葉が全世界に公開されることは承諾していたのだろうか。他の出演者についても同じことが言える。もしかしたら、「映画を見て初めて、伊藤氏と自分の会話が何年も前から無断で録音されていたと知った」と会見で語った西廣弁護士と同じ状況に置かれているかもしれない。これは個人が特定されないよう、顔の部分をカットしたり、姿形にぼかしを入れたり、ボイスチェンジャーを使って声を加工したりするのとは、また別の話だ。
映画が日本では未公開であることもあり、無断使用にショックを受けたと公に言っている出演者は多くない。メディアで働く女性たちの会合のシーンで、自分が画面に映り込んでいるのを削除してほしいという要請があったと報じられているが、会合で性被害経験を話した女性の許諾は取られていた。しかし、抗議の声が聞かれないから問題はない、というわけではないだろう。職場での立場上、声を上げにくかったり、騒動の渦中に入るのを避けるため、やむなく沈黙している場合も考えられるからだ。
『Black Box Diaries』のもう一つの特徴は、未許諾のものを含むそうした映像や音声が時々、一定の方向で切り取られていることにある。西廣氏は、ドアマンの証言を裁判で役立てたいという伊藤氏の意向に沿って自分は動いていたのに、映画の中ではそれを拒否したかのような発言が使われ、伊藤氏が孤立を深めていくストーリーにされていた、と指摘し、「心がズタズタにされた」と話している。代理人弁護士として8年半懸命に働いてきたのに、こうした取り上げ方をされるのはアンフェアではないかということだ。伊藤氏は声明で西廣氏に謝罪しているが、この映画のメッセージを届けるために、ある方向に映像をまとめていたということなのだろう。
■伊藤氏にとって証言してくれた人はヒーローだったが…
つまり、タクシー運転手やドアマンなど、彼女のために証言しサポートしてくれた人たちを讃えるという方向だ。声明で実際「彼らは私にとってヒーローです」と伊藤氏は書いている。これは伊藤氏がこの映画で一番訴えたかったことの一つではないだろうか。被害者なのに孤立無援で自ら証拠集めをしなければならない自分、その自分にとって心底ありがたい存在は、そうした自分に共感し証言をしてくれる、元々は無縁だった人たちだ、と。それは単に訴訟上の必要性を超えた、伊藤氏の精神的な支えとしても重要だったように見える。
そして彼らの存在が嘘ではないことを示すために、つまり証拠映像や証拠音声として示すために、証言の様子を映画に組み込んだのだろう。ただ、これをジャーナリスト活動として見た場合、映画という媒体でその証言を使っていいかどうか、彼らの確認が必要だろう。ジャーナリズムは事実を積み上げ、それを示すことではあるが、裁判で証言するのと媒体で取り上げられるのとでは次元が違うからだ。また西廣弁護士のような、自分以外の視線も組み込んで全体像を見る必要があった。
■セルフドキュメンタリーで、他者の視点が入っていない
そして、これを伊藤氏のセルフドキュメンタリーとして見た場合、誰かが自分に話したことが即、映画の一部となっていいわけではなく、編集というもう一段違うレイヤーがあるのに、その辺りが未分化で検討不足だったのではないだろうか。伊藤氏個人の心情と、映画で強調したいことの間に差がないように見え、それは一見自然なようだが、さまざまな問題を生む可能性がある。
一方、ドアマンらに比べてグレーな存在なのが、伊藤氏に警察の内部情報を知らせていた刑事だ。伊藤氏の今の代理人弁護士である師岡康子氏らは、伊藤氏の協力者という面もあるが基本的には捜査状況を説明しただけであり、内部通報者ではないと主張している。
しかし彼は捜査担当から外れた後にわざわざ伊藤氏に電話してきて、上の指示で逮捕状の執行が止まった時の詳しい内部情報を伝えている。通常なら新しい担当者が、容疑者は逮捕されなかったことを通知すればいいだけだ。さらにこの刑事はその後も伊藤氏と連絡を取り続けている。こうしたことから彼を内部通報者だと見てもおかしくない。少なくとも情報提供者であることは確かだ。だとすると、これも取材源の秘匿と保護というジャーナリストの倫理に関わってくる。
写真=iStock.com/y-studio
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/y-studio
■警察内部の情報を提供していた刑事はどうなるのか?
しかし伊藤氏はこの映画で、この刑事をそのようには位置付けていなかったということだ。映画の中で伊藤氏は刑事に何度か「自分のために証言してほしい」と訴えており、彼はそれを断っている。「孤立無援の性被害者には、証言してくれる協力者が必要だ」というこの映画のメッセージにおいて、刑事はそうした協力者になりえなかった存在ということだ。
ここで指摘しておかなければならないのは、伊藤氏はまたもこの刑事に、彼らの会話の様子を録画・録音しており、それを公開する可能性があることを告げていない。彼を警察という権力機構の一員と見るか、それとも情報提供してくれる協力者と見るかで、判断に違いが出てきそうだが、権力機構の一部であっても末端に位置する彼に配慮をするなら、個人が特定されないよう大幅な修正を行うだけでなく、そもそも自分の事件の捜査担当者であると明かさず、警察内部の一人というぐらいに留め置くべきだっただろう。
彼が事件担当者であることは既に出版済みの本『Black Box』で明かしているので、今更という感じがあったのかもしれないが、映像や音声は活字に比べ、人物についての情報量がけた違いに大きいことに、少し無頓着であるように見える。
■情報源が秘匿されないと、協力者が減ってしまうのでは
この刑事は伊藤氏との会話の中で不適切な戯言を言ったりしており、それも女性が日常生活の中で時々直面する不快な出来事の一例だろう。一方で彼がなぜ伊藤氏と連絡を取り続けているかと言うと、自分の手がけた事件が不自然に中止されたことへの疑問と、伊藤氏の窮状に対する理解と同情もあったのではないだろうか。彼が「この件はたぶん一生心に残る」と話している場面がある。
ところがこのように刑事の言動が映画の中でさらされてしまうと、被害者に対する人間的な共感は抑えて、今後は極力ビジネスライクに接するべきだという印象を警察関係者に与えてしまう恐れはないだろうか。それは今後、性被害者にとっての不利益にならないだろうか。
■ドキュメンタリー映画監督は「許諾」をどう考えているか
この許諾問題について、ドキュメンタリー映画関係者はどう見ているか、複数の関係者に聞いてみた。
映画監督の舩橋淳氏は「許諾を得るためできるだけ努力することが必要だが、全員からは許諾を取れないので、グレーゾーンもある」という考えだ。例えば、渋谷のスクランブル交差点で撮影した時、映り込んでしまった人たち全員に許諾を取るのは不可能だという。
また許諾を取った後、当人の考えや映画を巡る状況が変わることもたびたび発生する。「そのグレーゾーンについては、編集した後、そのシーンが単なる背景なのか、意図を込めた使い方なのかなど、監督やプロデューサーが判断し責任を引き受けるもの」だと話す。「伊藤氏は証拠を集めるため懸命に撮っていたのかもしれない。編集段階でプロデューサーなり制作会社が寄り添ってアドバイスすべきだった」と指摘する。
伊藤氏がホテルの防犯カメラの映像を目的外使用したことも問題になっているが、山口氏によってタクシーからホテルへ連れ込まれる映像は「伊藤氏への性加害を示す証拠映像として公益性があり、見られなければならないもの」という意見だ。
写真=iStock.com/RichLegg
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/RichLegg
■ジャーナリズムだから「事実であれば出していい」という判断
一方、ドキュメンタリー映画の編集に長く携わってきた秦岳志氏は「上映でリスクを背負うのは出演者。彼らが蚊帳の外に置かれているようで心配していたが、再編集されたと聞いてまずは安堵した」と話す。これは舩橋氏らも実践しているというが、秦氏らは出演者と作品の意図や方向性を共有し、話し合いながら制作するように心がけてきた。「作品表現の中心にいるのは出演者で、撮影者はそのサポート役」という考えに基づく。
「出演者でも監督でもあることからくるセルフドキュメンタリーにありがちな罠に、この映画もはまってしまった。また、ジャーナリズムと映画の感覚は微妙に違うと感じている。ジャーナリズムは事実を忠実に描こうとするので、事実であれば出していいという判断になりがち。でも映画は、出演者と作り手が一緒になって映画の中の現実を生み出すもの。その結果、主観的になったり曖昧になったりもする」という。
セルフドキュメンタリーの場合、映画の中に出演し行動している自分と、撮った内容を編集し外部に公表する自分を切り分けることは、極めて重要だ。こうした原則は徹底する必要がある。でなければ今の時代、もっと手軽なスマホ動画で、捜査や裁判の過程の一コマを撮影し、撮影者の主観に基づいて登場人物や出来事を位置づけた内容をSNSに流してしまうようなことも、正当化されかねないのではないだろうか。それは被害者の武器になるというより、被害者を警戒する捜査員や弁護士を生み出す結果につながりかねない。
■直撃取材をあまりしなかった理由は何か
最後に、この映画にはアタック・ドキュメンタリーのような加害者側や権力者側への直撃取材の映像があまり含まれていないことに触れておきたい。「週刊新潮」の取材に対し、「山口氏の逮捕は必要ないと止めたのは自分だ」と答えたのは、当時警視庁刑事部長だった中村格氏だった。その中村氏への突撃取材を、伊藤氏は「週刊新潮」のチームと一緒に行っているが、その後再び自分たちのチームだけで試みた様子は出てこない。
ただ、「週刊新潮」が公開している動画によると、実際には、伊藤氏は何度も中村氏に突撃取材を試みていたようだ。だとしたら、なぜその様子も映画に含めなかったのだろうか。伊藤氏のために証言することを拒んだ刑事より、中村氏の責任は大きいように思われる。これまでの社会派ジャーナリズムや社会派ドキュメンタリーは、権力と対峙(たいじ)したり、権力を持つ組織の内側に踏み入るような調査報道をするのが主流だった。
■二次加害された伊藤氏は深刻なトラウマを抱えている
伊藤氏はこれまで、極めて深刻な二次加害を受けてきた。日本にいられないと海外に脱出したほどだ。それを考えた時、組織の後ろ盾のない彼女がフリーの立場で加害者側や権力者側に直接挑んだら、どんなバッシングが起きるか心配したのかもしれない。しかも性加害と二次加害によるPTSDに苦しんできた経緯がある。
この映画の中で、伊藤氏は悪質な誹謗(ひぼう)中傷にさらされたことを、あまり具体的に描いていない。詳しく触れることができないほど深刻なトラウマを抱えているのではないだろうか。しかし、まさにそうした誹謗中傷をする者こそ、伊藤氏が何としてでも証拠になる協力者の証言を集めて、裁判で勝ちたいと強く願うように追い込んだ主犯格だった。
山口氏を除くと、警視庁幹部だった中村氏と誹謗中傷を行った当人たちという「追及の対象になるべき対象」が、この映画の中心にはならない結果になったこと——それにはいろいろな理由があるだろうが、その一端には伊藤氏、そして性被害者全般に対する誹謗中傷の、あまりにも深刻な現状があるように思う。
一方でこの映画が問いかける「困っている誰かのために、リスクを負って協力できるか」という問題は、多くの人にとって簡単に答えられないものだろう。それでも、それを求めずにはいられない伊藤氏の気持ちを、この映画は表現するというより、むしろ体現している。そして、性被害を受けたのに何の正義もなされなかった無数の女性たちが、伊藤氏の背後にいる。これはずっと変わらない光景だ。
----------
柴田 優呼(しばた・ゆうこ)
アカデミック・ジャーナリスト
コーネル大学Ph. D.。90年代前半まで全国紙記者。以後海外に住み、米国、NZ、豪州で大学教員を務め、コロナ前に帰国。日本記者クラブ会員。香港、台湾、シンガポール、フィリピン、英国などにも居住経験あり。『プロデュースされた〈被爆者〉たち』(岩波書店)、『Producing Hiroshima and Nagasaki』(University of Hawaii Press)、『“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する』(作品社)など、学術及びジャーナリスティックな分野で、英語と日本語の著作物を出版。
----------
(アカデミック・ジャーナリスト 柴田 優呼)