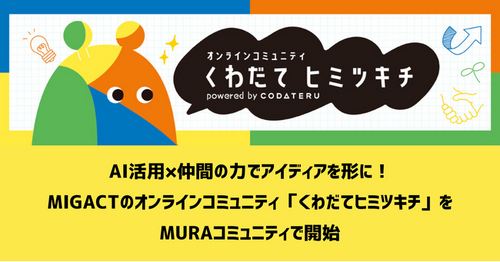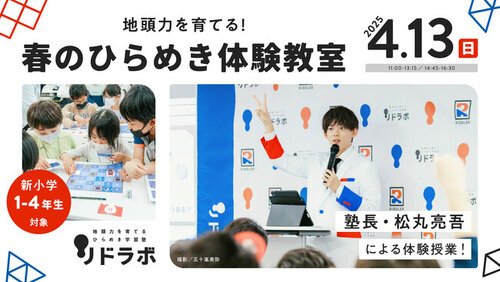「何度でも生まれ変わる循環型食器」一人の社員のひらめきが開発につながる
2025年3月13日(木)14時0分 PR TIMES STORY
丸紅株式会社は、2025年大阪・関西万博の「Co-Design Challengeプログラム」を通じて、これまでほとんど用途がなかった食物の皮等の食品廃材を独自の技術で食器にアップサイクルした「edish」を提供する。プラスチックは一切使わず、特殊な技術で耐水、耐油、耐熱性のある食器で、万博会場内の飲食の場で使用される。また、使用後は回収し、万博で発生する生ゴミとともに堆肥化し土壌改良剤として使い、それらを野菜や花として2回目のアップサイクルができることをめざす。そのプロジェクトについて、4回のシリーズ企画で迫る。

※シリーズ記事は、「Co-Design Challengeプログラム」のホームページに公開しています。各記事は、取材時点の情報のため、プロジェクトの進捗や開発状況によって当時から変更となった点などが含まれます。
「何度でも生まれ変わる循環型食器」一人の社員のひらめきが開発につながる Vol.1

循環型食器「edish(エディッシュ)」
小麦やカカオ、果物の皮などの食品廃材が、独自技術で食器によみがえり、最後は肥料となって動植物の栄養となる。こんな何度でも生まれ変わる循環型食器が、大阪・関西万博の会場で使用される。大手商社「丸紅」の一人の社員のひらめきが、プラスチックの使い捨てを減らしたいという熱意につながり、実を結んだ開発ストーリーに迫る。
2019年春、パッケージ事業課担当課長の簗瀬啓太は、取引先の音響部品メーカー「プラス産業」(静岡市)を訪れた際、気になる技術に出会った。紙の原料となるパルプ(木質繊維)をどんな形にも成型できる「パルプモールド」という独自技術で、紙以外の素材を混ぜて加工することも可能という。ちょうど、顧客の製粉会社から大量に余るふすま(小麦の表皮)の使い道を相談されていたところだった。
パルプとふすまを原料に食器に加工し、プラスチック容器の代わりにできないだろうか。海洋プラスチック問題が深刻化するなか、使い捨てされない素材の検討を進めていた時期でもあった。二つの懸案事項が一挙に解決でき、新しいビジネスの種になる予感がした。
簗瀬は会社に戻ると、その日から日常業務の合間を縫い、循環型食器のアイデアを練り始めた。使った後は、食器の残飯ごと回収し、粉々にしてから発酵させ、堆肥(たいひ)にする仕組みにしよう。そうすれば、食べ残しの食品ロス解消に一役買えるほか、最終的に食材を育むことで命そのものを循環させることができる。構想は定まった。
次に、事業化の予算獲得のため、前年から始まった全社員対象の「ビジネスプランコンテスト」に応募することにした。早速、プラス産業に製作の協力を依頼。素材がもつ色合いや模様を生かし、シンプルでおしゃれなデザインに仕上げた。そして、名称は「edish(エディッシュ)」に決めた。着想のヒントになった「ecological(自然環境との調和)」「ethical(倫理的)」「economical(無駄のない)」の三つの頭文字からとった。
簗瀬のプランは、12か国114件の応募のなかから2回の選考を勝ち抜き、最終審査に進む9組に残った。そして迎えた、20年1月16日の最終プレゼンテーション。東京・日本橋のイベントホールの客席には社員約400人が詰めかけていた。簗瀬は試作品を手に、ブラッシュアップしたプランについて熱弁をふるった。社外専門家の審査員と社員による投票の結果、事業化に挑戦できる3組に選ばれ、テストマーケティングや研究開発費用を見事に勝ち取った。審査員からは「世の中の潮流を捉え、広がりが感じられる」と称賛された。
「人生でこれほどやり遂げられたと思えたことはなかった」。自分のアイデアをゼロからビジネス化して社会課題に挑みたいという、入社以来の夢の扉が、15年目にして開いた瞬間だった。

丸紅 パッケージ事業部 簗瀬 啓太 さん

食品残渣(生ごみ)から堆肥を製造する様子
「何度でも生まれ変わる循環型食器」一人の社員のひらめきが開発につながる Vol.2

丸紅 パッケージ事業部 簗瀬 啓太 さん
2020年8月、葛西臨海公園(東京都江戸川区)から実証実験をスタートさせた。公園内のカフェでedishのボウル容器と平皿、深皿の3種類を使用。専用の回収ボックスを設け、お客さんには食事後、分別に協力してもらった。回収後は持ち込んだ小型の堆肥装置で肥料にし、公園内の花壇づくりに活用した。
普段は購入した商品の流通を担い、企業同士の仲介業務が中心の商社マンである簗瀬にとって、自分で開発した商品を消費者が使用する瞬間を見ることは、人生で初めての体験だった。「何とも言えない満足感と達成感を味わい爽快だった」。さらにスイッチが入った。
それから、サッカーJリーグの試合会場、ホテルの朝食ビュッフェ、バーベキュー場、海の家……。いろいろな場所で実証結果を積み上げていった。J1・川崎フロンターレのスタジアム前の屋台では、塩ちゃんこ1杯をプラスチック容器で500円、edishでは550円で販売したところ、説明を聞いた7割が50円高いedishを選んでくれた。
こうした反応に手ごたえを得る一方で、課題も徐々に浮き彫りになってきた。実験の際、目を離すと一般のゴミ箱に捨てられるケースが多く、分別回収の難しさを痛感した。堆肥装置を備えている施設も少なく、導入の手間とコストが重くのしかかった。
そんな矢先、大阪支社の社員からCo-Design Challengeの応募話がもたらされた。「日本中、世界各国から多くの人が押し寄せるビッグイベントで使ってもらい、認知度を高めることができれば、解決法を探るカギになるかも」。会場内の食事用にボウル型食器10万個を提供し、回収箱はCo-Design Challengeに参加する「日立造船」のグループが製作してくれることになった。
利用者の声を踏まえ、一つひとつ改善も重ねている。原料については食物アレルギーを考慮し、小麦以外にカカオやコーヒー豆の皮、リンゴやミカンなどジュースの搾りかす、茶殻など多様な食品廃材を使用。堆肥化の委託先も、実績豊富な食品リサイクル会社「アイル・クリーンテック」(さいたま市)の協力を取り付け、常時対応してもらえる道筋をつけた。
今後は、安価な使い捨てプラスチック容器に対し、いかにedishの付加価値を実感してもらい、利用の輪を広げられるかが勝負どころとなる。「これからが正念場。海外も視野に販路を開拓し、使い捨てが当たり前という消費者意識を根本から変えていきたい」
芽吹いた夢が大輪の花を咲かせるまで、簗瀬は大切に育み続けるつもりだ。

食品残渣(生ごみ)と一緒に処理されるedish

循環型食器「edish(エディッシュ)」
「何度でも生まれ変わる循環型食器」一人の社員のひらめきが開発につながる Vol.3

万博会場で提供を予定する「edish」の食器(ボウル)とフォーク
大阪・関西万博では、循環型社会の実現に向け、リデュース(削減)、リユース(再利用)により廃棄物を最大限減らしたうえで、リサイクルを徹底した運営を目指そうと様々な試みが行われている。
特に、短期間に多くの人が来場する万博会場では、一斉に大量の飲食物が提供されることから、食べ残しや使い捨て食器のごみ問題は避けて通れない。博覧会協会は、使い捨て食器が使われることの多いフードトラックにおいて、飲食物の販売に際しリユース食器の使用を原則にしているが、一部のフードトラックエリアではリユース食器の回収が難しいことを想定している。当該エリアは「edish」とは異なり、生分解性プラスチックの容器を導入し、食品廃棄物とあわせて堆肥(たいひ)化処理を予定している。今回採択された「edish」の食器も会場内で実施される一部のイベントで使用され、使用後は食品廃棄物と一緒に堆肥化される予定である。
万博が挑もうとしている大量の「イベントごみ」問題は、簗瀬がedishを開発しようとした理由のひとつでもある。通常であれば、焼却処理される食べ残しや使い捨て容器。そもそも日本では廃棄物の8割を焼却しており、世界でも突出して高い。特に、廃棄物のなかでも食品廃材などの生ごみは水分量が多いために焼却効率が悪く、大量の化石燃料が必要になるとされている。こうした現状に対し、「燃やす」以外の選択肢を多くの人に知ってもらいたい。簗瀬はCo-Design Challengeに参加を決めて以来、強くそう願ってきた。その思いの原点は、日本の農村部で慣習とされてきた幼少期の日常風景のなかにある。
簗瀬は転勤族の父親のもと、香川県丸亀市をはじめ、愛媛県今治市や松江市など自然豊かな地方都市で生まれ育った。特に、祖父母と同居した丸亀市では、自宅周辺に肥沃(ひよく)な田畑が広がり、野菜や果物の皮、お茶の出し殻などの生ごみがたまる度、祖母が当たり前のように田畑の堆肥場に持っていく姿を目にした。「生ごみには微生物のごはんになる有機物がいっぱい含まれているんだよ」。ある日、口にした祖母の言葉にハッとさせられた。汚いごみだと思っていたものが、土の品質を良くしたり、作物の栄養分を補給したりする働きを発揮し、次の命の芽生えに役立っている。ごみを燃やさなくてもいいだけでなく、ごみ袋や肥料代の節約にもなり、「“一石三鳥”ぐらいの価値があるじゃないか」。
この気づきが、とにかく無駄を嫌う簗瀬の行動の原動力となった。商社マンになってからも、「捨てられているものに価値を吹き込めれば、最強のビジネスモデルをつくりだせる」という信念を抱き、edishの開発へとつながった。

パッケージ事業部 簗瀬 啓太 さん

万博会場で提供を予定する「edish」の食器(ボウル)
「何度でも生まれ変わる循環型食器」 一人の社員のひらめきが開発につながる Vol.4

万博会場で提供を予定する「edish」の食器(ボウル)とフォーク
2024年夏、簗瀬は新しいごみ処理システムの商談のため、インドネシア・スラバヤ市の広大なごみの埋め立て地にいた。見渡す限りのごみの山には異臭が漂い、生ごみ周辺を飛び回るハエの群れや野犬に交じり、金目の品になりそうなプラスチックごみを漁る人の姿もチラホラ見えた。「ごみの堆肥化、リサイクル技術を導入できれば、この光景を変えることができるのに」。海洋プラスチックごみの流出量が世界ワースト3に入る同国を視察し、簗瀬は改めて、日本だけでなく海外でもごみ処理問題の解決に挑みたいという思いがみなぎった。
解決の糸口として注目するのは、やはり微生物を活用した発酵技術の可能性だ。2024年の夏以降、トンネルコンポストと呼ばれる方式によって、バイオマスの力でごみを処理するシステムの普及に乗り出している。この方式はヨーロッパでは一般的なごみ処理方法で、食べ残しや汚れのついた食品パッケージ、紙おむつなど雑多にまざり合ったごみでも、微生物と一緒に発酵槽に入れれば、きれいに分解され、においなども取り除いてくれる。分解で残ったプラスチックや紙を固形燃料の原料として有効利用することもできる。焼却処理に比べてCO2排出量を抑えられるうえ、焼却灰を埋め立てる最終処分場も不要になる。焼却が当たり前とされてきたごみ処理の常識を一新できる手法として、簗瀬は自治体などにアプローチしようと準備を進めている。
世界はいま、大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とせず、資源を効率的に利用しながら付加価値の最大化を図る「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行が加速している。博覧会協会は会期前より勉強会を開き、徹底した循環型の対策を議論し、世界に向けてレガシーを残そうとしている。
edishの開発をしていた時、簗瀬の頭に常によぎった言葉がある。祖母が口癖にしていた「もったいない」という6文字だ。「いまや世界共通語となった精神が改めて万博を通じて多くの人の心に浸透し、行動の変化につながってくれれば」。知らず知らずのうちに、地球環境に負荷をかけないライフスタイルを築き上げていた日本の先人への尊敬の思いとともに、持続可能な循環型社会の構築に向け、簗瀬はビジネスを通じて動き続けようと心に誓っている。

パッケージ事業部 簗瀬 啓太 さん

万博会場で提供を予定する「edish」のフォーク
Co-Design Challengeとは?
Co-Design Challengeプログラムは、大阪・関西万博を契機に、様々な「これからの日本のくらし(まち)」 を改めて考え、多彩なプレイヤーとの共創により新たなモノを万博で実現するプロジェクトです。
万博という機会を活用し、物品やサービスを新たに開発することを通じて、現在の社会課題の解決や万博が目指す未来社会の実現を目指します。
Co-Design Challengeプログラムは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が設置したデザイン視点から大阪・関西万博で実装すべき未来社会の姿を検討する委員会「Expo Outcome Design Committee(以下、「EODC」)」監修のもと生まれたプログラムです。
※EODCでの検討の結果はEODCレポートをご覧ください
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ