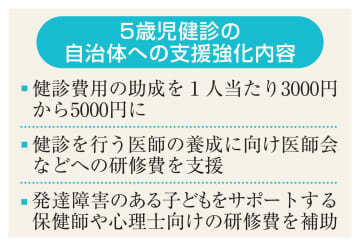「ウチの子は発達障害かも」と思った人に伝えたい…世界中でADHDの子供が爆発的に増えている意外な背景
2025年4月21日(月)9時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/MarkPiovesan
※本稿は、アンデシュ・ハンセン『多動脳』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/MarkPiovesan
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/MarkPiovesan
■世界中でADHDが爆発的に増加したワケ
地下水が危険な成分に汚染されたのだろうか──ADHDがこれだけ増えたことを考えるとそう疑いたくなるほどだ。爆発的に増加していて、アメリカでは子供と若者の3%だったのがわずか20年で15%にまで増えた。州によっては20%を超える所もあり、ミシシッピー州では男子の30%(なんと3人に1人)がADHDだと診断されている。
かくいうスウェーデンも数年遅れで必死に追いつこうとしている状態だ。子供や若者の5%がADHDだと診断されており、その増加傾向は止まりそうにない。2020年には男の子の7.3%、女の子の4.72%がADHDの薬を処方されていて、15年で4倍および9倍になっている。
この爆発的増加に商業的利益が関わっていることは火を見るよりも明らかだ。ADHDはビッグ・ビジネスであり、薬は年間250億ドルの収益を上げている。つまり製薬会社には薬を猛烈に勧めるだけの理由がある。
「ニューヨーク・タイムズ」紙によればADHDの薬を製造している製薬会社は1社残らず、「誤解を招くマーケティングを行った」という判決を受けている。製薬会社が狡猾なキャンペーンを行った結果、医師だけでなく一般市民も「子供も大人も高い割合でADHDだ」と納得してしまった感が拭えない。何もかも薬の需要を増やすためにだ。
■これは「間違った善意」
今の時代、少しでも精神的に問題があれば診断を受け、薬によって治療するというのが当たり前になった。1錠の薬があらゆる精神的問題を解決してくれればいいのだが、それは考えが甘すぎる。皆が躍起になって診断名をもらおうとしているのは『精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)』の売れ行きを見てもわかる。
1950年代に出版されて以来改訂を重ねるハンドブックで、精神医学の診断を下す際にも使われる。退屈なタイトルのこの本がベストセラーだとは想像もつかないだろうが、実は最新版だけで9億クローネ[およそ130億円]の売り上げを誇る。
刊行当初は一部の心理学者や精神科医が購入していた程度だったが、改訂を重ねるごとに売り上げが増え、今では世界で最も売れる書籍になった。
これほど多くの人がADHDだと診断されるなんて、何かの陰謀かと思う人もいるだろう。私自身は医療従事者として、「間違った善意」なのだと感じる。たいていの場合は性急に診断が下され、好奇心やエネルギーの強さが発達障害と取り違えられてしまう。
その可能性が数字にも表れていて、同じ学年でも遅い時期に生まれた子供に発達障害が多い。それも小さな差ではなく、1月生まれと12月生まれの男子では40%もの開きがある[スウェーデンは同じ年の1月〜12月に生まれた生徒が同じ学年]。
12月と1月で誕生時の環境が大きく異なるわけではないし、年が明けたからといって急にADHDの子供が生まれる可能性が下がることもない。これは成長の未熟さがADHDだと誤解されるせいだ。小学校低学年の子供にとって11カ月の差は大きい。
写真=iStock.com/Thx4Stock
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Thx4Stock
■「正常」の範囲が狭くなっている
「爆発的増加」の背後にあるのは企業の利益だけでなく、私たち人間の人を分類したいという欲求も大きいのだと思う。世の中が複雑だからこそ、初めて出会う人や物は素早く正しい引き出しにしまってしまいたいのだ。
この人は信用できるが、あの人とは距離を取った方が安全だ。この植物は食べられて、あの植物は病気になる。あの動物は危険だ──という具合にだ。
周囲の世界、中でも人を分類するという行為は歴史的にも生き延びるのに役立ってきた。驚くべきことに、脳は目に入ったもの(例えば相手の態度)に小さなパターンを探し、素早く正しい引き出しにしまおうとする。そして現代の「引き出し」には精神医学の診断名がついたものもある。
「あの人、絶対ADHDだよ」「彼はちょっと双極性障害っぽくない?」「うちの叔母さんは自閉症に違いない」といった具合だ。診断名がメディアの記事にも溢れ、あちこちで目につく。目につけばつくほど「正常」だと見なされる範囲が狭くなる。
これは危惧すべき傾向だと思う。あれこれ診断を下すよりも、本来は「正常」のスペクトラムが広くあるべきなのだ。自分のために診断名を使うだけならまだしも、現実に影響が出ては危険だ。「あなたは双極性障害ぎみだ」と言われたら、薬でしか治せない欠陥が自分にあると思い込んでしまうかもしれない。
同じことがADHDにも言えて、「自分はどこかがおかしい」「どうしても開かない人生の扉がいくつもある」と感じてしまう。診断自体に何の価値もないばかりか、現実を間違った方向に簡略化してしまう恐れがあるのだ。
診断を下す唯一の理由は最も辛い状態にある人を助けるためでなくてはならないと思う。
■今後も増える傾向
全員ADHDの傾向があり、そのグラデーションのどこかにいるわけだが、その内の何人に診断が下るべきなのだろうか。「正常」の範囲から大きく逸脱するのは5%だとするのか、あるいは10%? それとも20〜30%が妥当なのか。
正しい答えなどない。境界線は私たちが決めて引くものだし、根本的には医学というよりも「社会が何を正常とするのか」という哲学的な問いになってくる。
では医学の専門家はどう考えているのだろうか。世界で最も権威ある医学雑誌のひとつ『ランセット』によれば、一部の専門家は人間の3%がADHDだと考えている。しかし5%と考える専門家、少数だが7%とする専門家もいる。名のあるADHDの研究者で20%を支持する人はまずいない──いるかどうかも怪しい。しかしアメリカの州によってはそれだけの割合の子供や若者がADHDの診断を下されているのだ。
これらの要因をすべて足してみよう。
人間が生来持つ「分類したい」欲求、診断基準にはっきりとした線引きがないこと、ほとんどの人にADHDの傾向があること、薬で集中力が改善する人が多いこと、企業が利益を追求していること。
その他にADHDの診断が下るかどうかに興味を示す団体としては学校がある。ADHDの生徒の支援に自治体から予算が出る場合があるからだ。そうするとこんな結果になるのはやむを得ない。今後も診断される人の数は増え、薬もさらに処方されるだろう。それが今起きていることなのだ。
■誰もがADHDの傾向を持つのに
一体どこまで増え続けるのか──答えはもちろん誰にもわからないが、まだ当分続くと考えざるを得ない理由がある。誰もがADHDの傾向を持つのは全員背の高さが違うのと同じことだ。
身長や集中力が歴史的にどのように見られてきたのかを考えてみよう。19世紀中盤にはスウェーデン人男性の平均身長は167センチだったが、今ではそれが181センチに伸びている(栄養状態が良くなり、子供の頃に感染症に罹ることが少なくなったためだと考えられる)。
アンデシュ・ハンセン『多動脳』(新潮新書)
ということは19世紀中盤に177センチだった人は「背が高い」と思われたが、今は思われない。同じことが集中力についても言える。150年前は今ほど集中力を求められることはなく、例えば農場や工場で肉体労働をするなど、集中が苦手な人に向いた仕事も多くあった。しかし現在ではそういう仕事はほとんど消えてしまった。
社会が複雑になり、ますます高い知能が求められるようになり、学校や職場で期待される集中力の基準を下回ってしまう人が増えたのだ。だから今後も増加傾向にあると考えられる。
ロボット工学やAIといった技術が急速に発展し、生活は楽になるが仕事は合理化され、人間に残された業務にはより高い知能が求められる。そうするとなかなか仕事に就けない人は「自分には精神的な障害があるのかも」と疑い始めるだろう。
■ADHD薬の深刻な副作用
アメリカでは子供の10人に1人がADHDだと診断されているが、「同じ状況になるのは避けるべきだ」とスウェーデンのテレビの生放送で指摘したことがある。すると、「なぜそうやって多くの人に診断が下ったら良くないんですか?」と問い返され、一瞬答えに窮した。
むやみに診断を大盤振る舞いすべきではないのは当たり前として、診断にはちゃんと根拠があるはずなのだ。診断を下される人が多過ぎたら誰がどう困るのだろうか。
ADHDの診断が下るとほとんどの場合は薬を処方される。では学校の生徒全員に薬を出したらどうなるのだろうか。特に問題がない子供の集中力も上がるだろうか──おそらく上がるだろう。ADHDの傾向が強くない子もそれまでより頭が冴えるだろうし、注目すべきことに注目し、集中し、学校の成績や仕事の業績も上がるだろう。
アメリカの大学生の6人に1人がテスト前に集中的に勉強するために違法に薬を購入しているという事実からもそれがわかる。ある学生が薬に「ともかくやってしまうための薬」というわかりやすい名前をつけたほどだ。
集中力を強化してくれるなら、なぜ処方箋なしで薬局やスーパーで買えるようにしないのか。頭痛薬なら買えるのに。そこには複数の重要な反対論がある。ADHD薬には深刻な副作用があり、人によっては強い不安を引き起こすのだ。
写真=iStock.com/timnewman
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/timnewman
■治療しないことのメリット
食欲減退や睡眠障害、あるいは気分に変化がある人もいる。何十年も薬を飲み続けた人の心臓にどういう影響があるかもわかっていない。実際、心臓への悪影響を警告する心臓専門医もいる。
そもそも医療というのは常にメリットとデメリットを比較する行為だ。単に治療の効果と危険性を比べるだけではなく、治療をしないことのメリットとデメリットも考慮に入れなければならない。
医師は一般論を語るのには慎重になるべきなのだ。患者100人にまったく同じアドバイスをしたら99人には効果があるかもしれないが、1人だけ大変な問題が起きるかもしれない。だからこそ医師は患者1人1人の情報を可能な限り集め、慎重にメリットとデメリットを比較してからどういうアドバイスをするか決めているのだ。
■本当にADHDの子供の割合
副作用があることや長期的なリスクが不明なことがADHDの薬を気軽に出さない理由だ。それと同時に、大きな問題を抱えた人に薬を出さない場合の影響も考慮しなければならない。薬なしでは学校の勉強もできない状態なら、その子供は高い代償を払うことになる。このように様々な要因を検討するべきなのだ。
メリットとデメリットを比較すると、重い問題を抱えた患者の場合は薬を飲むメリットが上回るだろう。しかしそれほど大きな問題を抱えていない人は──私たち全員にADHDの傾向があることを考えるとそういう層は確実に大きいのだが──危険性がメリットを上回る。
その場合は様子を見るか、他のことをすべて試した上で薬を最終手段にするべきだ。
では結局、ADHDの子供はどのくらいいるのか。個人的には5%程度だと思っている。そしてその半分が薬を必要としていると考えるのが妥当だろう。ということは子供の3%弱、平均して1クラスに1人が薬を処方される計算だ。
----------
アンデシュ・ハンセン(あんでしゅ・はんせん)
精神科医
ストックホルム商科大学で経営学修士(MBA)を取得後、ノーベル賞選定で知られる名門カロリンスカ医科大学に入学。現在は王家が名誉院長を務めるストックホルムのソフィアヘメット病院に勤務しながら執筆活動を行い、その傍ら有名テレビ番組でナビゲーターを務めるなど精力的にメディア活動を続ける。『運動脳』は人口1000万人のスウェーデンで67万部が売れ、『スマホ脳』はその後世界的ベストセラーに。
----------
(精神科医 アンデシュ・ハンセン)