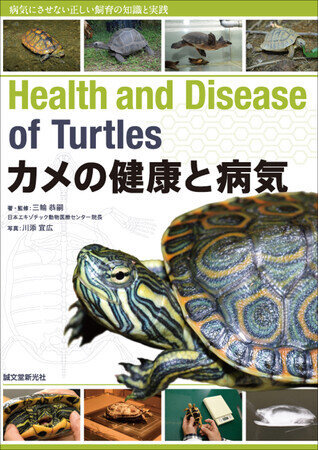「肝臓病=お酒の飲みすぎ」は大間違い…内科医が「病気の原因探しに固執しないほうがいい」と警鐘を鳴らすワケ
2025年4月22日(火)12時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/takasuu
写真=iStock.com/takasuu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/takasuu
■病気の原因を特定したい気持ち
「何が原因だったのですか? 食事が悪かったのでしょうか」
これは私が「進行膵がん」を告知した患者さんから投げかけられた質問です。一般的に膵がんのリスク因子は、糖尿病、アルコール摂取、喫煙、肥満といったところですが、この患者さんはひとつも当てはまりませんでした。つまり、膵がんになった原因はわからないとしかいいようがありません。
がんのように重い病気にかかったとき、患者さんが原因を知りたいと思うのは自然なことです。ところが、必ずしも原因がわかるとは限りません。というか、原因が明確であることのほうがまれだといったほうがいいでしょう。
例えば、喫煙者が肺がんになったとします。喫煙が肺がんのリスク因子であることは確実です。でも、それは集団における確率の話であり、個々のケースにおいて喫煙が肺がんの原因だとは断定できません。
日本人を対象とした研究で、喫煙者は非喫煙者に比べて3〜4倍ほど肺がんにかかりやすいことがわかっています。ということは、肺がんになった喫煙者の3分の1〜4分の1は、喫煙していなくても肺がんになった可能性があるということ。非喫煙者が肺がんになるケースがあることからも、喫煙者が肺がんになったケースでも必ずしも原因が喫煙「だけ」とは限らないことをご理解いただけると思います。
■「公正世界仮説」がもたらす影響
となると、「タバコが原因でなければ、何が肺がんの原因なのか?」という疑問が湧いてくるかもしれません。喫煙以外の肺がんのリスク因子としては、特定の職業における発がん性物質(アスベスト等)への曝露、大気汚染、糖尿病、結核やHPV(ヒトパピローマウイルス)などの感染症、ラドンガス、調理時の油煙や室内での石炭燃焼による煙などが知られています。しかし、こうしたリスク因子がなくても、肺がんになるときはなります。結局のところ、病気の原因はわからないことが多いのです。
このような状況を、心理的に受け入れがたいと思う人も少なくありません。「公正世界仮説」といって「この世界は公正であり、よい行いにはよい結果が、悪い行いには悪い結果がもたらされる」という心理的バイアスがあるせいかもしれません。
よい行いをすれば報われ、悪い行いには罰が下る——そう信じたい気持ちはよくわかります。でも、病気にまで当てはまると考えると話は複雑になります。重大な病気の裏には、喫煙や不健康な食事といった悪い行いという原因があるはずだと考えてしまうことにつながるからです。
タバコが原因だと考えて禁煙するなど、体に悪いことをやめるのであれば、好ましい変化だといえます。しかし一方で、「これを食べればがんが治る」といった、根拠の乏しい食事療法などに傾倒するケースも見受けられます。
■根拠のない食事療法には害しかない
がんを治すことが証明された食事療法は、現時点では存在しません。しかし、インターネットや書籍には、がんを治すと称する食事についてのニセ情報があふれています。その背景の一つに、「がんの原因がきっとあるはずだ。毎日の食事がその原因に違いない」という思い込みがあると私は考えます。いわゆる「がんを消す食事」を扱ったインチキ健康書の多くにも、似たような主張が繰り返されています。
バランスのよい食事ががんのリスクを下げるのは事実ですが、どれほど努力して健康的な食生活を送っていても、がんになるときはなってしまいますし、ましてや、がんが食事だけで治ることはありません。根拠のない食事療法は、効果がないばかりか、栄養が偏ったり食事の楽しみを奪ったりする害が大きいのでおすすめできません。臨床医は、こうした誤解に対して敏感であるべきです。不適切な食事療法によって患者さんの生活の質が低下することのないよう、注意深く見守る姿勢が求められます。
私たちにできるのは、コントロールできる範囲のことを淡々と積み重ねること。できないことにこだわらず、起きた結果をそのまま受け止め、現実と折り合いをつけて生きていくことではないでしょうか。
■「肝臓病=お酒のせい」という偏見
「病気の原因探し」の弊害は、がんに限りません。私の専門は肝臓内科ですが、「肝臓病といえば、お酒の飲みすぎ」という誤解をしている方にたびたび出会います。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
たしかにお酒を飲みすぎれば、「アルコール性肝障害」をはじめとした肝臓病になることは確かです。でも、あらゆる肝臓病が、お酒の飲みすぎによって起こるわけではありません。アルコール性肝障害以外にも、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどによる「ウイルス性肝炎」、自己免疫疾患による「自己免疫性肝炎」や「原発性胆汁性胆管炎」、代謝異常に関連する「脂肪性肝疾患」など、肝臓病の原因は多様です。
それなのに「肝臓の病気=お酒のせい」というイメージが根強いため、患者さん自身が「お酒を飲んだ罰」のように受け止めてしまうケースもあります。これは医学的には不正確であり、同時に患者さんを不必要に傷つける偏見です。
なお、さらに付け加えるなら、たとえアルコール性肝障害になったとしても、その背景には「アルコール依存症」といった疾患があることが多く、本人の努力や意志の強さだけではどうにもならない部分があることを理解しておかねばなりません。
■「生活習慣病」という呼称が招く誤解
こうした「○○のせいで病気になった」という単純で一面的な決めつけは、がんや肝臓病に限らず、そのほかの多くの慢性疾患でも見られます。
特に「生活習慣病」という言葉が広く使われるようになってからは、病気になった人への自己責任を問う風潮が、社会の中で確実に強まってきたように思います。こうした背景もあってか、最近では「生活習慣病という呼称は本当に適切なのか」と疑問を呈し、見直しを求める声も上がるようになってきました。
生活習慣病は、その名の通り、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣が主な原因となる疾患群を指し、糖尿病、高血圧、脂質異常症、さらにはそれらがリスク因子となる脳血管障害、心疾患、がんなどが含まれます。
こうした生活習慣がさまざまな疾患のリスク因子であることは間違いありません。そうした関係を社会に広く知らせ、病気予防の意識を高めてきたという点で、生活習慣病という呼称や考え方が果たしてきた役割は小さくないでしょう。ただ、その一方で、この呼称が「病気になったのは本人の生活習慣が悪かったからだ」という、単純な自己責任論につながってしまう危うさも否定できません。
写真=iStock.com/takasuu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/takasuu
■病気について安心して話せる社会へ
実際の病気の発症には、遺伝的な体質、働き方や収入といった社会経済的な要因、さらには環境要因など、さまざまな背景が複雑に関与しています。そして、病名や疾患の呼び方は、当事者が自分をどう捉えるか、周囲がどのように理解するかを左右する、非常に大きな力を持っています。社会的な偏見やスティグマを生まないよう、今改めて、言葉選びに丁寧な議論と配慮が求められているのではないでしょうか。
「生活習慣が病気のリスクに関係する」という知識は、誰かの努力不足を責めるためのものではなく、みなさんの健康を守るための大切なヒントです。ですから、「生活習慣の改善を通じて健康になろう」と啓発すること、「病気の原因は不健康な生活習慣とは限らない」と誤解を解くことは矛盾せず、本来は同じ方向を向いた取り組みといえます。健康的な生活が病気のリスクを下げることは確かですが、それをもってすべての病気を防げるわけではないからです。
病気になることは、誰のせいでもありません。単に「運が悪かった」としか言いようがないケースも多々あります。こうした理解が広がっていけば、きっと私たちの社会は、病気になっても安心して声を上げられる、もっとやさしい場所になっていくはずです。
----------
名取 宏(なとり・ひろむ)
内科医
医学部を卒業後、大学病院勤務、大学院などを経て、現在は福岡県の市中病院に勤務。診療のかたわら、インターネット上で医療・健康情報の見極め方を発信している。ハンドルネームは、NATROM(なとろむ)。著書に『新装版「ニセ医学」に騙されないために』『最善の健康法』(ともに内外出版社)、共著書に『今日から使える薬局栄養指導Q&A』(金芳堂)がある。
----------
(内科医 名取 宏)