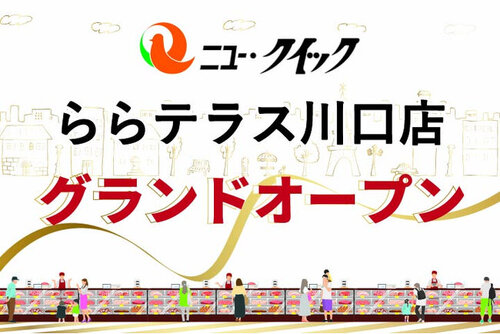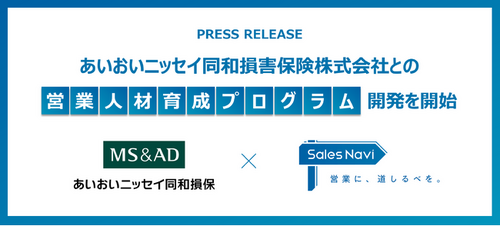だから営業は不人気職種になった…キーエンス→プルデンシャルの元トップセールスが語る「営業組織」の大問題
2025年4月24日(木)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/metamorworks
※本稿は、田中大貴『売れる組織 売れる営業』(実業之日本社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/metamorworks
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/metamorworks
■生き残る営業とAIに代替される営業
現在、日本で営業職に就いている人は800万人程度と言われています。
営業職は、これからもなくならないとは思います。
ただ、営業職の就労人口は減っていくと考えられます。販売職も含めると、おそらく半減するのではないでしょうか。
現在も拡大を続けるeコマースや、販売ができるAIに取って代わられるからです。労働人口の減少やコスト削減など、社会状況を考えてもその流れが加速していくことは間違いありません。
また、レベルの低い営業パーソンに気分を悪くさせられるぐらいなら、自分で選択できるeコマースや能力の高いAIで十分だと顧客が考えるのは自然なことです。
AIの技術革新は想像以上に目覚ましく、営業の現場でも、数年先と思われていたような実践的な「AIエージェント」の活用が進んでいます。
AIエージェントとは、与えられた情報をもとにAI自身が考え、行動し、まるで人間の代理人かのようにさまざまなタスクを実行してくれるAIプログラムのことです。
まだ能動的な営業活動ができるわけではありませんが、顧客側が営業を受ける相手を、人間かAIかを選べる時代は目前まで迫っています。
付加価値が高い商材はまだ人間の営業の存在価値が大きく、取って代わられにくいと考えていましたが、そうとも言っていられない状況になっています。
■自分の欲しいものが明確であればあるほど、営業の助けは必要ない
洋服を買いにショップに入ったときを想像してみてください。
自分が欲しい商品はある程度決まっているのに、店員さんが寄ってきて新作の話を延々とされたり、興味のないアイテムを勧められたりしたら、せっかくの買い物が台無しです。
そんな経験をするぐらいなら、ショップに入ると人ではなくAIが「どんなものが欲しいですか」と聞いてきて、欲しいものを伝えると即座に「こんなコーディネートはいかがですか」と提案してくれたほうが、気分良く買い物ができます。
これはアパレルにかかわらず、さまざまな場面で出くわすことです。自分の欲しいものが明確であればあるほど、営業の助けは必要ありません。
たとえば生命保険の世界でインターネット専業の生命保険会社、ライフネット生命が支持されているのはそういう理由です。すでに生命保険に加入していて、生命保険についての知識は持っている。
足りない保障を補いたいという目的が明確で、商品のラインナップを見れば目的に合う保険は自分で探せる。そういう人はわざわざ営業パーソンを介さなくても、自分で選んで契約すればいい。
営業パーソンが介在しないため、その分安い保険料で契約することができる。メリットは大きいのです。
■営業パーソンの価値はここにある
田中大貴『売れる組織 売れる営業』(実業之日本社)
一方で、自分の求めているものがはっきりしておらず、営業に相談しながら決めたいという人もいます。
保険で言えば、「保険への加入に興味はあるが、どの保険が自分に合っているかわからない」という人が実店舗に足を運び、そこで窓口の担当者に相談して加入する保険を選ぶという「ほけんの窓口」のような保険代理店がそのようなニーズに応えています。
この例からは、どの分野にも知識を持ち合わせていない人は必ずいるため、そういった顧客に対しては人間の営業が介在する価値があるということが言えるでしょう。
写真=iStock.com/maroke
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
生命保険に関する知識がない人に対して、保険の必要性を感じてもらうためには、人間の営業職の介在が必要であり、そこにこそ営業パーソンの価値があります。
いずれこの領域にもAIが応えていく未来は近いでしょうが、このような能動的な営業はいまのところ人間にしかできません。
■「型」を身につけ、専門家になれ
しかし、間違いなく言えるのは、どの営業スタイルであれ、営業職は「専門家」にならなければ生き残れないということです。
なぜ、顧客は営業パーソンに頼るのでしょうか。それは、その分野の専門家として、自分が抱えている課題を解決してくれると思っているからです。ただ単に、顧客の欲しいものを売るだけでは、顧客の満足度は高まりません。
プルデンシャルでは営業職のことを「ライフプランナー」と呼んでおり、ライフプランナーは医師や弁護士のように人々にとってなくてはならない専門家になるべきだと言い続けています。
だからこそ、営業職が専門的な知識を持つことは顧客に対する礼儀で、それがなければ顧客の前に立つ資格はないとまで言っているのです。
専門知識がない営業は、顧客にとってはAIよりも優先順位の低い存在になってしまいます。
別の視点で考えてみましょう。
営業職として専門家になれば、どんな企業にも移ることができます。営業としてのコアとなる部分はどの企業でも変わらないので、それぞれの企業ならではの専門知識をその都度マスターすることができれば、営業パーソンとしてのキャリアを自在に変化させることも可能です。
問題は、そのコアの部分が確立されていないことです。
これは、営業パーソン個人の問題というより、企業が営業の型を身につける環境を整えられていないことに要因があります。型は個人として身につけるべきことであり、企業として整理すべきことでもあります。
図表1、2をご覧ください。
出典=『売れる組織 売れる営業』
出典=『売れる組織 売れる営業』
昨今よく話題になるのが日本企業の生産性の低さです。
G7に加盟する7ヶ国のなかで、日本のGDP(国内総生産)はアメリカ、ドイツに次ぐ3番目の水準です(図表1)。ところが、時間あたりの労働生産性で見ると、圧倒的な低さの最下位です(図表2)。
なおかつ、営業生産性に関して日本とグローバルを比較したデータを見ても(図表3)、日本は多くの業種において、グローバル水準より劣っているのが現状です。日本全体だけでなく、日本の営業分野においても、きわめて生産性の低い状態が続いているのです。
出典=『売れる組織 売れる営業』
■圧倒的に人材不足の営業職
そうした一般的な知識を持ったうえで、図表4をご覧ください。
人材不足の職種ランキングを見ると、営業職が抜きんでて足りない状況が見て取れます。生産性が低いうえに、人材が不足している。この事実は、何らかの問題を内包していると考えていいでしょう。
さらに、人材不足の原因としてもっとも多いのは「退職による欠員」です。それに続く「中途で採用できない」という項目もあわせて考えると、営業職に対して多くの人が魅力も感じていないという事実が浮き彫りになります。
出典=『売れる組織 売れる営業』
人材不足の職種ランキングと人材不足の原因を掛け合わせると、営業職はかなりの人材不足に陥っているにもかかわらず、離職率も高く、採用の募集にも応じてもらえないという仮説が成り立ちます。その原因となるのが、営業の負のサイクルです。
教科書がないからやり方がわからず、成果があがらないことを上司に責められ、どうしていいかわからず営業が嫌いになり、やがて辞めていく。
その負のサイクルのイメージは広く流布され、あえて営業職に就きたいと考える人が増えない。これでは、営業の生産性が上がるはずはありません。
生産性が上がらない要因は、営業の教科書がないこと、経験でしか伝えられていないこと、組織として営業の仕組みと型をつくっていないことなどです。
こうした営業に関する現状認識を、知識として常にアップデートさせていく。こうしたことも営業パーソンとして必要な姿勢です。
現在地がわからなければ、どの方向にどれだけ進めばいいかわかりません。己を知ってはじめて、顧客のことを知るための準備ができるからです。
■感覚に頼った営業、教育体制はもはや通用しない
営業の世界は、これまでずっと「OJT文化」でした。
なんとなく先輩の営業に同行し、先輩はこんなふうにやっているのか、となんとなく学び、自分も見よう見まねでやってみて「なんとなくこういう感じかな」という感覚を身につける。
そのうち自分流のやり方を見つけ、気づいたときにはなんとなく自分流の営業スタイルができている。すべてが「なんとなく」なのです。
しかし、先輩によって言うことはまちまち、受け取るほうもセンスがある人とない人で異なるために、再現性はまったくありません。
しかも、なんとなく身につけたやり方であるため、言語化ができません。いざ聞かれても、売れる営業でさえ成果をあげられている理由を明確に言語化できないのです。
「どうしてあなたはそんなに成果が出せるのですか?」
「ただ普通に営業しているだけだけど。逆に、どうしてできないの?」
「うまいこと顧客の懐に入り込めるのは、どういう秘訣があるのですか?」
「ただ普通に会話をしているだけだけど。逆に、どうしてできないの?」
すべてが感覚なのです。
裏を返せば、言語化ができなくても売れる営業にはなれます。センスという言葉で片づけたくはありませんが、本書で紹介する知識、スキル、習慣・管理、心構えという営業において重要な4つの要素をある程度備えていて、運や縁に恵まれたひと握りの人が売れる営業になっていくのです。
かく言う私も、当初は言語化などできませんでした。
幸運なことに、キーエンスからプルデンシャルに転職した経歴に興味を持っていただき、営業を始めて5年目ぐらいにセミナーの講師の依頼がありました。その準備をしていたとき、はじめて気づきました。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
「セミナーで、何をどうやって話せばいいのだろう?」
言語化できないことに焦りました。このままではセミナーにならない。そう思い、必死で営業についての要素を棚卸しし、それを言語化することに努めました。
その結果、どうにかセミナーをやり遂げることができました。その後も幾度となく「田中大貴営業セミナー」という小さな営業塾が催されることになり、内容をブラッシュアップするために言語化する訓練を積んでいきました。
ほとんどの営業パーソンには、そのような機会はありません。そうなると、言語化する必要性を感じることもないのです。脳内の知識を誰かに伝える機会もなく、その知識は暗黙知のまま営業パーソンそれぞれの脳内に感覚として放置されます。
形式知にならない知識は、埋もれたまま共有されませんから、「売れる組織」になりようがありません。「売れる組織」が増えなければ、「売れる営業」も増えず、労働生産性も上げられないままになってしまいます。
■トップセールスに依存しない組織の営業力強化
企業の大半は、一部のトップセールスの成果に依存しています。なおかつ、安定した成果をあげる人もいれば、不安定な人もいるというバラつきが生じています。
キーエンスには、土台となる営業の型がしっかりとつくり込まれていたので、その不安定さはありませんでした。
つまり、営業の型がない企業の成果は、0から100までのバラつきがある一方で、営業の型がある企業のバラつきはかなり小さくなり、おおむね50から100までの間に分布するイメージです。
このバラつきを可能な限りなくし、営業力の底上げができれば、組織の生産性は必ずアップします。
この点、プルデンシャルは成果に応じて自身の報酬が決まる「フルコミッション制」のため、キーエンスに比べてどうしても個々の営業パーソンにおける成果にバラつきは生じていました。
しかし、プルデンシャルには「ブルーブック(保険営業の教科書)」というまさに営業のバイブルがあります。入社後に受ける研修のなかでブルーブックの内容を学び、営業の型を身につけることで強い組織になっている点は、キーエンスとの共通点です。
型を身につけるための教育体制と組織としてのカルチャーがあること。この2点が、2社の共通点であり、営業の強さの源泉です。
教育体制においては、両社ともに入社してすぐに手厚い研修を受けることになります。その間、現場に出ることはいっさいありません。
対して、多くの会社は数週間から1カ月程度の研修を受けたら、次にはすぐに現場に放り込まれます。先輩の営業を見て覚える。自分の営業に同行してもらい、先輩からフィードバックを受ける。
運良く、相性のいい先輩や上司、顧客と出会うことができればいいのですが、反対であれば厳しいスタートになる可能性が高いでしょう。この時点で運の要素に大きく左右されます。
■効率を追求するキーエンス、自由度に任せるプルデンシャル
またカルチャーは、キーエンスとプルデンシャルではある意味正反対です。本書で詳しくお話ししていますが、効率を追求することでその先に結果があるとするキーエンスに対して、プルデンシャルは型の部分以外は本人の自由度に任せ、メンバーの感情をうまく鼓舞することで結果に繋げるという社風です。
カルチャーは正反対ですが、それを組織に根づかせるために両社ともあらゆる方法を用いています。
厳密には、フルコミッションで自由な社風のプルデンシャルにおいて、営業パーソンの成果にバラつきが生じてしまうのは、先述したフルコミッション制であることに加え、見込み客(リード)を自分で発見しなければならないからです。
プルデンシャルでも企業側が見込み客の提供をしてくれれば、まったく異なる結果になっていると考えられます。
このような例外はあるにせよ、営業の型があることによって、成果のバラつきを50から100までの間に縮小できることに間違いはありません。
----------
田中 大貴(たなか・だいき)
Sales Navi 代表取締役
2008年同志社大学文学部を卒業後、キーエンスに入社。連続で目標を達成したのち、2010年にプルデンシャル生命保険にスカウトされ入社。以来11期連続社長杯入賞。2017年に、当時全国最年少でエグゼクティブ・ライフプランナー(部長)に就任。2017〜2021年度には、日本の生命保険募集人登録者、約120万人のなかで上位0.01%しかいないとされるMDRT TOT会員に認定される。順風満帆な営業人生を送る一方で、「道しるべがないがために営業に悩んでいる組織や人」の存在を知り、「営業の道しるべを創る」というビジョンを掲げて2021年にSales Naviを創業。事業を推進する傍ら、ひとりでも多くの営業パーソンが抱える課題や悩みを解決したいという想いから「営業の教科書」をつくることを決意し、『売れる組織 売れる営業』を執筆。
----------
(Sales Navi 代表取締役 田中 大貴)