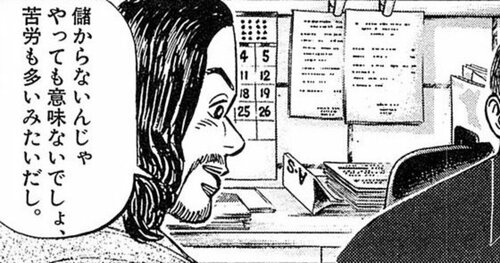京都人の「ぶぶ漬けどうどすか」は「高度な嫌み」ではない…"遠回しのフレーズ"に込められた本当の意味
2025年4月28日(月)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/HanzoPhoto
※本稿は、小野純一『僕たちは言葉について何も知らない 孤独、誤解、もどかしさの言語学』(NewsPicksパブリッシング)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/HanzoPhoto
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/HanzoPhoto
■京都人の「ぶぶ漬けでもどうどす?」
京都で「ぶぶ漬け(お茶漬け)でもどうどす?」と言われたら、「はよ帰れ」と理解しなければいけないという話があります。日本、特に京都ではこのような「空気を読む」とか「行間を読む」ことが重要だとされます。
このように文脈依存度が高い文化をハイコンテクストの文化といいます。共有される常識や文脈に依存する割合が高いコミュニケーションを普段から行う文化のことです。京都はこの文化を高度に発展させたコミュニケーションの場となっているとされます。
このことは、日常会話では言語が情報伝達よりも〈情動への効果〉という機能に重点を置いている、という問題と直接関わります。
京都を特徴づけるこの表現そのものが、実際に京都でいま使われるかは別にしても、このことが一般に知られている点が重要です。それは、京都では、言いづらいことを遠回しに言う〈センシティブ〉な言語行為が実践されることをよく示しているからです。
京都の「いけず文化」とか「高度な嫌み」と言われる表現は、摩擦を避けるための言語行為だといえます。しかし、〈センシティブ〉な言語行為は京都に限定されません。
■トイレの「いつもきれいにご利用いただき…」も同じ
たとえば、私の住んでいる関東でも、日本の各地でも、公衆トイレに「いつもきれいにご利用いただき、ありがとうございます」と張り紙があります。
これを読んだ人が、「このトイレを初めて使う人もいるのに、何言ってるんだろ」と理解するなら、その人はもう少しコミュニケーション能力を開発するか、社会性を身につけるようにしなさい、と言われかねません。
写真=iStock.com/yugoro
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/yugoro
なぜなら最初から、「ありがとう」は「汚すな」という命令として機能しているからです。これを、文字通りに「お礼」だと理解すべき内容の文だと理解するなら、理解力に問題がある、〈センシティブ〉ではないと思われてもしかたありません。
「いつもきれいにご利用いただき、ありがとうございます」は、たしかに汚させないことを目的とした文ですが、聞き手が可能なかぎり不快にならない、ということも含んでいます。そして、この相手への配慮は、日常会話において決して二次的で重要性の低いものではありません。むしろ、この言語表現では、相手への配慮がきわめて重要な目的として意図されています。
■文字通りの意味だけを捉えるのは浅はか
いわゆる「遠回しに言う」という形式は、〈センシティブ〉であることを最優先した苦心の結果です。こういった文字通りではない表現を、私たちは日常的に行っています。
「おはよう」は別にそこまで早い時間でなくても言うでしょう。もし文字通りの意味を伝えるのが言語の本質なら、遅れてきた人には「お早うございます」ではなく「お遅うございます」と言うことになるでしょう。
そこには「あいさつによって相手の存在を認めていることを伝える」意図はありません。そこにあるのは、事実だけを伝える情報交換です。
ほとんどの人は無意識に、言葉を文字通りには理解していません。だから、「お遅うございます」を嫌みととらえることになるのです。文字通りの意味が言葉の本質だと考えるのは少々〈浅はか〉ということになってしまいます。
■だから日本語の自動翻訳は難しい
言葉の意味とその対象が、1対1で対応するような「一義性」の考えかたは、記号的でデジタルだといえます。これに対して、実際の言葉は文脈に依存する割合が高く、意味の働きが「多義的」だといわれます。
しかし、「ぶぶ漬け」のときと同じように、「かげ」という言葉でも、それが陽の差さない場所か月の光か、あるいは人の姿か助力や援助かは、そのつど「一義的」です。この一義性は、記号的でもデジタルでもありません。だからこそ、AIを用いた自動翻訳は、なかなか完璧とはいかないのです。
小野純一『僕たちは言葉について何も知らない 孤独、誤解、もどかしさの言語学』(NewsPicksパブリッシング)
ただ、英語とフランス語、ドイツ語のような欧米語どうしでは、ほとんどデジタルに単語を置き換えるだけで、つまり言葉を1対1で対応させるだけで、大部分の翻訳ができる可能性があります。それは、言語の構造ももともとかなりの程度で同じであり、文化をかなりの程度で共有しているからでしょう。
哲学者の今道友信は『東西の哲学』第四章で、欧米の言語はふだんの使用でも、できるだけ記号的(デジタル)であり、日本語はできるだけデジタルでないように発展してきたと指摘します。そうだとすれば、欧米の言語で自動翻訳がうまくいき、日本語ではなかなかうまくいかないのも説明がつきます。
----------
小野 純一(おの・じゅんいち)
自治医科大学准教授
1975年、群馬県生まれ。自治医科大学医学部総合教育部門哲学研究室准教授。専門は哲学・思想史。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ベルギー・ゲント大学文学部アジア学科研究員、東洋大学国際哲学研究センター客員研究員などを経て現職。
著作に『井筒俊彦 世界と対話する哲学』(慶應義塾大学出版会、2023年)などがある。訳書にジェニファー・M・ソール『言葉はいかに人を欺くか』(慶應義塾大学出版会、2021年)、井筒俊彦『言語と呪術』(安藤礼二監訳、慶應義塾大学出版会、2018年)。
----------
(自治医科大学准教授 小野 純一)