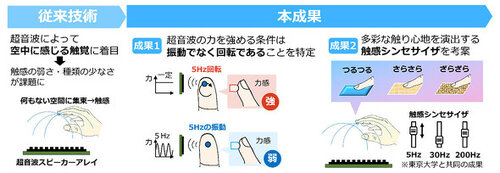「半導体世界一」の奪還はNTTにかかっている…「iモード失敗」から学んだNTTが「グループ大再編」を進める狙い
2025年5月19日(月)9時15分 プレジデント社
記者会見を終え、握手するNTTの島田明社長(左)とNTTデータグループの佐々木裕社長=2025年5月8日午後、東京都千代田区 - 写真提供=共同通信社
■バブル期、「世界一の企業」からの転落
5月8日、NTTは、データセンタの運営などを担うNTTデータの完全子会社化を発表した。その背景には、1990年代以降、NTTの地位が大きく後退したことがある。NTTは、ある意味で、バブル崩壊後の日本経済の低迷を象徴しているとも言えるだろう。
写真提供=共同通信社
記者会見を終え、握手するNTTの島田明社長(左)とNTTデータグループの佐々木裕社長=2025年5月8日午後、東京都千代田区 - 写真提供=共同通信社
バブルの絶頂期の1989年、NTTは世界最大の時価総額を誇る企業だった。ところが、その後の株価低迷もあり、2025年4月末現在、世界の時価総額トップは米アップル、2位はマイクロソフト、NTTは第199位に沈んだ。
バブル崩壊後、わが国の多くの企業は、新しいビジネスを生み出すことができなくなった。一方、米国ではIT革命で情報通信の重要性が大きく上昇し、大手IT企業が大きく成長した。また、中国、韓国、台湾は工業化を進め、世界的な水平分業体制を硬直することで圧倒的な競争力を高めた。残念だが、わが国企業はその波から取り残され、世界市場での地位は低下した。その象徴の一つがNTTともいえるだろう。
■「電電公社」の遺産が足かせに
NTTは、元々、日本電信電話公社であり制約も多かった。研究成果の開示を義務付けた法律も、NTTの業績を圧迫した。また、関連企業を分割したことで、横断的な活動が思うように進まなかった面もある。そうした状況からの脱却を狙い、今回、NTTはNTTデータを完全子会社化し親子上場を解消する。
NTTは、データ関連事業で得たキャッシュフローを次世代半導体である“光半導体”関連分野につぎ込み競争力の回復を狙った。それは必要な方策だが、光半導体分野では先進の欧米に加えて中国勢の追い上げが顕著だ。わが国企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、NTTの試みが成功するかは不透明な部分が多い。ただ、わが国経済の回復のためには同社の動きは必須で、是非とも成功してほしいものだ。
■電電ファミリーが支えた日本の繁栄
1985年、当時の電電公社が民営化された。85年といえば、わが国のバブルが始まる時期だ。その後、わが国の経済は高い成長を実現した。NTTは事実上の独占状態だった、国内の固定電話サービスから大きな収益を得た。その資金を、高速通信技術や半導体の研究開発に投下し成長を実現した。
当時、研究開発の拠点となったのは、NTTが運営する各種研究所だった。本業である通信をはじめ、通信ケーブルの素材開発や通信インフラに関する新しい手法、半導体の研究、宇宙開発などを積極的に展開した。まさに、NTTは電電公社時代から、幅広い分野で基礎・応用研究を積み重ね相応の成果を上げた。
当時、NTTの研究開発には、日本電気(NEC)、富士通、三菱電機といった国内の主要総合電機メーカーも協力した。NTTが取り組む通信技術の高度化は、わが国の総合電機メーカーのメモリー半導体の製造技術向上の波及効果をもたらした。
■世界の時価総額ランキングを日本が総なめ
その成果として、1980年代半ば、わが国の半導体産業は米国を上回り世界トップの競争力を手に入れた。1986年には、世界の半導体メーカートップ10のうち、6社がわが国の企業だった。1988年、世界の半導体市場でわが国は50%超のシェアを獲得した。
NTTは、わが国エレクトロニクス産業の成長の基礎を形成した。電電ファミリーの企業は、テレビをはじめとする家電やパソコン、通信機器など新しい需要の創出に取り組んだ。自動車と並んでカラーテレビなどの家電、トランジスター等の電子部品の輸出は増加した。
1985年のプラザ合意以降、わが国は米国の要請に応じて内需の拡大を重視した。緩和的な金融環境も加わり、成長期待は過度に高まり、株式と不動産の価格が上昇する資産バブルが発生し、わが国の経済は過熱した。
1989年末、日本株が当時の最高値を記録した時、NTTの時価総額は1639億ドルだった。2位だった日本興業銀行(当時、716億ドル)の2倍以上の規模だ。時価総額世界トップ5はNTTをはじめ日本企業がおさえ、第6位に入ったのが米IBMだった。
■バブル崩壊が招いた「守りの経営」
しかし、バブル崩壊の1990年以降、NTTの国際競争力は大きく低下した。バブルの崩壊で業績は悪化した。わが国経済は、1990年代初頭以降、不良債権処理の重荷もあり急速な景気の減速と資産価格の下落に直面した。1997年頃からデフレ環境も深刻化し、NTTは成長より経営の守りを重視したといえるだろう。
その間、NTTを取り巻く事業環境も変化した。1986年の第1次日米半導体協定以降、わが国の企業は韓国や台湾の企業に半導体製造技術を供与した。台湾や韓国の企業は、予想をはるかに上回るスピードで高度な製造技術を習得した。
1990年台中盤、米国ではIT革命が起きデジタル化が加速し始めた。米国の大手IT企業は、ソフトウェアの開発に集中するようになり、ハードウェアの製造は中韓台の企業に委託することが増えた。そして、世界的な水平分業が加速した。
■垂直統合にこだわり、世界の波に乗り遅れた
ところが、NTT、および関連企業は、製品の設計、開発、製造、販売を自己完結する垂直統合の事業運営を重視した。その結果、同社は世界の水平分業体制に大きく遅れた。中韓台の企業は国の支援もあり、意思決定のスピードを向上させた。それに加えて、米国企業からの製造受注を支えに、NTTグループを上回る競争力を発揮した。
NTT法も、同社の事業運営の足枷になった。電電公社民営化に伴い制定されたNTT法は、同社に全国にアナログ電話を提供することを義務付けた。それに加えて、NTT成長の基礎だった研究成果の開示も義務付けた。
デジタル化の時代、アナログ電話を保守し続ける責務は事業ポートフォリオの構造改革を阻害した。研究開発の成果を開示する義務は、競争相手に自ら収益獲得の重要な方策を教示することと言い換えてもいいかもしれない。
国内事業は縮小均衡し、iモード失敗も重なり国際競争力も低下した。それに加えて、NTTの競争力の源泉であった、通信や半導体関連の研究成果の開示義務が重なったことで、1990年代からNTTの業績は低迷傾向をたどった。それは、“失われた30年”などと呼ばれるわが国経済の長期停滞と似ている。
写真=iStock.com/ben-bryant
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/ben-bryant
■光半導体で逆転を狙う壮大な挑戦
NTTデータの完全子会社化により、2018年以降のNTTグループの再編は完結するとみられる。2024年4月、研究成果の開示義務を撤廃する改正NTT法も成立した。NTTはNECと業務資本提携を結び、かつての電電ファミリーとの結束を再度高めようとしている。
NTTが狙うのは、光半導体の早期の実用化だろう。NTTによると、光半導体の実用化で電力効率は100倍に高まる。伝送容量は125倍に拡張する。さらに、送信元から送信先(エンド・ツー・エンド)への遅延は200分の1に抑えられる。
それは、AIの成長に伴う世界的な電力需給の逼迫を解消し、ビッグデータの超高速伝送を実現する切り札になる可能性がある。今のところ、光半導体に関する実証研究において、NTTは主要国の中でもトップクラスの実績を持っているようだ。
■世界情勢の中で試される復活への道
NTTは、データセンタ関連事業で世界第3位のNTTデータを傘下におさめ、意思決定のスピード向上や、光半導体関連分野への資金再配分の積み増しを狙う。NTTデータの完全子会社化は、NTTが起死回生を狙う不可欠の策といえる。
ただ、光半導体分野などNTTの事業戦略が、期待通りに進むかは不透明な部分がある。光半導体分野では中国企業、研究機関の追い上げが猛烈だ。中国では、ファーウェイや浙江大学など研究機関が光半導体関連の研究開発を増強した。特許出願数で中国は世界トップだ。関連企業と中国電信(チャイナ・テレコム)が連携して、中国国内や一帯一路加盟諸国域で次世代の中国型の超高速通信網が普及する展開も想定される。
世界経済の先行き見通しも悪化しつつある。トランプ関税の影響により世界経済の成長率鈍化リスクは上昇傾向だ。米国の企業業績の悪化懸念も高まり始めた。本当に米国の主要企業の収益が落ち込むとなると、雇用環境は軟化し、米国の個人消費や設備投資も減少するだろう。
関税引き上げや人手不足で、米国の景気の後退と物価上昇が同時に進むと米国の株式や債券相場の不安定性は高まるだろう。NTTがそれらのリスクに対応し、関連企業との連携を深め、光半導体など次世代通信技術の実用化を実現できるか、先行きに楽観は禁物だろう。
----------
真壁 昭夫(まかべ・あきお)
多摩大学特別招聘教授
1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学院教授などを経て、2022年から現職。
----------
(多摩大学特別招聘教授 真壁 昭夫)