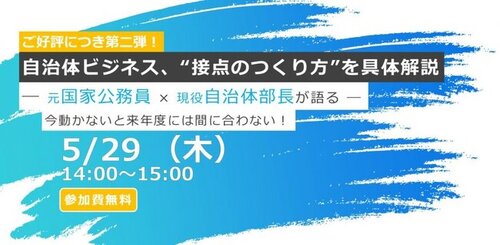トヨタが70億円を出資したインターステラテクノロジズ ロケットビジネスで日本が圧倒的に有利な理由とは?
2025年5月14日(水)4時0分 JBpress
ロケットや人工衛星と聞くと、多くのビジネスパーソンは「自分の仕事や日常とは遠い世界の話」と考えるかもしれない。しかし実際には農業、漁業、鉱業、金融、災害対策、地図、通信など、現代社会ではあらゆる産業に宇宙技術が活用され、人々の暮らしを支えている。本稿では『宇宙ビジネス』(中村友弥著/クロスメディア・パブリッシング)から内容の一部を抜粋・再編集、壮大な宇宙空間が生み出すビジネスの可能性を探る。
スペースXが主力とする大型ロケットと対照的に、インターステラテクノロジズなど国内企業で開発が進む小型ロケット事業。宇宙輸送における日本のビジネスチャンスとは?
ロケットビジネスで日本が有利な理由
まず、
日本の勝機のひとつは、南と東が開けている島国であるという地理的な特性です。これは、ロケットを打ち上げる射場の条件として、非常に有利なのです。
まず、「打ち上げた方角に人家や他国をさけ安全を確保する」ために、打ち上げる方角には何もない状態であることが求められます。
そのうえで、ロケットは東向きに打ち上げることで、特に静止軌道や静止軌道以上に遠くに衛星や探査機を運びたい際に「地球の自転を利用する」ことができるため、燃料費の削減につながり、顧客が打ち上げに支払う料金も下げられるようになります。また、南向きに開けていると、主に地球観測衛星が利用したい軌道に運びやすくなるというメリットがあります。
つまり、日本は、顧客の人工衛星の種類と目的に応じて、ロケットの打ち上げが東側にも、南側にも可能であるというメリットをすでに持っています。そのため、日本では、北海道の大樹町、和歌山県の串本町など、これまでJAXAのロケットを打ち上げていた鹿児島県の種子島や肝付町の射場以外にも、複数の地域でロケット射場の整備が進んでいます。
同様に、オーストラリアも面積は違えど、1つの国で東側も、南側も開いていることから射場の整備を国が力を入れて推進しています。地の利を持つ各国が未来のロケット打ち上げ需要を好機ととらえ、競い合っています。
また、日本の宇宙ベンチャーが現在開発を進めるロケットは、スペースXのロケットと比較すると小型です。
「大は小をかねる」という言葉が日本にはあるように、大型ロケットのほうが載せられる衛星の大きさも選べ、小型の衛星を大量に運べるメリットがあると思われる方も多いでしょう。
ただし、大型ロケットで小型衛星を打ち上げる場合、ライドシェアと呼ばれる大型の衛星や他社の小型衛星と相乗りするような形で打ち上げることが一般的です。その場合、たしかにコストは安くなるのですが、打ち上げの予定を自社の衛星の都合だけに合わせることはできず、調整も長期間となります。同様の理由から衛星を射場に運んでから実際に打ち上がるまでの期間も長くなってしまいます。
一方で、小型ロケットは、大型ロケットのライドシェアでの打ち上げよりもコストはかさみますが、小型衛星を打ち上げたい顧客の要望にある程度柔軟に応えることが可能です。
ちなみに、打ち上げのコストは、2022年1月時点で、スペースXのライドシェアを利用すると、1kgあたり5000ドルかかるところ、小型ロケットベンチャーのリードランナーであるRocket Labのロケットを利用すると1kgあたり2万3000ドルと4倍以上の差があります。
そのうえで、近年、国が主導で開発するような大型衛星だけでなく、小型衛星の打ち上げ需要も増えています。小型ロケットが求められている象徴的な事例としては、日本の小型SAR衛星ベンチャーであるSynspectiveとRocket Labが2024年に、10機の衛星打ち上げを行うことに合意したという大きな発表がありました。小型衛星企業にとっては、スペースXのロケットだけがすべての需要を満たすわけではないという事例のひとつです。
スペースXは大型ロケットによる打ち上げを主力としており、小型衛星を所定の軌道に直接投入するサービスは限定的です。現在、日本でもインターステラテクノロジズ、将来宇宙輸送システム、スペースウォーカー、スペースワン、AstroX、PDエアロスペースといった多くの民間企業がロケットや宇宙機の開発を進めています。そして、すでに紹介した通り、日本ではロケットの打ち上げにおける地の利があり、新たな宇宙港の整備が進んでいます。
さらに、日本は自動車産業が強く、モノづくりという観点でもロケットエンジニアとなれるスキルを持った人材や企業が他国と比較して豊富にある国です。ロケットの製造に必要なモノづくりのスキルがあり、そして、小型衛星を打ち上げたい顧客の要望に、
2025年1月には、インターステラテクノロジズがトヨタグループの1社としてモビリティの変革をリードするウーブン・バイ・トヨタと資本および業務提携に合意。ウーブン・バイ・トヨタがリード投資家としてシリーズF ファーストクローズまでに約70億円をインターステラテクノロジズに出資することが決定したという非常に大きな発表がありました。
プレスリリースには「トヨタの知見を取り入れ、ロケットを低コストで高品質、量産可能なモノづくりに転換」といった記載もあり、日本がこれまでに継承し、培ったモノづくりの技術が、業界の壁を超えて日本産業全体をさらに成長させるかもしれないという期待が膨らみます。
そして、この勝機を活かすためには政府の支援も欠かせません。ロケットの技術開発については宇宙戦略基金やその他政府支援プログラムがあり、金銭的な補助が非常に増えています。また、技術開発のためのお金に加えて重要なのが、現状の宇宙ビジネス時代の実態にあった法整備です。今後は射場の建設やロケットの打ち上げに関するルールメイキングのスピードという観点も非常に重要な要素となっています。
実際に、宙畑でも取材の機会をいただいた、宇宙ビジネスの実務に精通した弁護士として活躍されているTMI総合法律事務所の新谷美保子さんは、日本の宇宙港のハブとして活動するSpace Port Japanの理事としても活躍されています。「日本にSpace Lawyerが文字通り一人もいなく、国益が損なわれかねない状況だ」と知って「私が日本で第一号になろう!」と奮起したエピソードは、その場にいた編集部全員が感銘を受け、取材後に私たちも頑張らねばと奮起したことをいまだに覚えています。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
筆者:中村 友弥