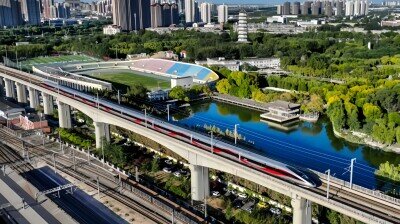筆と墨がつなぐ「千年の絆」、大阪・関西万博「北京ウイーク」で日中の書道交流会が開催
2025年5月15日(木)19時30分 Record China
大阪・関西万博の「北京ウイーク」で日中の書道交流会が開催されました。
2025年大阪・関西万博の中国館でこのほど開催された「北京ウイーク」では、「書林翰墨伝友誼—中日書法交流会(筆と墨がつなぐ友情 日中書道交流会)」と名づけられたイベントが盛大に開催されました。同イベントには中国の薛剣駐大阪総領事、北京市人民政府の劉梅英副秘書長、日中友好協会の宇都宮徳一郎会長をはじめとして、両国政府および民間の友好人士、さらに唐招提寺の松浦俊海第85代長老など、多くの重要人物が出席しました。
熱気に包まれた会場では、中日両国から集まった書道家34人が筆を執り、両国の素晴らしい未来への願いを込めて、リレー形式で数多くの作品を完成させました。この催しは、日本の書道愛好者や来場者の注目を集めました。
薛総領事はあいさつの中で、「書道は日中両国が共に大切にしてきた伝統文化であり、民間交流の中で独特な役割を果たしてきました。翻訳の要らない『魂の言葉』とも言えます。この催しを契機に、書道芸術の継承と東洋文化の精髄の発揚に向けて日中両国が共に努力し、両国民の友情に温かさと力を注ぎ込むことを期待します」と述べました。
北京市人民政府の劉梅英副秘書長は、「筆、墨、硯、紙は、日中両国の人々の心をつなぐ懸け橋になっています。本日、両国の書道家が筆を媒介にして交わることは、1000年にわたる文化の継承であると同時に、新時代における中日友好の生き生きとした象徴でもあります。この催しにより民間交流が深められ、中日友好が両国民の心の奥深くに根づくことを希望します」と述べました。!<1403140>
日中友好協会の宇都宮徳一郎会長は、「日本の書道は中国に源を発し、そこから独自の発展を遂げてきました。書道は日中両国の国交正常化の過程でも重要な役割を果たました。今回のイベントは、東京都と北京市の書道芸術の交流をさらに深め、日中文化交流の相互理解に貢献するでしょう」と述べました。!<1403141>
現場での書道実演では、書家の杭迫柏樹(くいせこ・はくじゅ)さんがまず「敬隣永安」という四文字を書き、会場から大きな拍手が起こりました。この四字熟語は、薛総領事が外交の場で用いた言葉であり、その後に民間にも広まり、日中関係を語る多くの場で引用されるようになったものです。!<1403142>
会場では司会者が薛総領事に、「敬隣永安」という言葉の由来を尋ねました。薛総領事は、「ここ2年間で、『敬隣永安』という言葉が日本の書道家の作品にたびたび登場するようになり、大変光栄に思います。特別な出典があるわけではなく、私が日本での仕事と生活の中で感じた思いから生まれた言葉です」と説明しました。薛総領事はこの言葉についてさらに、「双方が互いを尊重し、善意と敬意をもって接すれば、平和共存と長期にわたる安寧を実現できることを示すものでです」と説明した上で、「複雑な国際情勢の中にあって中日関係は改善と発展の重要な時期を迎えています。今回の催しを機に、さらに多くの民間の力が文化関連など中日関係のさまざまな分野の発展と協力を促進することを期待します」と述べました。!<1403143>
書道とは、各時代の書体を通じて、多様な思想や文化精神を表現するものです。会場では、日中両国の書道家たちがまずそれぞれの得意とする作品を披露し、司会者の通訳を通じて、作品の背後にある物語を来場者に紹介しました。披露された作品は篆書、隷書、行草や草書といった書体の幅広さに加え、古典からの引用や個人的な感慨まで内容も多様で、両国の書道愛好者が新たな視野を得ることになりました。!<1403144>
書家で書道教育者の竹内勢雲(たけうち・せいうん)さんは取材に対し、「日本では『書道』が小学校と中学校で、国語科の一部として必修です。高校以降は芸術科目に分類されます。日本の子どもは、まず書道を通して文字の読み方や書き方を学び、成長とともに書を通して情操を養います。イベント会場でも、日中両国の観衆のいずれもが、書道と漢字への高い素養を示していました」と説明しました。!<1403145>
杭迫柏樹氏は、「この50年間で北京、上海、寧波、そして多くの中国の内陸部の都市に行きました。上海博物館の完成も目の当たりにし、数えきれないほどの友好的な人々と出会い、中国の急速な発展と変化を感じてきました」と語りました。書道の研鑽を続ける杭迫氏にとって、漢字発祥の地である中国は、まるで『親』のような存在といいます。杭迫氏は、「漢字を共に書くことで、日中の人々に、私がずっと感じてきた両国の親密さを実感していただければうれしいです」とも語りました。(提供/CRI)!<1403146>