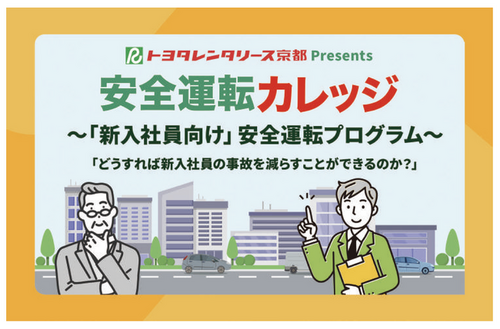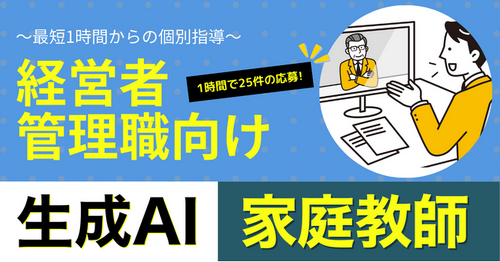正妻として母として…情と非情さを兼ね備えた女指導者・北条政子の決断
2025年1月28日(火)5時50分 JBpress
歴史上には様々なリーダー(指導者)が登場してきました。その
母としての憤り
北条政子の夫・源頼朝は、建久10年(1199)1月、病死します。政子は42歳にして、後家となったのです。政子は、夫の死の前に、娘を亡くしていました。長女の大姫を建久8年(1197)に、19歳という若さで亡くしているのです。
大姫は、源(木曽)義仲の嫡男・義高と婚姻していましたが、頼朝と義仲の関係が破局を迎え、義仲が頼朝により滅ぼされると、頼朝は後難を避けるため、義高を殺そうとするのでした(1184年4月)。
頼朝は後に、異母弟・源義経と静御前の間に生まれた男子も殺害しますが、頼朝は、義高が成長してから、自らに刃向かってくることも恐れたのです。
義高は、藤内光澄という武士により討たれますが、義高が死んだことを大姫はすぐに知ってしまいます。そして、水も喉を通らぬほど、悲嘆に暮れてしまうのでした。
その様を母・政子は見て、大いに悲しみます。悲しみだけでなく、義高を殺した武士に怒りが芽生えたようで、藤内光澄は同年6月に斬首されてしまいます。頼朝の命令によって斬首となったのでしょうが、その裏には「御台所(政子)の御憤り」(鎌倉時代後期の歴史書『吾妻鏡』)があったようです。
藤内光澄も頼朝の命令があったから義高を討ったのであって、本来ならば、斬首される謂れはないはず。哀れと言えば哀れです。とは言え、政子としては、夫の頼朝に激情をぶつける訳にはいかず、光澄にやり場の無い怒りが向いたのでしょう。大姫は、体調が回復する時もありましたが、頗る悪化することもあり、とうとう、20歳の頃に病死してしまいます(1197年)。
そしてその2年後(1199年)には、夫・頼朝の突然の死。更に、同年6月には、次女・三幡を病で失くすのです。若くして、次々と世を去っていく政子の子供達。政子の懸念の種は、頼朝の後継となった嫡男・源頼家(母は政子)にもありました。
有力御家人(安達景盛)の愛妾を強奪するというあり得ないことをしでかした頼家。更には、恨みを抱く景盛を討伐せんとする頼家。不肖の息子に対し、政子は「粗忽の至り。佞臣を重用している」「それでも未だ景盛を討とうというのなら、私を討ってからにせよ」と啖呵を切るのでした。命懸けで息子・頼家を翻心させようとしたのです。
結果を出すリーダーはみな非情である
その甲斐あって、頼家は景盛を討つことはありませんでした。頼家はその後、北条氏(時政)の手により、将軍の座から引き摺りおろされ、出家、鎌倉を追放されます。伊豆の修善寺に追放となるのです(1203年9月)。出家は、母・政子の計らいだったようです(『吾妻鏡』)。政争の渦中から、少しでも我が子を遠ざけ、命を長らえさせたい、母の思いを感じることができます。
が、元久元年(1204)7月、頼家は修善寺にて死去。『吾妻鏡』には、死因については触れていませんが、『愚管抄』(僧・慈円が著した史論書)によると、暗殺だったようです。北条氏の手の者に殺されたのです。暗殺は、北条時政(政子の父)らが主導したものであり、おそらく、政子は関与していなかったのではと推測します。
頼家の後は、その弟・源実朝(母は政子)が将軍となりますが、その実朝もまた建保7年(1219)1月、実朝の甥で頼家の遺児・公暁により、鶴岡八幡宮で殺害されてしまいます。
娘2人は病死し、息子2人は非業の死を遂げる。しかも未だ若い。母として、これほどの苦痛と悲しみはないでしょう。承久の乱(1221年)が勃発した際、政子は御家人たちの前で自らの言葉を聴かせて奮起させたことは有名ですが、『承久記』には「皆さん、聞きなさい。私のように若い頃から悲しい思いをしてきた者はいないでしょう。初めは、長女の大姫に先立たれ、次は頼朝様。その次は頼家。そしてほどなく、実朝に先立たれました。4度の思いはもう過ぎた事だけど、今度、弟の(北条)義時が討たれれば5回目の思いになります」との言葉が書かれています。
勿論、この時、政子が本当にこのようなことを御家人らの前で話したのかは疑問ですが、辛い思いをしてきた政子が(もう、そのような思いはしたくない)との思いを持っていたとしても不思議ではありません。政子は、承久の乱の際、官軍を関東で迎え撃つか、西上して討つか、幕府首脳部で見解が割れている時に「上洛して討つべし」と義時に主張したことで知られています(『吾妻鏡』)。結果、幕府軍は西上し、官軍を撃破することになるのですが、政子は女性といえども、戦略眼に秀でていたことが分かります。
まさに「尼将軍」の名に相応しいというべきでしょう。これまで見てきたように、政子の性質は情に溢れている面がある一方で、時に激烈でした。頼朝の愛妾を様々な方法を使い、蹴落とす。頼朝の命令で娘の大姫の夫・義高を討った武士を処刑させる。そうした非情さを持っていたからこそ、政子はいざという時に、動揺せず、的確な判断ができたのではないかと思います。『結果を出すリーダーはみな非情である』(ダイヤモンド社、2012年)との冨山和彦氏の書籍もありますが、女指導者の政子にもそれは当て嵌まっていたと言うべきでしょう。
筆者:濱田 浩一郎