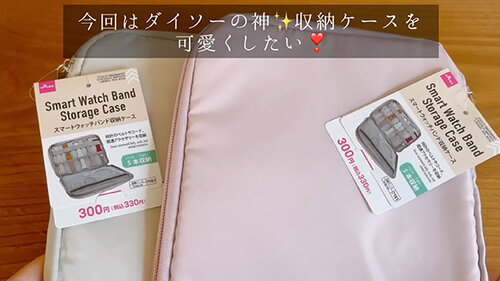草乃しずか80歳、日本刺繍で日々を彩る「同居する義母が脳梗塞で倒れ、介護に。刺繍を続ける道はあきらめなかった」
2025年3月9日(日)12時30分 婦人公論.jp

左から、半襟、かかえ、振袖、帯、帯締め。紫式部をイメージして仕立てた着物は、草乃さんが反物の染めからこだわり、刺繍を施した。「新春のお出かけは何を着ていこうかしらと、こうしてソファに並べて組み合わせを考えるのが楽しいの」(撮影:大河内禎)
古くは仏教美術として広まった日本刺繍。美しく光り輝く絹糸は、能装束や格式の高い着物に用いられてきました。その伝統工芸を日常でも楽しめたら—。80歳になる草乃しずかさんが、半世紀以上かけて提案する作品の魅力、手仕事の面白さとは
(取材・文:山田真理 撮影:大河内禎)
* * * * * * *
産着に一輪の花を
NHKの番組講師をはじめ、国内外で作品展を開催し日本刺繍の魅力を伝える草乃しずかさん。その作品をこの目で見たいと、2024年に日本橋で開かれた「草乃しずか 日本刺繍展—源氏物語を花で装う—」を訪ねた。
絞られた照明の中に浮かぶ絹糸の光沢、繊細な色彩の表現。会場を訪れた人々が、食い入るように作品を見つめる姿が印象に残った。
東京都杉並区の静かな住宅街にあるアトリエを訪ねると、自身が考案した作業台で針を動かす草乃さんの姿が。「この台を好きな場所に動かして、家事の合間でもすぐ作品に取りかかります」と微笑む。

「永遠なる祈り」(命のタペストリー) 上段のつがいの鳥は、円の上部のもの
能登地方の豊かな自然に囲まれ、「生き物や野の花とおしゃべりするような子どもでした」。幼い頃の夢はオペラ歌手か、幼稚園の先生。しかし夫となる人に強く望まれて20歳で結婚、ほどなく子どもを授かる。
「当時はおしめや産着を手縫いする時代。実家の母に習ってなんとか縫い始めました」。生まれたての赤ん坊を包む産着を作るとき、ふと家庭科の授業で習ったフランス刺繍を入れようと思いつく。白い布に咲いたピンクの花。「幼い頃『あなた可愛いわね』って話しかけていた、野の花を思い出しました。好きなものに愛情を注いだ当時の気持ちが、母となる喜びと重なって」。
長男の服や部屋飾りにも夢中で刺繍をあしらった。そんなある日、小児科で待合室に飾られた刺繍の額が目に入る。美しい光沢を放つそれは、伝統技法・日本刺繍だと教えられた。
「その頃の私は結婚や出産で夢をあきらめて、『一生このままなの?』と不満をため込んでいて。昔から着物は好きだったので、子育ての傍ら日本刺繍を学ぼうと思いました」

ランプシェードの刺繍は灯をともすと違う表情をみせる

作業台は、天板を替えれば机にもなる優れもの。折りたたんで持ち運びがしやすいよう工夫されている
主婦から伝統工芸の道へ
日本刺繍の教室を探し、作家の丹羽正明氏に師事が叶う。《糸撚り三年》とも言われ、細い絹糸を何本使い、どの程度の強さで撚るかを学ぶだけでも年月のかかる世界。
「着物や帯にも刺繍をするようになった頃、生涯教育講座で日本刺繍を担当することになりました」。

この日、江戸小紋に合わせた帯。折り鶴、ぽっくり、恋文……。少女のような気持ちを大事にしたいと遊び道具を刺繍でちりばめた
戦前は女学校でも教えられていた日本刺繍だが、戦後は職人を目指す人が学ぶものという風潮が強まっていた。
「そこへ主婦の私が、『半襟のように簡単なもので楽しみましょう、道具もお手持ちのフランス刺繍の丸枠でいいですよ』と提案したのが思いのほか喜ばれて」。暮らしの中で気軽に日本刺繍を楽しむ講座は評判を呼び、NHKの教養番組の講師として呼ばれるようにもなる。

床の間がなくても季節を感じたいと、アトリエでは毎月しつらえを替える/「睦月」

床の間がなくても季節を感じたいと、アトリエでは毎月しつらえを替える/「如月」
草乃さんは美術全集を見ながら図柄を考え、手書きで図面を作成し配色を決めていく。時には異なる色の糸を撚り、絵の具を混ぜるようにして繊細な変化を生み出す。
「たとえば同じ花でも、野山に咲くか花壇なのか、場所が違えば色も違って感じられるでしょう。私はその繊細な差も糸で表現したい。図案通りに刺していても、思いもよらぬ物語が浮かび上がることがあります。それが面白くて、夢中で作品を作りました」。
40代になった頃、同居する義母が脳梗塞で倒れて介護が必要になる。施設に入居した義母の世話に毎日通いながらも、刺繍を続ける道はあきらめなかった。
「介護の日々は心身ともに疲弊も大きかった。それでも帰宅して一針一針進める時間は、自分への優しさを取り戻すために大切なものでした」。それは手仕事の効能でもあり、美しいものを自らの手で生み出す創作の力でもあると言う。
「母は、父を亡くしてから20年間、一人暮らしでした。その寂しさや体の痛みをやわらげる《おくすり》と呼んだのが、自分で考えたアップリケ刺繍。
新聞紙に色とりどりの布を貼って切り、野菜や布に見立てた作品を作って、92歳の時にコラージュ作家としてデビュー。それが話題を呼び、本を出したり、私と一緒にテレビに呼ばれたり忙しい晩年を過ごして、103歳まで元気でいてくれました」

「太陽への讃歌 夏」部屋に置いても可愛いはがきサイズの作品。「伝統工芸品を〈買う〉のではなく〈作る〉。身近に置いたり、プレゼントしたりする喜びを、多くの人に味わってほしいのです」

「命ひとつひとつを抱いて」(桜日記 四十歳)
母を目指して、80歳の決意
アトリエで開く教室には、さまざまな年齢の女性たちが集う。
「同じ糸と構図でも完成品は人それぞれ。昨日と今日でも微妙に仕上がりが違う、そこが手仕事の面白さ。いつでも同じものができる機械刺繍ではないですもの。そこに表れる人の心を感じ取っていただければと思います」。
手鏡やブローチなど愛らしい品々から、展覧会に向けた大型のタペストリーまで幅広い創作を続ける草乃さん。
10年ごとに発表する「桜日記」と題した作品では、80歳になった2024年の春、炎のような構図の桜を施した。
「103歳まで創作に励んだ母のように、命が燃え尽きるまで自分自身を見つめていきたい」。その指先からは今日も、自然の息吹を秘めた美の世界が生み出されていく。

「年を重ねてこそ熱く」(桜日記 八十歳)
関連記事(外部サイト)
- 韓国の手芸品・ポジャギ制作を55歳で始めて20年。一生続けたいと思える理由は?老眼鏡をかけながら、一針一針根気強く縫い上げる【2023編集部セレクション】
- コシノヒロコ×コシノジュンコ×コシノミチコ「三姉妹」ではくくれない、三者三様の人生。「競争心がモチベーションになって成長できた」
- 韓国の手芸品・ポジャギ制作を55歳で始めて20年。一生続けたいと思える理由は?老眼鏡をかけながら、一針一針根気強く縫い上げる【2023編集部セレクション】
- 年金月5万円でも楽しく暮らす”ひとりシニア”71歳の紫苑さん「オシャレな人ほど工夫する襟と袖。私のコムデギャルソン“風”リメイク術」
- コシノミチコ 日本人の私が英国で認められたのは「だんない」の精神があったから。「実力より少し高めの目標を作り、辿り着くように頑張る」