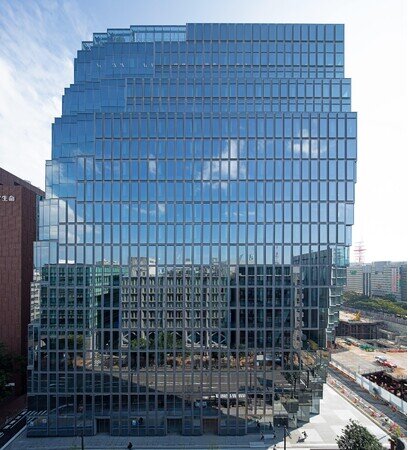八幡神社や八幡宮、日本で最も多い「八幡信仰」の歴史をたどる。『古事記』にも『日本書紀』にも登場しない八幡神が広く信仰された理由は…
2025年3月14日(金)12時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
近年のインバウンド需要で、日本の神社を訪れる外国人が増加しています。そのようななか、島根県親善大使・出雲観光大使を務めるヒーリングシンガー・深結(みゅう)さん曰く「最近は、海外のビジネスエリートが日本の神様や神道に興味を持ち、学ばれることも増えてきている」とのこと。そこで今回は、深結さんの著書『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』から、ビジネスパーソンの教養となりつつある日本の神様や神社に関する知識を一部ご紹介します。
* * * * * * *
全国に広がる神社の神様
日本全国津々浦々にまである神社の中に、「八幡(はちまん)社」「稲荷社」といった神様の名前を冠した神社が数多くあります。多くは特定の神社の神霊を移す勧請(かんじょう)によって各地に広がっていったものです。
神道系宗教法人が持つ神社の99%超にあたる7万8535社の神社を包括している包括宗教法人・神社本庁(東京都)は、1990(平成2)年からの5年間で「全国神社祭祀祭礼総合調査」を行っています。
創建の由緒や祭りの概要などをもとに直接・一律に調査したもので、神社名から主に祀られている祭神がわかる神社を都道府県ごとに集計し、「**信仰」と分類しています。
同調査によると、神社数の多い信仰形態は順に上記のとおりです。
神社本庁調査部として岡田米生氏が行った著名神社の分社数の調査(「全国神社祭神御神徳記」1966年)は数字が大きく異なっています。当時の神社本庁の包括神社が約8万社であり、上位4社だけで8万5000社を超える同調査は法人格のない神社や小さな祠なども集計したものとみられます。
日本人の信仰のほどを知るうえで参考になる数字で、文化庁が毎年発行している宗教年鑑でもこの数字を紹介しています。
同調査による著名神社別の分社数は多い順に上記のとおりです。
神社創建の由来はそれぞれですが、その地域の人々の属性や職業などによって崇敬する神様に違いがあり、勧請される神社も異なってきます。それぞれの神様の信仰圏が歴史的にどのように広がったのかを見ていくと、その神様の性格を改めて知ることができます。
八幡信仰
八幡神を祀る「八幡神社」や「八幡宮」は全国にくまなく広がっています。『古事記』『日本書紀』に登場しない八幡神の信仰が広がったのは、常に政治の中心に近い位置で崇敬されてきたからだと考えられています。
八幡信仰の発祥は宇佐八幡宮(大分県宇佐市)です。祭神は八幡大神(誉田別尊<ほんだわけのみこと>=応神天皇)、比売大神(ひめおおかみ)(多岐津姫命<たぎつひめのみこと>・市杵嶋姫命<いちきしまひめのみこと>・多紀理姫命<たぎりひめのみこと>)、神功(じんぐう)皇后の三神です。

『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(著:深結(みゅう) 監修:西岡和彦/あさ出版)
宇佐地方の御許山(おもとさん)信仰が原型とされていますが、神託を受けて宮司家となった渡来系氏族の辛嶋氏(からしまうじ)が大陸や半島の文化と仏教をもたらし、やはり神託を受けた宮司家で畿内(近畿)出身の大神氏(おおみわうじ)が応神天皇崇拝を持ち込んで融合し、7世紀までに八幡神となったとされています。
地理的に大陸文化がいち早く入り、7世紀後半には関連寺院が設けられました。8世紀初頭に現在の場所に建立されたころから境内に弥勒寺(みろくじ)という神宮寺があり、正式には「宇佐八幡宮弥勒寺」と号し、神前読経が行われるなど、神仏習合が最も進んだ神社でした。
720年に南九州で起きた隼人の反乱では朝廷の軍は手を焼きましたが、八幡神の神輿が加わったのち勝利を収めました。
その後、八幡神の託宣があり、多くの命を奪った罪を贖うために年に一度、生類を放つ仏教由来の「放生会(ほうじょうえ)」が宇佐八幡宮で行われるようになりました。八幡宮の最も重要な神事として各地の八幡宮で現在も受け継がれています。
神仏習合がさらに進む
聖武天皇によって進められていた東大寺大仏造営事業では、神々を代表して奉仕するという八幡神の託宣があり、749(天平勝宝元)年に宇佐八幡宮の禰宜尼(ねぎに)が八幡神を奉じて入京したことで朝廷との関係が深まり、中央進出のきっかけとなりました。
769(神護景雲3)年には、朝廷内で権力を握った僧・道鏡の皇位簒奪(さんだつ)を八幡神の託宣が阻止しており、朝廷の守護神としての性格を強めています。
8世紀後半になると八幡神は「菩薩」と自称する託宣を下しました。菩薩とは、仏になることができるにもかかわらず、迷いの中に生きる生類、「衆生(しゅじょう)」を救済するためにあえて仏にならずにいる存在とされています。
781(天応元)年に八幡大菩薩の神号を朝廷から奉られると神仏習合がさらに進み、大和や京近隣の有力寺院の鎮守社として勧請されました。これ以降、菩薩を号する神が全国に多数現れるようになりました。
860(貞観元)年には八幡神の託宣を受けた僧侶・行教(ぎょうきょう)によって山城国(現在の京都)に勧請されました。「石清水八幡宮護国寺」と称し、明治維新後に神仏分離が行われて破壊されるまで護国寺は本殿と一体でした。
僧侶でありながら妻帯(さいたい)し、世襲する別当が全体を治めるという神仏習合らしい体制でした。こうした形態を「宮寺(みやでら)」といい、各地に広がっていきました。
武士の守護神
宇佐よりも都に近い石清水八幡宮は朝廷との関係を深めて政治的な力を強めました。各地に荘園を広げ、新たに神社を設けたり、もとからある神社を取り込んだりして荘園経営の拠点とし、八幡神を鎮守神として祀りました。
応神天皇と同一視されている八幡神は天皇の祖神とされていましたが、臣籍降下(しんせきこうか)した皇族を祖とする源氏が氏神として崇め、源義家が石清水八幡宮で元服して八幡太郎を名乗り、さらに武神としての性格が前面に現れていきました。
平安末期には鎌倉に鶴岡八幡宮が勧請され、武家の棟梁として鎌倉幕府を開いた源頼朝は境内を整備して熱心に参詣しました。全国の御家人たちも、自らの氏神とは別に、武神として所領に八幡神を祀りました。
その後の幕府を開いた足利家、徳川家とも源氏を名乗っており、八幡神も武士の守護神であり続けて全国に広がったものとみられています。
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(あさ出版)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- なぜ神社の境内にマンションを建てるのか?賀茂祭でおなじみ、下鴨神社の境内に建つ「高級集合住宅」の謎
- 中園ミホ「ラッキーな人と不運な人の違いは?運がいい人に共通する行動を解説。朝ドラ『あんぱん』の脚本も、開運行動を取り入れた暮らしの中で執筆」
- 1年を健やかに過ごせるかどうかが決まる3月にオススメの<養生法>とは?人気漢方家「『春の皿には苦味を盛れ』という食養生のことわざがあるほどなので、たとえば…」
- 140年以上の歴史をもつ地図記号「卍」の変更が検討された理由。かつては「鳥居」や「灯籠」の記号もあった!
- 「終活」という言葉の誕生は2009年。それ以前に『遺言ノート』や葬儀の多様化も。『婦人公論』誌上に見る女性の「終活」事情