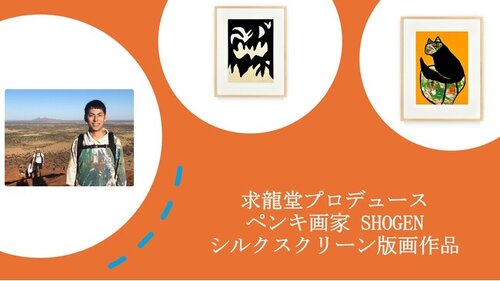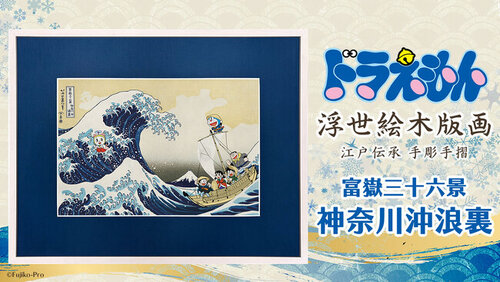銅版画家・山本容子「ホスピタルアートに善意の押し売りや制作者の〈我〉は不要。手術や抗がん剤治療…自身の大腸がん闘病を経て、その思いは深まり」
2025年3月23日(日)12時29分 婦人公論.jp

銅板画家の山本容子さん。那須のアトリエで愛犬のルカと(撮影:荒木大甫)
腐食した銅版にインクをのせ、プレス機にかけて——。刷り上がった紙を取り出す瞬間が一番心躍ると語る山本容子さんは、今年、画業50年を迎える(構成:菊池亜希子 撮影:荒木大甫)
* * * * * * *
<前編よりつづく>
心を癒やす絵は薬になる
絶対安静だった父は、毎日何を見ていたのだろう。父が寝ていた病院のベッドに横になり、天井を見上げると、視界に入ったのはシミだらけの風景でした。こんな景色を見て逝ったのかと思ったら、涙が止まりませんでした。
入院中、病室にお花や絵を飾ったけれど、動けない父には何も見えていなかった。なんと独りよがりなことをしていたんだろうと思いました。自分がよいと思うものを飾るだけでは、人を癒やすアートにはならない。病院という空間にふさわしいアートを考え始めたのは、それからです。
当時は「ホスピタルアート」という言葉も知らぬまま、お医者さまと話をする機会があると、「病院の天井、どうにかしませんか」と訴えるようになりました。実を結んだのは10年以上後のことですが、その間、自身でホスピタルアートを学びスウェーデンへ取材にも行きました。
そして2005年、愛知県の中部ろうさい病院とのご縁を得て、初めて病室に天井画を描くことができたのです。以来、全国各地の病院やさまざまな施設の天井画や壁画、ステンドグラスを制作しています。

【病院を彩る】
「Les Chemins de L’amours 愛の小径」高松赤十字病院西玄関 壁画 230cm×650cm(2014)
「病院にアート作品を」という動きは日本にもありますが、善意やボランティアと混同され誤解されていると感じます。地元の名士が寄贈した絵画や、子どもたちがお絵描きした壁を、闘病中に毎日見たいとは思わない。
まずアートとして成立する確かな技術が不可欠で、善意の押し売りや制作者の「我」が見え隠れするのはよくない。ホスピタルアートは患者や家族、そこで働く医療従事者の心によい影響をもたらすもの。そして何より、患者の治療効果を高める薬にならなくてはいけないのです。
私がホスピタルアートに携わるときは、その施設のできるだけ多くの人に、何が好きか、どんなときに穏やかな気持ちになるかを取材します。やはりその地域に根差す伝統や、自然にまつわるものが人々の心に届くのですね。
たとえば高松赤十字病院の玄関には、瀬戸内の穏やかな海と島々、オリーブの花咲く丘を描きながら、海辺をモチーフにした「愛の小径」というシャンソンを絵に表してみました。
ホスピタルアートへの思いは、私自身ががんを経験したことでいっそう深まりました。初めて天井画を描かせていただいた病院で、夫と一緒に人間ドックを受けたところ、思いがけず大腸がんが見つかったのです。
手術や抗がん剤治療で気力、体力を奪われ、病室の照明など強い人工の光には耐えられない……。そういう状態のとき、どんなものなら見られるか、見たいと思えるか、身をもって体験することになりました。
それはフワフワの雲でも、クマのキャラクターでもない。モーツァルトの音楽のような絵。雨音のような、優しくて温かい時間が流れている空間とでもいったらいいでしょうか。
生きていれば、さまざまなことに見舞われます。慌てふためくようなときには、自分が今、何をいちばん大切に思っているかを自身に問いかける。そうすれば、判断を誤らないと思うのです。
私の場合、「もしがんが転移していたら余命1年半」と言われましたが、そのときまず思ったのは、「鉄道博物館のステンドグラスだけは仕上げたい」ということ。それは企画段階から任された仕事でした。
小川洋子さん、池澤夏樹さんら10人の作家に書いていただいた鉄道にまつわるエッセイから、私が10枚の絵を描き、谷川俊太郎さんの詩「過ぎゆくもの‐SL挽歌」がそれらをつなぐというプロジェクト。途中で投げ出すわけにはいきません。
そう思ったとき、ああ、これが私なのだと気がつきました。幸い転移はなく、15年以上経つ今も元気に生きています。
真剣に好きなことを求めてきた
来年で結婚20年。50歳を過ぎての結婚なのでラブラブではないけれど、一緒にいて心地よい。私にとって、アトリエに籠もって制作する孤独も、一人静かに音楽を聴く時間も大切なものですが、誰かと一緒に聴きたいこともあるし、話をするのも好きなのです。
数年前に栃木・那須の山の上にアトリエを建て、夏はできるだけ夫と愛犬のルカと山で過ごしています。風の音を聞いたり、暖炉の火がパチパチ燃えるのを眺めたりするのは、心に栄養が与えられていると感じる時間。今後は東京での便利な生活から、少しずつ那須の暮らしに軸足を移していくことになるでしょう。
人生のなかでずっと真剣に好きなことを求めてきたし、無理なことは手放してきました。その過程でいくつかの恋愛、結婚もあります。そういう私の生き方の根底には、父の教えがあるように思います。父は家業に反発して自分で会社を興し、失敗もしたけれど、やりたいことを貫いた人でした。
私が大学生になったときに言われたのは、「みんなが右と言ったら左を見てみなさい」。これは反骨ではなく、「周りに流されず、本当に自分が面白いと思うほうへ進め」という意味。私がへそ曲がりなのは父の影響ですが、今の私に導いてくれた言葉です。
一昨年、36年ぶりに村上春樹さんから伝言が届き、村上さん翻訳のカーソン・マッカラーズ著『哀しいカフェのバラード』に挿画を描かせていただきました。村上さんの訳文を読み、物語のどこをどう切り取って挿絵にしていくか……久しぶりに設計図を描きながら1年間、1冊の小説に入り込みました。
これからは、60歳で始めた俳句を大切に続けながら、頭でなくもっと心でものを見て感じていきたい。そうしようとすることで、人は優しくなれると思いますから。
関連記事(外部サイト)
- 『TUGUMI』『婦人公論』表紙を手掛けた銅版画家・山本容子「おろし金で銅板を作った時は気付いたら手が血だらけに。夢中で遊び続けた幼少期のように楽しんで」
- ディジュリドゥ奏者・画家GOMA「交通事故で脳に障害、記憶を失っても音楽活動は諦めなかった。意識が戻る時に見てる〈ひかりの世界〉を描かずにはいられない」
- 寄席紙切り・林家正楽さんが急逝「ドラゴンと虎はどの国でも大人気?大谷翔平、プーチン大統領、アイアイ、お客さんの注文でなんでも切り絵に」
- 『徹子の部屋』出演の絵本作家・飯野和好さん、成功までの紆余曲折を語る「どの出版社も門前払いだった『あさたろう』。浪曲を入れたことで思わぬ展開に」
- 73歳、全国で唯一の女性盆栽技能保持者は、盆栽の常識をくつがえす。針金で枝を曲げず、何十年もかかる「自然盆栽」を追求して