【水野誠一 連載】小池一子(中)「いいと思うなあ、わかりあってる人たち」。慎重さをものに託し、手渡す。無印良品の創生を語る
2025年5月20日(火)7時0分 ソトコト
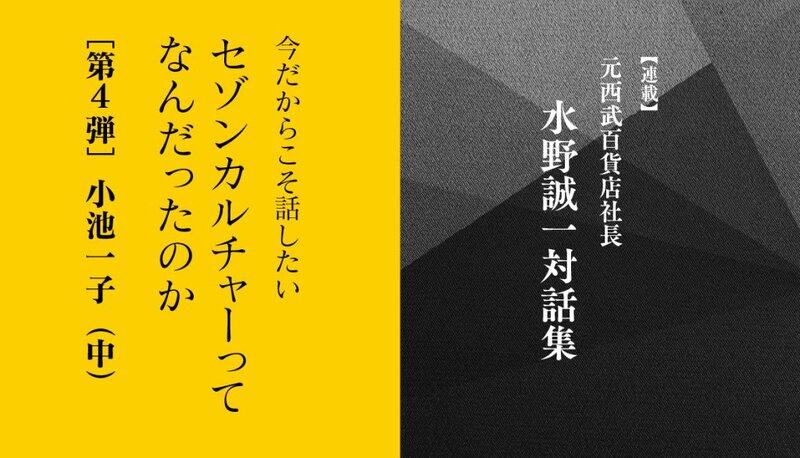
西武百貨店でセゾンカルチャーの礎を築いた堤清二のもと、グラフィック・デザイナーの田中一光とともに無印良品を創生した小池一子。現在も無印良品のアドバイザリーボーダーを務める彼女が、セゾンカルチャーを見つめ続ける水野誠一と語る、無印良品の始まりとそこに息づく一貫した思想性とは。

ブランドネームに踊らされず、物とちゃんと対峙する
水野 小池さんや一光さんにお世話になりながら、西武に面白い展開が起きていくわけですが、そのなかでの一番は、無印良品ですね。
これを西武百貨店じゃなくて、西友でやると聞いたときには、僕はすごくジェラシーを感じました。西友にこれをわかる人がいるんだろうかと(笑)。
しかし今にして思えば、西友だったから別会社化して、ここまで大きく育てられたんですけどね。
当時いろんな意味でブランドというものがあふれ出してきた。
西武百貨店は特に、堤邦子さんという伝説の大バイヤーがいらしたので、いち早く有名ブランドを導入していました。
エルメス、サンローラン、ソニア・リキエルなど。
それとは対照的に「ノーブランド」というブランドをつくるというコンセプトがすごく堤さんらしいなと思ったんですよね。
小池 そうですよね。一方にそれらの海外ブランドの導入をしつつ。それは、水野さんが前段でおっしゃった物語のひとつですよね。
事の始まりはブランドネームに踊らされず「物とちゃんと対峙する」ということだったと思います。
だから、田中一光さんとインテリアデザイナーの杉本貴志さんとで仕事をして、毎晩、そのまま飲んでまたしゃべって。そういう時間の中からコンセプトが生まれてきたんです。堤さんもそういうところにいらっしゃって、何かを感じ取られたのでしょう。
その頃、スーパーマーケットが自社ブランドを盛んに始めたときでした。堤さんは「西友としてもその自社ブランドのものをつくりたいんだけど、どういう考え方がいいかな」っていうところから入られた。
西友の宣伝部に面白い方たちがいらしたから、そういうみなさんとの雑談の中で、生まれていったという実感があるんですよね。
日本の経済は、数字だけがどんどん上向きになっていって、一方で生活者の豊かさはどうなっていくのかと。
でも、生活に一番優しいものを手渡ししたい。
水野 生活に一番優しいもの!素晴らしいですね!
小池 それはどういうものだろうか。そんな話を、本当に真面目に毎晩しゃべっていたのを覚えています。
そこから、世の中の趨勢であるスーパーマーケットの自社ブランドだと、西友はどういう方向がいいかと、デザイン的にいろいろ考えた時期がありました。
はっきりと私が覚えてるのは、自社のミルクを出すのに、その頃まだ新しかったと思うけど、カートンのデザインで、田中さんがね、3本の線を西友のパッケージに入れた時があるんですよ。
それのポスターも作りました。それが終わってから、これはなんかデザインの問題じゃないんじゃないかな、どういうふうにものを提案していく、供給していくかってことなんだという話になったのです。
もう本当に、ただ、ものが主役であるようなグルーピングができないかなって。
その品揃え、そこから無印が生まれていったと思います。
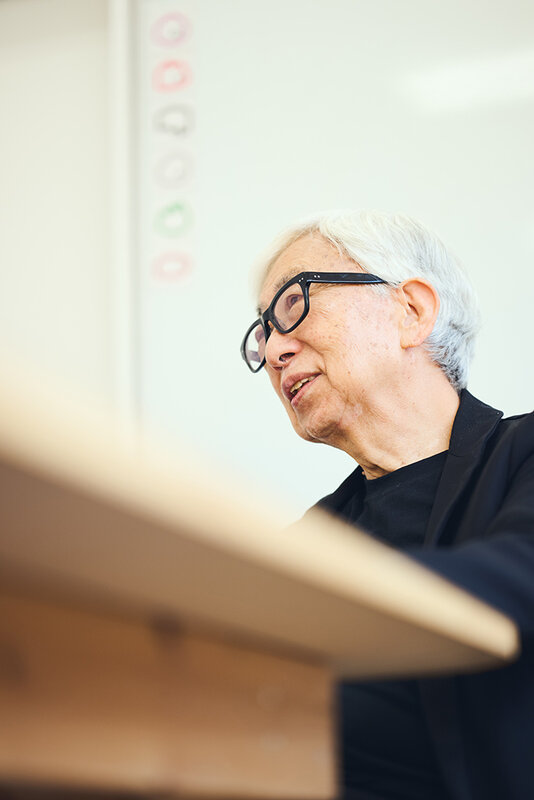
一番難しい青山に原点となる無印良品一号店を
水野 あのとき、僕は最初無印良品が出たというので、西友に見に行きました。
そうしたら、西友のなかといえども、ブランドオンパレードなわけですよ。
有名ブランドじゃなくても、ともかく商品というのはブランドという記号がついてるわけですよね。
その中で、記号とかブランドをなくして、まったく無印の商品があるというのは、いかにも目につきづらい。
それで僕は堤さんに「これはすごくもったいないから、独立店舗として無印良品をやるべきだ」と言った記憶があります。堤さんは「それは考えている」とおっしゃった。
小池 そうですか。ちょうど内側から水野さんがおっしゃったので、私たちは外側から言いました。スーパーマーケットの広い店内に分散して置いてもわからないから、まとめて一つのお店を、一番厳しいところに出したらどうでしょうと。
それで、青山の1号店を出したんですよね。
水野 あそこはあらゆる意味で原点ですね。
小池 そうですね。それで田中さんと堤さんと、あと宣伝部の方と、日暮真三さんとでネーミングやコピーを決めていきました。そこで私はね、商品部の方の話をすごく勉強したんですよ。
確かバイヤーの井口さんとおっしゃったかな、彼らの中に蓄えられていたリサーチの結果をたくさんのメモに書き留めていらしたんです。藁半紙のような紙に持ってらして。それを見るたびにふわっとアイデアが浮かんで。
例えば、私がポスターで「しゃけは全身しゃけなんだ。」というコピーを書きましたが、あれもそういう方のメモから生まれています。
つまり、今まで見過ごしてきたようなもの、これから活かせるようなものというものも全部徹底的に調査しようっていうオーダーが堤さんから出されていたんだと思うんですけど。
そのバイヤーの方たちのメモは、とっても勉強になったんですね。
だから、そういうことで言うと、社内でも機は熟していました。
水野 一番厳しい目をもった顧客がいる青山辺りに、うん、1店舗ですべての考えがわかるライフスタイルの店を出そうということになったわけですね。
小池 確か杉本さんには私が連絡したんですが、あまり細かく説明しないで、こういうことだと言ったら、見事に溶鉱炉で使われてきた煉瓦の外壁と、竹を使った什器などが運ばれてきたんです。
昔からみんなが使ってきたようなもの。見事な品揃えと、プレゼンテーションでした。あの店ができた時は、本当に感激しましたね。
ちょうどDCブランドブームで日本のデザイナーのショップがあり、海外のブランド店も来始めた青山で、無印良品をぶつける。それが面白かった。
わかってくれる人たちに本当にいいものを手渡そうという性善説で
水野 小池さんが無印良品で書いた名コピーはいっぱいありますけど、そのなかでも「わけあって、安い。」っていうのが、すごく重要な意味をもってると思います。
「わけあり」というのは、スーパーマーケットの自社ブランドだから、品質が劣るもを安く売ってるっていうのが、お客さんの受け取り方としては常識的にあったと思う。
いや、そうじゃない。品質が劣るのではなくて、安くできる訳が必要だということをおっしゃっているんですよね。例えばおせんべい。一般的には欠けているおせんべいは全部捨ててしまう。でも、少々欠けていても味は変わりませんよね、と。例えば余計なパッケージはなくてもいいでしょうとか。
だから安くできるんだ。品質は劣っていないんだということを、たったひとことで言い表したコピーだった。
小池 それぐらい話し合いが十分にできたんですね。
あの頃、青山にクリエイティブのスタジオがいっぱいできて、いろんなデザイナーが引っ越してきていて、南青山3丁目の田中さんの事務所は、青山の灯台とか言われるくらい、夜中まで煌々と輝いていました。
皆、話し合って仕事してね。絶対に顧客はこちらが信じて出すものは受け止めてくれるという、明らかな性善説というか、そういうものに立っていたような気がするんですよね。
わかってくれる人たちに本当にいいものを手渡そうという。
だから初期のコピーで「いいと思うなあ、わかりあってる人たち」っていうのを書いて、コマーシャルもつくりました。
そういう時代の雰囲気というものに支えられた気がしています。
水野 素晴らしいことは、いまだにそれが続いてるということだと思います。
普通だと、最初のコンセプトは小池さんや田中さんがつくって、店のインテリアは杉本さんにお願いして、じゃあもうあとは自分たちでやりますからお任せくださいというのがほとんどの事例なんですよ。ですが、だんだんと似て非なるものになっていっちゃうんですよ。これがほとんどの勘違いなんですね。
ところが、無印良品はそのコンセプトを生み出した方々にずっと見張っていてもらうことを愚直にやった。これは素晴らしいことだと思うんです。
小池 そうですね。
水野 堤清二がいなければ「そんな余計なコストかけるな」という話になったと思う。
もう今はどこでも、経済構造自体がコスト重視ですからね。
でも僕はやっぱり、無印がやっぱり本当に世に誇れるって要素は、未だに無印の精神っていうのをしっかりと持ち続けていられるということだと思いますね。

無 印 良 品という3つのスペースに3つの憲法を
水野 僕は小池さんが無印良品で書いたコピーで「愛は飾らない。」というのも好きですね。
余計なデコレーションをいっぱいつけるというのは、自信がないからなんですよね。
その愛に自信がないから、デコレーションしてしまうんだけど。
今の時代にこそ、その無印のコンセプト「愛は飾らない。」とか「わけあって、安い。」という考え方がないとダメだと思うんです。
片方でブランドというのは本当にラグジュアリーなのかなんなのかわからない、値段が高いだけの曖昧なものが出てきちゃってますから。
ただそのラグジュアリーブランドと言われるものも、エシカルなものを作らなければいけないと、ようやく環境問題に対して敏感になろうとしています。でも無印良品は、最初からそういうことを考えていたんだから。
小池 そうですね。素材に対峙するということは、大事にし続けていますね。
そういえば初期に、田中さんが池袋から青山の事務所に帰る移動のタクシーのなかで、こんな話をしていました。
「『無 印 良 品』という4文字の間に3つスペースがあるだろう。その3つのところに、3つのポイントを置こうよ。まず素材を選ぶ、それから、その工程を点検して省略していく。3つ目に、包装を、パッケージを簡略化する」。 その3つの憲法っていうのを田中さんが作ったのが、タクシーの中。それで、私は帰ってすぐそれを「何文字、何行ぐらいにできる?」って言われて書く。そういう仕事をしてきました。
だから、その無印良品っていうことの中に、こういう、なんかクリエイティブサイドもそうあるといいなと思うような、慎重さをものに託せるっていう、そういう幸せな出会いのプロジェクトなんですよね。
本当にビジネスとクリエイティブサイドの幸せな出会い。
幸いなことに、ずっとそれが今も無印良品のカンパニーの中で生きていますね。
水野 そのDNAをどう引き継いでいけるかということが、無印良品のこれからの課題ですね。それで今までの無印良品を現代のMUJIに進化させていかなければいけないから。
小池 時代ですね。今の社長は、そのあたりよくわかる人で、だから、やっぱり無印良品本来の哲学、というと重いんだけど、ある種の思想性みたいなものの大切さをよく理解しておられます。
水野 これから「進化」する一方で、永遠のブランドとして「深化」もしてほしいですね。
構成:森綾 http://moriaya.jp/













