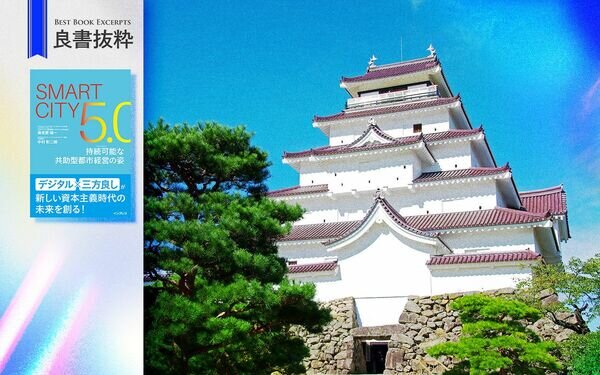ベースは「三方良し」、共助型スマートシティ「会津モデル」の5つの特徴
2023年12月27日(水)4時0分 JBpress
地方部を中心とした人口減少による地域課題が顕在化し、日本の産業競争力低下が叫ばれる。そうした中、デジタルの力で地方の社会課題を解決し、魅力を高める「デジタル田園都市国家構想」をはじめ、「スマートシティ」への取り組みが本格化している。本連載では、先進事例として注目を集める福島県会津若松市の取り組みを中心に、スマートシティの最前線と自立分散型社会の実現について解説した『Smart City 5.0 持続可能な共助型都市経営の姿』(海老原城一、中村彰二朗著/インプレス)より、内容の一部を抜粋・再編集。スマートシティを成功に導くための秘訣を探る。
第3回目は、多くの自治体がスマートシティの先進事例として参考にする「会津モデル」の主要なポイントについて解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 市場規模は10年間で5倍の予測、世界のスマートシティの新潮流とは?
■第2回 都市OSを実装してデータをフル活用、会津若松市のスマートシティ構想
■第3回 ベースは「三方良し」、共助型スマートシティ「会津モデル」の5つの特徴(本稿)
■第4回 主人公は市民、スマートシティ会津若松の「10の共通ルール」とは?(1月10日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
■会津モデルが持つ五つの特徴
第2ステージの説明に入る前に、会津モデルの特徴を整理しておきたい。
2022年12月末時点で「スマートシティ官民連携プラットフォーム」のプロジェクト一覧に掲載されているスマートシティは、全国で275カ所を数える。
多数のスマートシティがひしめく中、会津モデルは他のプロジェクトとどこに違いがあるのだろうか。
基本的には、これまでの10数年の歩みで紹介してきたように、実証実験で終わらず、国家プロジェクトとしての採用を受けつつ、補助金終了後も自律的に継続・改善できるビジネスモデルを持つ点にある(図2-1-1- 2)。
そのモデルは、会津を訪れた多くの自治体から先進事例として参照され、持ち帰られた後は、それぞれの自治体の実状や理念に合わせてカスタマイズされている。
会津モデルは、2022年の会津若松市の資料では、次のように紹介されている。
「核となる都市OSを通して、市民のオプトイン前提で得られたデータを活用してパーソナライズされたサービスを提供し、地域・市民・企業のすべてが納得感のある“三方良し”の考え方をベースにした“共助型スマートシティ”」
その主要なポイントは、①都市OSベースのアーキテクチャー、②オプトイン&パーソナライズ、③地域丸ごとスマート化する幅広いサービス領域、④“三方良し”が織り込まれた共助型スマートシティ、⑤ 10の共通ルール、の五つである。それぞれについて解説しよう。
ポイント1:都市OSベースのアーキテクチャー
スマートシティの説明としては、「IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などのデジタルテクノロジーとデータを利活用し、さまざまな社会課題を解決する新しいサービスが縦横無尽に提供されている街」などとされるケースが多い。だが、これはあくまでもスマートシティの表層をとらえた姿でしかない。
重要なのは、その裏側でデータとサービスをつなぐデータ連携基盤としての「都市OS」がアーキテクチャーに組み込まれているかどうかである(1-2-1参照)。会津モデルでは、都市OSを早い段階から構築し2015年には実装している。都市OSがあるからこそ、デジタルとデータを活用し、市民のQOL向上に役立つ新サービスの開発が容易になっている。
都市OSの構築に先立ち会津モデルでは、行政が持つ統計情報などのオープンデータを扱うためのプラットフォーム「Data for Citizen(D4C)」を2013年に整備している。オープンデータとは、一定のルールの下に公開/見える化されたデータを指す。「データは囲い込むよりもオープンにして活用したほうが社会のためになり、企業にとってもリターンがある」という理念が、その前提にある。
会津若松市は、市政の原則としてオープンガバメントの推進を掲げている。行政が保有するデータの著作権を保持したまま自由に流通できるようにする「クリエイティブコモンズ(CC)」のルールに基づき、オープンデータ化を市役所全体に広げている。D4Cに公開されているデータセットは、2022年末時点で352セット、開発されたアプリケーション数は56種に上る。
D4Cでは、データは可能な限り、機械やコンピューターでの直接読み取りが可能な「マシンリーダブル形式」で格納され、そのデータを使うアプリケーションを地元のベンチャー企業や学生、市民が制作・提供できるようになっている。ソフトウェア開発プロジェクトをイベント形式で進めるハッカソンから誕生したアプリケーションも少なくない。なお現在、このオープンデータのプラットフォームには、D4Cに加え、欧州で標準化されてきたIT基盤のためのオープンソースソフトウェア「FIWARE」も利用している。
都市OSが提供する中核機能はデータ連携である。さまざまなデータを集約・管理し、連携を仲介する。出所が異なるデータや他のシステムに蓄積されているデータとの連携では、標準化された「オープンAPI(アプリケーションプログラミングインタフェース)」を用いて呼び出すのが原則である。
また都市OSから提供される各種サービスを利用する際の本人確認には一般に、サービス提供者ごとに異なるID(個人認証番号)を利用する仕組みが採用されている。これに対し会津モデルの都市OSでは、複数のサービスに共通で利用できるID管理機能を採用することで、サービス間の横連携や、利便性を高めるための改修、新サービスの効率的な開発を容易にしている
これらの仕組みにより、ポイント2に挙げる「オプトイン済みのパーソナルデータ」を活用できるようにしている点も、他のスマートシティとの大きな違いになっている。
<連載ラインアップ>
■第1回 市場規模は10年間で5倍の予測、世界のスマートシティの新潮流とは?
■第2回 都市OSを実装してデータをフル活用、会津若松市のスマートシティ構想
■第3回 ベースは「三方良し」、共助型スマートシティ「会津モデル」の5つの特徴(本稿)
■第4回 主人公は市民、スマートシティ会津若松の「10の共通ルール」とは?(1月10日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:海老原 城一,中村 彰二朗