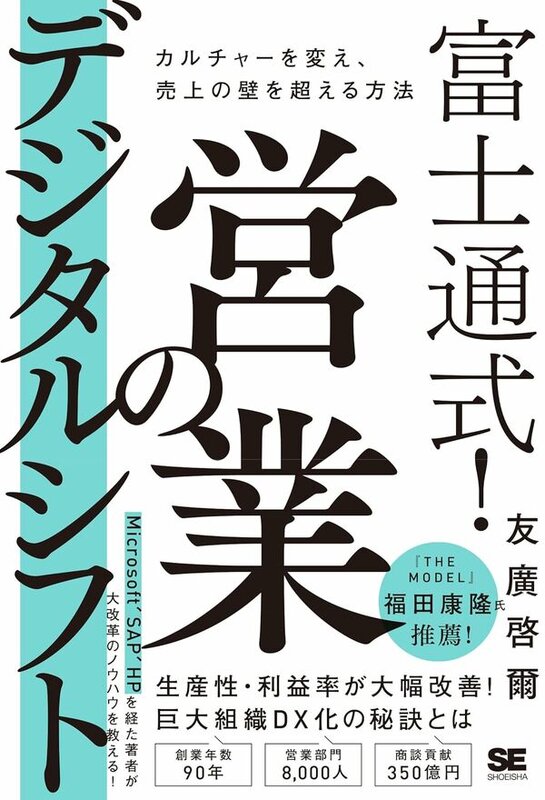「お手並み拝見だね」期待値低めで始まった富士通の営業変革が営業部員から大きな支持を得られた理由
2025年1月10日(金)6時0分 JBpress
富士通が自ら「DX企業」に進化することを目標に掲げる中、営業部門の変革も進めている。「従来とは異なる売り先」へ顧客層を広げるために、どのような取り組みを進めているのか──。2024年8月、書籍『富士通式! 営業のデジタルシフト カルチャーを変え、売上の壁を超える方法』(翔泳社)を出版した富士通カスタマーグロース戦略室の友廣啓爾氏に、同社が進める営業DX推進の舞台裏について聞いた。(前編/全2回)
営業DXの遅れを招く「先発完投型の営業スタイル」
──著書『富士通式! 営業のデジタルシフト カルチャーを変え、売上の壁を超える方法』では、富士通のデジタルセールスチームを題材として営業部門のDXについて解説しています。チーム立ち上げの背景には、どのような組織課題があったのでしょうか。
友廣啓爾氏(以下敬称略) 私が入社した当時、富士通は「モノ売りからコト売り」へのシフトを更に推進している時期でした。これは、顧客企業の情報システム部門の発注に応じて製品を納品する「モノ売り」主体の営業から、LoB(Line of Business)と呼ばれる事業部門のニーズを察知し、提案型でソリューションを提供する「コト売り」主体の営業への転換を意味します。
しかし、私たちがデジタルセールスチームを立ち上げる際に営業担当者を対象として実施したアンケートでは、「既存顧客のフォローで手一杯」「新規顧客の開拓ができない」といった課題が多く挙がり、変革は難航していました。
このような状況に陥る背景にあったのが「先発完投型の営業スタイル」です。先発完投型とは、特定の顧客を一人の営業担当者が専属的、かつ長期的に担当する営業スタイルを指します。これは富士通に限らず、日本企業の多くで見られる現象で、営業DXの遅れを招く要因の一つです。
なぜ、先発完投型の営業スタイルが課題なのかというと、生産性が低く、業務効率も悪いからです。
富士通型The Modelで独自に取り組む「あるアクション」
──先発完投型の営業スタイルでは、どのような点に生産性の低さや非効率さがあるのでしょうか。
友廣 先発完投型の営業では、既存顧客との人間関係や、人脈強化を通じた案件の獲得に重点を置きます。そのため、一人の営業担当者が見積書を作り、受注後のクレームや問い合わせにも対応し、足しげく顧客の元へ通い、時には接待もします。
このような属人的な営業スタイルでは、営業担当者は常に既存顧客のフォローに時間を割かれてしまうため、部門の売上目標を達成するための打ち手は「営業担当者を増やす」という方法になりがちです。結果として、労働集約型のビジネスに陥り、やがて成長の限界に直面します。
私は、前職の外資系企業で、DXによるさまざまなビジネスの変革を経験してきました。だからこそ、富士通の現場が抱える課題を見極め、これまで培ってきた知見を生かせば組織に貢献できるのではないか、と考えたことがデジタルセールスチーム立ち上げのきっかけです。
──デジタルセールスチームを立ち上げることで、どのような営業体制を目指したのでしょうか。
友廣 私たちが構築した営業のチーム体制では「これまで営業担当者が一人で担っていた業務」を特性ごとに切り分け、分業制にしています。分業を進めることのメリットは、各自が専門性の高さを追求しやすくなることです。人的リソースの適正配分も進めやすくなり、組織全体の生産性も向上します。
具体的には、マーケティング、インサイドセールス(富士通におけるデジタルセールス)、フィールドセールス(従来型の営業)、カスタマーサクセスの4部門が顧客情報を共有しながら営業活動を進める「The Model型」と呼ばれる体制を構築しました。
The Model型の営業では、マーケティングが見込み顧客を発掘し、その中からインサイドセールスが受注角度の高い案件を精査します。そして、フィールドサクセスがその案件を引き継いで受注に導き、カスタマーサクセスがさらなる売り上げの獲得を目指す、という専門分業型で営業を展開します。
私たち富士通が「インサイドセールス」の呼称を「デジタルセールス」としているのは、役割の違いがあるからです。富士通のデジタルセールスは、インバウンド型のインサイドセールスを意味するSDR(Sales Development Representative)に加えて、自ら電話やデジタルを駆使して新規開拓を行うBDR(Business Development Representative)の機能も果たしている点が最大の特徴です。
BDRでは、マーケティング活動がなかろうとも、社内の営業部門や商品部門と連携しながら「自社が狙いたいターゲット」を対象に、潜在的なニーズの発掘や、キーパーソン(決裁権者)の探し出しを行います。その中から購買確度が一定基準以上に達した案件のみ、営業担当のフィールドセールスに引き継ぎます。
こうした体制を取ることで、従来の営業担当者が抱えていた「既存顧客の対応に忙しく、新規営業にリソースが割けない」という課題の解消につなげています。このように、デジタルセールスが営業課題を解決することで、先発完投型の営業スタイルからの脱却を進めています。
受注獲得にために行った「アウトバウンド型のアプローチ」
──著書では、営業DXを推進するために「フィールドセールスの理解獲得」から着手したと述べています。具体的には、どのようにして営業現場の理解を得たのでしょうか。
友廣 営業DXを推進するためには、フィールドセールスの方々に「デジタルセールスの価値」を理解してもらうことが必要です。しかしながら、多くの日本企業ではフィールドセールスが契約を獲得する役割を担うため、社内での発言力が強く、結果として組織内のパワーバランスが歪みがちです。そのため、フィールドセールスに新たな取り組みの価値を理解してもらうことは至難の業といえます。
営業DXを推進するためには、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスといった営業4部門が対等な立場で連携し、データ活用を進めていくことが必要不可欠です。だからこそ、私たちはフィールドセールスの方々と何度も膝を突き合わせ、説明を繰り返しました。その数はトータルで1000回を超えています。
しかしながら、それだけで理解を得ることはできませんでした。フィールドセールスは既存顧客からの紹介で一定の売り上げを確保できていたので、私たちとの協業に時間をかけてまで新たな商談を増やす必要性を感じづらかったためです。
そこで私たちは、検証プロセス(PoC)としての実績づくりに注力しました。実際に私たちが創出した商談をフィールドセールスに引き継ぎ、受注に至る件数が増えれば、この一連の取り組みの有用性を実感してもらえると考えたからです。
具体的には、PoCの対象を「営業20部門」に定め、各部門が狙いたい企業や業界、売りたい商品についての協議を重ねました。そこでの要望を踏まえ、私たちが約600社、1400部門に向けたアウトバウンド型のアプローチを起こすことで、受注に結び付く良質な案件を増やすことができました。
このように具体的なアクションによって小さな成果を積み重ねることで、フィールドセールスをはじめとする社内各部門からの信頼感と存在感を高められたと考えています。
「営業現場の声」が本格稼働の後押しに
──PoCを実施した後、営業DXの取り組みを次のフェーズへ進めるためには、どのような社内コミュニケーションが有効でしたか。
友廣 私たちデジタルセールスの「活動内容の見える化」と、フィールドセールスとの「密なコミュニケーション」という2つの取り組みが有効だったと考えています。
具体的には、私たちデジタルセールスが「どのような方法で見込み顧客を探したか」「どの企業にアプローチし、どのようなヒアリングを行ったのか」といった事柄を詳細に記録し、報告書としてフィールドセールスに情報を共有していました。
このように情報共有を続けることで、フィールドセールスは次の一手を考えることができます。また、当初散見された懸念点である「デジタルツールで入手した情報は浅い」といった先入観も払拭できたと考えています。こうして積み重ねた実績を説得材料として活用するために資料に整理し、再びフィールドセールスや経営層に説明を行う、という取り組みを繰り返しました。
デジタルセールスのチーム立ち上げ当初は「お手並み拝見だね」「突然できたチームが、30年営業をやってきたベテランに勝てるわけがない」という声も散見されました。しかし、実績を重ねて信頼感が増すにつれて「(従来型の)営業の在り方を考え直さなければいけないね」という声も聞こえるようになりました。
さらに、PoC終了後に社内で行った満足度アンケートでは、協業した営業担当者の95%から「活動を継続したい」「次も協業したい」と肯定的な評価をいただきました。ここで得られた高評価が他部門からの引き合いにつながり、今では富士通の本格的な営業DX推進へとつながっています。
【後編に続く】富士通の営業変革チームが「50人の壁」を乗り越えるために組織から「徹底排除したこと
■【前編】「お手並み拝見だね」期待値低めで始まった富士通の営業変革が営業部員から大きな支持を得られた理由(今回)
■【後編】富士通の営業変革チームが「50人の壁」を乗り越えるために組織から「徹底排除したこと」
筆者:三上 佳大