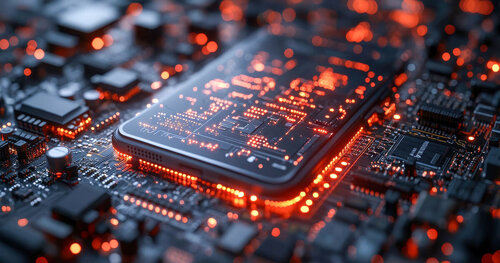ソニー、ルネサス、キオクシア…日本の3大半導体企業は世界売上高トップ10圏外から巻き返せるか?
2025年1月30日(木)4時0分 JBpress
かつて最先端の半導体技術を誇っていた日本。だが、今や半導体市場の勢力図は大きく塗り替えられ、日本企業は外国企業に大きく水をあけられている。AI(人工知能)の「頭脳」であり、経済安全保障の「重要物資」とされる半導体製造において、日本は再び輝きを取り戻すことができるのか? 本連載では『半導体ニッポン』(津田建二著/フォレスト出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。日本と世界の半導体産業の「今」を概観しながら、世界市場の今後を展望する。
今回は、日本の半導体市場の現状と各半導体企業の実力、政府の半導体産業支援について解説する。
日本の半導体産業の現状
■浮き沈みのある日本市場の現状
2023年1〜12月における、日本の半導体産業で最も売上額の多いのは、ソニーセミコンダクタソリューションズの1兆5530億円、ルネサスエレクトロニクスの1兆4697億円、そしてキオクシア(旧東芝メモリ)の9997億円となっている。
前年比では、ソニーが18.7%増、ルネサスは2.2%減だったが、キオクシアは30%減と大きく凹んだ。ソニーはアップル向けのイメージセンサで大成功を収めており、3〜4眼カメラがハイエンドからローエンドまで拡大し、カメラの数量とともにセンサの数量も増えたことで売り上げ増につながった。
ルネサスもそれほど大きく凹むことなくわずかな減少で済んだ。ルネサスは、もはやかつてのルネサスではなくなった。海外の売り上げが80%弱と増え、国内向けのICメーカーから大きく脱却したことで成長を遂げている。
買収したIDTのマネージャーをルネサスのマネージャーに引き上げ、シリコンバレーの最新情報を常に取り入れているだけではなく、これまでカバーの低かったインドやアジアの受注(デザインイン)を増やしてきている。日本人社員は過半数を割り、グローバル競争できる体制を整えている。現在(2024年8月時点)の柴田英利CEOに代わってから海外売り上げを増やすことでルネサスの成長につなげている。
キオクシアは、スマホとパソコンの市場に大きく左右されるNAND型フラッシュメモリを手掛けているが、ここも海外売上比率が上がってきている。ただし、スマホとパソコンの市場が飽和してきている世界的な影響を受け、大きく凹んだ。
DRAMなどのメモリビジネスは浮き沈みが激しい。
2017年〜2018年のメモリバブルでは大きく成長したものの、その反動によって2019年は沈んだ。そして2020年からの新型コロナの影響でオンライン業務や教育が増え、パソコン需要が盛り返した。ただ、車載向け半導体はロックダウンからの回復が大きく遅れ、車載用半導体から端を発した半導体不足の影響で需要が急増した。
しかし流通系を中心に、半導体メーカーへの二重、三重の発注によって流通系とユーザーの在庫も急増し、その解消に22年後半から23年いっぱいかかり生産調整が続いた。24年になってようやく在庫調整が終わりに来て生産量を少しずつ増やしていく結果になってきている。本格的な回復は24年後半から25年だといわれている。
■ 日本の半導体企業のトップテンとは?
ソニー、ルネサス、キオクシアは日本のトップ3社だが、世界的に見るとトップ10にも入らない。2022年の世界半導体企業売上高ランキングでは1位サムスン電子、2位インテル、3位クアルコムとなっていて、日本企業トップのルネサスが16位、キオクシア17位、ソニー18位という順になっている(図1-4)。
この時点では、メモリメーカーのサムスンがトップで、インテルが2位に甘んじている。そして今をときめくエヌビディアはまだ8位にランクインしている。これでも日本で最も稼いだルネサスが16位だから、はるかに上のレベルに来ている。2022年の平均円ドルレートは約119円だったからルネサスは121億ドルを売り上げていた。
日本の半導体メーカーはこれら3社だけではない。ややデータは古いが、2021年における日本の半導体企業のランキングを市場調査会社のオムディアが持っている。それによると、1位キオクシア、2位ルネサス、3位ソニー、4位ローム、5位東芝、6位日亜化学、7位三菱電機、8位サンケン電気、9位富士電機、10位ソシオネクスト、となっている(図1-5)。
日本トップスリーの3社はおおよそ売上1兆円前後だが、それ以下となるとその半分以下となる。4位のロームはアナログICやパワー半導体(高い電圧、大きな電流を扱うことができる半導体)で稼いでおり、5位の東芝もパワー半導体をはじめとするディスクリート(個別)半導体を量産している。日亜化学は青色発光ダイオード(LED)の発明によって23億ドルを稼いでいる。7〜9位はパワー半導体が強いメーカーだが、売上額はそれほど多くない。
ソシオネクストは唯一の工場を持たないファブレス半導体で、海外の半導体メーカーから設計作業を行うデザインハウス的な色彩が強い。自社ブランドのICは少なく大部分はOEMブランドのICだからである。
さらにこれらの下にも日清紡マイクロデバイスやミネベアミツミなどの中堅企業がいる。
日清紡は旧新日本無線とリコーマイクロデバイスを買収し半導体企業となった。2023年の売上額は767億円。ミネベアミツミはミツミとエイブリック(旧精工舎)の半導体部門がある。2024年3月期におけるセミコンダクタ&エレトロニクス部門のうちの半導体売上額は750億円程度だが、日立のパワーデバイス部門を買収したことで25年3月以降には営業利益1000億円を突破し、2029年には2500億円を目標に掲げている。
■半導体産業への支援はもはや国策に
政府、経済産業省が半導体産業に対する支援に目覚め、TSMCの誘致やラピダス設立に加え、日本の3大半導体メーカーや4番手のロームにも支援することになった。米国で半導体産業の強化と科学技術分野への投資を促すCHIPS法案が成立し、民間企業の研究開発や設備への投資を国ができるようになった。このことが日本でも支援しようという動きにつながっている。さらに欧州でも欧州版CHIPS法案が成立し、欧州で半導体製造への強化につながっている。
日本では、2023年までにラピダスへの3300億円の補助を経産省が表明。24年度にはさらに5900億円を投じることで総額9200億円の補助金をラピダス1社に投じている。さらにソニーやルネサス、キオクシアなどの新工場建設などの設備投資に補助金を与えており、2021年から3年間で3.9兆円を補助金として支援したことになる。
この金額について、財務省は他国と比較している。米中対立などを背景に過去3年間の補正予算に計上した半導体支援額は、経済産業省を中心に約3.9兆円。国内総生産(GDP)比は0.71%で、半導体メーカーの誘致や育成に注力する米国の0.21%、ドイツの0.41%をそれぞれ超えるという(時事エクイティより)。
日本では、これまで政府が半導体を支援してこなかったため、半導体産業が弱体化し、半導体開発人口が減っている。特に設計者の人口が減少し、人材育成が早急の課題となっている。
<連載ラインアップ>
■第1回ソニー、ルネサス、キオクシア…日本の3大半導体企業は世界売上高トップ10圏外から巻き返せるか?(本稿)
■第2回 世界一のファウンドリTSMC誘致、国策会社ラピダス設立は、日本の半導体産業に何をもたらしたか?
■第3回ルネサス、ソシオネクスト、ソニー、キオクシア、東京エレクトロン…成長を続ける半導体企業に共通する稼ぎ方とは?(2月13日公開)
■第4回 なぜエヌビディアCEOは社長室を持たず、シリコンバレーのエンジニアはファミレスで議論するのか?(2月20日公開)
■第5回 半導体産業で今後も有望な企業は? エヌビディア、クアルコム、TSMCがファブレスとファウンドリで成長し続ける理由(2月27日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:津田 建二