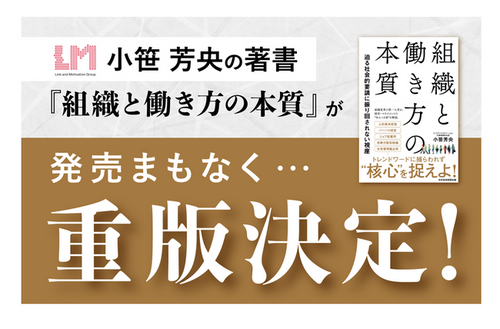27歳で「年季明け」しても、遊女に逆戻り…吉原で働く女性たちを待ち受けていた"地獄のような選択肢"
2025年2月9日(日)8時15分 プレジデント社
「吉原遊郭娼家之図」(出所=「国立国会図書館デジタルコレクシション」より、加工して作成)
「吉原遊郭娼家之図」(出所=「国立国会図書館デジタルコレクシション」より、加工して作成)
■年季が明けたあとも「苦界」は続いた
遊女の経歴には、幼いころに売られて禿(かむろ)として育てられ、その後に客を取るようになる場合と、売られてきてすぐに客を取る場合の二通りがある。
一般に、吉原の遊女は「年季は最長10年、27歳まで」という原則があったが、あくまで原則である。
禿から始まった女は、客を取り始めてから10年が適用されたため、妓楼にいる年月は10年をはるかに超えた。
しかも、妓楼で生活していくなかでいろいろな出費を強いられる。結果として、遊女はさまざまな借金を背負うことになった。
その借金を返すため、年季が明けたあとも数年、働かなければならないこともあったし、鞍替えという形でほかの妓楼に売られることもあった。
■手形をもらい、晴れて外の世界へ
明確な統計はないが、健康な体で無事に年季明けを迎える遊女は少なかったと思われる。年季が明けないうちに、20代で病死する遊女が多かった。
梅毒や淋病など性病の感染、密集した生活をしているため労咳(肺結核)など伝染病の感染、栄養不良、過労などが死因であろう。
ようやく年季が明けた遊女には、楼主が身売り証文を返却し、つぎのような文言が書かれた手形を渡した。
支配家持誰抱遊女誰事誰
今度相定申候季明候に付門外身寄之者へ引渡し遣し候間大門無相違可被通候事
○月○日 名主 印
大門 四郎兵衛どの
切手を持たない女は四郎兵衛会所の番人が見咎めて、大門(※)から外には出さないからである。こうした手形を切手の代わりに示して、年季が明けた女は晴れて大門から外の世界に出て行った。
※「お歯黒どぶ」でかこまれた吉原の唯一の出入り口
図表1は、遊女の一生をおおまかに図示したものである。
出所=『図説 吉原事典』(朝日文庫)
■13〜14歳になると、修行期間が終了
つぎに、遊女としての出発から見ていこう。
禿が下級遊女である新造になるときのお披露目が新造出しである。いわば、禿卒業といえる。
『古今吉原大全』(明和5年)に、こうある——。
五、六歳、あるいは七、八歳より、この里へきたりて、姉女郎に従い、十三、四歳にもなれば、姉女郎の見はからいにて、新造に出すなり。
13、4歳くらいで新造出しになったようだ。ただし、まだ客は取らない。
新造出しの10日ほど前、妓楼内をはじめ引手茶屋や船宿にも蕎麦を配った。また、赤飯を炊いて、あちこちに配った。
当日は、妓楼の前に蒸籠(せいろう)を積み重ね、一番上に白木の台をのせ、そこに縮緬、緞子(どんす)などの反物を飾った。
こういう派手なお披露目には多額の費用がかかったが、すべて姉女郎である花魁の負担となった。
遊女は自分の客から金を引き出すしかない。それができなければ、自分が借金を背負うことになる。
■初めて客をとる時も盛大にお祝いした
新造が初めて客を取り、遊女として一人前になるのが突出しである。
この突出しに際しても着物や夜具を新調しなければならないし、盛大なお披露目もおこなうため、かなりの費用がかかった。
ただし、新造出しとは異なり、突出しの費用は原則として妓楼が負担した。
大田南畝は天明6年(1786)、江戸町一丁目の大見世松葉屋の遊女三保崎を身請けし、妾とした。南畝が三保崎に取材して書いた『松楼私語』で、当時の松葉屋の様子がわかる——。
突出しの日には紋所をつけた金銀の扇や、盃を配った。挨拶まわりには幇間や引手茶屋の若い者が同行するが、祝儀に一分ずつあたえた。強飯(こわめし)を蒸かせて吉原中に配り、引手茶屋には蒸籠を配った。
■「水揚」を40歳以上の男性に頼んだ理由
水揚(みずあげ)とは性の初体験(破瓜(はか))である。
既婚の女や、結婚前でもすでに男を知っている女が身売りしてくることもあるが、幼いときに売られてきて禿として育てられた女や、未婚の生娘が売られてきた場合は、突出しの前に水揚という儀式がある。
春本『正写相生源氏』(嘉永4年ころ)に、妓楼では抱え遊女の水揚には気心の知れた客のなかの、40歳以上の男に依頼するとし、その理由として、つぎのように述べている——。
「若ェ者はいざ戦場と言ってみねえ、松の根ッ子か、山椒の摺子木(すりこぎ)のようにして突き立てるから堪らねえ。ところが四十以上の者は、たとえ勃起てもどこか和(やわ)らかで、ふうわりとするだろう。そのうえ、おめえ、場数巧者で、なかなか雛妓(しんぞ)を痛めるようなことはしねえサ」
春本(しゅんぽん)だけに表現はやや下品だが、妓楼の内情がよくわかる。水揚は「場数巧者」、つまり女扱いに慣れた男に頼んでいた。当時、40歳はすでに初老だった。
■3つの儀式を経て、一人前の遊女に
妓楼は水揚にかなり気を使っていたが、要するに遊女が商品だったからである。いったん突出しをすませると、どんどん客を取ってもらわねばならない。初体験で男性恐怖症になったり、性への嫌悪感を持ったりしないようにする配慮だった。
戯作『にほひ袋』(享和2年)に、生酔いの客が廊下で禿をつかまえ、
「どれ、てめえの水揚をしてやらう」
と、からかう場面がある。
禿は客の手を振りきり、
「アレ、およしなんし、エエ」
と、逃げ出す。
禿はすでに水揚がどんなものか知っていた。禿から育てられた女の子は10歳前後から、こんな環境で生活していたのである。
図表2に、禿から育てられた女が一人前の遊女となって、客を取るようになるまでの儀式をまとめた。
出所=『図説 吉原事典』(朝日文庫)
■莫大な金がかかった「身請け」
まだ年季が明けないうちに吉原を抜け出す方策として、身請けがあった。
客が金を出して年季証文を買い取り、遊女の身柄をもらい受けるのが身請けである。
元禄13年(1700)、松葉屋の抱え遊女薄雲が樽代(身代金)三百五十両で身請けされた。身請けしたのは町人である。
安永4年(1775)には、当時全盛の松葉屋の瀬川を、盲目の高利貸し烏山検校が千四百両で身請けし、江戸中の話題となった。
『藤岡屋日記』には、弘化3年(1846)、ある人が遊女を三百両で身請けしようとしたが、妓楼は六百両を主張して譲らず、けっきょく断念したという話が記されている。妓楼はこのときとばかり、吹っかけたのであろう。
瀬川の千四百両は極端としても、身請けには莫大な金がかかった。
妓楼に支払う身代金のほかに、朋輩や妹分の遊女、妓楼の奉公人一同、引手茶屋、幇間、芸者などに挨拶をし、金品を贈らなければならない。
そのほか、盛大な送別宴も客の負担である。
抱え遊女が身請けされると、妓楼は大もうけをした。
■幸せを手にできるのはごく一部の遊女だけ
ただし、因業(いんごう)な楼主だけではなかった。『街談文々集要』につぎのような身請けの話が出ている——。
三十間堀の大店(おおだな)の主人が京町の海老屋の遊女杣川(そまかわ)のもとにかよっていたが、病に倒れ、まもなく死んでしまった。文化6年(1809)の暮れのことである。
年が明けてから、女房が海老屋を訪れ、杣川を身請けしたいと申し入れた。死期を悟った主人は妻に、杣川を自由の身にしてやってほしいと頼んでいたのだ。
本来なら五百両のところ、楼主も心を打たれて百両で身請けに応じたという。
身請けという僥倖(ぎょうこう)を得るのは才色兼備で幸運にもめぐまれた、ごくひとにぎりの遊女である。多くの遊女は指折り数えて、ひたすら年季明けを待つしかなかった。
■家事経験も常識もなく、女房としては失格
しかし、年季が明けたあと素人の女に戻り、裏長屋に住む庶民の女房になろうとしてもかなり困難だった。
というのは、とくに禿から妓楼で生活してきた女は吉原の外の世界のことをほとんど知らなかったからである。炊事洗濯裁縫などの家事はまったくできないし、世間の常識もなかった。
戯作『後編婭意妃』(享和2年)に、遊女が客に、年季明けには女房にしてくれと願う場面がある。客はとくに裕福というわけではなく、普通の庶民である——。
「廓(くるわ)にいればこそ、面白いこともあり、おかしいこともあるが、素人になっては、あいそづかしだ。女郎あがりというものは、髪はろくに結いもええず、仕事はできず、おらがような貧乏者の女房にはごめんだ」
と、男はきっぱり断わる。
房事(ぼうじ)で男を悦(よろこ)ばす技には長けていても、家事ができなくては裏長屋に住む庶民の女房としては失格だった。
■子供ができにくいという“後遺症”
また、結婚しても、
「勤めあがりは、できいせんと申しいす」(戯作『ふたもと松』)
「女郎衆はマア十人が九人、めったに子供を産まねえから」(戯作『春色梅児誉美』)
とあり、元遊女の女は子供ができないのが普通だった。遊女時代の荒淫と病気が原因である。「勤めあがり」は元遊女のことで、「商売あがり」ともいった。
苦界の年月は、吉原を出たあとの人生にも大きな影響をおよぼしたことになろう。
裕福な町人の妻や妾(めかけ)に迎えられる例もあったが、この場合は妾宅に住み、女中や下男、下女が家事全般をおこなってくれるため、元遊女でもやっていけた。また、男のほうも妻や妾が吉原の花魁だったことを自慢し、世間もうらやましがった。
戯作『春告鳥』(天保7年)で、元遊女のおやなに対し、近所の女がこう言う——。
「此の裏も能婦(いいおんな)ぞろいであったッけが、おまえが来てから年増は言うに及ばず、十六、七の娘たちまで、不残(みんな)おやなさんに押し付けられたという評判だわネ」
おやなが住むようになって以来、一帯では既婚の女も娘も、みな圧倒されてしまった、と。元遊女の容色や色気がいかに目立ったかがわかる。
■帰るところもなく、体を売るしかない女たち
年季が明けたあと、実家に戻る女は少ない。
すでに実家は兄や弟が継いでいる。もと玄人の姉や妹が戻ってきては、実家は迷惑なのだ。かつて親孝行をしたはずの女であるが、素人になったからといって、こころよく受け入れる実家はほとんどなかった。
そのため、幇間や、河岸見世の楼主、小料理屋の亭主など、妓楼に関係する男と所帯を持つ女が多かった。けっきょく、吉原から離れられないわけである。
永井義男『図説 吉原事典』(朝日文庫)
戯作『廓之桜』(享和元年)に、年季明けのあと、西河岸にある河岸見世の楼主の女房となったお定という女が登場する。
お定はかつて自分が遊女だった妓楼にしばしば顔を出すが、いちおう楼主の女房になっただけに勝組の感覚だろうか。もし河岸見世の遊女に零落していたら、とてもかつての朋輩に顔見せはできないであろう。
いっぽう、所帯を持とうと言う男もいないため、やむなく吉原のなかの河岸見世や、吉原の外の岡場所などに流れていく女も多かった。生活の手段としては、体を売るしかなかったのだ。
いったん苦界に沈んだ女の多くは、遊女の暮らしが死ぬまで続いた。
ただし、吉原から岡場所や宿場の女郎屋に流れてきた遊女は光ったようだ。戯作『里のをだ巻評』(安永3年)は、「掃溜の鶴」、「砂(いさご)の中の金(こがね)」と評している。
やはり禿から育てられた女には、遊女としてのしつけが行き届いていたのであろう。
----------
永井 義男(ながい・よしお)
小説家
1949年生まれ、97年に『算学奇人伝』で第六回開高健賞を受賞。本格的な作家活動に入る。江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原、はては剣術まで豊富な歴史知識と独自の着想で人気を博し、時代小説にかぎらず、さまざまな分野で活躍中。
----------
(小説家 永井 義男)