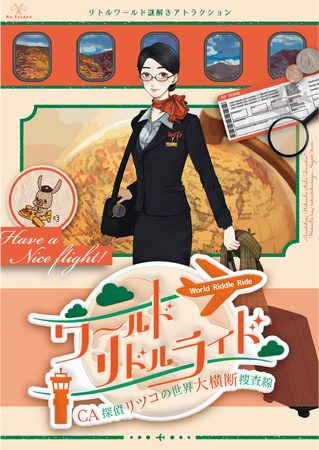夏目漱石でも芥川龍之介でも島崎藤村でもない…国立博物館館長として観覧者数を爆増させた意外な明治の文豪
2025年2月23日(日)10時15分 プレジデント社
国立国会図書館 近代日本人の肖像(https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/342)より
※本稿は、『宮内官僚 森鷗外 「昭和」改元 影の立役者』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
■「軍医として陸軍トップ」→「博物館総長」になった心境
宮内官僚として晩年の鷗外が取り組んだ『帝諡考(ていしこう)』『元号考』は、これまで鷗外作品を研究する学者や評論家の間で注目度は高くなかった。例えば文芸評論家の唐木順三は「清閒の地にふさはしい純考証的な仕事」と評している(唐木、1943年)。
鷗外には「十二月廿五日作」と題する漢詩がある。1917(大正6)年に帝室博物館総長兼図書頭(現在の国立博物館館長と宮内庁書陵部長)へ就任した日付だ。七言絶句の転句に「石渠天禄(せききょてんろく)清閑の地」とある。帝室博物館と図書寮を、中国・漢代に貴重書が納められた「石渠閣(せききょかく)」と「天禄閣(てんろくかく)」という楼閣にたとえ、俗世間に煩わされない「清閑の地」と表現した。唐木の評はこれに倣ったものだ。
ところが、鷗外は同年12月30日に親友の賀古鶴所宛書簡には以下の和歌を書き送った。
老いぬれど馬に鞭うち千里をも走らむとおもふ年立ちにけり
陸軍を退官していた鷗外は、この時56歳。自身を老いた馬にたとえ、歳をとってしまったが鞭を打ってでも千里の道を走ろうという思いだ、と再出仕への意欲を伝えている。
こちらについて唐木は、山県有朋を中心として賀古と鷗外で「何事か政治的な画策をしてゐた跡」が見られる中での「世間的な野心の一表白」と評する。
「清閒」と「野心」の二面性を唐木は指摘するが、鷗外の心情はどちらに傾いていたのだろう。
「十二月廿五日作」の漢詩は前任の帝室博物館総長の股野琢や桂湖南ら著名な漢詩人の添削を経た上で、「大正詩文」に発表されたものである。高級官僚や政治家、帝国大教授らが名を連ねる漢詩の同人誌で、発表される作品は半ば公的なものだ。個人的な心境を吐露したというより、謙遜の意が込められていると見た方がよい。
国立国会図書館 近代日本人の肖像(https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/342)より
■56歳でも志を失わない
賀古に送った歌には基になった鷗外作品がある。1916(大正5)年1月から5月まで東京日日新聞で連載した『渋江抽斎』である。冒頭、抽斎の志を述べた以下の漢詩から書き始められる。
三十七年一瞬の如し、医を学び業を伝へて薄才伸(の)ぶ。栄枯窮達は天命に任せ、安楽を銭に換へて貧を患へず。
そして、この詩について鷗外は「老驥(らうき)櫪(れき)に伏すれども、志(こころざし)千里に在りと云ふ意が此中に蔵せられてゐる」と解説を記している。
「老驥」は年老いた駿馬で、「櫪」はくぬぎの木から転じて馬小屋を指す。英傑は年老いてもなお勇壮な志を失わない、という意味で、出典は中国・三国時代の魏の武帝(曹操)の詩である。
江戸末期の弘前藩に仕えた医師であり儒学者、考証学者でもあった抽斎という人物に関心を抱いたことが、鷗外を「史伝」という新しいジャンルの歴史小説へといざなった。
鷗外は「抽斎を敬慕する余りに」、前掲の詩を居間に飾るほど入れ込んだ。そして以下のように記す。
抽斎は医者であつた。そして官吏であつた。そして経書や諸子のやうな哲学方面の書をも読み、歴史をも読み、詩文集のやうな文芸方面の書をも読んだ。其迹(あと)が頗(すこぶ)るわたくしと相似てゐる。(中略)若し抽斎がわたくしのコンタンポラン〔同時代の人〕であつたなら、二人の袖は横町の溝板(どぶいた)の上で摩れ合つた筈である
その抽斎と同じ志を抱いていると表現するところに、強い意志が表れている。
■小説をやめて官僚に専念する
就任翌月の1918年1月23日には、永井荷風宛の書簡で「当方又々(またまた)官吏と相成(あいなり)、今回は一時全く筆硯(ひつけん)廃絶の覚悟に御座候」と記した。
筆と硯を廃絶するとは、小説家としての文筆を絶つという意味である。宮内官僚の職務に専念する決意を伝えたのだ。
実際、東京日日新聞に連載中だった『北条霞亭(ほうじょうかてい)』は一時中断した。翌日の1月24日には賀古宛の書簡でも「上野も三年町も活気を生ぜしめ度(たき)と日々奔走仕居(つかまつりおり)候」と書き送っている。上野は帝室博物館、三年町(現・霞が関)は図書寮が置かれていた場所である。
鷗外の私的な書簡からは、新たな公務に積極的に取り組もうという心境がうかがえる。決して、俗世間に惑わされない静謐な場で史料の山に囲まれながら、純粋に考証的な著述に没頭しようとしていたわけではない。「清閒」よりも、「野心」の方が本音であろう。
■軍服姿で仕事をこなす
1918(大正7)年1月14日の東京朝日新聞朝刊五面に鷗外の就任直後の仕事ぶりが紹介されている。勤務の様子がよく分かるので、少し長くなるが引用したい。
森総長が就任匆々(そうそう)/博物館の改革/◇相変らず軍服姿で/◇早出晩退の執務振(ぶり)/=正平版の論語翻刻計画
『森さんは学者よりも事務家だ』といふ噂は最近博物館の役人さん達の間に囃(はや)されて新帝室博物館総長森林太郎氏は甚だしく怖い小父(おじ)さん扱ひにされて居る。博士が三宅坂の陸軍省を退(ひ)いてから軍服はお払ひ箱と思ひきや『事務は是れに限る』と許(はか)り又候
▲無風流にも 金地に二つ釦(ボタン)の肩章厳めしく例の長剣をがちやつかせて宮内省の図書寮と博物館とへ交(かわ)る交る毎日早出晩退の精励恪勤(せいれいかくきん)、遉(さすが)に抜けぬ軍隊気質(かたぎ)、一分の遅刻も無く総長室に納まり神谷博物館主事を督励(とくれい)して『あの帳簿を』『この書類を』と万端抜目なく、列品目録と首つ引しては館内を隈無く取調べて居る(中略)館内役人共の職務振りにも注意し
▲専心館務に 力を致させるやう自ら率先して事に当るといふ風なので役人諸氏は恰(あたか)もライオンの前に跼蹐(きよくせき)した態である(中略)之を要するに新総長は着任匆々未完の儘の目録完成、列品の整理等寸分の余裕なく遺憾なく精力主義を発揮し着々改革の歩を進めて居るといふことである
鷗外は単なる文人ではない。巨大組織の陸軍で出世し、軍医として最高位であり医官の人事権を握る陸軍省医務局長まで登り詰めた。その行政官としての経験と能力を、宮内省でも発揮したのだった。
写真=iStock.com/leodaphne
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/leodaphne
■博物館総長として5つの功績
帝室博物館総長としての業績は、山崎一穎『森鷗外論攷』(おうふう、2006年)、須田喜代次『位相 鷗外森林太郎』(双文社出版、2010年)に詳しい。
業績として以下の5つが挙げられる。
①時代別陳列方法の採用
②研究紀要としての「学報」の刊行
③目録作成の推進
④正倉院拝観資格の拡大
⑤蔵書解題と著者略伝
特に①②④は鷗外の発意によるもので、実現に向けて予算獲得に奔走した。
まず取り組んだのが、陳列替えだった。これまで開館以来のしきたりで品目種別による分類陳列をしていたが、時代別の陳列配置に変えようとした。具体的には、上古、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、足利、豊臣、徳川、明治という区分である。
■観覧者数を増加させた取り組み
ただし、当然ながら費用が掛かる。鷗外は早速、博物館の繰越金1万5千円を、1918(大正7)年度の追加予算として提出しようとした。だが、6月に入っている以上、緊急でないものは次年度予算に計上するのが筋である、と宮内省の会計をつかさどる内蔵寮(くらりよう)に難色を示された。とはいえ、次年度に回せば必ず予算が付く保証はない。石原健三・宮内次官と折衝を重ね、8月になってようやく了承を取り付ける。
野口武則『宮内官僚 森鷗外 「昭和」改元 影の立役者』(KADOKAWA)
18年度の東京帝室博物館の歳出総計は前年度比で約7万5千円増の24万8千円余となり、うち臨時費が6万3千円余を占めた。この年の臨時費の多さは大正期で突出しており、陳列配置換えの関連費が多く含まれたのが要因とみられる。「学報」の刊行や陳列品の目録作成も、鷗外在任中に大きく増えた。
博物館の歳出総計は1919年が26万3千円余、20年が35万2千円余、21年は39万7千円余と年々増加し、鷗外の総長就任から4年間で倍以上になった。
歳出の伸びは観覧者数の増加にもつながった。1906(明治39)年の33万7千人余をピークに減少傾向にあったが、鷗外の在任期間中に急増し、20年には過去最高の40万5千人余を記録した。
正倉院御物特別展覧会が行われた40(昭和15)年の69万8千人余を除けば、戦前の帝室博物館時代にこの記録は破られなかった。鷗外の改革は着実に実を結んだといえる。
(参照)
唐木順三『鷗外の精神』筑摩書房、1943年
須田喜代次『位相 鷗外森林太郎』双文社出版、2010年
山崎一穎『森鷗外論攷』おうふう、2006年)
----------
野口 武則(のぐち・たけのり)
新聞記者
1976年埼玉県生まれ。中央大学法学部卒。2000年毎日新聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部を経て、令和の代替わりで各部横断の取材班キャップ。20年3月末まで政治部官邸キャップを務めた後、政治部副部長、論説委員。小泉、野田、第2次安倍政権で官邸の皇室問題を担当し、令和改元の約7年半前から元号取材に取り組み、舞台裏を最も深く知る記者の一人。森鷗外記念会会員でもあり、公文書を基に宮内官僚としての森鷗外の公務について独自の研究を続けている。著書に『元号戦記 近代日本、改元の深層』(角川新書)。共著に『靖国戦後秘史 A級戦犯を合祀した男』(角川ソフィア文庫)、『令和 改元の舞台裏』(毎日新聞出版)がある。
----------
(新聞記者 野口 武則)