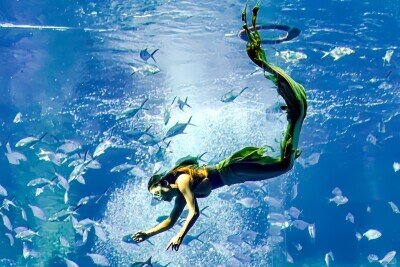朝早く目が覚める原因は「老化」ではない…60代の脳内科医が「9時間しっかり寝る」ために毎日やっていること
2025年3月21日(金)6時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/stevanovicigor
※本稿は、加藤俊徳『すごい記憶力の鍛え方』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/stevanovicigor
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/stevanovicigor
■「記憶力がいい人」は何をやっているのか
一度覚えたことを忘れない、つまり記憶量を「減らさない」ことが大切です。
減らさないためのテクニックには「自力」と「他力」、つまり自分で減らさない工夫と、人に「増やしてもらう」工夫があります。ここでは、英語学習を例にとって解説していきましょう。
記憶量を自分で減らさない「ラベル付け復習」
英単語や文法など、自分がどれくらい覚えているか、模擬テストなどを行ってみてください。そして、問題のカテゴリーごとに4段階でラベルをつけていきましょう。
・どのように出題されても間違えない(完全に理解できている)→◎
・ほぼ理解しているが、間違えることがある→○
・曖昧に理解しており、迷ったり間違えたりする→△
・ほぼ理解していない、毎回間違える→×
これは、問題の「できる」「できない」を可視化する行為です。「できない」が多いとネガティブな感情を抱きがちですが、「できる」に目を向けましょう。
なぜ「できる」ができているのかを自分自身で分析し、繰り返してください。次第に×(できない)が減り、△や○が増えていくことを実感できるでしょう。一度覚えたことが減らない感覚を実感すると、脳は「ご褒美」をもらったような気分になり、より知識を身につけようと動きます。
他力で「情報のシャワー」を浴び続ける
もうひとつ覚えたことを減らさない方法が「情報のシャワー」を浴びられる環境作りです。
英語の学習をしているのであれば、その情報が勝手に入ってくる環境を構築する。たとえばイングリッシュスピーカーの友人を作ることもそうですし、海外のニュースを見るでも、もちろんYouTubeやNetflixで常に英語が流れる番組を観るといったことでもかまいません。
特に効果があるのは、授業を受けているのであれば、先生から聞くだけではなくて、同じ授業を受けている友達とも授業の内容を話してみること。仲の良い友達がやっているテキストや勉強法などを試してみることも効果的です。
これらの行為は、情報との「親密度」を上げることに繋がっています。楽しく学んだことは長期記憶へと移動しやすく、かつ定期的に“英語のシャワー”を浴びることで、学んだことを定期的に思い出し、減らさないような効果が期待できます。
■頭を良くしたければ寝たほうがいい
脳の最も大切な記憶時間「睡眠」を効率よく活用する
すごい記憶力を作り、育てるために大事なことは「睡眠」です。睡眠は、脳が活性化しやすくなるベースづくりのひとつ。
複数の脳番地を動かした「脳トレ」の最も大切な締めくくりは「眠ること」なのです。
睡眠をおろそかにしている人は、頭が良くならないと言っても過言ではありません。眠っている間に、脳は学習した知識を記憶に定着させます。つまり、よく眠らない人は学習の効果が薄い状態になっているのです。
眠っている間は、何もできません。つまり、脳にとっては新しい情報が来ない貴重な時間です。
日中営業しているお店は、営業していない時間にどんなことをしているでしょうか。必要であれば掃除や、倉庫の整理、従業員の休息が営業時間外に行われていますよね。脳も、寝ている間に無意識化で記憶の整理を行い、エネルギーを溜めておくことで次の日の“営業”に備えています。
睡眠不足はそもそも次の日に使えるエネルギーが少ないので、勉強しても集中できず、理解も進まず、思うように学習することができません。次の日も睡眠不足だと、前の日に学習したことも身につかず、さらに学習効率は悪くなる負のスパイラルのできあがり。
そもそも「眠気」という不快感は、脳全体に司令を送る思考系脳番地の70%程度を使ってしまいます。たっぷり寝るだけで、脳を動かすための思考系脳番地のパフォーマンスが上がり、ひいては脳全体をしっかり動かせるようになるのです。
睡眠を利用することで「4回」思い出せる
学習したことをその日のうちに復習することで学習効率が上がります。
実は睡眠中に脳の記憶が整理されているため、無意識のうちにその学習内容をもう一度思い出しています。つまり、初めの学習、復習、睡眠時と1日に3回その内容を思い出すことになるため、記憶の定着がよくなります。
次の日もその内容を復習することによって、脳は2日で合計4回思い出す機会を得られます。記憶を定着させるためにも、睡眠はとても重要なのです。
写真=iStock.com/CoreDesignKEY
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/CoreDesignKEY
■「夜型」はただの思い込み
脳にとって夜はしっかりと眠り、朝から活動することが大切なことだとお伝えすると、しばしば「私って夜型だから……」とおっしゃる方がいます。夕方から頭が冴えてくるのは、実は“日中に頭がぼんやりしている”証拠です。日中の脳の活性度が低いため、少しよく働くようになるとそのような錯覚を起こしてしまうのです。
朝から脳のパフォーマンスを上げられる人と比べたら、その差は歴然。
脳の活性度のピークが変わってくることがおわかりになるでしょうか。活動量の面積の差で見ても、朝からきっちり脳が活性化している人と、“自称夜型”の人とでは、2〜3倍程度の差がついています。夜型の人は、自ら重たい「ハンデ」をその身に課しているのです。
「寝不足で頭がぼんやりする」「ちゃんと寝たのに、朝は頭が動かない」という方は、睡眠の質が悪い証拠です。
■睡眠中の脳波を測定すると…
脳番地の“司令塔”である思考系のパフォーマンスは、睡眠の質に大きく左右されます。
トップがぼんやりしていると、その組織全体がぼんやりしてしまうように、睡眠不足の脳は深い思考をすることができず、司令を送られたその他の脳番地もぼんやりと働くことになります。特に、日中に眠気があると、視覚系や聴覚系の脳番地の働きが低下して、見る力、聞く力が低下します。
「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という言葉を聞いたことがある方もいると思います。
睡眠中の脳波を測定することで図のように、判定することができます。
「ノンレム睡眠」では、徐々に睡眠が深くなります。深睡眠には、脳全体が休息し、脳の老廃物アミロイドβが排泄されやすく、前日起こったことの記憶が定着する時間です。
「レム睡眠」は、眼球が活発に動く“急速眼球運動”(Rapid Eye Movement=REM)が起こっており、脳が活発に動き、夢を見る一方で、運動系脳番地の働きが低下します。これによって、全身の筋肉をリラックスできます。時には金縛りを体感することも起こります。加齢に伴って「レム睡眠」の時間が減ることがわかっていますが、「レム睡眠」の時間が短い場合、日中の記憶力が低下する研究報告があります。
出所=『すごい記憶力の鍛え方』(KADOKAWA)
■脳の働きが落ちているサインとは
思考系脳番地が最もよく休める時間は、睡眠の前半、入眠から4〜5時間までの間に起こりやすい「ディープスリープ」と呼ばれる深いノンレム睡眠の時です。
「ノンレム睡眠」は、睡眠の前半に、「レム睡眠」は睡眠の後半により多く出現します。
出所=『すごい記憶力の鍛え方』(KADOKAWA)
パソコンは長時間起動しているとパフォーマンスが落ちて、再起動を行うことがありますが、まさにこのディープスリープは脳にとっての再起動までの充電時間であるといえます。
夜、人の話を聞くのが面倒になったり、本を読んでも思うように頭に入ってこなかったり、考え事をしてもなかなか結論にたどり着かない……そんな時は、脳の働きが落ちているサイン。あなたの思考系脳番地は、休息を欲しています。
おおよそ夕方6時以降、このサインに気づくような意識づけを行いましょう。先程の脳の活性度のグラフで、日中の脳の活性度が高い人ほどこの「落差」に気づきやすいものです。逆に自称夜型の人はピークが低いため、パフォーマンスの低下に気づきづらいところがあります。
夜になって、思考系脳番地が休息サインを出してきたら、可能な限りその日はさっさと休息を取るようにしましょう。なかなかはかどらなかった難しい課題も、翌日の脳のパフォーマンスが上がった状態であれば、的確に進めていくことができるはずです。
■「歳を取ると眠れなくなる」はウソ
加齢とともに睡眠に関する悩みを訴える方は増えていきます。寝付きが悪い、すぐ起きてしまう、寝ても疲れが取れないなど、質の良い睡眠が取れないことを「歳のせいだ」と思っている方は少なくないことでしょう。
実は脳が休めていないのは「日中よく動いていない」から。脳がしっかりと休息をとるためには、日中にきちんと脳を使うことが大切なのです。
加藤俊徳『すごい記憶力の鍛え方』(KADOKAWA)
おすすめの方法としては、朝に運動系脳番地を動かすこと。運動系脳番地は、脳の動きが悪い時に動かすと、率先して他の脳番地を目覚めさせる力を持っています。
朝にウォーキングやジョギングといった軽い運動を30分〜1時間程度行うことで、脳全体は活性化します。
私自身も朝のウォーキングを欠かさないようにしてから、60歳を超えた今、睡眠時間を6時間前後から9時間弱程度にまで約3時間延ばすことができています。
現在、成人では、平均8時間以上の睡眠をとることが推奨されています。
睡眠時間を十分に確保することで、次の日の脳のパフォーマンスが向上し、日中を活動的に過ごすことで、夜もまた眠れるという好循環を得られます。
最初は日中の行動を変える必要があるかもしれませんが、まず1週間だけでも睡眠時間をいつもより「30分」延ばすことから始めてみてはいかがでしょうか。
----------
加藤 俊徳(かとう・としのり)
脳内科医
昭和大学客員教授。医学博士。加藤プラチナクリニック院長。株式会社「脳の学校」代表。MRI脳画像診断・発達脳科学の専門家で、脳を機能別領域に分類した脳番地トレーニングや脳科学音読法の提唱者。1991年に、現在世界700カ所以上の施設で使われる脳活動計測「fNIRS(エフニルス)」法を発見。1995年から2001年まで米ミネソタ大学放射線科でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、コミュニケーション障害など発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。著書に『1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き』(ダイヤモンド社)、『アタマがみるみるシャープになる!! 脳の強化書』(あさ出版)、『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)など多数。
----------
(脳内科医 加藤 俊徳)