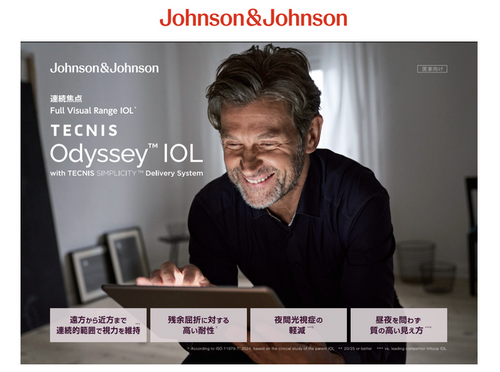「ブラック・スワン」を見逃さない ジョンソン・エンド・ジョンソンが新事業の使い捨てコンタクトで成功できた理由
2025年3月25日(火)4時0分 JBpress
マッキンゼー・アンド・カンパニー出身のコンサルタントらが行った調査によると、40年前に「超優良企業」と呼ばれていた企業群のうち、現在までに約4分の1が破綻もしくは買収を経験しているという。栄枯盛衰が激しいビジネスの世界において、輝き続ける企業とそうでない企業との違いは何なのか。本連載では『超利益経営 圧倒的に稼ぐ9賢人の哲学と実践』(村田朋博著/日本経済新聞出版)から内容の一部を抜粋・再編集。成長を続ける経営者たちの思考や哲学を元に、現代の経営に求められる教訓を探る。
今回は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの高収益部門となった使い捨てコンタクトレンズ事業を取り上げる。この事業を立ち上げた元社長・大瀧守彦氏の試行錯誤の日々とは?
ジョンソン・エンド・ジョンソン元代表取締役 大瀧守彦氏
「ブラック・スワン」を捕え高収益事業を創った経営者
大瀧守彦氏は転職したジョンソン・エンド・ジョンソンにおいてコンタクトレンズ事業を立ち上げ、43歳で代表取締役に就任しました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、第1章で取り上げた「エクセレント・カンパニー」にも「ビジョナリー・カンパニー」にも選ばれ、かつ、その評価に違わぬ実績を記録し続けている稀有な企業です。
世界恐慌の1932年に減収を記録した後、リーマンショック前の2008年まで76期連続増収(2009年の減収率も3%)。世界大戦、「米国病」といわれた米国の停滞期、多くのバブル崩壊があったことを考えると、驚異的な実績です(76期連続増収企業が他に存在するでしょうか?)。
筆者はアナリストとしてハイテク産業を長らく担当してきたため、ジョンソン・エンド・ジョンソンを取材したことがなかったのですが、現在所属するフロンティア・マネジメント主催の企業経営者を対象にした勉強会に大瀧氏をお招きするにあたり、事前にお話を伺いました。
ゼロからの新規事業立ち上げの苦難とともに、同社の強さの源泉が「理念」「長期」「成長(への執着)」「分権」にあることを学んだのです。そして、(よいほうの)「ブラック・スワン」の実例を知ることができました。また、岩淵明男氏、高橋浩夫氏の著作からも多く学んだことを明記しておきます。
■ゼロからの新事業立ち上げ
大日本印刷の米国法人に勤務していた大瀧氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの日本での使い捨てコンタクトレンズ事業の立ち上げのためにスカウトされ、転職しました。1991年、36歳のときです。
とはいえ、医療分野の経験は全くなく完全にゼロからの立ち上げです。自ら、販売、人員、資金など事業計画を策定。まずは顧客の特定です。当時、日本国内には1万人ほどの眼科医がいました。いまではほとんどの眼科医院がコンタクトレンズの処方箋を出してくれると思われますが、当時はそうではなかったからです。
NTTの電話帳、眼科医の会員名簿、街角の看板(「コンタクトレンズ処方します」)などをもとに、対象を絞り込み、採用した15名(医療産業の知見ほぼなし)の営業社員とともに飛び込み営業をかけたそうです。まずは取引の口座を開いてもらわないといけません。2年ほどで1000〜2000件の眼科医が口座を開いてくれたものの、売上高はわずかなものでした。
いまでは、コンタクトレンズといえば使い捨てが一般的ですが、当時は医師にも患者にも使い捨ての概念がなく、また、使い捨ては(年間の費用でみると)通常のコンタクトレンズよりも高価であることも障害でした。
試行錯誤の日々が続きましたが(2年間売上高が僅少で赤字事業のトップ、辛かったと思います)、営業の目標数値の変更(口座開設数 ⇒ 眼科医当たりの処方箋の数)や、それまでの地道な営業の累積効果もあったのでしょう、3年ほど経過したころに売上高が伸び始めました。
ちょうどタイミングよく「1日使い捨て」タイプが日本でも発売となり(1995年。それまでは1週間もしくは2週間使い捨てでした)、その利便性・衛生性などが浸透すると、業績は急速に拡大。その成果が認められ、入社わずか6年後、43歳でジョンソン・エンド・ジョンソン代表取締役に就任しています。
コンタクトレンズ事業の業績は公表されていませんが、産業規模(日本コンタクトレンズ協会によると、2011年2127億円、2023年3340億円)と同社占有率(30〜40%で日本1位)から推定すると、2011年の社長退任時には700億円程度の売上高(とおそらくは、ジョンソン・エンド・ジョンソン全体を上回る高利益率)を達成していたと思われます。
理念は最も重要ですが、とはいえ、理念で食べていけるわけではありません。新事業の成功は、トップ自らが全国を駆けまわる泥臭い努力があってこそのものであることを学びました。
■「ブラック・スワン」を見逃さなかった!
ナシーム・ニコラス・タレブ氏のベストセラー『ブラック・スワン——不確実性とリスクの本質』(ダイヤモンド社)。同書では、想定できないこと、予想できないことを「ブラック・スワン」と呼んでいます。
ブラックとついていることから想定できない「悪い」こと(例えば、中南米の金融危機、リーマンショック、米国同時多発テロ等)と認識されがちですが、そうではなく、純粋に想定できないことを指しており、したがってよいほうのブラック・スワンもありえるのです。
大瀧氏は、まさしくブラック・スワンを見逃しませんでした。人生を変えるチャンスが訪れた際には楽観的に挑戦する勇気が必要だと認識させられました。この点は、第3章でも触れます。
■ 使い捨てを実現するための技術探索
この後、ジョンソン・エンド・ジョンソンの新規事業のための仕組みを取り上げますが、その仕組みが使い捨てコンタクトレンズ事業で発揮されたことを先に紹介します。
同社におけるコンタクトレンズの始まりは、1981年に米国の小さなコンタクトレンズ企業を買収したときに遡ります。ただ当時は、医師が患者に合わせて1枚ずつ削る製品で、量産技術の確立が必須でした。
筆者は、コンタクトレンズの製造は、清潔さという点では特殊ですが、一般的な樹脂成型でできるものと思っていました。しかし実際はそんな単純なものではなく、成型した後に水分を含有させる工程が必要などの理由から、使い捨てを実現するだけの価格を実現できなかったのです。
技術を探索する日々を経るうちに、ベルギーのグループ企業からある情報がもたらされました。デンマーク企業が、水分を含んだまま成型できる技術を持っているというのです。幹部がすぐさまデンマークに飛び、その技術を買い取ったそうです。そして、1988年に米国国内において世界で初めて、1週間で取り換えるコンタクトレンズを発売しています。
その後、1995年には、日米で1日使い捨てコンタクトレンズを発売します(日本では30枚4050円)。当時、使い捨てではないコンタクトレンズは1枚2万〜3万円でしたから、100倍もの生産性を実現したことになります。
劇的な価格の低下すなわち生産性の向上には、前述のデンマーク企業の技術に加え、コンタクトレンズとは全く関係のないある日本企業が貢献しています。その企業の連続生産ライン技術を導入することで、製造時間および人件費の劇的な削減が実現したのです。
この話を聞いて思い出したのは、横河電機の元社長・美川英二氏の「新幹線方式」です。在来線をいくら改善しても時速300キロメートルは実現できない。新幹線が開発できたのは、従来の延長線上ではない全く新しい発想によるものである。革新的な製品開発のためには新幹線方式が重要である、というものです。
■ 経営者に課せられた厳しい責務
後述するように、ジョンソン・エンド・ジョンソンにおいては「分権」が基本思想であり、世界に250ほどの法人がある、すなわち同数の社長がいます(企業規模はさまざまですが、単純に割り算すれば、1社当たりの売上高は平均500億円程度となります)。
社長は目標管理(MBO:Management By Objectives)をされるそうです。年度が始まる前に、定量(売上高、利益、占有率、新製品比率等)と定性(社員の満足度向上のために○○をする、Credo〈企業全体の従業員が心掛けるべき信条や行動指針を明文化したもの〉を浸透させるために○○をする等)の双方において、会社と合意をし、その達成度合いで評価されるとのことです。
例えば、売上高に占める新製品比率が基準に届いていない(全売上高に占める、3年以内に発売された製品の割合が20〜30%のようです)と厳しい評価になるそうです。もちろん、新製品の定義によりますが、20〜30%を達成し続けることは至難と感じます。
また、面白いなと思ったのは、組織の要職に関しては、例えば財務責任者について「いますぐに昇格させられる人」はAさん、「2〜3年後に可能な人」はBさんといったように、将来の組織イメージの提示も求められるそうです。
<連載ラインアップ>
■第1回「僕はギャンブラー」祖業の抵抗器から半導体事業へ転換して大勝ちした、ローム創業者・佐藤研一郎氏の勝負眼とは?
■第2回 虎の子の設計図を完全開示「競争を楽しむ」が信条のマブチモーター創業者・馬渕隆一氏の非凡人的な発想の原点とは?
■第3回破綻寸前のルネサス エレクトロニクスを奇跡の復活へと導いた「最後の男」作田久男氏が修羅場で見せた胆力とは?
■第4回「キーエンスはつんく♂である」創業から50年にわたり驚異の粗利益率80%を維持する製品企画力の源泉とは?
■第5回 「ブラック・スワン」を見逃さない ジョンソン・エンド・ジョンソンが新事業の使い捨てコンタクトで成功できた理由(本稿)
■第6回 20年間停滞し続けたミネベアミツミ、中興の祖・貝沼由久氏はいかにして業績5倍に成長させたのか?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:村田 朋博