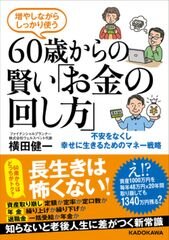子供の習い事にどこまでお金をかけるか…お金の専門家が自分の子に多額の投資をしてたどり着いた納得の答え
2025年4月3日(木)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Hakase_
※本稿は、井戸美枝『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(講談社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Hakase_
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Hakase_
■教育費の「平均1000万円」は参考にならない
Q 子供の教育費、いくら貯めればいいですか?
A 「普通」がないのが教育費。シミュレーションしてみましょう
子供ひとり育てるための費用は、平均で1000万円などといわれますが、これほど“平均”が参考にならないものもないでしょう。通う学校だけではなく、塾、習い事、部活、留学など、さまざまな出費があり、総額いくらになるかは、家庭の方針や子供の進む道によってあまりにも違うからです。
お金をかけようと思えば際限なくかけられますし、節約しようとすると子供の選択肢を狭めてしまうことにも。親としては悩みどころですが、いずれにしても、大学入学時に向けて、産まれた瞬間から計画的にお金を貯めることがポイントです。
一方で、介護費や老後資金とは違い、教育費は、「どのタイミングで」「どのくらいのお金が」かかるかをある程度、想定できるのがいいところ。貯蓄計画のロードマップを描きやすいのです。
ぜひ一度、幼少期から大学を卒業するまでの進路を想像して、費用を書き出してみましょう。
出典=井戸美枝『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(講談社)
■高校生年代まで延長された児童手当の有効な使い道とは
Q 児童手当のいちばん賢い使い道は何ですか?
A 使わず貯めれば、約230万円になります
2024年10月から児童手当が拡充されました。
・所得制限がナシに
・高校生まで延長(18歳になる年の3月末まで)
・第3子以降は3万円に増額
(第1子、第2子の場合、3歳未満は月1万5000円、3歳以上は月1万円)
また、支払回数が年3回から年6回になり、2カ月に一度、入金されます。さて、このお金をどうするか? とくに決まりはないですし、生活費に充てることも想定されている使い方の一つです。
とはいえ、先々のことを考えると、やはり「貯金」がおすすめ。高校生年代まで延長されたことで、産まれてから高校卒業まで貯めておけば234万円になります(第1子か第2子の場合)。これは、大学の初年度納付金と入学準備費くらいに相当する金額。子供にもっともお金がかかるタイミングなので、非常に助かるはずです。
出典=井戸美枝『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(講談社)
■学資保険が元本割れしやすい理由とは
Q 親から学資保険に入るよう言われたけど……
A 貯蓄と保険は「混ぜるな危険」と覚えてください
昭和の時代から根強い人気がある学資保険。今でも「子供が産まれたら、学資保険に入るのが常識」と信じている人も多いようです。
学資保険は、文字どおり学費を準備するための保険で、保険料を払う期間と受け取るタイミングを設定できるのが特長。たとえば0歳から10年間、毎月保険料を払い、大学入学の18歳で満額を受け取るといった選択ができます。
契約者である親に万が一のことがあった場合には以降の保険料の支払いが免除され、子供が亡くなった場合にも死亡給付金が支払われます。生命保険と貯蓄を兼ねた商品なので、その分、支払う保険料が高くなっていることを意識しましょう。
写真=iStock.com/Ivan-balvan
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Ivan-balvan
昔は保険の金利が高かったので、払った金額より受け取る金額のほうが多くなりお得だったのですが、今はどうでしょう。金利が低いため、保険の特約をつけたり途中で解約すると、返戻率が100%未満、つまり、受け取る金額が払った金額より少なくなる(元本割れする)ことがあり、注意が必要です。また、受け取りのタイミングを4月に設定していたために、初年度の学費を払うのに間に合わなかったという失敗談もよく耳にします。
学資保険がなぜ元本割れしやすいのかというと、子供と親、両方の死亡保障が含まれていて、保険にかかるコストが高いからです。子供の死亡保障は必要ないので、親だけが掛け捨てなどの生命保険に加入していればいいでしょう。
本来、お金を貯蓄・運用することと、万が一に備えて保険に入ることはそれぞれ別の目的なはず。この2つが一緒になった貯蓄型の保険商品は、学資保険以外にも外貨建て保険などさまざまなものがありますが、おすすめしません。
■親から教育費の援助を受けると贈与税はどうなる?
Q 私の親にお金を出してもらうの、ありですか?
A ありです! 教育費は1500万円まで非課税にできます
身内であっても、一定以上の金額を贈与すると税金がかかってしまいますが、課税なしで生前贈与する方法もあります。まとまった大きな金額を援助してもらうなら「教育資金の一括贈与」の手続きを。条件を満たせば、最大1500万円まで非課税になります。
・父母、祖父母など直系尊属からの贈与のみ
・受け取る子供(孫)は30歳未満
・金融機関等で教育資金管理契約を結ぶ
・教育費に使ったと証明できる領収書などを提出
といった条件があるほか、贈与を受けた子供(孫)が30歳になるまでに使いきれなかった残額が110万円を超えて入れば、贈与税が課されます。この制度は2026年3月末までの期間限定です(延長される可能性もあります)。
出典=井戸美枝『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(講談社)
■子供の習い事にどこまでお金をかけるべきか
Q 才能が開花するかも? 習い事を減らせません!
A 親の自己満足になっていないか、見つめ直しましょう
英会話、ピアノ、ダンスにプログラミング。小さなうちから習い事を始めれば、才能や適性を見つけてあげられるかもしれないという気持ち、よくわかります。
私もそんな親のひとりでしたし、子供の習い事にはずいぶんお金をかけましたが、その投資に見合った成果が得られたかというと……。
ピアノを習っている子のうち、将来、本気で音楽の道をめざす子はあまりいませんよね。幼少期から始める英会話も、ちゃんと一生ものになるかは疑問です。酷なようですが、子供時代に週1回通っている程度の習い事は、体験の一つとしては価値があるものの、将来に直結することはかなりのレアケース。その子の人生を支えるスキルになるほどのものが身につくわけでもないと、どんな親も薄々わかっているのではないでしょうか。
井戸美枝『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(講談社)
何が言いたいかというと、お金をかけるべきはそこじゃない! ということ。今どきのお稽古にかかる費用は月1万円以上が当たり前。周りのお友だちがみんなやっているからといって、家計のなかから無理をして習い事代を捻出していると、将来の大学進学へ向けた備えができなくなってしまいます。
夫一人の収入では当然足りなくなるので、妻が習い事代のためにパートを始めるケースもよくみられます。もっと習い事をさせたい→夫の収入だけじゃ足りない→パートで補填、という自転車操業のようなやりくりは、大変なわりに実はそれほど子供のためになっていないかもしれません。
お金の面では、目先の習い事代よりも、将来の大学進学に向けた貯蓄を優先すべきです。
----------
井戸 美枝(いど・みえ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)
関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』(日経BP)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』(日本実業出版社)など著書多数。
----------
(ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者) 井戸 美枝)