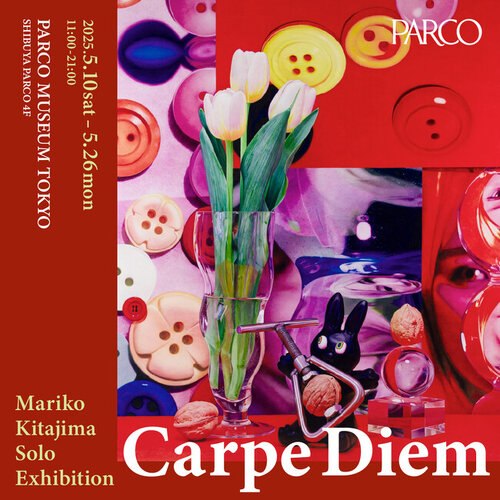誕生日を祝ってくれる人は一人もなかった…「里子村」に捨てられた女性がわが子に手をあげる虐待連鎖の苦しさ
2025年4月7日(月)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/MoMorad
※本稿は、黒川祥子『母と娘。それでも生きることにした』(集英社インターナショナル)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/MoMorad
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/MoMorad
■ずっと震えていた「里子村」での共同生活
里子だけ、毎朝、お寺の本堂から縁側まで雑巾掛けをしなければいけなくて、朝早く起きて、真冬でも冷たい水で、手がかじかんで震えながら雑巾掛けをするのです。もちろん、雑巾掛けは里子だけの仕事で、お寺の家の子どもは暖かい布団でぐっすり眠っています。
トイレは外にあって、穴を掘っただけのもので、ドアもなくて、逆側から見たら丸見えでした。便器もないので、もう、落っこちそうで怖くて……。大をする時は穴とは反対を向いてやるんですけど、落ちそうで怖いから、手前にウンコが落ちちゃうんです。排泄物が、穴まで落ちていかない。お寺の家族の人は家の中の水洗トイレを使っているって聞いたけど、それを見たこともなかった。お寺の人たちが暮らす場所には、入ったらダメって言われていたから。
実際に私の面倒を見てくれたのは、「おばあちゃん」ではなくて、里子の上のお兄ちゃんたちでした。多分、赤ちゃんの時からそうだったと思うので、お兄ちゃんたちは小学生とかで、赤ちゃんの面倒を見ていたのです。お兄ちゃんたちは中学を出ると近所で働いていたけど、ある日突然、村から蒸発していって、気がついたらみんないなくなっていました。
いつも空腹でどうしようもなくて、だからお店からくすねたり、友達の家から持ってきたり、ゴミ箱を漁ったりするしかありませんでした。他に、どうしようもないから。お店で見つかって、「また、お寺のもらわれっ子か」って怒られて。だけど、どんなに「ください」ってお店の人にお願いしても、絶対に食べものはもらえませんでした。
パンツも小さい時から自分で洗うしかなくて、洗い方もよく知らないし、裏表にして両方穿くから、友達のお母さんに見つかって「そんな汚いパンツ、なんで、穿いてんのー! 穿き替えておいでー」って言われても、新しいパンツなんか、持っていないし……。お風呂は幼稚園ぐらいの時から一人で入っていて、だから、髪の洗い方もよくわからないわけです。右左と、半分ずつ洗っていたような記憶があります。お箸の持ち方を教えてもらったこともないし、歯磨きも教えてもらったことがないから、虫歯がすごい状態でした。
靴も買ってもらえなくて、でも小さくなって痛いから、おばあちゃんに言いました。そしたら、おばあちゃん、靴を買ってきてくれたんだけど、小2の時に24センチの靴を買ってきたんです。もう、ぶかぶかで、ティッシュを詰めても大きくて、それを小学6年まで履かなきゃならないと言われました。大きすぎるから、結局、小さい靴を履いていた。それで、親指のところに穴が開いて……。
■「お父さん、お母さん」が何かも知らなかった
そうだ、ある時、友達にこう聞かれました。
「さおりちゃんって、お父さんとお母さん、おらんの?」
お父さん、お母さんって、何? 私には、よくわかりませんでした。だって最初から、お父さんという人もお母さんという人もいなかったから。深く考えたこともなかったし、だから、おばあちゃんに聞いてみました。7歳ぐらいの時かな。
「おばあちゃん、私のお父さんとお母さんって、どうしたの?」
そしたら、「死んで、もういないよ」って言われて、「ああ、そうなんだ」って思いました。
「お兄ちゃん」という存在も何なのか、よくわかっていませんでした。仲のいい友達の家に男の子がいて、その子を「お兄ちゃん」って呼んでいて、お兄ちゃんという人がいるんだっていうのが、なんだか不思議でした。ところが、いつだったか、おばあちゃんに突然、言われました。
「あの子があなたのお兄ちゃんだから、お兄ちゃんって呼びなさい」
そこからは「お兄ちゃん」って呼ぶようになったのですが、「お兄ちゃん」とは呼ぶのですが、それがどういう意味なのかもわかっていませんでした。里子はみんな一緒に暮らしているから、「お兄ちゃん」と他の里子がどう違うのか考えたこともなかったし、何もわからないまま、それまで暮らしていたのです。突然、「お兄ちゃんと言え」と言われましたが、私はずっとこれまで通りに「かずちゃん」と呼んでいたように思います。
これが私にとっての「普通」の生活でした。
なぜか、幼い頃からずっと不眠でした。自分は何のために生きているんだろうって、小学校低学年の頃から思っていました。生きる意味がわからない。「生きるって、そんなに大事なことなの?」って、ずっと思っていました。
■「この人がお母さんになってくれたらいいな」
一度、別の家に里子に出されたことがありました。お寺の息子さんが九州の五島列島まで送ってくれたのですが、そこは立派なブドウ農家で、夫婦に子どもができなかった家でした。その家のお父さんとお母さんは優しくて、何でも買ってくれたし、お姫様みたいなドレスも着せてくれました。でも、私はちっとも、その人たちに懐きませんでした。
一人だけ、大好きになった人がいました。その家の親戚だったのかどうかはわかりませんが、きれいなお姉さんでした。私はこの人がお母さんになってくれたらいいなーって、心の中でお祈りしていました。手をつないだだけでドキドキして、私に笑ってくれるだけでとろけるような気持ちになりました。ある時、お姉さんのお腹が大きくなって、お腹に赤ちゃんがいることを教えられました。しばらく、お姉さんと会えなくなって、久しぶりに会った時には、お姉さんは赤ちゃんを胸に抱いていました。その時、その赤ちゃんに明確な殺意を持ったことを覚えています。赤ちゃんにお姉さんが取られてしまったことが悲しくて、悔しくて、だから「殺したい」と思ったのです。
写真=iStock.com/west
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/west
お姉さん以外のことといえば、毎日、一人で遊んでいて、てんとう虫を捕まえて、潰して、おもちゃの冷蔵庫に入れていたことしか、覚えていません。お寺に帰りたいから、毎日、わざと、おねしょをして、それで養子は無理だとなって、お寺に帰ってきたのです。
なんで、でしょう? お寺は寒いし、少ししかごはんはないし、朝早く起こされて掃除をしなきゃいけないのに、五島の家では大切にされたのに、なんで私はあんなにムキになって帰ってこようとしたのでしょう。あの時、「本当のお父さんとお母さんだよ」って言われたら、懐いていたのかなー。幼稚園に入れてくれて、友達ができたら、また変わっていたのかなー。やっぱり、あの時、あの家の里子になっていればよかったのかな……。時々そう思うことがあります。
里子の中に、学くんという悪いことばっかりする子がいました。車とかに落書きをするんですよ。釘で、ギーッて。それ、多分、私も一緒にやった気がします。車のボンネットに、ドラえもんを描いたことを覚えています。
学くんは悪いことばかりするし、何か悪さをすれば施設に送られてという、施設とお寺を行ったり来たりしていました。学くんの苗字は捨てられていた街道の名前で、「学」という名はたぶん、施設の人がつけたと聞きました。私にはまだ祖父母がいたけれど、学くんは最初から誰もいない子どもでした。学くんは本当に悪いことばっかりする子で、すぐ人のものを盗んでいました。友達の筆記用具とか、いろんなものを。でも、いつも里子同士、一緒にいる私も同じでした。学くんは私たちに悪いことを、とっても親切に教えてくれるんです。
■シルバニアファミリーを1つだけ盗んだ
小学校に、シルバニアファミリーのおもちゃを持ってきた子がいました。その時、私は「シルバニアファミリー」自体、名前もそうだし、何のことかわかリませんでした。でも、その見たこともないお人形たちは、ものすごく可愛くて、キラキラしていて、眩しいぐらいに輝いていました。その子は、その可愛い人形を給食の時に、ずらりと机に並べたんです。だから、私、そっと1つだけ盗みました。そしたら、その子がクラスの子一人一人に人形を持ってきて聞き始めたのです。「この子のお友達の、誰々ちゃんがいなくなったんですけど、知りませんか?」って。焦りましたけど、私は「知りません」と答えました。なんで、盗んだかって? どうしても、欲しかったから。
誕生日もクリスマスも、お寺では何もありませんでした。クリスマスの近くに友達の家に行ったら、ツリーが飾ってあってね。すごく、おっきなクリスマスツリーだったの。リースの飾りがすごく、綺麗だったー。こんな綺麗なもの、私、それまで一回も見たことがなくて、目が吸い寄せられて、こんな綺麗なもん、この世にあるんだーって。綺麗で、綺麗で、内緒でポケットに入れて持ってきました。だけど、お兄ちゃんの「かずちゃん」に見つかって、「返しに行こう」って。一緒に返しに行って謝ってくれたけど、本当は私、返したくなんかなかった。それから、私、クリスマスが嫌いになりました。
筆箱とかマスコットとか、学校の友達が普通に持っているものが全部、羨ましくて、くすねたことは何回もありました。空腹で食べものを万引きするのも普通のことでしたが、古いお寺の汚い布団の部屋には絶対にありえない、綺麗なキラキラしたものを見るだけで、衝動が湧いてきました。自分には絶対に買ってもらえない、望むべくもないものだとわかっているからこそ、自分のものにしたかった。
だけど振り返れば、その時までは私の人生はまだ、幸せだったのです。寒くてひもじくても、朝早く起きて雑巾掛けをやらされる毎日ではあっても、友達はいたし、学校は楽しい場所だったから。
■仲良しのお父さんの応援の声が聞こえてきた
運動会では徒競走の時に、一番、仲良しだった友達のお父さんが、「さおりー、がんばれー」って、おっきな声で応援してくれて、とってもうれしくなったのを覚えています。張り切って、走ったなー。青空がキラキラ、眩しかった。だけど、その後の借りもの競走では、そのお父さんと一緒に走りたかったのに、お父さんは娘と一緒に走るわけで、私は全然知らないおじさんと走ることになって、「あんた、誰?」って。悔しいのか悲しいのかわからないけど、一瞬、うれしい気持ちになっても、結局、こんな目に遭うんだって、ばかみたいって思いました。借りもの競走で持って走った棒を、ゴールした後に投げ捨てました。もう、空は一欠片(ひとかけら)も輝いてなんか、いませんでした。
無邪気な子ども時代だったとは思います。もちろん、不眠は続いていたし、生きる意味がわからない日々に変わりはないのですが、片道40分の通学路も友達と一緒なら笑ってばかりだし、周りの大人たちもみんな「お寺のもらわれっ子」ってわかっているけど、私に優しくしてくれました。
実は私、「おばあちゃん」のことが大好きでした。お母さん代わりだから、すごく懐いていて。でも、今、思えば、どうだったんだろうって思います。実の祖母は一切、会いにはこなかったけれど、生活費だけは送っていたようでした。
「おばあちゃん」は、里子がもたらすお金に、すごい執着があった人のように思うんです。里子のなかに、お父さんが呉服屋で、愛人との間にできた子がいたのですが、毎年、お父さんはその子のために着物を送ってくるのです。だけど、「おばあちゃん」の孫がそれを着ていました。その子の着物なのに。中学を卒業すると、里子はみんな働くのですが、その給料を「おばあちゃん」は全部、自分によこせと渡させていたみたい。だからみんな、ある日突然、里子村を出て行ったきり、誰一人、戻ってきませんでした。私の面倒を見てくれていたお兄ちゃんたちは、電気屋さんとかで働いていたけど、みんないなくなりました。
■大人になった「被虐待児」と虐待の連鎖
私が沙織さんと会ったのは、児童養護施設出身者の当事者活動を行う団体に、「大人になった元被虐待児に会いたい」と連絡を取ったことがきっかけだった。その団体から私に紹介されたのが、沙織さんだった。沙織さんはその活動を支援し、時にイベントにも参加していた。
当時、私は、のちに『誕生日を知らない女の子 虐待——その後の子どもたち』としてまとめた本のための取材をしていた。虐待を受けた子どもなどを治療する、小児の心療内科病棟が閉鎖病棟であったことに衝撃を受け、虐待が一体、子どもにどのような影響を与え、どのような重い後遺症をもたらすのかを、主に里親家庭を中心に取材を進めていたのだ。
黒川祥子『誕生日を知らない女の子 虐待——その後の子どもたち』(集英社文庫)
それぞれの里親から聞いた里子たちの状況は、想像を絶するものだった。「愛着障害」はほぼどの子にもあり、なかには幻聴や幻覚、解離などの重たい症状を持つ子も少なくなかった。施設養育で、ネグレクトや暴力などの犠牲となっている子もいた。それほどまでに痛めつけられ、深い傷を負った子どもたちだったが、里親からあたたかい愛情をうけ、安心できる家庭という居場所を得て、確実に育ち直しの時を生きていた。回復していく子どもたちの姿に、紛れもなく「希望」を得た取材だった。
そして、取材の終盤に、私は滝川沙織さんという女性と巡り合ったのだ。
沙織さんが住む街で、私たちは初めて会った。冬の終わりの頃だったと思う。ユニークなデザインの白いニット帽がよく似合う、切れ長の瞳が印象的な美しい人が目の前にいた。小柄で、アート系のセンスを感じる服装もきっと、「彼女らしさ」なのだと感じた。一目で、女優の尾野真知子によく似ていると思った。
取材に際して、沙織さんは、話す内容をまとめたメモを手にしていた。瞬時に、ある文字に目が射抜かれた。私はこれから、たじろがないで、彼女が語る事実を受け止められるのだろうかと身を固くした。
沙織さんは当時、6歳の夢ちゃんと2歳の海くんを育てていた。夫は、会社員。実母の記憶がなく、育ててもらったことのない彼女にとって、子育ては「やってもらえなかった」ことが1つ1つ甦る、苦しみの過程でもあった。
「誰が、私が歩いたことを喜んだ? 七五三なんか、誰がやってくれた? え? 誕生日なんて、何もない」
夢ちゃんは3歳になるまでほとんど寝ないという、非常に育てにくい子だったということも相俟(あいま)って、夢ちゃんへの殴る蹴るの虐待がどうしても止まらないという「今」を、沙織さんはありのまま、赤裸々に語ってくれた。
■三代続く虐待とネグレクトの連鎖
悲しいまでの虐待の「連鎖」に、胸が潰れるような思いを抱え、彼女の言葉を受け止めた。
ここで初めて、私は「里子村」という言葉を聞き、そうした村が70年代に存在していたことを知ったのだ。
黒川祥子『母と娘。それでも生きることにした』(集英社インターナショナル)
それにしても、いくら新聞で里子村の記事を読んだとはいえ、実の孫を無責任にも捨てることができるものなのだろうか。それも養育を依頼して受け入れてもらったわけではなく、勝手に寺の本堂に置いてきたのだ。このことは警察官の夫も、同意していたのだろう。児童相談所に相談すれば、裕福な家庭だから育てられるだろう、保護者としての責任を全うせよと、言われることを恐れたのだろうか。だからいわば、非合法な手段で「捨てた」のか。
この妻と夫が作った家庭に流れる、酷薄さを感じないわけにはいかない。ここで、沙織さんの父は育ったのだ。自分の子どもや妻を顧みず、別の女性との快楽を選ぶという身勝手な無責任さは、この家庭に由来するものなのか。沙織さんの父の弟は幼い頃から優秀で、公務員になったというが、彼は両親と兄と絶縁し、両親の葬式にも来なかったという。そこまで、覚悟を持って訣別しなければならない家庭だったということか。
沙織さんが里子村に遺棄された時、栄養失調で死ぬ寸前までの状態になっていたというのは、どういうことなのだろう。母親はいつまで、沙織さんを育てたのだろう。引き取った実の祖父母は、ろくに面倒もみなかったということなのだろうか。
何度目かの取材の際に、沙織さんは自身の母子手帳を見せてくれた。それによれば実母は妊娠期間中、毎月欠かさず検診を受け、臨月には毎週、検診に出向いていた。実母はお腹の赤ちゃんのためにと、赤ちゃんを大切に考え、きちんと産もうと動いていたことがわかる。
産んだ後も、生後2カ月で「乳児検診」を行なっていた。この時の「指導」欄には、「精神的」と記されていた。次の「乳児検診」は生後9カ月、場所は打田地区がある自治体の病院に変わっていた。この間に実母は出奔し、沙織さんは祖父母に託され、そして里子村へと遺棄されたのだ。1歳児検診も、同じ里子村の場所で行なわれている。1歳時点での体重は7.2キロ。生後2カ月の4.5キロから、3キロも増えていない赤ちゃんだった。
母子手帳に残る、母の痕跡。生後2カ月までは実母が手元で育てたことは確かであり、何らかの「精神的」理由で、育てることができなくなったのだ。この記録以外、沙織さんには、実母が自分を置いて消えた理由について辿るすべがない。
沙織さんの「普通」だった日常の一コマ一コマに、心が凍りつく。
----------
黒川 祥子(くろかわ・しょうこ)
ノンフィクション作家
福島県生まれ。ノンフィクション作家。東京女子大卒。2013年、『誕生日を知らない女の子 虐待——その後の子どもたち』(集英社)で、第11 回開高健ノンフィクション賞を受賞。このほか『8050問題 中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語』(集英社)、『県立!再チャレンジ高校』(講談社現代新書)、『シングルマザー、その後』(集英社新書)、『母と娘。それでも生きることにした』(集英社インターナショナル)などがある。
----------
(ノンフィクション作家 黒川 祥子)