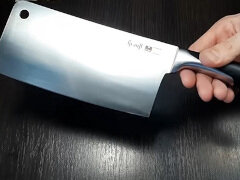「外注するといいかもしれません」はどういう意味か…「話をちゃんと聞かない人」の頭の中で起きてしまうこと
2025年4月12日(土)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Pinkypills
※本稿は、山口拓朗『読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■話をちゃんと聞かない人、文章をちゃんと読まない人
話をちゃんと聞かない人や、文面をちゃんと読まない人が急増しています。
「どこをどうしたら、この文章をここまで(おかしな方向に)読み解くことができるの?」と驚くことも少なくありません。当の本人は、情報を正しく読み解けていないことに気づいていないケースも少なくありません。
このような傾向は、読書量やコミュニケーション量の低下、さらには、動画主体の受動的インプットの偏重、スマホの長時間使用によって引き起こされる「スマホ脳(注意散漫、集中力の低下、記憶力の減退など)」の問題とも無関係ではありません。
写真=iStock.com/Pinkypills
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Pinkypills
現代人は、日々すさまじい量の情報に接してはいるものの、それらの情報は猛スピードで私たちの目の前を通り過ぎていきます。これでは、ひとつのテーマについてじっくり思考する暇などありません。
気軽に楽しめるショート動画がその象徴です。次々に流れてくる動画を見ている間、多くの人が思考を停止させています。〈なんとなく〉それを見ているだけ、という状態です。
■話の内容を正確に把握する「表層読解」
MM総研によると、2024年1月時点における1週間のスマホ平均利用時間は1215分(約20時間)。約5年で6割ほど増加したとのこと。1日のうち3時間弱をスマホに奪われているのです。
怖いのは、思考する機会が減れば減るほど、「ああ、こういうことね」と短絡的に決めつけたり、「どうせこういうことでしょ」と、都合よく情報を解釈したりするケースが増えることです。
思考していないため、情報のつながりを論理的に見ていく力や、論理を支える証拠や根拠を分析する力なども、当然落ちていきます。
情報を鵜呑みにすることで理解した気になっている人もいます。
表層読解とは、話の内容を正確に把握する読解のことです。
大事なのは〈そこに何が書かれているか〉であり、それが、行間や背景などの言外情報の読み解きを必要とする本質読解や深層読解と異なる点です。
内容を正確に把握するためには、文章であれ会話であれ、まずは、そこに何が書かれているか(どんな言葉が発せられたか)、適切に判断できなければいけません。
表層読解では、言葉を理解し、文を理解し、そのつながりを理解していきます。その際、なんとなくの感覚や、主観を用いて読み解いてはいけません。
■「外注するといいかもしれません」の意味は…
ところが、この表層読解を苦手にしている人が少なくありません。
今では仕事の場面でも、なんとなくの感覚で、主観という色眼鏡を堂々と使って、読み解く人が増えているのです。
それが前述した「話をちゃんと聞かない」「文章をちゃんと読まない」などの症状です。
「外注するといいかもしれません」は、「外注しなさい」という命令ではありませんし、ましてや「あなたひとりに任せてはいられない」という批判でもありません。しかし、読解力が低い人は、勝手に「◯◯さんが、外注しろ、と言った」「◯◯さんが自分のことを批判した」と誤読してしまうのです。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
同じように、「プレゼン資料、だいぶ良くなってきたね」は、「この完成度でOK」という意味ではありません。
たしかに、文脈や行間次第では、言葉を額面通りに受け取るべきでないケースもあります(本書の第5章でお伝えします)。しかし、文脈や行間をていねいに読み解いたうえで導き出した解釈と、自分勝手な思い込みによる解釈は、似て非なるものです。
残念ながら、昨今は言葉の意味を無視し、自己流の解釈をする人が増えています。
「話をちゃんと聞くこと」「文章をちゃんと読むこと」は、読解において重要なファーストステップです。
話をちゃんと聞く能力、文章をちゃんと読む能力を伸ばすことを目的に、言語情報を正しく読み解く方法(=表層読解)についてお伝えします。
■「表層読解」と並行して発揮したい「俯瞰する力」
表層読解とは、前述したように、話の内容を正確に把握する読解のことです。
内容を正確に把握するために、言葉を理解し、文を理解し、そのつながりを理解していきます。
ただ、いきなり表層読解を始めると、木を見て森を見ず——視野が狭まって、物事の全体像を見失ってしまうことがあります。
そんな状態に陥らないために、表層読解と並行して発揮したいのが、「俯瞰する力」です。俯瞰とは、高い位置から全体を見渡すこと。上から広く見渡す視点を持つことで、物事の全体像——構造や関係性など——を把握することができます。
部分的・断片的な情報の拡大バージョンが「全体像」とは限りません。部分では「悪」に見えていたものが、俯瞰では「善」に見えることや、部分では「A」と見えていたものが、俯瞰では「Z」に見えることもしばしばあります。
真にその対象について理解したいのであれば、部分的な情報ばかりにとらわれず、全体の流れや背景を把握する必要があるのです。
たとえば、自己啓発書で「成功の秘訣は習慣にある」という主張がある場合、俯瞰する力がある人は、「早起き」や「目標設定」といった具体例が、全体のテーマである「習慣化」の一部であることを理解できます。
■表層読解と俯瞰する力は補完関係にある
同様に、心理学の本を読む際、「ビリーフ」「シャドー」「トラウマ」といった概念が独立した話題ではなく、「自他を問わず人間理解に役立つ要素」であると理解できるでしょう。
もっと言えば、さらに俯瞰する力を発揮すれば、それらが仕事で成果を出したり、人間関係を良好にしたりする際に有効である——という観点を持つこともできます。
さらに、俯瞰的に読み解くことで、伝え手の意見や考えに偏りや抜けがあることにも気づきやすくなります。
たとえば、新しいビジネスモデルを提案する本が、経済的メリットばかりを強調し、環境への影響を無視している場合、その不均衡を指摘することが可能です。
山口拓朗『読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術』(SBクリエイティブ)
このように、俯瞰する力は、物事の全体理解を深めると同時に、表層読解で陥りやすい穴を塞ぐセキュリティシステムの役割をも果たしてくれるのです。
このように、表層読解と俯瞰する力は補完関係にあります。
たとえば、昨今の社会動向(の全体像)をつかみたいと思っても、社会でどのような動きやニュース、トレンドが存在するのか、個別の事案を解像度高く把握していなければ、真に社会動向をつかむことは難しいでしょう。
俯瞰することは、表層に浮かぶ島々を結びつけて考えることにほかなりません。個別の島々を正しく読み解いていれば、視点を上空に飛ばしたときの理解がより広く深いものになるのです。
----------
山口 拓朗(やまぐち・たくろう)
伝える力【話す・書く】研究所所長
山口拓朗ライティングサロン主宰。出版社で編集者・記者を務めたのちライター&インタビュアーとして独立。27年間で3800件以上の取材・執筆歴がある。現在は執筆や講演、研修を通じて「論理的に伝わる文章の書き方」「好意と信頼を獲得する伝え方の技術」「売れる文章&コピーの作り方」など実践的なノウハウを提供。2016年からアクティブフォロワー数400万人の中国企業「行動派」に招聘され、北京ほか6都市で「Super Writer養成講座」を23期開催。著書に『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』(日本実業出版社)、『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける87の法則』(明日香出版社)、『書かずに文章がうまくなるトレーニング』(サンマーク出版)、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』(ダイヤモンド社)など27冊。中国、台湾、韓国など海外でも20冊以上が翻訳されている。NHK「あさイチ」などのテレビ出演も。
----------
(伝える力【話す・書く】研究所所長 山口 拓朗)