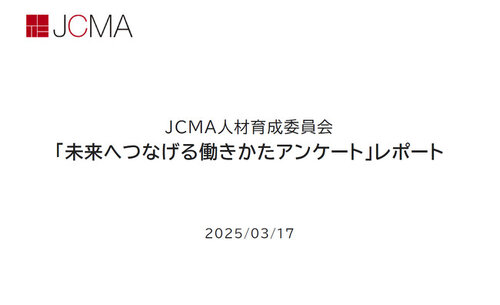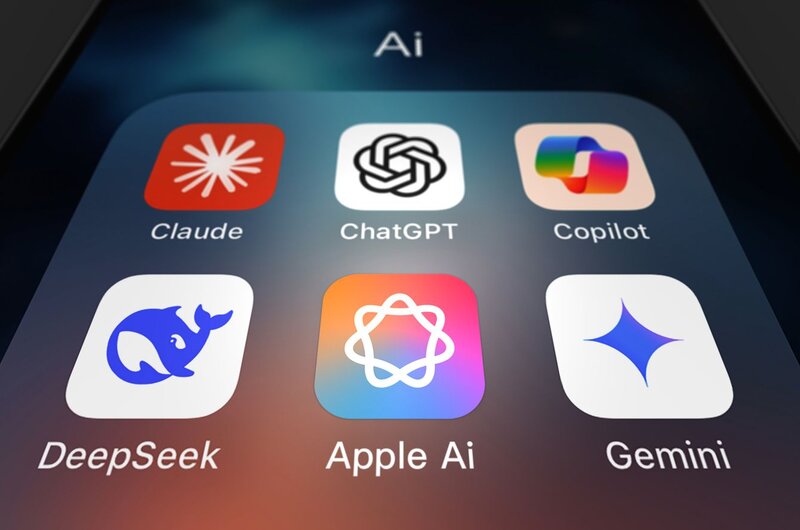バカほど「AIの回答は薄っぺらい」と嘆く…仕事で「AIを使いこなす人」がやっている"たった一つの習慣"
2025年4月17日(木)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/lixu
※本稿は、茂木健一郎『脳はAIにできないことをする 5つの力で人工知能を使いこなす』(徳間書店)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/lixu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/lixu
■AI時代に必要な5つのスキル
これから本格的なAI時代を迎えるにあたって、どんな力が必要になり、また身につけておかないと生き残ることが難しくなるのかは、多くの人が知りたいことでしょう。
あらかじめ断っておきますが、それらは特別なことをして身につけるものではありません。AIがまだなかった時代にも、またAIが普及し始めている現代も、そしてこれから本格的にAIが普及する時代においても、必要なことです。その意味では、人間が生きていくために必要な力は、古今東西を通じて変わりません。
その必要な力はそれぞれが独立してはいますが、複雑に絡み合っています。どれか1つを身につければいいということではなくて、可能な限り、すべてを会得していったほうがいいでしょう。次の5つです。
・質問力
・ボキャブラリー
・判断力
・疑う力
・インテリジェンス
■あるかないかで天と地ほどの差が付く能力
また学校教育で学べるものでもなく、実社会で仕事やさまざまな付き合いを通じて身につけていくものであり、どうすれば会得できるのかという正解やコツもありません。いろいろな人たちとの交流の中で、ときに失敗しながらも、身につけていくものです。おそらくAIに聞いても、身につけ方を教えてくれないでしょう。
なぜこの5つが必要なのかは、追々説明していきますが、どんなにAIが進化してもこれらを身につけているかいないかで、天と地ほどの差が生じてしまうと言っても、過言ではありません。身につければ、AIを使いこなせるようになるし、会得できなければAIの指示どおりに行動するだけになります。
果たして、あなたはどちらになるでしょうか。もちろん、前者になることを望んでいますが、次からは1つ1つ説明していきます。
■質問することができれば問題は半分解決している
AI時代に求められる力 ①質問力
AI時代に求められるのは、何よりも「質問力」です。質問力は本格的なAI時代になったときに必須のスキルとなっていくもので、もし1つだけ磨いておくとしたら、真っ先に選ばなければならないものです。
質問と言うと、たんに「分からないことを聞く」ことだと思って、何も考えずに単純にできることだと思う人もいそうですが、大げさではなくかなり高度な技術を必要とします。「質問することができれば、問題は半分解決している」と言っても、過言ではありません。
そもそも質問するには、本人が今どこにいるのかという「現在地」が分かっていなければなりません。現在地が分からないのにむやみに質問する人は本当に多いです。
現在地とは、言い換えれば、現状の把握。何ができて、何ができないのか、あるいは分かっていることは何で、分からないことは何なのかを、当の本人がしっかり把握できていること。その現在地が分からないと、質問のしようがありません。
画像提供=徳間書店
茂木健一郎さん - 画像提供=徳間書店
■自分の現在地を知る
成績がよくない人の中には、よく「勉強ができないんです。どうすれば成績が上がるでしょうか?」と質問する人がいますが、まさに現在地が分かっていない典型的なタイプです。
成績がよくないとしても、すべての科目がよくないということはなくて(なかには、すべてよくないという人もいるかもしれません)、比較的できるものと、まったくできないものに分かれるはずです。それなのにすべてを一緒くたにして「成績がよくない」ととらえるのは、現在地が分かっていない証拠です。
現在地を把握するのは、自分自身を客観的にとらえること。そう、メタ認知です。
メタ認知ができていないと、的確な答えが返ってくる質問はできません。まずは自分自身がどこにいるかという現在地をしっかり把握しないと質問ができないので、この前提条件を押さえておく必要があります。
現在地が分からないと、的確な質問ができず、当然ながら、欲しい答えも返ってきません。できる教科もできない教科もあるのに、「成績を上げるにはどうすればいいですか?」と聞くと、「しっかり勉強すること」とか「予習復習を必ずやること」といった当たり障りのない、一般的な答えしか返ってきませんが、それは質問をした人が求めている答えではないはずです。
■質問力を制する者はAIを制す
AIに聞いても、答えは同じ。いいえ、忖度も気遣いもしないAIに聞いたら、こんな無味乾燥な答えを返してきます。
「成績アップには、継続的な努力と自分に合った勉強法を見つけることが大切です。焦らず、少しずつステップアップしていきましょう」
そんなことは言われなくても分かるよ……。そう言いたくなるでしょうが、それは現在地を把握していない質問をしたから。質問の仕方が悪ければ、いくら豊富な知識量を誇るAIでも、こちらが求める答えを返してくれるわけではありません。
質問力を制する者はAIを制す──。いきなり大上段に構えるようなことを言いましたが、質問力のある/なしはAIを使いこなせるか使いこなせないかという大きな分かれ道になることは間違いありません。
写真=iStock.com/CHBD
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/CHBD
■質問力を伸ばす方法
現在地を把握したうえで、AI時代に質問力を磨いていくには、何をすればいいのかと言うと、次の3つが挙げられます。
1つ目が、ゴールを明確にする。たんに成績を上げるのではなく、「○○の国家試験に合格できるだけの実力をつける」とか「△△大学に推薦入学できるように成績をよくする」というように、ゴールがどこなのかを明確にします。ゴールが分かってポイントを絞った質問をしていくと、求めている答えが返ってきます。
その答えは、ゴールまでの道筋。ゴールが分かっているからこそ、そこにたどり着くためのやり方や方法を得られます。あいまいな質問しかできないのは、現在地が把握できていないことのほかにゴールが明確になっていないことも一因です。
2つ目が、足りないところを補う。現在地が分かっていれば、自分自身に何が足りないのかも明確なはずです。その足りないところを補っていけば、実力は伸びます。記述問題が苦手なら、「記述問題ができるようになるには、どんなことに気をつければいいですか?」とピンポイントの質問をしていけば、欲しい答えが返ってきます。
反対に、今以上に伸ばすべきところがあるなら、それを強化していけば、同じように実力が伸びます。「選択問題でもっと正解率を高めるにはどうすればいいですか?」と質問すれば、いいヒントがもらえるかもしれません。
■身の回りの問題の解決方法を尋ねる
3つ目が、不安の芽を摘む。
ゴールまでの道筋も足りないところを補うやり方や方法を入手しても、試験当日にどんなハプニングが起こるかは予測不能。「もし知らない問題が出たら」「もし習ったのに思い出せなかったら」と考えると、当日までに不安が大きくなって、肝心な勉強が手につかなくなることもなきにしもあらず。
不安を抱えないように、事前にそうしたものを根絶する方法をAIに聞きます。同じような不安を抱えている人はたくさんいるはずですから、ピンポイントの質問をすれば、的を射た答えが返ってきます。その答えを知っていれば、試験日まで、もちろん、当日も不安にならずに済みます。
以上、3つのポイントをお伝えしましたが、そのうえでどんな質問をすれば、AIを有効活用できるのかと言えば、やはり身の回りの問題の解決法です。仕事や勉強、あるいはそのほかのプライベートのことでもいいですが、自分が直面していることについて、その解決法、あるいはもっと効率的になる方法を知りたいときに、AIに質問していきます。
■AIは自分専属のコンサルタント
言うなれば、質問はAIをコンサルタントとして活用すること。上司や先輩、同僚、あるいは友人知人に聞いたら、「そんなことで悩んでいるの?」「そんなことができないの?」と鼻で笑われそうなことでもいいです。ポイントを絞った質問をすれば、AIはおそらくそうした人たちよりはるかに実践的、かつ役に立つ答えを返してきます。
あなたのことをよく知る、あなただけの専属のコンサルタント──。的確な質問をしていれば、AIはあなたにとってそんな頼りがいのある存在になってくれます。AIを使いこなすことで、ほかの人よりもグーンと抜きん出ることができます。
ただし、それを可能にするのは、質問力があってこそ。膨大な知識量を誇るAIから最適な答えを引き出すには、あなた自身に質問力が備わっていなければなりません。それは、ただ聞くのではなく、抱えている問題を解決するような答えが出てくる質問をしなければならないということ。誰にとっても一朝一夕にできることではないですが、磨いていけば必ず役に立つ答えを得られます。
ある意味では、AIの力を引き出すのは、質問力次第。AI時代に最も必要なスキルです。
■質問力と語彙力は表裏一体
AI時代に求められる力 ②ボキャブラリー
続いて、ボキャブラリー。質問力に関係してきますが、ボキャブラリーはあればあるほどよくて、あって邪魔になることはありません。
茂木健一郎『脳はAIにできないことをする 5つの力で人工知能を使いこなす』(徳間書店)
AIから最適な答えを引き出すには質問力がなければなりませんが、その前にボキャブラリーがなければ、何を言えばいいのかさえ分からなくなってきます。質問力の土台になるのが、ボキャブラリー。質問力とボキャブラリーは、コインの表と裏のような関係にあります。
ボキャブラリーと言っても、難解な漢字を書けるようになるとか、辞書を見なければ分からないような日常的に使われない言葉を知っていること、文学的な表現ができることを指すのではありません。あくまでも、自分の言いたいことを表現するのに最適な言葉を状況に応じて使いこなせるだけの言語量があればいいということです。
■新聞よりも小説や詩集
「お客さんと会ったのに、契約が取れない。どうすればいいですか?」と漠然と質問するより、「見込み客と会うことはできるのですが、1回だけで終わって次のアポが取れず、契約まで持っていくことができません。2回目のアポを取るには何が必要でしょうか?」と具体的に聞いたほうが、AIも的確な答えを返してくれます。ボキャブラリーがないと、ピンポイントの質問をすることができないのは、偽らざる事実でしょう。
ボキャブラリーを増やすには、一にも二にも読書をすること。新聞も悪くないですが、できれば小説や詩など、内面の表現が豊かな作品を読んでいくのがいいでしょう。夏目漱石やドストエフスキー、シェイクスピアなどが書いた名作を、一文一文を味わうかのように読んでいくと、自然にボキャブラリーが増えていきます。
豊富なボキャブラリーに裏打ちされた質問をしていくと、AIもピンポイントの答えを返してくれます。そのうえでその答えをすぐに実践していきます。ボキャブラリーも一朝一夕に増やせるわけではないので、毎日少しずつ名作を読んでいくしかありません。
----------
茂木 健一郎(もぎ・けんいちろう)
脳科学者
1962年生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学大学院特任教授(共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory)。東京大学大学院客員教授(広域科学専攻)。久島おおぞら高校校長。『脳と仮想』で第四回小林秀雄賞、『今、ここからすべての場所へ』で第十二回桑原武夫学芸賞を受賞。著書に、『「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本(共著)』『最高の雑談力』(以上、徳間書店)『脳を活かす勉強法』(PHP研究所)『最高の結果を引き出す質問力』(河出書房新社)ほか多数。
----------
(脳科学者 茂木 健一郎)