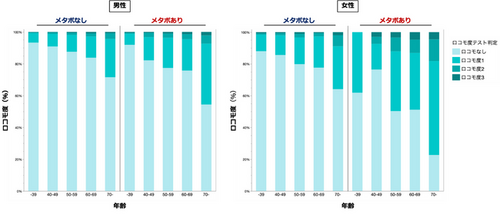国際先導研究「腎臓を創る」を発足
2025年4月17日(木)10時17分 PR TIMES
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/124365/236/124365-236-fb8446a542579909e0ccb21c78c23164-540x304.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
(ポイント)
● 成熟して機能を持つ移植可能なヒト腎臓オルガノイド*1を作ることを目指し、熊本大学を中心と
する国内4施設、海外5施設が6年間の国際共同研究を行う。
● 若手研究者を積極的に海外に派遣して、研究を進めるとともに、国際的研究人材を育成する。
● これによって、多くの若手研究人材を輩出するとともに、移植可能なヒト腎臓オルガノイド作製に
大きく前進する。
(概要説明)
腎臓は再生できない臓器です。世界人口の約10%が慢性の腎臓病を患っているとされており、200万人以上が人工透析や腎移植を受けています。その一方で、根治的治療法は存在せず腎移植のドナーも圧倒的に不足しています。わが国でも臓器移植希望者の88%は腎臓が対象です(約14,500人)。しかしながらドナー数が少なく、腎臓移植まで平均して14年9ヶ月の待機期間となっているのが現状です。
複雑な構造と機能を有する腎臓を人工的に作るということは夢物語とされていましたが、2014年に我々は「腎臓オルガノイド」と呼ばれるミニチュアの腎臓を試験管の中で作り出すことに成功しました。この発見が転機となり、この10年で腎臓オルガノイドは遺伝性腎疾患の病気の仕組みを解明する研究などに用いられつつあります。
本計画は将来の移植医療のために、この技術を更に発展させ、高次な構造*2と機能・成熟度を持つ次世代腎臓オルガノイドを作製することを目的とします。ヒト発生学、微細な装置を使った技術、新規全胚培養システム、さらには動物の体内で臓器を作る技術など、多様かつ最先端の手法を結集することで、より成熟し機能を有する移植可能な腎臓オルガノイドを目指します。そのために国内、海外の研究者が強固な国際研究ネットワークを形成して共同研究を行うとともに、その中で若手研究者を流動させることによって次世代のリーダーを育成します。
(説明)
[背景]
腎臓は尿を生成することで生命維持に重要な役割を持っていますが、再生しない臓器です。腎不全による人工透析患者は日本だけで約35万人おられますが、腎移植の機会は限られています。
熊本大学発生医学研究所の西中村隆一教授の研究グループは2014年に、マウスES細胞*3及びヒトiPS細胞*4から腎臓オルガノイドの作製に世界に先駆けて成功しました。さらに、2017年には腎臓を作るのに必要な3種類の細胞のうち、2つ目のパーツを作る方法を、2022年には同グループの谷川俊祐講師らが3つ目のパーツを作る方法を発表し、これらを組み合わせてもっと複雑な腎臓オルガノイドを試験管内で作ってきました。また、オーストラリアの高里実博士(現在理化学研究所チームリーダー)やハーバード大学の森實隆司准教授も腎臓オルガノイド作製法を相次いで発表しました。これらの進展によって、腎臓オルガノイドは腎臓病発症の仕組みを解明する研究などに使われるようになってきました。このように腎臓オルガノイド研究は日本人が先導してきたと言えます。しかし、移植医療を考えたとき、現在の腎臓オルガノイドはまだ未熟で、機能も不十分です。
[研究の内容]
そこで本計画では、将来の移植医療のために、現在の技術を更に発展させ、高次な構造と機能・成熟度を持つ次世代腎臓オルガノイドを作製することを目的とします。ヒト発生学、微細な装置を使った技術、新規全胚培養システム、さらには動物の体内で臓器を作る技術など、多様かつ最先端の手法を結集することで、より成熟し機能を有する移植可能な腎臓オルガノイドを目指します。そのために国内4機関5名のオルガノイド研究者(熊本大学の西中村教授と谷川講師、理化学研究所の高里実チームリーダー、京都大学の横川隆司教授、東京慈恵会医科大学の横尾隆教授)がオールジャパン体制を構築し、海外の第一線の研究者(米国のハーバード大学の森實隆司准教授や、ワシントン大学セントルイス校、カリフォルニア工科大学、ドイツのチュービンゲン大学、イスラエルのワイズマン研究所など)と強固な国際研究ネットワークを形成して共同研究を行います。
そして、この中で若手研究者を流動させることによって次世代のリーダーを育成します。本計画は特に若手の育成に重点を置いており、優秀な博士研究員や大学院生の雇用、彼らが自分で管理できる研究費の配分、海外への長期・短期派遣とそれに伴う旅費の支援、最先端機器へのアクセス提供、論文成果の発表費用支援などを行います。さらに毎月webで国際会議を行うとともに、毎年熊本で対面の国際会議を開催します(今年は7/26-27)。この会議自体は未発表データを話し合うため非公開ですが、その前後(7/25と7/28)に熊本大学発生医学研究所において海外から招聘した研究者によるセミナーを行います(同研究所ホームページに掲載予定)。また12/5には日本分子生物学会において冠シンポジウムを主催します。より詳細は本国際先導研究のホームページをご覧ください。
https://creating-kidney.jp
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/124365/236/124365-236-2a84238e976140ffab8648eacdbe08c6-1412x794.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
本研究は日本学術振興会 科学研究費 国際共同研究加速基金(国際先導研究)の採択を受けて、6年強(2024年12月から2031年3月まで)の期間で実施されるものです。2024年度の採択は全国で5件、生命科学系は2件のみであり、熊本大学として初めての採択になります。生命科学系としては九州初でもあります。
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/05_sendou/ichiran.html
国際共同研究加速基金(国際先導研究)は、優れた国際共同研究に対して基金による柔軟性の高い大規模・長期間の支援を実施することによる、独創的、先駆的な研究の格段の発展を目的とするものです。 我が国の優秀な研究者が率いる研究グループが、国際的なネットワークの中で中核的な役割を担うことにより、国際的に高い学術的価値のある研究成果の創出のみならず、当該学術分野全体の更なる国際化、研究水準の高度化を目指します。 さらに、ポストドクターや大学院生が参画することにより、将来、国際的な研究コミュニティの中核を担う研究者の育成にも資するとともに、国際共同研究の基盤の中長期的な維持・発展につながることを期待するものです。
[展開]
本国際共同研究によって、多くの若手人材が輩出し、移植可能なヒト腎臓オルガノイド作製に向けて大きく前進することが期待されます。
[用語解説]
*1 腎臓オルガノイド: 試験管内で作られた腎臓のミニチュア版。
*2 高次な構造: 「ネフロン前駆細胞」、「尿管芽」、「間質前駆細胞」という3種類の前駆細胞
から作られる腎臓の構造。
*3 ES細胞: 受精卵から作られた多能性幹細胞。胚性幹細胞。
*4 iPS細胞: 皮膚や血液などの体細胞から作られた万能細胞。
(詳細情報)
ホームページ:
国際先導研究「腎臓を創る」:移植可能な次世代腎臓オルガノイドを目指したグローバルネットワーク
URL: https://creating-kidney.jp