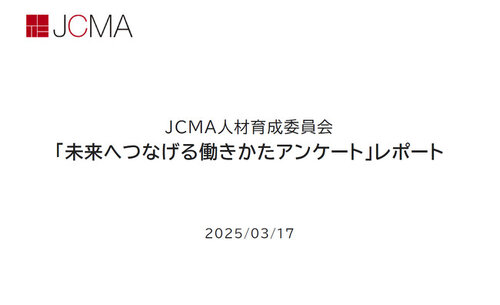「打たれ弱く仕事が続かず就職できない」そんな"短所"を"能力"にあっさり変えたたった1つの方法
2025年4月20日(日)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Sorranop
※本稿は、杉田隆史『「なんだか生きづらい」がスーッとなくなる本』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Sorranop
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Sorranop
■自分のダメな部分が妙に気になったら……
図表1をご覧ください。このリンゴの絵、どこが一番気になりますか?
出所=『「なんだか生きづらい」がスーッとなくなる本』(三笠書房)
欠けている部分ですよね。でもこのリンゴ、欠けている部分以外は完璧なのに、なかなかそちらには目を向けられないんですよね。
あなたが一人で考え事をする時なんかも、やっぱり自分のダメな部分が妙に気になったりしませんか?
お金が「ない」、時間が「ない」、カワイく(カッコ良く)「ない」……。
自分が持っていないものや、できないことが次々と浮かんできて、どんどん不安になることとか、ありますよね。特に夜に考え事する時なんか。
人は足りない部分が気になるものなのです。
■「不完全さ」こそ愛したい
そんなふうに、人は足りない部分に目がいきやすいですから、どうも自分の「ない」部分を恐れ、毛嫌いしてしまうんですけど、ある本を読んだ時、「ない」に対する考えが変わったんですよ。
アメリカを代表するジャーナリストであるビル・モイヤーズの質問に対して、世界的な神話学者であるジョーゼフ・キャンベルがこう答えているものです。
モイヤーズ 欠点があるからこそ人間を愛せるとおっしゃるのはなぜでしょう。
キャンベル 子供たちが可愛いのは、しょっちゅう転ぶから、それに小さな体に似合わない大きな頭を持ってるからではありませんか。ウォルト・ディズニーはそういうことをすっかり心得たうえであの七人の小人を描いたんじゃないでしょうか。それに、人々が飼っているおかしな小型犬、あれだって、とても不完全だからこそ可愛いんでしょう。
モイヤーズ 完璧な人間なんて、もしいても、退屈な人間だろうと?
キャンベル そうなるほかないでしょう。人間らしくありませんから。人間のへそのように中心的な要素、つまり人間性があってこそ、人間は──超自然的ではなく、不死不滅でもない——人間らしい存在になれるのです。そこが愛すべき点です。(後略)
(『神話の力』ジョーゼフ・キャンベル&ビル・モイヤーズ著、飛田茂雄訳/早川書房刊)
これを読んだ時、ハッとなったんですよ。考えてみれば、人が「愛おしい」と思うものって、たしかにどこか「不完全」なものなんですよね。
日本人に長年愛されている映画の寅さんとか、ミスターこと長嶋茂雄さんなんかもそうですよね。何かが大きく欠けているからこそ、よけいみんなから愛されている。
もっと身近な例で言うと、「赤ちゃん」なんて、まさに「ない」の極みですよね。話せないし、歩けないし、一人で食べられないし、なんにもできないのに、なんとも愛おしい。ある意味、「完璧な不完全」とも言える存在かもしれません。
写真=iStock.com/Yagi-Studio
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Yagi-Studio
ところが私たちは、ふと人恋しくなると、
「もっと痩せれば、モテるかもしれない」とか、
「もっと明るくなれば、友達が増えるかもしれない」とか、
「もっと仕事ができるようになれば、みんなから好かれるかもしれない」とか、
自分が「もっと何かを手に入れたり、能力を身につけたりすれば」、人から愛されるだろう、なんて考えてしまうんですね。
でも、神話学者のジョーゼフ・キャンベルはそうじゃないと言っているんです。
人は「できる部分」、「持っている部分」があるから愛されるのではなく、むしろ「できない部分」、「持っていない部分」があるからこそ愛されるのだと言っています。
もし、9頭身でスタイル抜群のミッキーマウスがいても、カワイくないですよね。品行方正な寅さんや、理路整然と話す長嶋茂雄さんがいても、どこか「愛おしい」とは思えない気がしませんか?
——評価されるには「ある」が必要です。
愛されるには「ない」が必要です。
■“短所”を“能力”にあっさり変える方法
「企業がメンタルヘルスに取り組んでいる」なんていう話は近年よく耳にします。
テレビでもそんな特集をやっていて、ある番組で、うつになって1年以上休職しているお父さんのいるご家庭のVTRが流れました。
家族が食事をしている場面なのですが、重苦しい雰囲気なんですね。そんな中、こんなナレーションがかぶります。
「お父さんがうつになってから、娘がやたらとはしゃぐようになった」
この映像を観た時、なんだかせつなくなったんです。「ああ、この娘さん、私だな」って。
■子供の頃のクセを引きづると生きづらかった理由
この娘さんは、無意識に家族のバランスを取っているんですね。まだ小さな子供なのに、けなげに家族を明るくしようとしている。
私も子供の頃、家族がうつになったりして気まずい雰囲気だったので、いつも家族を明るくしようと「気をつかって、はしゃいでいた」んです。だからこの娘さんのせつない気持ちがよくわかるんですよ。
でも問題は、このような子供の頃に身につけてしまったクセって、大人になってからもずっと続けてしまうことが多いということなんです。
私の場合は、この「まわりの人の意向を敏感に察知してバランスを取る」というクセをずっと引きずって、気がつけばとても生きづらくなっていました。
■「家族以外の場所」で頑張っても報われない
では、なぜ子供の頃に身につけたクセを引きずると、生きづらくなってしまうのでしょうか? それには、以下の理由があります。
子供の頃に身につけてしまったクセを、「家族の中だけ」で発揮している分には、まだ問題がありません。家族からそれなりに感謝されるので、本人は自分のやったことが報われたような気がします。
ところが、「家族以外の場所」でそのクセを発揮しても、まわりの人たちは赤の他人ですから、本人が期待するほど感謝や見返りをくれません。
たとえば会社で、家族の中でやっていたように、気をつかって社内のバランスを取ろうと奮戦しても、上司や同僚はそのことにあまり気づかなかったり、評価をしてくれなかったりします。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
そうなると、本人はどんなに頑張っても報われない気がするので、疲れ果ててしまうんですね。
そして、本人はそんな子供の頃に身につけてしまったクセを、「まわりに気をつかいすぎる」とか、「自分がない」など、自分の「短所」として自覚するようになります。
■「ある分野の天才」かもしれないあなた
ところが、そんな自分が「短所」だと思っていることも、じつは「状況」さえ変われば、活かせることがあるんです。
私の場合、「気をつかって、はしゃぐ」というのは、人が多く集まって楽しもうとしている状況、たとえば飲み会なんかで発揮すれば役に立ちます。
“おもしろい人”と思われて、次も人から誘ってもらえます。そんな出会いから、いろいろなつながりをつくることができました。
それに「まわりの人の意向を敏感に察知する」というのも、心理セラピストとして、今まさに役立っています。
そういえば、私が心理セラピストになったキッカケも、「打たれ弱さ」ゆえに、仕事が続かず、就職できない私に対して、友人がこんなことを言ってくれたからなんです。
「どうして杉田さんが就職活動しているんですか? 杉田さんは感度が高いんだから、それを活かす仕事をすればいいじゃないですか?」
友人にしたら何気ない一言だったかもしれません。でも私にとっては、この一言は衝撃でした。
友人は、私がずっと「短所」だと思っていた「打たれ弱さ」を、「感度が高い」と表現してくれたんです。
そうか! 私は「感度が高い」んだ!
だったらその「感度の高さ」が活かせる「状況」で仕事をすればいいんだ!
私はその瞬間、短所と長所は、結局同じことを言っているんだということ、そして、自分がずっと苦しんでいた短所は、「状況」さえ変われば活かせるんだということに初めて気づいたんです。
■「状況さえ選んで」使えば、それはむしろ「能力」になる
そのことに気づいてから、私の人生は静かに変わっていきました。
子供の頃に身につけてしまったクセというものは、それを「人生全般で」発揮しようとすると苦しくなります。でも「状況さえ選んで」使えば、それはむしろ「能力」になります。
あなたは気づいているでしょうか? あなたが子供の頃に身につけてしまったクセって、じつは非常にレベルが高いということを。
子供の頃からバイオリンや歌舞伎を習っている人は、同じものを大人になってから始めた人がなかなか追いつけないほどレベルが高いですよね。
となると、あなたが子供の頃から否が応でも身につけてきたそのクセも、それと同じなんですよ。
たとえば、「人に気をつかいすぎる」といった些細なクセでも、子供の頃から気をつかっていた人は、筋金入りですから、誰もが気づかないようなことまでとことん気をつかえるのでしょう。
杉田隆史『「なんだか生きづらい」がスーッとなくなる本』(三笠書房)
危機回避、たとえば絶対に粗相をしてはいけない接客をする時とか、大きなサプライズを仕掛ける時とかに、そういう人の能力は活かせますよね。
そんなふうに子供の頃から気をつかっていた人は、大人になってから「人に気をつかう」ことを学ぼうとする人が、けっして追いつけないくらいのレベルのことができるんです。これはある意味、あなたは「その分野の天才」と言えるかもしれません。
あなたが短所だと思う、あなたのクセって、なんですか?
そしてそれは、どんな状況でなら活かすことができますか?
——「短所」の数だけ「長所」がある。
----------
杉田 隆史(すぎた・たかし)
心理セラピスト、メンタルトラベル代表
1970年東京都生まれ。高校の頃から漠然とした生きづらさに悩み、「心の病気じゃないけどツライ」という状態を20年間続けて、引きこもりも経験。2006年に心理セラピーと出会い、初めて生きづらさから解放されたことをきっかけに、日本における第一人者たちからさまざまな心理セラピーの技法を学ぶ。自らの経験から、「心の病気じゃないけどツライ」という人の受け皿の必要性を感じ、「悩んでいない人の悩み相談」という看板を掲げて、心理セラピーの個人セッション、ワークショップを開催。クライアントは日本国内はもちろん、海外からも訪れ、これまで5000人以上の悩みを聴き、セラピーを行なってきた。
----------
(心理セラピスト、メンタルトラベル代表 杉田 隆史)