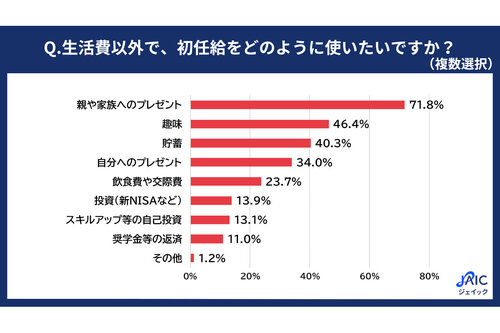「今年の新入社員は子供っぽい」ウンザリする大人世代が気づいていない"弱い若者"を量産した真の原因
2025年4月21日(月)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/byryo
■春の風物詩としての「最近の若者は」
春がくるたび、街には初々しいスーツ姿の新社会人が溢れる。その姿を横目に、私たちはいつの間にか毎年恒例のように「今年の新入社員は○○だ」などと話し始める。
曰く、「最近の若者は叱られ慣れていない」「自己主張がなく指示待ちだ」「コミュニケーション力が弱い」——そんな「今年の新入社員論」がビジネス誌やニュースサイトの誌面を飾り、SNS上でも共感を集める。このプレジデントオンラインでも、4月に入って早々そうした記事がいくつも出され、そのつど話題を集めているようだ。
毎年の風物詩となっている「今年の新入社員は○○だ」ネタの2025年版は、「今年の新入社員はマスク世代(コロナ世代)だ」である。コロナ世代、マスク世代と名付けられたかれらは学生生活の大半を「コロナ禍」と呼ばれた期間のなかで過ごし、表情を隠すマスクをつけ続けてきた。その結果として、対人関係の構築や感情表現に苦手意識を持つとされている。
写真=iStock.com/byryo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/byryo
だが、私はその“他人事”のような批評に対して強い違和感を覚えずにはいられない。なぜなら、マスクをつけさせたのは、かれら自身ではなく、私たち大人側——社会そのものだったはずだからだ。
これから議論を進めるにあたり、まず私たちが立つべきは、「マスク世代」と名付けられた若者たちの「弱さ」を観察しあれこれ品評する立場ではない。その「弱さ」を作った社会の一員であるという立場をわきまえるべきだろう。
ここから少しずつ、そのことについて考えてみたい。
■新しい生活様式という“青春の否定”
忘れるはずもない2020年。
新型コロナウイルスのパンデミックが始まると、「新しい生活様式」という言葉が社会全体を覆い尽くした。これは感染拡大を防ぐための行動指針として提唱されたもので、政府や専門家、メディアを中心に瞬く間に浸透した。人との距離を取ること、密集を避けること、会話を控えること、そして外出を最小限にすること——社会的な合意形成を経て、これらが「善」とされるようになった。
子どもたちや若者たちも例外なく、そのルールに従わざるを得なかった。むしろかれらは、大人以上に徹底的に監視され、管理される立場に置かれたといっても過言ではない。世間は「自粛要請」だったかもしれないが、かれらはさながら「自粛強制」とでもいうべき状況におかれていた。学校では授業中はもちろん、給食や昼食時の会話は禁止され、「黙食」などという奇怪な名称でもって、異様なまでに静かな給食時間を徹底された。カフェやファストフード店やカラオケで友達と笑い合い、会話を交わすというごく自然な行為が、あたかも非道徳的で危険な行為であるかのように扱われた。
■「静かに、目立たず、黙っていること」が求められた
修学旅行や文化祭、体育祭といった学校生活のハイライトは次々と中止になった。感染リスクを理由に、青春の思い出が作られるべきイベントが次々と削ぎ落され、代替となるような満足な策が提示されることもほとんどなかった。
さらに放課後や休日の外出も厳しく制限された。地域の内外から発せられた外出自粛要請により、周囲の目やSNSの目も厳しかった。旅行や友達との遠出は「自粛」を求められ、外で遊ぶ子どもたちは「非常識」として大人たちから冷ややかな目を向けられた。「不要不急」な外出も許されず、部屋の中でただじっと息をひそめて過ごすことが「模範的で良識的な若者の姿」とされたのだ。それに異を唱える者は、「お前は間接的な人殺しなのだ」と言わんばかりの非難が向けられることもあった。
写真=iStock.com/AzmanL
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/AzmanL
こうした息苦しい抑圧的な生活は1年、2年と継続された。気づけばかれらの高校時代や大学時代の大半は失われていた。若者らしい青春の発露は「非常識」であり、「人間としての良識」とは静かに、目立たず、黙っていることだというきわめて奇妙な社会観が出来上がった。
■社会に出た途端「コミュニケーション能力が低い」
ここまで徹底的に「若者らしさ」を抑圧し、「外」に出ることを抑制し、「他者とのまじわり」を抑止しつづけた環境を強いられたかれらが、いざ社会に出たときには、かれらにそういう暮らしを求めた大人たちが他人事のように「コミュニケーション能力が低い」「表情が読めない」などと騒ぎ立てるのは、さすがに非道というものではないか。
そもそも「新しい生活様式」を作ったのは誰で、誰がそれを守らせたのか? 「コロナが明けて」しばらく経って、多くの人がもうすっかり忘れてしまったのかもしれないが、その事実を丁寧に掘り起こすことから始めるべきではないだろうか。
■「大人として成熟する」ために必要だったプロセス
プレジデントオンラインに掲載されて大きな話題を呼んでいた「マスク世代」に関する記事では、新入社員が叱られた経験がないことが言及されている。こうした意見は決して少数派ではない。SNS上でも似たような声が頻繁に聞かれ、多くの人がその主張に同意を示している。SNS上ではそうした若者たちの特徴が「未熟さの原因である」とする意見もある。
たしかに、そうした主張は偏見でも単なる愚痴でもなく、一定の現実を捉えているのかもしれない。だが、叱られた経験の乏しさやあるいはそれに起因する未熟さを単純に若者に帰責することは妥当なのだろうか。
わかりやすく言い換えよう。子どもが「子どもの殻」を破って大人になるために必要なものは何だったのか? それはおそらく「外」に出て他者との交流を通じて、多様な経験や価値観に触れることだったはずだ。友人や先生だけではない。アルバイト先の上司や先輩との交流もそうだ。学校や社会で直面する様々な困難、挫折や葛藤を経験し、それらを乗り越えることが「大人として成熟する」ために欠かせないプロセスだったのではないだろうか。
しかし思い返せば、新しい生活様式はこれらの経験を明確に否定していた。
写真=iStock.com/koumaru
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/koumaru
■若者の「成長機会」を奪ったのは大人である
他者と直接交わることはリスクと見なされ、面と向かって議論したり、共に苦労したり、集団で行動したりすることは社会から厳しく制限された。結果として、多くの若者が「大人になるための経験」を積む機会そのものを奪われたのである。「社会」や「外」のほうを向いて家を出て、まだ見ぬ場所、まだ見ぬだれかを求めて冒険することができなかった。
「若者が外の世界に目を向けていなかった」「若者が苦労を避けてきた」という意見も完全に的外れというわけではない。外形的にはそう見えてしまう若者は少なくない。けれど、「外に目を向ける」「他者と伍して協働し、他者貢献や組織人としての自覚を得る」といったことは、新しい生活様式が求めた行動規範とトレードオフの関係にあった。
つまり私たち大人の側は、若者たちが本来得るはずだった経験や成長の機会を奪った代わりに、安全や安定を手に入れてきたということだ。私たちが「大切な人を守るために」というもっともらしいスローガンを掲げて実施してきた「疎(まば)ら」な人間関係の代償として、かれらの大人としての成熟が遅れたりすることは当然予測できたはずだ。言い換えれば、かれらの未熟さもっといえば年齢不相応な幼さとは、私たちがかれらに多大な「犠牲」を強いてきたことの裏返しだ。
■「叱られる」は信頼関係の上に成り立つ
「最近の若者は叱られたことがない」。
これは最近よく耳にする言葉だが、その背景を深く考えると、一つの疑問が浮かぶ。若者たちは本当に「叱られること」を自ら避けてきたのだろうか。それとも、私たち大人が「叱る」という行為そのものを避けてきた結果ではないだろうか。
そもそも、「叱られる」ことは、ある種の信頼関係の上に成り立つ行為である。叱る側が相手を理解し、関心を持ち、相手の成長を願うからこそ、真剣に叱責する。叱られる側もまた、叱ってくれる相手を信頼し、指摘を受け入れようと努力する。だが、ここ数年の新しい生活様式の下では、こうした人間関係を築くこと自体が極めて難しかった。
繰り返し強調するが、若者たちは人と会い、触れ合い、葛藤を経験する場所を徹底的に制限された。授業はオンラインで、サークル活動やバイト先での人間関係は希薄化し、そもそも叱られる機会すらほとんど消失した。叱られる場面が存在しなければ、若者が叱られる経験を持つはずがない。
写真=iStock.com/Thapana Onphalai
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Thapana Onphalai
■大人も「叱る」ことを避けるようになった
しかし、問題は若者側だけではない。大人もまた、「叱る」こと自体を避け始めていた。これは若者への理解や関心が薄れたたというのもあるかもしれないが、なにより「叱る」という行為そのものがリスクに感じられるようになったからだ。パワハラだのセクハラだのというご時世では、色々とリスクになる「叱る」をやるより「見限る」ほうが楽だからと。
コロナ騒動とホワイト化する社会のダブルパンチで、若者たちは叱られる機会を失ったまま大人になり、叱られた経験がないと批判される。これはなかなか気の毒な話だ。
一方で、若者側にも一言だけ伝えたい。叱られた経験が乏しいからこそ、いざ叱られた時に強いショックを受けてしまうことがあるだろう。しかし、このようなハイリスクな社会で、それでもあえて叱ってくれる人というのは、相当に貴重な存在であることも忘れてはならない。ハラスメントや不快感というもっともらしいイマドキの言葉で片付ける前に、その叱責の背後にある相手の本当の気持ちや愛情を感じ取る努力も必要だ。
■若者を「自分たちとは異なる存在」として切り離している
たしかに若い世代を分析し、その傾向や特性を捉えることには一定の価値がある。それは否定しない。だが、そうした営みには暗に「線引き」の含みがある。ようするに、私たちは気づかぬうちに、若者を「他者」として遠ざけ、「自分たちとは異なる存在」として切り離し、その未熟さや至らなさを批評しているということだ。
「表情を読み取れない」「叱られたことがない」「コミュニケーション能力が低い」——そうかもしれない。実際にそういう社員が入ってきて、自分の部署の新入りになったら、ウンザリするかもしれない。これを読んでいる人の中には、まさにそういう「どうしようもないマスク世代」の新人が配属されて、部署のムードがどんよりしているという憂き目の真っ只中にいる人もいるかもしれない。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
■大人に必要なのは「共犯」の自覚
けれども、私は言いたい。かれらには「やさしく」してあげてほしいと。
かれらの未熟さは、まさに私たちが望んだとおりの産物である。
私たちは決して無実ではなく、むしろ積極的な共犯者であることを認識するべきだ。
若者をあれこれと品評することは簡単だが、本当に大切なのは、これからかれらとともに社会を作っていくという意識を持つことだ。大人として、かれらの成長を共に支え、あの4年間に刻み付けられたその古傷を癒し、社会全体で若者たちが安心して成長できる環境を整えることに力を注ぐべきだ。
かれらの失った時間を批評するのではなく、これからの時間を共に作り上げていく責任が私たちにはある。その「共犯」の自覚こそが、いま最も求められているのだ。
----------
御田寺 圭(みたてら・けい)
文筆家・ラジオパーソナリティー
会社員として働くかたわら、「テラケイ」「白饅頭」名義でインターネットを中心に、家族・労働・人間関係などをはじめとする広範な社会問題についての言論活動を行う。「SYNODOS(シノドス)」などに寄稿。「note」での連載をまとめた初の著作『矛盾社会序説』(イースト・プレス)を2018年11月に刊行。近著に『ただしさに殺されないために』(大和書房)。「白饅頭note」はこちら。
----------
(文筆家・ラジオパーソナリティー 御田寺 圭)