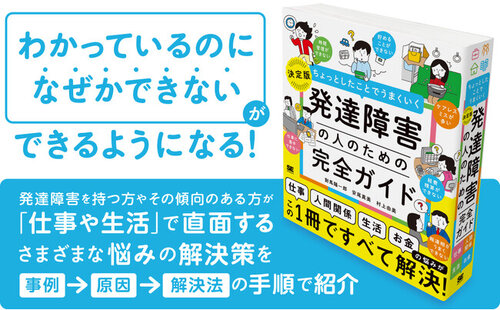人間関係がこじれてプロジェクトが悲惨な状況に…ビジネス競争力世界一のデンマーク人の見事な解決プロセス
2025年4月24日(木)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/78image
※本稿は、針貝有佳『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』(PHPビジネス新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/78image
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/78image
■「仕事だからお互いを好きになる必要はない」
ところで、デンマーク人はいつでもどこでも建設的な議論をしてうまくいくのだろうか、という疑問が湧いてくるかもしれない。もちろん、デンマーク人でも、うまくいかないことはある。
デンマーク人もやはり人間である。人それぞれに好き嫌いもあれば、相性もある。
そこで、相性が合わない人との仕事の仕方や、どうしても人間関係がうまくいかない場合の対処法について聞いてみた。これがなかなか興味深い。
労働組合運営管理局(Fagenes Bofallesskab)のトップを務めるケネットは、職場で起こり得る問題のなかで一番厄介な問題は、メンバー同士の相性が合わないケースであると言う。
ケネットは、その場合は「ここは仕事をする場だから、お互いを好きになる必要はない」と伝え、割り切って仕事してもらうようにする。
だが、時には、間に入って揉(も)め事を止めなければならないこともある。
ポイント職場では、お互いを好きになる必要はない
■相性が悪い2人の仕事は「分離」する
建築家として第一線で20年以上働いてきたエヴァは、うまくいっていないプロジェクトを立て直す役を引き受けることも多い。
そして、悲惨な状況に陥(おちい)っているプロジェクトの裏には、必ずと言っていいほど「人間関係の問題」がある、と指摘する。
「仕事で成果を出したかったら、何か問題があったときに、ちゃんと話さなくちゃいけない。でも、いい人間関係がないと、話すことすらできない。だから、仕事の成果は、人間関係で決まると言ってもいい」
人間関係がうまくいっていない場合、すぐ近くの席で仕事をしていても、会話を交わすことなく、メールだけでコミュニケーションをとっていることが多々ある。エヴァによれば、こういった関係からは、どうやっても良い仕事の成果は生まれない。
逆に、良い関係があれば、一日中一緒にいても苦にならないし、何かあったときに質問も相談もしやすい。そして、それは仕事の成果としてはっきりと表れる。
人間関係の修復には、膨大なエネルギーが必要だ。しかも、頑張ったところで、関係が修復できるとは限らない。
その場合、エヴァは、関係修復の努力をするよりも、相性の悪い2人の仕事を分離して、2人が共同作業をしなくても済むように対処する。
ポイント相性が悪い2人は、共同作業をしなくて良いように「分離」する
■欠点ではなく「方向性の相違」と考える
約15年間にわたって映画プロデューサーを務めてきたモニカは、アカデミー賞にノミネートされるなど華々しいキャリアの持ち主である。プロデューサーとして、これまで様々な人と協力して映画制作をしてきた。
1作品の制作には少なくとも100人から150人程度が関わり、その制作プロセスでは色んな壁にぶつかる。何か問題が起こったときには、どのように対処するのだろうか。
モニカが意識していることは、まずは対話をして、何が問題になっているのかを正確に把握することである。そして、どんなときも、いい作品を作るためのベスト解を模索する。
「『この作品にとっての最適解は何か』ということを、常に第一優先に考えるようにしてる」
つまり、何か問題が起こっても、誰かの責任追及にフォーカスするのではなく、状況を把握したうえで、建設的に解決策を導くのである。
モニカによれば、一般的に、デンマーク人は感情を脇(わき)に置いて、合理的に物事を解決していく傾向がある。どんな状況でも、冷静に「問題解決」にフォーカスする。
また、人はみんな違うので、それぞれの方向性やスタイルに相違があるのは当然であると考える。モニカは、このように説明する。
「何か問題があっても、誰かが間違ってる、というふうには考えないようにしてる。誰かが仕事ができないわけでも、間違ってるわけでもない。私たちはみんな違う方向性やスタイルを持ってるのだから」
何か問題があっても、誰かに欠点があるのではない。ただ、方向性やスタイルの相違があるだけなのだ。
ポイント感情を脇に置いて、「成果」にフォーカスする
■対立は悪いことではない
クリエイティブ業界で長年キャリアを積んできたマリエ・ルイーセは、対立は必ずしも悪いことではない、と指摘する。
「最高の成果というのは、意見の不一致を恐れずにぶつかり合って、そこから一緒に解決策を導き出せたときに生まれるもの。だから、『批判』にもオープンに耳を傾けるのは、とても大切なこと。『批判』をしっかり受けとめると、そこからいいアイデアを思いついて、最高の瞬間が訪れるの」
彼女によれば、最悪なケースは、批判に耳を傾けずに、そのまま商品化してしまうことである。そうなると、結局、売れない商品や欠陥品が市場に出回ることになって、誰も喜ぶ結果にならない。だから、批判に耳を傾けることは大切なのだ。
「ネガティブなフィードバックを受けると、一時的に嫌な気持ちになるかもしれない。でも、それで終わりにするのではなくて、そこから再出発しようと思うことが大事なんだと思う」
■「耳の痛いこと」を伝える効果的なフィードバック
ただし、ネガティブなフィードバックも、内容や伝え方が大切である。
個人的な批判や相手を否定してはいけない。
彼女は、「サンドイッチモデル」という建設的なフィードバックの方法を教えてくれた。これは、実際にデンマークの口頭試験の試験官の間でもよく使われているフィードバック方法だ。
「サンドイッチモデル」〜フィードバックの方法
1 取り組んでくれたことに感謝の気持ちを伝える。
2 気になった問題を指摘する。
3 きっとうまくいくから健闘を祈っている、と伝える。
これならば、フィードバックを受けた側も嫌な気持ちにならない。
また、問題を指摘するときは、相手の立場になって話すことが重要である。相手の気持ちになって、相手が何を考えてそのようにしたのかを推測する。
決して、「なんで○○しなかったんですか?」とか、「○○すべきだったと思います」と相手を責めてはいけない。
そうではなく、「なるほど、○○をしたいんですね。そういうことでしたら、こんな方法もありますよ」と、相手を否定せずに、別の方法を提案するのだ。
問題点を伝えるときは、相手を否定するのではなく、本人が気づいていない「別の視点」を提供してあげること。また、伝えるときは、最初に感謝の気持ち、最後に応援の気持ちを添える。
いかがだろう。これだったら、あなたにもできそうな気がしないだろうか。
仕事だけでなく、色んなシーンに使えそうだ。家族、親戚、恋人、仲間、友達、知り合いに問題点を伝えたいとき、「サンドイッチモデル」を活用してみるのはいかがだろうか。
相手を否定せずに別の視点に気づかせてあげる。それを、感謝と応援のメッセージで挟むのだ。
ポイント「別の視点」に気づかせてあげる
ポイント問題点の指摘は、感謝と応援のメッセージで挟む
■冒頭で「決め方」を説明しておく
メンバー間の意見の不一致を解消できないまま、一緒に仕事をしていかなければならない場合はどうすればいいのか。
製薬会社ノボノルディスク本社で職場カルチャーづくりを担当しているオーレに、どうしても意見がまとまらない場合はどうするのかと尋ねてみると、真剣に答えてくれた。
ポイントは「決め方」を、最初に明確に説明することである。
たとえば、会議を開くとき、トピックに合わせて最適な「決め方」を考えておく。
この会議は、最終的に全員が合意する必要があるのか、全員が合意できなくても多数決で決めるのか、意見を出してもらって最終的に誰かが決めるのか……。冒頭で「決め方」を説明し、ルールを共有するのだ。
写真=iStock.com/Morsa Images
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Morsa Images
■会議後の文句や悪口を防ぐ
「この件は、全員が合意する必要があるので、意見が一致しない場合は、みんなの意見を擦り合わせて合意に持っていく必要があります」
「この件は、意見が一致するものではないと思いますので、最終的には多数決で決めます」
「この件は全員の意見を聞いたうえで、最終的には私が決めます」
このような形で「決め方」を冒頭で説明することで、参加者全員の希望どおりの結論に至らなかった場合にも、文句が出るのを避けられる。
■反対者へのフォローも忘れない
また、満場一致ではなかった場合、必要性を感じたら、反対意見の人へのフォローも忘れない。納得しておらず、不満を抱えていそうな人には、会議の後で個人的に話をしに行くのだ。
「反対しているのはわかってる。ただ、A・B・Cという他の要素もあるから、こういったことも考慮して、今回は私の責任でこう決定する。ぜひ、この決定をバックアップしてもらいたい」
個人的に話をしに行って、こういったフォローをする。そうすることで、後になって「自分はこう思うのに、違う決定をされた」と、他の同僚に悪口を言いふらされるのを防ぐのだ。
オーレはとても誠実で柔らかな人柄である。だが、真剣にフォローアップの話をしてくれる彼の姿には、大企業で管理職を歴任してきたリーダシップを感じた。重要な場面では、メンバーと踏み込んだ対話をしっかりするのである。
オーレによれば、悪口の蔓延(まんえん)を防ぐのは重要である。悪口が広がると、組織はバラバラになってしまうからだ。
ポイント会議の冒頭で「決め方」を伝える。ただし、反対者へのフォローアップも忘れない
■対話し、違いを認めながら解決策を探る
デンマーク人は問題を包み隠さず、対話を通じて問題を明らかにしていく。
針貝有佳『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』(PHPビジネス新書)
そして、目的を達成するうえでベストな選択は何なのか、お互いに歩み寄って合意に至れる問題なのか、妥協して一緒にやっていけるのか、それとも、一緒にやっていくうえでは致命的な問題を抱えているのか、といったことを対話しながら探っていく。
「臭い物に蓋」をせず、対話を通じてグリグリッと問題をこじ開けて、問題の核心に迫るのである。そして、特定の誰かが悪いと決めつけるのではなく、考え方やスタイルの違いを認めたうえで、その件に関するベストな解決策を模索する。
余談になるが、デンマーク人が、子どものために、離婚した元パートナーとも関係を断たずに付き合い続けられるのも、そのせいかもしれない。
デンマークでは、離婚しても元パートナーと交代で子どもの世話をし続けるのが一般的だ。子どもの誕生日や記念日には、元パートナー同士が、お互いの新たなパートナーも一緒に連れてきて、みんなでお祝いすることもある。
同じ場に「複雑な関係」の人たちが集まって、穏やかに時間を共有するのである。
そんなデンマーク人のプライベートライフについて見聞きするたびに、いったいどうなっているのだろう? と不思議に思っていたのだが、それが可能なのは意見の不一致を受け入れるコミュニケーション方法のおかげなのかもしれない。
「デンマーク流のコミュニケーション術」は、仕事でもプライベートでも、まさに最強である。
ポイント「臭い物に蓋」をせず、対立意見の存在を認める
----------
針貝 有佳(はりかい・ゆか)
デンマーク文化研究家
東京・高円寺生まれ。早稲田大学大学院・社会科学研究科でデンマークの労働市場政策「フレキシキュリティ・モデル」について研究し、修士号取得。同大学・第二文学部卒。2009年12月に北欧のデンマークへ移住して、デンマーク情報の発信をスタート。首都コペンハーゲンに5年暮らした後、現在はコペンハーゲン郊外のロスキレ在住。著書に『デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか』『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』。
----------
(デンマーク文化研究家 針貝 有佳)