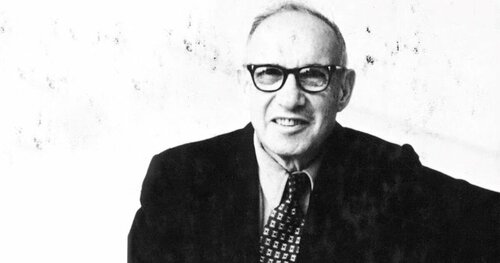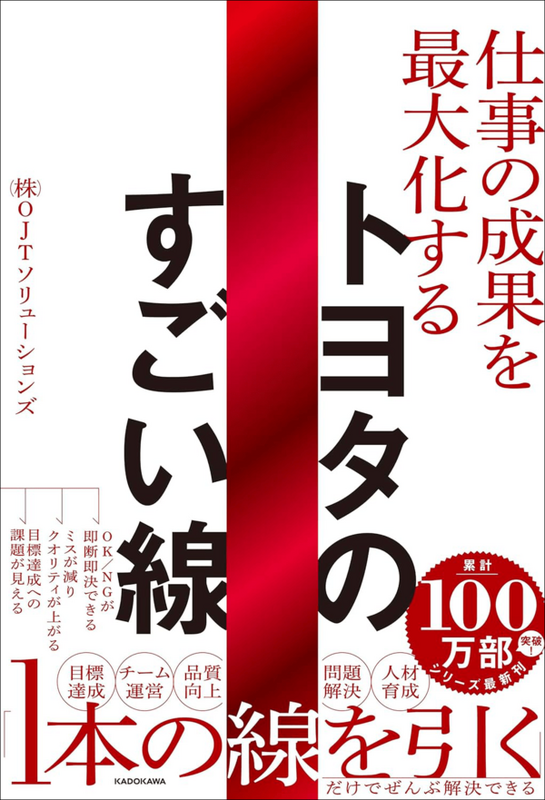トヨタ式「線を引く」問題解決法、線引きの基準を厳しくするほど問題が浮き彫りになる「納得の理由」
2025年4月22日(火)6時0分 JBpress
国内製造業のみならず、海外でも多くの企業が取り組んでいる「トヨタ生産方式(TPS)」。その実践に当たって「まずは1本の線を引くことが重要」と語るのが、さまざまな企業の現場へTPSの導入・指導を行ってきたOJTソリューションズのトレーナー、岡田憲三氏だ。2024年12月に同社より出版された著書『仕事の成果を最大化する トヨタのすごい線』の中身をひもときつつ、トヨタの強さを支える「線を引く」アプローチについて話を聞いた。
あらゆる場面で見られる「1本の線」の役割
——著書『仕事の成果を最大化する トヨタのすごい線』では、仕事の成果を最大化するために「線を引く」ことを提唱しています。これはトヨタの現場に見られる特徴とのことですが、具体的にどのような場面でどんな線が引かれているのでしょうか。
岡田憲三氏(以下敬称略) トヨタの現場では、仕事を安全に、求める品質に沿って効率よく行うために必要なことすべてに「基準・標準となる線」が引かれています。
線とは、現場にある物の置き場や動線を決める際に用いる「目に見える線」のみならず、仕事の基準・標準となるルールや目標といった「目に見えない線」も含みます。1本の線があることで「正常か、異常か」が決まるため、問題が生じたことをただちに職場のメンバーが認識でき、手遅れにならずに対処できるのです。
さらに、一度引かれた線は引かれたままになるわけではありません。変化に合わせて引き直されることがトヨタの現場の大きな特徴です。
私はかつて、トヨタで試作車を作ってテストを行う部署に在籍していました。当初、試作車を1日あたり7台作っていましたが、世界シェア拡大のために1日あたり10台作る必要が出てきました。そうした時にも、さまざまな基準となる線が引き直されます。
例えば「試作車が10台必要ならば、エンジンは12台分用意する必要がある。そのためにはこれだけの工程や作業が必要で、それをいつまでに行わなければならない」といった具合です。この線引きは上長が行うのではなく、現場にいるそれぞれの立場の人が目標や納期を考え、客観的に判断できる基準線を引くことが特徴です。
製造現場だけではない、会議室でも見られる「驚きの光景」
——著書では、製造現場で使う台車のみならず、会議室の椅子や机にも区画線が引かれ、置き場が明確に決められている、とあります。これはトヨタでは日常的な光景なのでしょうか。
岡田 トヨタの用語に「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った「5S」があります。特に重視しているのが整理・整頓で、物を置く場所も各人が勝手に判断するのではなく、ベストだと思われる場所に線を引き、物を使ったら線の場所に戻すということを徹底しています。
——こうした考え方は、製造業以外の業界でも応用できるのでしょうか。
岡田 もちろんです。例えば、人事部や総務部は社内のサービス業だと言えますよね。人事部や総務部に何かを依頼するとき、いつでも受け付けてくれる方が依頼する側としては非常に助かります。しかし、依頼される側の人事部・総務部の人は自分の仕事を止めて、時には五月雨でやってくる依頼に対応していることを見逃してはいけません。
つまり、いつでも仕事を受け付けることは結果として、組織全体の業務効率を落としていることになります。そこで「他部署からの依頼を受け付ける時間は何時から何時まで」と線を引くと、全体効率を高めつつ、お互いに気持ちよく仕事ができるようになります。
この他にも、例えば「社外の方が機密エリアに入る際には腕章を着用してもらう」といったルールがあるとします。社外の方を案内する担当者は、事前に管理部門から腕章を受け取る必要がありますが、これを担当者が各自都合の良いタイミングで取りに行ってしまうと、管理部門の方はそのたびに自分の業務を中断して対応しなければなりません。これが1日に数件であればよいかもしれませんが、数十件になるようであれば大きな負担となります。
突発的に発生する来客対応を除き、担当者は来訪予定を管理部門に事前申請する仕組みを整えておくことが望ましいでしょう。管理部門としても、来客の申請は何日前までにと線を引いて、当日に必要な分の腕章を事前に準備するルールを設ければ、双方にとってイレギュラーな対応が減り、業務をより効率的に進めることができるはずです。
——企業によっては明確なルールを設けず臨機応変に対応することがよい、とされるケースもありそうです。
岡田 時として臨機応変さは必要になります。確かに、お客さまからの要望は千差万別ですから、一つ一つ丁寧に対応すればするほど満足度も上がります。ただし、企業として製品・サービスを売る以上、そこには企業としての品質の基準があるはずです。お客さまのすべての要望に対応していては、企業活動は破綻してしまいます。企業として利益を出し続ける以上、その企業としての基準があるべきであり、その基準に沿って仕事をしようとすれば自ずと線を引くことはできるはずです。
また、ルールを一度決めたならば曖昧にせず、しっかりと守りきる姿勢も必要です。しかし、急に「明日からこのルールで運用します」とトップダウンで決めてしまうと、社内での人間関係が悪くなり業務に悪影響を及ぼしかねません。お互いの仕事が計画的になり、気持ちよく仕事ができるようになるには、現場の意見を採り入れ、徐々にルールを浸透させていくことが必要です。
基準を厳しくするほど問題が見える「線を引く」問題解決法
——著書では、組織の問題解決を図る上で「線を正しく引くことが必要」と述べていますが、線を引くことは、どのようにして組織の問題解決に役立つのでしょうか。
岡田 トヨタでは「問題を見つけることができれば、解決したも同然」という考えがあります。しかし、線を引かなければ基準を可視化できないため、問題に気付くこともできず、解決策を講じることもできません。つまり、まず線を引くことで「問題に気付ける職場環境」を構築することが問題解決への第一歩になります。
この考え方は、湖面の水に例えると分かりやすいのではないでしょうか。湖面に十分な水があれば、湖の底に隠れている岩は見えません。しかし、湖の水を減らして水面を下げると、それらの岩が見えてきます。問題に気付ける職場環境をつくることも、これと同じ考え方です。
湖面を少し下げること、すなわち線を引いて基準を厳しくすることで、途端にさまざまな問題点が見えるようになります。
——こうした考え方は、製造現場以外でも応用できるのでしょうか。
岡田 もちろん可能です。例えば、オフィスワークでの応用例を考えてみましょう。
情報を編集加工し、書類を作成する部署があったとします。こうした現場の従業員の方に「書類を1セット作るために、どのくらいの時間がかかりますか」と聞くと、大抵は「作る書類の種類や内容によって時間が変わるため、分かりません」と返答があります。これは「線が引かれていない」状態です。
そこで、現場の改善を支援する立場の私たちトレーナーがさまざまな分析を行い、まずは「1セット20分で作りましょう」と線を引きます。そのルールで運用をすると、ぎりぎり20分で作り終わる書類もあれば、早く作り終わってしまうものもあります。そして20分で終わらない書類も出てきます。
ここで大切なのは「なぜ、20分で作り終えることのできない書類があったのか」という部分です。問題とは「あるべき姿」と「現状」との差(ギャップ)ですから、作り終えることのできなかった理由を追究し、その原因を取り除くことが問題解決につながります。ただし、「20分」という線を引かなければ、この問題そのものが見えてこなかったのではないでしょうか。線をひくということは、問題に気づける環境をつくるということなのです。
——まず一度線を引いた上で、徐々に問題点をあぶり出すことが大切なのですね。
岡田 そうですね。そして、状況の変化に合わせてあるべき姿も変化していきます。そして、あるべき姿が変化すれば、現状とのギャップも生まれます。その度に線を引き直していくことが重要です。
筆者:三上 佳大