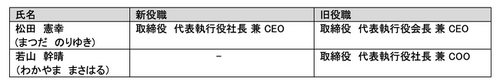だから若手がどんどん辞める…「手書きのバースデーカードを送り社員旅行を開催する」社長に欠けている視点
2025年4月25日(金)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
■社員が生き生きと働く「会社の特徴」
社員が主体的に生き生きと働いている会社には、ある共通点があります。それは、社員が会社の成長を「自分ごと」としてとらえていることです。
会社がどれだけ発展・成長しても、「自分には関係ない」「会社が大きくなるほど自分の負担が増えるだけ」と感じている社員が多い職場では、なかなか社員の主体性が育ちません。逆に、会社の発展・成長を喜び、その成果が自分にも還元されると感じられる環境では、社員は主体的に生き生きと働いています。
その「還元」は、必ずしも給料増やボーナスアップといった金銭的なものに限りません。
「何のためにこの仕事をしているのか」「その成果が社員自身や会社、お客様にどんな価値をもたらすのか」——社員が意義を感じられる仕事を提供できているかどうかが、職場の活気を左右するのです。
■成功率はたったの2割
社員の会社への愛着は「社員エンゲージメント」ともいいます。これは、社員が会社や仕事にどれだけ愛着や意欲を持ち、主体的に貢献しようとしているかを表す概念です。そして、社員エンゲージメントが高い状態とは、単に「会社が好き」という感情だけでなく、社員が自発的に会社の目標達成に向けて努力し、仕事に意義を感じている状態を指します。
「社員エンゲージメント」の重要性が語られるようになって久しく、社員が主体的に生き生きと働いてもらうために、多くの経営者がさまざまな施策を実施しています。しかし、それがうまく機能している会社もあれば、思うような成果が出ていない会社があるのが現実です。
私の感覚では、成功しているのは全体の2割。どちらともいえないのが6割、全くうまくいっていないのが2割といったところでしょう。さらに、施策が成功している会社でも、経営者が計画的に取り組んだ結果と、試行錯誤の末に偶然良い形に落ち着いた場合があります。
以下にて、経営者が社員エンゲージメントを高めるために、さまざまな施策を講じても、思うような成果が得られなかった具体的な例を3つご紹介します。
■【ケース①】「風通しの良い会社」を目指したはずが…
A社長は「社内コミュニケーションが活発で、風通しのいい会社」が働きやすい会社だと考え、社員旅行やイベントを積極的に企画していました。しかし、参加を促しても盛り上がるのは一部の社員だけ。結局イベントは定着しませんでした。
写真=iStock.com/coldsnowstorm
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/coldsnowstorm
こうした社内イベントを実施する経営者は少なくありません。風通しの良い職場を作ろうと、飲み会やバーベキューなどを企画するケースはよく見られます。
しかし、社員の立場からすると、「上司といると気を使うので疲れる」「仕事仲間との旅行はプライベートの時間を削られるだけ」「仕事が終わってまで飲み会に参加するのは時間の無駄」と感じることもあり、むしろ負担に思われてしまうこともあるのです。私たち世代からしたら、「何甘えたことを言ってんだ!」と思ってしまうこともありますが、それが現実のようです。
もちろん、社内コミュニケーションを楽しむ社員も数多くいますが、「嫌だ」と思う人が目立つと、結果的に全体の雰囲気が悪くなっていきます。このように、良かれと思って行った施策が、むしろコミュニケーションを減らしてしまうこともあるのです。
こうした状況が続くと、最初は熱心に取り組んでいた社長も、次第に心が折れてしまいます。そして、「せっかく頑張って企画しても報われない」と感じ、最終的には何もやらなくなってしまう——そんなケースは決して珍しくありません。
■【ケース②】「一人前の社会人に育てねば」が裏目に…
B社長は「新卒社員を採用したら、一人前の社会人に育てることが会社の責任であり、社員への愛情だ」と考えました。そこで、自ら新卒社員の教育に力を入れ、出張の際にはカバン持ちをさせ、移動中も社会人の心得や仕事の厳しさを説くようにしました。
しかし、その結果はB社長の想定とは真逆のものに。会社に愛着が生まれるどころか離職者が増え、せっかく採用した新卒社員が1年以内に半分も残りませんでした。
このケースは「人好きな社長」によく見られるパターンです。新卒を採用すると、親心のような気持ちが芽生えて、手取り足取り指導し、仕事の厳しさやプロ意識を強く求めるようになります。
ここで問題になるのが、社長と新卒社員の間にある「圧倒的な距離感」です。社長と新卒社員では立場も経験も違うため、社長の言葉が社員には響きづらく、「プレッシャー」や「圧」だけが強まっていってしまいます。その結果、社員はストレスを感じて辞めていってしまうのです。
これは社長に限らず、部長や課長などの管理職にも見られる現象です。「若手を育てよう」と意気込んだ結果、逆に人が辞めていくというケースは珍しくありません。
新卒社員にとって、何が正解で何が不正解かも分からない状態で、レベルの高すぎる教育や過度な期待を押し付けられると、プレッシャーに耐えきれなくなってしまうのです。
■【ケース③】「圧」と受け取られたプレゼント
C社長は「働いてくれる社員に愛情を示すことが、信頼関係の構築につながる」と考えました。そこで社長自ら、社員全員の誕生日に手書きのバースデーカードと花束を贈るという取り組みを開始し、さらに社員の家族にも喜んでもらおうと、お歳暮のプレゼントも実施しました。
しかし、5年間続けても社員エンゲージメントは一向に向上せず、それどころか社内からは、「社長からの圧が強い」「お返しを考えるプレッシャーが……」という声が密かにあがっていたのです。そんなある日、「社内いじめ」や「レジからの盗難」が発覚。社長は失望し、プレゼントの習慣をやめてしまいました。
「愛情を態度で示し、社員とのつながりを大切にすることが重要だ」と考える社長は意外に多いです。特に、「率先して自分がトイレ掃除をするべき」といった考えを持つような現場主義の社長には、この傾向は見られます。
社員への感謝を形にして伝える姿勢を示し、背中を見せることが、会社の結束を強めると信じているのです。
しかし結果的には、社長の想いが伝わらず、「せっかくここまでやったのに、結局こんな仕打ちか」と落胆し、やめてしまうケースが珍しくありません。
■「社員のため」の施策が空回りする理由
ここまで挙げた数々の施策を、経営者はすべて「社員のため」と思って行っています。しかし、その「距離感」を誤ると、結果的に社員の心が離れ、会社を去ってしまうこともあるのです。
経営者たちはもちろん真剣に取り組んでいます。ただ、内情をよく見てみると、経営ノウハウの“コレクション”のようになっていることも少なくありません。今回紹介した3人の社長も、「他社でうまくいった」と聞いた施策を取り入れただけで、自社の社員に合っているかどうかまで、深く考え抜いていなかったのかもしれません。
ご紹介した施策そのものが、悪いわけではありません。問題なのは、どの施策も「社長」や「会社」がメインになっていたことです。主語が「自分」なのです。
・「社長が」良いと思ったからバースデーカードを贈る
・「会社に」愛着を持ってもらうために社員旅行を企画する
どれも「社員のため」と言いながら、実は「社長がやりたいことをやっているだけ」「会社のため」になってしまっていたのです。
■「イベントを開く」よりも大切なこと
逆に、主語を「社員」に変えていけば、同じ施策でも違ったやり方ができるのではないでしょうか。例えば社内イベントを開く場合でも、経営者が決めて実施するのではなく、社員自身が考え、決めるプロセスを作るだけで、まったく違った結果になるはずです。
さらに言えば、「イベントをしなくても本音を言い合える組織になるにはどうすればいいか?」という視点を持てたなら、「職場をもっと良くするためにどうすればいいか?」を社員が勤務時間中に話し合う場を設けることだってできます。
大切なのは、「イベントを開くこと」ではなく、「社員エンゲージメントを高める」ことです。そのためには、仕事のやり方をどう工夫するか、人間関係をどう築くかを、社員自身が考えられる環境を作るほうが、社員にとっては嬉しいのではないでしょうか。
■社員にモテる会社になるために
結局のところ、主語を「自分」にするということは、働きかける相手に変化を求めているのと同じことです。つまり、経営者は社員に変わることを求めているが、自分や会社のあり方を変えようとはしていないのです。
もちろん、社員に変化を求めること自体は悪いことではありません。しかし、本当に大切なのは「会社がどう変われば、社員にとってより良い職場になるのか」を考えること。経営者の視点ではなく、社員の視点から考え、変化のベクトルをそちらに向ける必要があります。
これは、恋愛関係にも似ています。「俺に合わせてお前が変われ!」と言い続ける男性は、今の時代ではなかなかモテませんよね。それと同じように、「社員が会社に合わせるべき」という考え方では、社員の心をつかむことはできません。そうではなく、「社員にとって魅力的な会社とはどんな状態か?」を想像することが重要です。
そのためには、給料、労働環境、仕事のやりがい、仕事の難易度、会社のブランド(知名度)といった要素を客観的な指標で評価し、自社がどれくらい「社員にとって魅力的な会社」なのかを分析することが必要です。そして、それをもとに改善を続けることで、「モテる会社」になっていくのです。
■「客観的な指標」を取り入れる
私がおすすめするのは、毎年「社員満足度調査」を実施すること。実際に私の会社でも実施していますが、「社員が何を求めているのか」を数値で確認できます。その客観的なデータをもとに、社員と話し合いながら、どうすればより満足度が高まるかを考え、改善を繰り返していくのです。
この方法のポイントは、調査は外部の業者に依頼すること。内部で行うと「誰が何を答えたか」が分かってしまい、社員が本音を言いにくくなるからです。外部業者を利用すれば、他社との比較もでき、自社がどのレベルにあるのかも把握できます。また、改革は会社側の押し付けではなく、社員の意見をもとに改善していくのが重要です。そうすることで、自然と社員の満足度は向上していきます。
施策を打ち、うまくいけば社員の満足度が上がり、失敗すれば下がる。極めてシンプルなことです。だからこそ、感情論ではなく、客観的な指標をもとに改善し続けることが大切だと私は考えています。
結局のところ、社員エンゲージメントを高めるには、一度の施策で解決しようとせず、社員の声を反映しながら継続的に改善していくしかありません。客観的なデータをもとにトライアンドエラーを繰り返すことで、初めて「社員にとって魅力的な会社」となり、自然と社員のエンゲージメントは高まっていくのです。
----------
安東 邦彦(あんどう・くにひこ)
ブレインマークス 代表取締役
1970年大阪府生まれ。ITベンチャーの取締役を経て、2001年に中小企業向けのマーケティング支援を行うブレインマークスを設立。社員30人以下の中小・ベンチャー企業に『社長が不在でも事業を拡大する仕組みづくり』を支援し続け、現在までに個別での支援した企業は約200社、主催する経営塾の卒業生は1000社を超える。中小・ベンチャー企業の事業拡大に特化した実践的な講演で、経営者団体、金融機関、保険会社などからの講演依頼は年間50回を超える。
----------
(ブレインマークス 代表取締役 安東 邦彦)