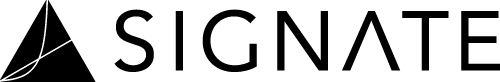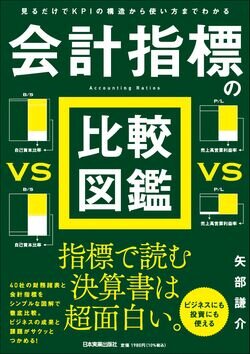実質無借金経営を貫く神戸物産 「店舗資産ほぼなし」「製販一体」で高収益を実現する独自のビジネスモデルとは?
2025年4月21日(月)4時0分 JBpress
ビジネスや投資に欠かせない「会計指標」。うまく使いこなすことができれば、決算書からビジネスの成果や課題が見えてくる。本稿では『見るだけでKPIの構造から使い方までわかる 会計指標の比較図鑑』(矢部謙介著/日本実業出版社)から内容の一部を抜粋・再編集。実在する会社の決算書を比較しながら、会計指標とビジネスの結びつきをさまざまな視点で分析する。
「業務スーパー」を展開する神戸物産は、2024年10月期に連結売上高・営業利益ともに過去最高を記録した。店舗資産をほとんど持たない同社は、なぜ高い収益性を実現できているのか? 独自のビジネスモデルを、決算書や売上構成比から分析する。
B/SとP/Lを組み合わせて分析する
「まったく違う」業務スーパーとヤオコーの儲け方
■ なぜ神戸物産の原価率は高く販管費率が低いのか?
次に、神戸物産の決算書についても見ていきましょう。次ページの図は、神戸物産における2023年10月期の決算書を図解したものです。
B/Sの左側で最大の金額を占めているのは流動資産(1420億円)です。この流動資産には、現預金が930億円、売掛金が270億円、棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)が190億円含まれています。
次いで大きいのは有形固定資産(640億円)です。神戸物産の有形固定資産の内訳を見てみると、店舗の有形固定資産が多く計上されていたヤオコーとは異なり、業務スーパーの店舗の建物や土地は4店舗しか計上されていません。
その他は本社や物流センター、食品製造工場やメガソーラー発電設備となっています。店舗が少ない理由については後ほど詳しく解説しましょう。
続いて、B/Sの右側を見てみると、流動負債が490億円、固定負債が480億円計上されており、有利子負債(借入金、リース債務)が流動負債に10億円、固定負債に370億円含まれています。現預金を930億円保有していることを踏まえると、神戸物産は実質無借金経営であるといえそうです。純資産は1140億円で、自己資本比率は54%となっています。
P/Lについても見ていきましょう。売上高が4620億円であるのに対し、売上原価は4090億円(原価率は89%)、販管費は220億円(販管費率は5%)となっています。その結果、営業利益は310億円計上されており、売上高営業利益率は7%という高水準です。
ヤオコーの原価率72%、販管費率23%と比べると、神戸物産の原価率は17ポイント高く、販管費率は18ポイント低くなっており、コスト構造がヤオコーと大きく異なることがわかります。また、先述のとおり神戸物産では業務スーパーの店舗に関わる有形固定資産がほとんど計上されていません。この理由は一体何でしょうか。
その理由を探るため、神戸物産のビジネスモデルについて詳しく説明しましょう。
■ 店舗資産をほぼ持たない神戸物産の収益性が高い理由とは?
神戸物産のビジネスモデルを解説するにあたり、まずはヤオコーと神戸物産のセグメント・部門別の売上高構成比を見てみます。
ヤオコーの売上高構成比(上図の左)を見てみると、最も大きな割合を占めているのが生鮮食品(33%)で、加工食品(27%)、日配食品(冷蔵食品など、23%)と続いています。基本的に直営でスーパーマーケット事業を運営しているヤオコーの売上高構成比は、商品カテゴリーごとに分類されています。
一方、神戸物産の売上高構成比(上図の右)は事業セグメント別の分類となっています。その中でも最大の割合96%を占めているのが、業務スーパーFC(フランチャイズ)事業です。その一方で、業務スーパーの直営小売事業は1%に過ぎません。
業務スーパーの全国における店舗数は2023年10月末現在で1048店舗となっていますが、そのうち直営店はわずか4店舗しかなく、それ以外はすべてFCオーナーによる運営となっています。そのため、神戸物産の有形固定資産には店舗の資産がほとんど計上されていないのです。
その一方で、神戸物産の有形固定資産には多くの食品工場などの資産が計上されています。神戸物産では「食の製販一体体制」をめざし、積極的な M&Aにより多くの食品メーカーを傘下に収めてきており、こうした子会社の有形固定資産が含まれているためです。
その結果、神戸物産では、プライベートブランド(PB)商品の売上高に占める割合が国内製造と輸入を合わせて35%弱に達しています。ヤオコーもPBの開発に力を入れていますが、それでもその売上高に占める割合は10%に過ぎません。
こうしたことを考え合わせると、FC本部としての神戸物産のビジネスモデルの本質は、PBをはじめとした商品の企画製造販売ということになります。いわゆるナショナルブランド(NB)については仕入れ、FC店への卸売も行なっていることから、神戸物産は「食品メーカー」と「食品卸」の特徴を併せ持つ事業形態だといえます。
一般的に、小売業に比べて卸売業の原価率は高いためことから、直営で小売事業を運営しているヤオコーに比べて神戸物産の原価率は高くなっています。
ただし、神戸物産のビジネスモデルには商品の企画製造といった付加価値もあり、一般的な食品卸の原価率である93〜94%に比べると神戸物産の原価率は89%と低くなっています。
加えて、店舗でかかる人件費、家賃、水道光熱費といったコストはFC店側の負担となることから、神戸物産のP/Lには計上されません。そのため、神戸物産の販管費率は5%と、食品卸と同等の水準に抑えられています。結果として、神戸物産では売上高営業利益率7%という高い収益性を実現できているのです。
なお、神戸物産は業務スーパー事業以外に、外食・中食事業やエコ再生エネルギー事業にも進出しています。
いずれもまだ事業規模としては小さいものの、特に外食・中食事業は業務スーパー事業で構築したローコストなサプライチェーンを生かしたビジネスであり、その事業拡大は同社の「中期経営計画2024-2026」においても重点施策の1つに位置づけられています。業務スーパー事業の今後の成長に加えて、外食・中食事業についても注目していきたいところです。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
筆者:矢部 謙介