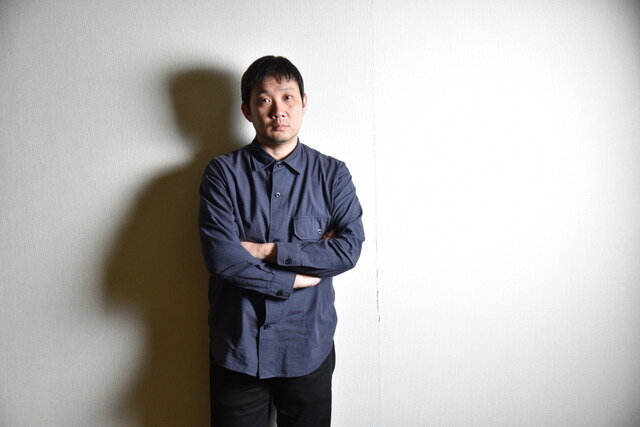【映画と仕事 vol.26】人々の心をざわつかせる濱口映画はどうやってできる? 濱口竜介監督が語る、キャラクターの膨らませ方、ラストシーンの描き方
2024年4月26日(金)15時0分 シネマカフェ
ヴェネチア、カンヌ、ベルリンの世界三大国際映画祭とアカデミー賞の全てで受賞歴を持ち、いまや新作が発表されるたびに常に世界的な注目を集める存在となった濱口監督だが、彼はどのようにして“映画監督”になったのか? そして、彼はどのように新作を企画し映画として形にするのか?
まもなく公開となる『悪は存在しない』は、『ドライブ・マイ・カー』でもタッグを組んだ音楽家の石橋英子のライブパフォーマンスの映像作品として企画がスタートし、制作の過程で当初の作品とは別に1本の長編映画として誕生したという、まさに異色の作品だ。世界を魅了し、驚かせ続ける“濱口映画”の作り方について、じっくりと話を聞いた。
映画監督への道
「漠然としていました」
——濱口監督は、大学で映画サークルに入る以前は、映画をむさぼり観るようなタイプではなかったとうかがいました。それ以前は、どういったカルチャーに触れられていたのでしょうか? また、映画に深くハマるようになったきっかけは何だったんでしょうか?
テレビドラマにゲーム、漫画、J-POP…当時の日本のどこにでもあったサブカルはごく普通に触れて楽しんでいましたが、夢中になっていたとは言えないですね。引っ越しばっかりしていたもので、その土地に根ざした遊びはしてなくて、それしかなかったというのが実際だと思います。
ただ、映画館に行くのは昔から好きでした。小学生の頃『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観て、中学生で『ターミネーター2』を観て面白いと思って、高校生くらいになるとミニシアター系やアート系の映画も観るようになって、自分のことを「映画好きなんじゃないか」と思って、大学で映画サークルに入るんです。そこで、自分なんて実は全然観てなかったんだって気づいた感じです。映画自体は好きだったけど、全然足りていなかった…と。
——「自分で映画作りたい」という思いで映画サークルに入られたんですか?
そうですね。僕は一年浪人して大学に入ったので、浪人期間中は、なかなか映画館にも行けず、すごくつらさもありました。なので、大学に入ったらやりたいことをやろうって思いが強まって、そのひとつが映画でした。とはいえ、いま思うと、映画をどう作るのかということについて、何も知らなかったですね。
——その後、大学生活を送りつつ、仕事として“映画業界”を志すようになったのは?
大学3年くらいになると就職活動が始まるんですけど、何を大学でやってきたかと振り返るわけです。大学で大して勉強したわけでもないんですけど、何かしら、大学でやってきたことを就職で活かしたいなと思うんです。学科も映画で卒論を書けるところを選んだし(※大学では文学部 美学芸術学専修課程を専攻)、考えたら映画のことしかやってこなかったので、就活でも映像関係の会社ばかりを受けていました。
でも、時代が就職氷河期だったからなのか? 私のコミュニケーション能力に問題があったのか…(苦笑)? 映像関係の会社も軒並み落ちまして…。「どうしようか?」と思っていた時、助監督の仕事を紹介していただけたんですね。
——その後、しばらくして、東京藝術大学大学院の修士課程に入り直されていますが、そこに至る経緯は?
商業映画の現場で助監督の仕事を始めたんですけど、何も知らないまま入ったわけです。助監督としてどう動くかなど全くわかってない状態で、しかも、そんなにコミュニケーション能力も高くなくて、ちゃんと人から教えてもらえないまま、目の前で現場が動き始めているという状況で…。商業映画1本と2時間ドラマの助監督をやったんですけど、端的に言って仕事ができなかったんですね(苦笑)。
その時の監督の知り合いの映像制作会社を紹介していただいて「修行してきなさい」となって、そこでそれなりに楽しいと思いながら働きつつ、その会社が作っているのはBSテレビの経済番組などでしたので「楽しい」がちょっと違うわけですね。「自分は映画がやりたかったはずなんだけどな…」と。
そうしたら、芸大の映像研究科が映画監督になるコースを開講することになって、2005年に第一期生を募集していて、しかも教授は北野武監督と黒沢清監督だと。そりゃすごい! 自分のこれまでの趣味と照らし合わせても「ここしかないかもしれない」と思って受けました。一年目は落ちて、二度目で翌年の2006年に受かりました。流れ流れてという感じでしたね。
——当時から「将来、映画監督になる」といことは意識されていたんでしょうか?
本当に五里霧中というか「なんも見えねぇ…」って感じでしたね。あの当時、いや、いまも若い人にとってそうかもしれませんが「監督にどうやったらなれるのか?」というのが全然わかんなくて、聞いたところでは「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」で入賞するとプロデューサーにピックアップされるらしいとか、助監督を続けて階段を昇っていくと、30代後半から40代手前くらいで監督の口があるんじゃないか? とか…漠然としていました。
ただ自分に助監督の能力がないことは明瞭にわかったので、その線は消えたわけです。PFFに出したりもしたんですが、全部落ちたり。とは言え、そんなに悪いものは撮っていないはずだという思いもあったので、自主映画で撮っていこうと。「職業にする」というよりは、まずは自主映画・学生映画という形で作品をつくらないと、次の段階に進めなさそうだなって感覚でした。それで藝大大学院も受験するわけなんですけど、「職業として映画監督になれるか」というのはどこまでもわかんなかったですね。
——その後、自主映画で短編、長編を含めて様々な作品を手掛け、『寝ても覚めても』では商業監督映画デビューを果たしましたが、自分が「映画監督である」と実感がわいたのはいつ頃ですか?
これもすごく難しくてですね…、ある意味、意識の中では自分はずっと「監督」ではあるんですよね。その意識は学生時代からあるんですけど、ただそれが「職業」になったのは、本当に最近ですね。それで食べていけるようになったのが本当にごく最近なので。
“商業映画”の意識
「せめぎあいの中で作品ができていく」
——『寝ても覚めても』以前に『ハッピーアワー』が国際的にも非常に高い評価を受けました。ただ、あの時点で無名の若手監督が5時間を超える映画を作り、劇場公開されるというのはすごいことだと思います。企画を通すということや、プロデューサー的な視点でどうやったら多くの人に劇場で映画を観てもらえるか? といった部分は、意識されていたんでしょうか?
その意識が全くなかったわけではないですが『ハッピーアワー』に関して言えば、コントロールが全く効いてなかったというのが実際のところですね(苦笑)。クレジットとしても自分はプロデューサーではないですし。
『ハッピーアワー』やその後の『偶然と想像』、今回の『悪は存在しない』でもプロデューサーに入ってもらっている高田聡さんという方がいて、(高田プロデューサーが所属する)「NEOPA」という会社は、実はIT企業なんですけど、高田さんは映画サークル及び学科の先輩なんです。その会社の取締役である高田さんの裁量の範囲で、NEOPAから出資していただけることになりました。
最終的に「すいません、5時間になっちゃいました」という感じだったんですが、それでもOKをいただけて、これはプロデューサーである高田さんの度量の広さというのがまずありますね。
『ハッピーアワー』は製作に2年くらいをかけていて、僕にとってもスタッフにとっても人生の一部のような存在になるわけですよね。“お祭り”というよりは、生活の一部みたいな感じですね。有名な人も出ていないですし、『ハッピーアワー』の時は、お客さんというよりは、一緒に仕事をした人たちのために最良の形で完成させるというモチベーションが強くて、その結果、あの長さになって、それを受け入れていただいたという感じです。
その意味で、プロデューサー的な才覚は自分にはあまりないと思いますね。
——『ドライブ・マイ・カー』のような作品の製作プロセスでも、商業的な部分を意識することはないのでしょうか?
特に、いわゆる商業映画の枠組みでやるときはプロデューサーという立場の人たちがいて、C&Iエンタテインメントにいた山本晃久さん、その上司の久保田修さん、ビターズ・エンドの定井勇二さんが主にクリエイティヴ面でも関わってくださっているんですけど、その方たちの意見はきちんと聞いて参考にしています。まず、多大な経済的リスクを負っているのはその方たちなので、その人たちの「これでよいか悪いか?」というジャッジは受け入れるんですけど、そこで「自分が面白いと思うことかどうか」という部分はきちんと出すようにしています。
ただ、山本さん、久保田さん、定井さんは『寝ても覚めても』の頃から、それぞれの立場から、かなり自分のやりたいことを尊重してくださったので、自分も含めたそれぞれの立場の意見の、そのバランスの中でできていくというか。自分もプロデューサーのジャッジへの信頼があるので、そのせめぎあいの中で作品ができていくという感じですね。
——本作『悪は存在しない』は、石橋さんからライブパフォーマンス用の映像の依頼を受けて企画がスタートし、そこからさらに枝分かれして長編映画になったという異色の作品ですが、この作品に関しても、クリエイターとしての「これは映画になる」という手応えと、プロデューサー的な目線で「これは(商業)映画になる」という感覚が重なるような瞬間は?
それはどこまでもなかったですね。今回、また高田さんにプロデューサーをお願いしていますが、製作中の高田さんの名言で「まあ、できてから考えようか」というのがありまして(笑)。完成してどんな作品なのかわかって、それから考えればいいんじゃないかと。まあ経済的なリスクが自分たちの耐えられる範囲内であるならば、明らかにそれが最良の選択肢なので、じゃあそうしようかとなった感じです。実際、それがこうやって劇場公開までされることになって、本当に運がよかったなって思いますし、高田さんのそのスタンスには心から感謝していますね。
——濱口監督にとって、映画づくりのプロセスにおける「映画監督」の役割・仕事はどういうものだと思いますか?
ある種のビジョンを提示したり、作品の全体の方向性を示すことが求められる部分もありますが、基本的には撮影の1テイク、1テイクであったり、編集の一工程、一工程に対し「OK」か「NG」かを判断する仕事ですね。単純に「OK」か「NG」かを示すだけでは暴力的なので、必要なら言語化も説明もしますけど、究極的には、個人の生理的な判断で「OK」と「NG」を振り分けていくのが仕事のような気がします
その基準をきちんと守り通せたら、映画になるだろう、という思いでやっています。
——繰り返しの質問になりますが、企画を「成り立たせる」という部分や「いかにこの企画を通すか?」という部分に関して、意識されたことはないんでしょうか?
これは本当に、僕がプロデューサーに恵まれているんだと思いますが、そういう経験がないんですよね。プロデューサーが「こういうことなら商業映画として劇場に掛けられる」と判断して、商業映画の枠に入れてくれたり、高田さんのように、僕のジャッジを信頼してくださって、とりあえず完成させて、その後のことは、できたものを見て考えればいいと考えてくださる——。
もちろん「お金にならなくてもいい」と思っているわけではないでしょうが、そこは自分に対する信頼感をもって「この枠組みの中でやるなら、何をしてもいいですよ」とやらせてくださる方がいるので、「この企画をどうしなきゃいけない」ということは考えず、どちらかというと、その時に自分の中にある課題意識——「現場のここをもうちょっと改善したい」「演出のここをもうちょっとうまくなりたいな」みたいなことに取り組める企画を立てることが多いですね。
インプット、キャラクター、ラスト…
濱口映画ができるまで
——ここから、具体的な作品づくりのプロセスについてもお聞きしていきます。今回の物語はオリジナル脚本ですが、石橋さんの知り合いから実際に起きた問題について話を聞き、それらをベースに物語を構築していったそうですね。物語の組み立てやキャラクターの膨らませ方はどのように行なっていくのでしょうか?
脚本に関しては本当に難しくて、いまだに「これが正解」というものがないんですよね。「こうしたら面白い本が書ける」という方式は良くも悪くも確立していなくて、その都度、企画に合わせて七転八倒的な感じで、のたうち回るようにしてできていきます。
今回は、まずリサーチをしてみようということで、でも、どこから手を付けていいかわからず、とりあえず、石橋さんの音楽ができる場所の近くでリサーチをすれば、石橋さんの音楽に合うものが何かできるんじゃないか? というくらいのところから、藁をもつかむような思いでリサーチを進めていったら、だんだんと「こういうものが撮れるな」とか「こういうことがあるのか」というのが積み重なっていき、ある時、スーッと筋が通ったということしか言えないんですよね。
ある瞬間に突然、組み上がっていくというのは、今回もそうだし『ドライブ・マイ・カー』もそうでした。原作を何度も繰り返し読む中で、ある時、組み上がったという感覚でした。そのために必要なのはインプットをするということですね。インプットが十分にされていれば自然とアウトプットされるんだろうと思います。
——今回でいうとインプットにあたるのは…?
今回の場合はリサーチそのものがインプットでしたね。使われなかった要素もいっぱいあるんですけど、土地を回って教えていただいた「あの木が〇〇で…」「水はこっから湧いていて…」といった話やその土地の歴史や何かの話のひとつひとつがそうですね。『ドライブ・マイ・カー』では原作そのものもそうだし、「ワーニャ伯父さん」の存在もインプットになったと思います。
『偶然と想像」では、喫茶店で隣のテーブルで話されていた会話がインプットになったことがありました。あとは普段の日常の暮らしの細かい感情がインプットになる——「いま、自分の中でザワっとしたこの感覚を覚えておこう」ということもありますね。
——キャラクターの膨らませ方に関して、例えば今回の物語で巧(大美賀均)や娘の花(西川玲)を中心に進むかと思いきや、中盤以降で思いもよらない人物が重要な存在になっていきますが、これはどのように…?
これは面白くしようと思ったらそうなったって感じですね。単純な映画の好みの話なんですけど、僕自身が不意打ちを食らうのが好きなんですね。「まさかそんなことになるなんて!」というのがすごく好きで、そのパターンのひとつとして「お前、そんな重要なキャラだったのか?」というのがありまして(笑)、急にガツンと来るみたいなのが、映画を見る側の体験としても好きで、自分が作るときもそういうことを起こそうとするんですよね。
先ほどのインプットで言うと、映画を観ている時の自分の身体に起こる状態の変化も、ひとつの大きなインプットとしてありますね。
——ラストシーンの意図や重要性についてもお聞きします。『ドライブ・マイ・カー』では、ラストで描かれているあの状況はどういうことなのか? という“論争”が起きましたが、そうやってラストシーンの描き方で観る者の心をざわつかせようというのはかなり意図的にされているんでしょうか?
それはメチャメチャあると思いますね。映画を観た人は、ラストシーンの印象を引きずって映画館を出るということになるので、ラストシーンというのはかなり大事だと思っています。
これも個人的な映画の趣味なんですけど「え? これはどう感じたらいいんですか…?」という気持ちで映画館を出るのが好き、というかかけがえのないことだと思うんですよね。数日途方に暮れますが、気がついてみれば、それが最も残る体験になっている。長く映画ファンでいますが、それが結局最高なのでは、と思っているので、観客にもそういうものを提供したいです。
とはいえ、あまりにもわからないと「え? これはどう感じたらいいの?」と感じる“土台”そのものがなくなってしまうので、ある程度の土台を構築した上で、どこかでズレというか、ある種の不条理が入ってくることで「いや、こういうふうに思ってたのに、何なんですか、これは?」というものができるのが大事だなと思います。
ただそれもあまりやり過ぎると、観客との関係性が切れてしまうので、その塩梅は常に難しいですけど、観客の体験のためにやるのが大事なことだと思いながらやっています。
——今回のラストの衝撃に関しては『ドライブ・マイ・カー』以上だと思いますが、監督の中で様々な構築があった上で、あのラストを選ばれたということですか?
ああいうのを明確に言語化してやっているかというと、必ずしもそうではないと思います。ただ結局「こうあるべきだ」という基準が言語化されずとも自分の中にあるわけです。ずっと物語を書いてきて「これがこの物語のラストになるんだ」という納得感——自分の中で腑に落ちた感じで書けることがすごく大事で、そういう身体レベルの納得感があると、やはりそれを演じる人にも伝えることができる気がします。
そうすると、今度は演じる人も「これはこういうものなのだ」と確信をもって演技をしてくれて、その確信に満ちた演技を見ると「やはりこういうことなのかな」と観客もまた納得ができるのでは……と思っています。
(そのラストが)起きたこととして、そこから「じゃあ、なんでそういうことになったのか考えよう」という、書いているときの感覚は、観客の視点とすごく近いと思いますね。
——最後に映画業界で働くことを志している人に向けて、メッセージをお願いします。
大事なことは二つで、まず「イヤなことは無理にやらない」ということですね。いまの若い人の感覚で「なんかこの映画の現場、おかしいんじゃないか?」、「こういう働かせられ方は変じゃないか?」と感じたら、その感覚は正しいです。そんなところにいる必要はありません。その感覚を大事にして成長してほしいし「何かがおかしい」と思うことに無理に自分を合わせないことはとても大事だと思います。
とはいえ、イヤなことから遠ざかるだけでは成長できないのは確かなので、何かしら勉強を続けることが大事だと思います。
現場から離れた時期も自分がやっていたことは、「映画を観る」ってことですね。現場の経験があると、「これはこう撮っているのかな」とか「こう撮れるのはすごいことだ」という感覚もより繊細なものになっていきます。映画館に行くのがベストですが、最近では配信サービスも充実して、低コストでたくさんの作品を観ることができる。これはやっぱりすごいことです。現場に行くと、やっぱり映画を観るって大事なことだなというのはスタッフやキャストとのコミュニケーションでもすごく感じます。
「勉強する」というと堅苦しいですが、でも勉強して自分の感覚が変わっていくのを感じるって楽しいことなんですよ。そういう楽しみを自分から手離さなければ、イヤなことを拒みながらでも意外と生きていけると思います。保証はできませんが(笑)、自分の人生を振り返るとそういうことなんじゃないかと思います。