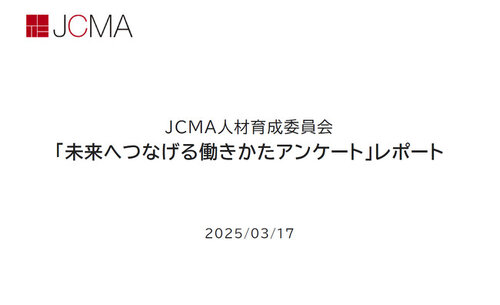「仕事があればこそ怠けられる。仕事が私を怠けさせる」……戦争体験作家、梅崎春生のユーモア
2025年5月19日(月)15時30分 読売新聞
愛猫と写る梅崎春生(かごしま近代文学館所蔵)
特異なユーモアと鋭敏な感性で存在感を発揮した戦後の作家、梅崎春生の文庫が近年相次ぎ刊行されている。戦争体験を踏まえ生と死の極限を見つめた代表作だけでなく、怠け者の生活をつづった短編集まで、幅広い作風の作品が掘り起こされている。(池田創)
戦争文学も脚光文庫化続々
<寒くなると、
こんな文章で始まる「寝ぐせ」など、『怠惰の美徳』(中公文庫)は、怠け者である生活をいかに送ってきたかを語った短編小説や随筆を収めている。勉強せず、落第し、就職してもすぐに辞め、昼過ぎに起きて、昼食を食べるとまた布団にもぐる。『桜島』などの重厚な戦争文学で知られる戦後派の作家というイメージから大きく離れ、親近感をもって迫ってくる。
原稿用紙数枚の表題作は、仕事がさし迫ってくると怠け出す傾向があることをとつとつと述べる。
<仕事があればこそ怠けるということが成立するのであって、仕事がないのに怠けるということなんかあり得ない。すなわち仕事が私を怠けさせるのだ>
これらの文章に漂う不思議な論理は、読者を妙に納得させるユーモアがある。
『ウスバカ談義』(ちくま文庫)は、山名君と呼ばれる男が主人公のもとを訪れ、珍妙な問答を繰り返す表題作など11編を収録する。ユーモア小説の形を取りつつ、どこか人生の抱えている虚無のようなものがぼんやりと浮かんでくる読後感がある。
梅崎は大学卒業後、海軍に召集され、暗号通信の業務に従事した。復員後、戦争体験をもとに描いた『桜島』で一躍脚光を浴びた。兵隊小説集と冠した『桜島・狂い
『桜島』は鹿児島・桜島の基地に赴任したある兵隊の日々を描く。敗戦が現実味を帯びる極限状況下での心象風景を
<たくさんの人間が、そうやって空しく死んで行ったのだろう。何という悲惨なことか。やはりこういうことは、再びあらしめてはいけない>
「兵隊小説集」2巻目の『日の果て・幻化』は今月発売予定だ。解説を担当した文芸評論家の平山周吉さん(73)は「士官ではない、他の戦争文学では光があたらない、落ちこぼれの人たちを描いている」と語る。戦後80年の今年、戦争体験者がいなくなっている中で、梅崎の戦争文学は再び注目を集めそうだ。「決まりきった反戦ではなく、当時の庶民が感じた実感を最大公約数的に伝えている。梅崎の文学は、言葉にならないような戦争の実情を知るアプローチのひとつになるのではないか」と話している。
文体使い分け、緩急秀逸
梅崎春生の作品に心酔し、中公文庫などの解説を担当した文筆家の荻原魚雷さん(55)にその文学の魅力を聞いた。
30歳ぐらいの頃に手にとり、とんでもない面白さを感じ、すぐに全集を買いに走った。言葉の選び方、細部のスケッチの伝え方が秀逸で、自分もライターとして、梅崎の文章の緩急のつけ方はお手本になっている。
『桜島』などにおける戦争文学は、集団の中に置かれると人間がどうなるのか、どの時代にも起こりうる恐ろしさを描く。一方で『怠惰の美徳』に収められたナマケモノ文学は、戦後派の作家の中では、かなり力が抜けている。様々な文体を使い分けた作家だ。
「寝ぐせ」を読んでいて、いいかげんに生きていても何とかなるんだと感じ、梅崎を好きになった。現代社会はちゃんとしていなくちゃいけないレベル、当たり前の基準が上がりすぎている。怠惰な日々にも文学はあり、現代社会でもそのような文学に救われる人はいると思う。