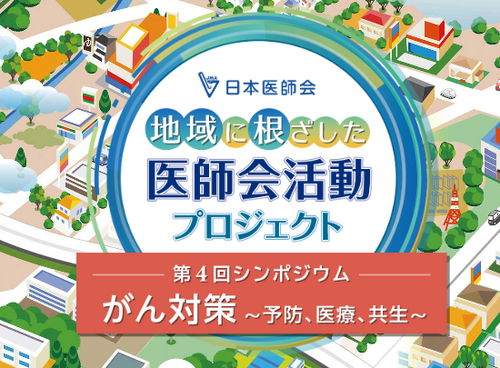ミャンマー被災地で住民多数がテント生活、日赤看護師「熱中症や感染症の対策必要」
2025年4月23日(水)18時40分 読売新聞
マンダレーに到着し、ミャンマー赤十字社の職員らと情報収集を行う苫米地氏(手前、15日)=日本赤十字社提供
3月の地震で大きな被害を受けたミャンマーを拠点に活動する日本赤十字社医療センター国際医療救援部の苫米地則子副部長(61)が23日、読売新聞などの取材に応じた。被災地では40度近い猛暑の中、テント生活を続ける住民が多いと指摘し、「住居の支援が間に合っていない。熱中症(対策)や、衛生環境がより悪化する(5月以降の)雨期に向けた感染症対策が必要だ」と訴えた。
看護師の苫米地さんは16〜19日、震源に近い中部マンダレーとサガインでミャンマー赤十字社による巡回診療などに同行した。現在は最大都市ヤンゴンで支援計画の策定にあたっている。マンダレーやサガインには倒壊したままの建物が点在していると説明し、「医療施設や水道も完全には復旧していない。(復旧は)これからが正念場だ」と強調した。
日赤によると、2021年のクーデター以降続く国軍と民主派勢力などの戦闘の影響で、マンダレーなどには避難民のキャンプが多くある。苫米地さんは「避難生活に地震が重なった被災者の心理的負担は大きい。カウンセリングのニーズがある」と話した。
今後の支援については「地震から1か月近くたち、急性期から早期復興に移るタイミングだ。海外の支援団体が撤退しても、現地の人を中心に復興できるよう支援する中長期的な関わりが必要になる」と語った。(国際部 古林隼人)