江原啓之「3人目の孫が生まれたが、今まで通りの援助は経済的に難しい…。無理は禁物、理由をはっきり伝えて」
2025年3月19日(水)11時0分 婦人公論.jp

(イラスト◎大野舞)
スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』のリニューアルにあたって始まった新連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第39回は「3人目の孫が生まれたが、今までどおりの経済的援助は厳しい」です。
* * * * * * *
Q 3人目の孫が生まれたが、今までどおりの経済的援助は厳しい
A)生活費を削って少額でも援助を続ける
B)理由を説明して援助をやめる
無理は必ず歪みを生む
初孫には手厚い援助をしていたけれど、孫が増えるとともに金銭的余裕がなくなってきた。老後のことを考えれば、援助をやめたいのが本音、というのが今回のテーマです。
子どもに「今後は援助をするのが難しい」と伝えていいものか思案中で、親として「任せておきなさい」と言えないもどかしさや、先の2人の孫に援助してきて3人目だけしないという罪悪感も見え隠れしています。さてこの状況で、親として無理をしてでも援助を続けるか、それとも宣言してやめるのか、どちらの選択が幸せぐせなのでしょうか。孫がいる方も、いない方も、一緒にお考えください。
スピリチュアルな視点で言えば、無理は必ず歪みを生みます。「できることはできる。できないことはできない」が正しいので、幸せぐせはBです。
理由を正直に打ち明けて
高度経済成長期を経験した世代にとって、物やお金を贈るのは愛情の証し、バロメーターのように思うのかもしれません。ただそんな時代はとっくに終わり、今や物価も軒並み上昇、年金生活者にとっては自分の暮らしを守ることで精いっぱいというのが正直なところでしょう。これまでしてきたからといって、同じような援助を孫たちに続けるのが厳しい事情はよくわかります。
ただし、今まで援助してきたのに、「もう援助はしない」と一言で打ち切るのは一方的な気がします。それでは子どもが親の事情を理解できず、これまでと態度を変えても仕方ありません。「以前より物価も高くなっているし、生活するのに精いっぱい。老後に迷惑をかけないためにも、今までと同じことをする余裕がないのよ。ごめんなさい」と、正直に打ち明ける必要があるでしょう。
そんな丁寧に説明する必要があるの? 子どもや孫は、援助してもらって当然だと思っているの? それは都合がよすぎる! と憤る方がいるかもしれません。しかしもとはと言えば、そういう習慣をつけたのは親。安易に物やお金を与えてきた自分の行動を反省するしかありません。
少子化の時代、一人の子どもにかけるお金も増えているようです。最近はランドセルひとつとっても高額で、なかには自分の食費を削ってでも孫が希望する高いランドセルを買ってやりたいと思う方もいると聞きます。人というのは誰かに頼られたり、慕われたりするのが生きがいになるもの。孫から「おばあちゃん、これが欲しい」とねだられるのも生きがいのひとつなのでしょう。なんとしても買ってやりたいと、自分が納得して食費を削るならそれもいいのかもしれません。けれど、無理して買ってあげたランドセルを最初は喜んでも、卒業まで孫が同じ気持ちで使い続けるでしょうか。1年も経たないうちに乱暴に扱われるかもしれませんし、不登校になって使わなくなる可能性だってある。それでも買ってよかったと思えるのならばいいのですが。
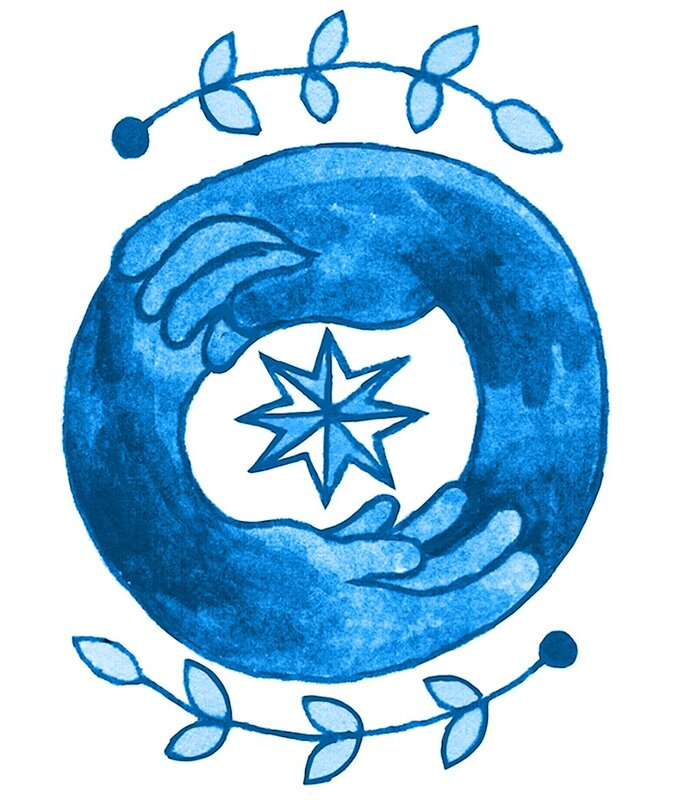
(イラスト◎大野舞)
その援助は自分のため?
いくら幸せぐせがBだとしても、必要とされなくなるのは悲しい。求められることが私の幸せだ、と考える方は、Aを選んでしまうのかもしれませんね。しかし、減額しても無理な援助は続きません。前述のように食費や光熱費を削りたくても、これ以上削りようがないという場合もあるのではないでしょうか。
それでも援助したいという方にアドバイスするとすれば、自宅にある不用品を買取業者に売り、資金を作ってはどうかということ。いつか子どもや孫にあげようと思っていた着物やジュエリーが、タンスに眠ってはいませんか。だいたいその手の物は、子どもや孫がもらっても「こんなの趣味じゃない」とかなんとか言われて、喜ばれないことが多いもの。それよりも現金化して、援助費用としてもらったほうが、子どもも孫もありがたいでしょう。
大事にとってあった着物やジュエリーを二束三文で買い叩かれる現実を突きつけられるかもしれませんが、「こんな安物を大事にとっておいたなんて無駄だったわ」と気づくいい機会かもしれません。それをきっかけにどんどん家の中が整理されれば、終活も兼ねることができ一石二鳥です。
ただ、気づいてほしいことがあります。求められるのが幸せだからと、ねだられるままに買い与えるのは、相手のためではありません。子どもに嫌われたくない、孫に慕われたい。それは自分のためにしていること。相手のためを思ってする本来の援助とは違うことを忘れてはいけません。
ましてや、物やお金をあげないと寄ってこない孫との関係は、あまりに悲しすぎます。経済的に余裕がない暮らしで無理を続けるのは、悲愴感が漂うものですよ。せっかくの人生なのですから、もっと自分の生活を優先して、本当の意味で有意義なお金の使い方を考えるときなのかもしれません。
前回「就職し家を出た子どもから『あなたは毒親。干渉しないで』宣言。どう対応するかで、毒親度がわかる」はこちら













